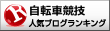ぐずついた天気ながら、比較的涼しかったので、ベランダで久しぶりに3本ローラー練習。
最近、サドルを3mm下げて、右足のクリートを前に出したので、3本ローラーでセッティングの完成度を確認。うむ、特に問題ないな。
乗り始めてしばらくは車体がふらつくがすぐに安定し、ほぼ揺れることもなく淡々と踏める。そうなると座禅のようなもので、無心でいれば揺れず、気を取られると揺れる。ケイデンスは84〜87rpmくらいで安定。これくらいのケイデンスがベストなリズムなのだろうか。
3本ローラーの踏み心地で特徴的なのは、足で踏んでいる感じがなく、ヘソの下の腹から太ももの付け根くらいの体幹や胴体で踏んでいる感覚。特に大臀筋がよく動いている。GT−Rollerではでない感覚だ。体幹でバランスを取っているということなのだろうか。
汗でびしょびしょになるまで、1時間程度LSDくらいの感じでペダルを回し、終了。たまには3本ローラーをやるべきだな。もっと涼しければ良いのだけど。
最近、サドルを3mm下げて、右足のクリートを前に出したので、3本ローラーでセッティングの完成度を確認。うむ、特に問題ないな。
乗り始めてしばらくは車体がふらつくがすぐに安定し、ほぼ揺れることもなく淡々と踏める。そうなると座禅のようなもので、無心でいれば揺れず、気を取られると揺れる。ケイデンスは84〜87rpmくらいで安定。これくらいのケイデンスがベストなリズムなのだろうか。
3本ローラーの踏み心地で特徴的なのは、足で踏んでいる感じがなく、ヘソの下の腹から太ももの付け根くらいの体幹や胴体で踏んでいる感覚。特に大臀筋がよく動いている。GT−Rollerではでない感覚だ。体幹でバランスを取っているということなのだろうか。
汗でびしょびしょになるまで、1時間程度LSDくらいの感じでペダルを回し、終了。たまには3本ローラーをやるべきだな。もっと涼しければ良いのだけど。