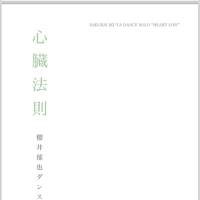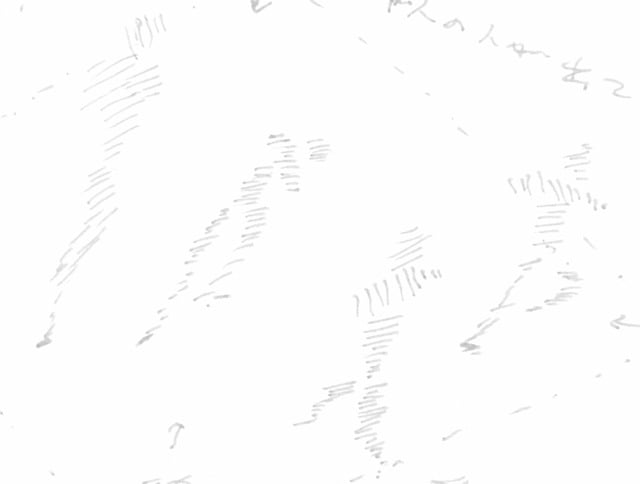
ひとつだって同じカラダは無い、ひとときだって同じ時間は無い、
としばしば思うそのことについて、考える機会を与えてくれた作品が、サミュエル・ベケットにありました。
「この厳密な規則の終わりない反覆を見ていると、なにか世界に恐ろしい破壊が生じてくるような印象が生まれる」という、多木浩二さんの一文から興味を持って探して見たのですが、それは『Quad(クワッド)』という、1981年に製作されたテレビ用の演劇作品でした。
劇場での多様な視点に対して、テレビ用と特化するということは、あえて視点を単一化・固定化してあるのでしょうか。
空間に四角形に区切られたエリアがあり、登場人物は4人である。
彼らは、とてもよく似た体型をしている。
彼らは顔と体を、やはり似た形の布で隠している。
彼らは、その布の色によって区別されている。
彼らは、四角形の四隅、そのそれぞれから、一人づつ現れ、別々の隅に向かって素早く移動する。
その繰り返しが淡々と、かつ延々と続くのです。
セリフは無い。
筋書きもない。
ただ「移動スル」。
移動という行為の規則だけが、足捌きやスピードや重心や体軸の傾斜や、という細部まで、非常に厳密に「ソコに」あるのです。
そして、あるとき呆気なくプツリと終わる。
個性を消した人物たちは、あるいは差異を隠したカラダたちは、自由度をもカットしようとするかのように「動き」ます。
彼らはあえて同じであろうとし、あえて同じときを繰り返そうと、して、いるのですが、それらを通じて、実は彼らは、彼ら自身を消すこと、さらに、時を消すこと、に関わる実験をしているようにさえ、僕には見えました。
しかし、何故かこれは無機的には感じられなくて、むしろ、奇妙に生々しく、それから、規則性の割には様式とか形式が感じられなくて、むしろ、逸脱感さえある。
特徴的なのは速さでした。
彼らの動きは均質で滞りがない。しかし、
常に慌ただしいのです。
一見、歌舞伎の黒子みたいな感じにも見えるが、違う。
やはり速度感や呼吸感やリズム感の点で、ベケットのこの作品は異様なのです。
その速度や反覆感や累積される何かは、実験室のマウスみたいな感じなのです。
それは、自らが生み出した速度に追い立てられているようでもあり、周囲にもどんどん速度が伝染してゆくような、例えば、あくせく街を行き交う僕らの仕事モードの身体みたいな感じにも、感じてしまうのでした。
そして、一旦始まってしまうと後は坂道を転がるように展開してゆくような世界の暴力的な勢いをも、そこはかとなく感じさせられるのでした。
ある意味すこし不気味な、その速さが、しかしパフォーマンスとしては非常に面白い。
また、人物たちがこのように己れを、今を、「消そう」とすれば「する」ほど、そこに現れてくる意味合いとはパラレルに、人や場所や時間の生々しさというか、実体というようなパックリしたものが垣間見えてしまう。そこも面白く感じました。
あるのにナイ、ないけれどもアル、というような遊び方は、生身の人の、またカラダの、特有な遊びかとも感じられるのですが、、、。
それにしても、まあ、どこから、どのようにして、このような「ふれ」や「くるい」が滲み出てくるのでしょうか。
この作品は、ものごとの裏側にある「生まれ壊れ」に、つまり時間と存在の「仕組み」に関わろうとしているような作品にさえ見えました。
としばしば思うそのことについて、考える機会を与えてくれた作品が、サミュエル・ベケットにありました。
「この厳密な規則の終わりない反覆を見ていると、なにか世界に恐ろしい破壊が生じてくるような印象が生まれる」という、多木浩二さんの一文から興味を持って探して見たのですが、それは『Quad(クワッド)』という、1981年に製作されたテレビ用の演劇作品でした。
劇場での多様な視点に対して、テレビ用と特化するということは、あえて視点を単一化・固定化してあるのでしょうか。
空間に四角形に区切られたエリアがあり、登場人物は4人である。
彼らは、とてもよく似た体型をしている。
彼らは顔と体を、やはり似た形の布で隠している。
彼らは、その布の色によって区別されている。
彼らは、四角形の四隅、そのそれぞれから、一人づつ現れ、別々の隅に向かって素早く移動する。
その繰り返しが淡々と、かつ延々と続くのです。
セリフは無い。
筋書きもない。
ただ「移動スル」。
移動という行為の規則だけが、足捌きやスピードや重心や体軸の傾斜や、という細部まで、非常に厳密に「ソコに」あるのです。
そして、あるとき呆気なくプツリと終わる。
個性を消した人物たちは、あるいは差異を隠したカラダたちは、自由度をもカットしようとするかのように「動き」ます。
彼らはあえて同じであろうとし、あえて同じときを繰り返そうと、して、いるのですが、それらを通じて、実は彼らは、彼ら自身を消すこと、さらに、時を消すこと、に関わる実験をしているようにさえ、僕には見えました。
しかし、何故かこれは無機的には感じられなくて、むしろ、奇妙に生々しく、それから、規則性の割には様式とか形式が感じられなくて、むしろ、逸脱感さえある。
特徴的なのは速さでした。
彼らの動きは均質で滞りがない。しかし、
常に慌ただしいのです。
一見、歌舞伎の黒子みたいな感じにも見えるが、違う。
やはり速度感や呼吸感やリズム感の点で、ベケットのこの作品は異様なのです。
その速度や反覆感や累積される何かは、実験室のマウスみたいな感じなのです。
それは、自らが生み出した速度に追い立てられているようでもあり、周囲にもどんどん速度が伝染してゆくような、例えば、あくせく街を行き交う僕らの仕事モードの身体みたいな感じにも、感じてしまうのでした。
そして、一旦始まってしまうと後は坂道を転がるように展開してゆくような世界の暴力的な勢いをも、そこはかとなく感じさせられるのでした。
ある意味すこし不気味な、その速さが、しかしパフォーマンスとしては非常に面白い。
また、人物たちがこのように己れを、今を、「消そう」とすれば「する」ほど、そこに現れてくる意味合いとはパラレルに、人や場所や時間の生々しさというか、実体というようなパックリしたものが垣間見えてしまう。そこも面白く感じました。
あるのにナイ、ないけれどもアル、というような遊び方は、生身の人の、またカラダの、特有な遊びかとも感じられるのですが、、、。
それにしても、まあ、どこから、どのようにして、このような「ふれ」や「くるい」が滲み出てくるのでしょうか。
この作品は、ものごとの裏側にある「生まれ壊れ」に、つまり時間と存在の「仕組み」に関わろうとしているような作品にさえ見えました。