
1.はじめに
先日書き込んだ「成長の限界の回避と持続可能な世界実現への選択」の記事について、ある心あるご婦人から「事の重大さは伝わってくるが問題が大きすぎて、日常の生活に追われている人たちには今しか見えず、また今よければ将来のことまでは考えたくないとか、自分だけではどうにもならないとか、じゃどうすればいいの?等々、むしろ消極的な諦めに陥ってしまいそう」等々の私的コメントをいただきました。大変もっともなご指摘です。そういう大勢の方々が発想転換いただけるかどうかが、今後の時代にとても大切です。満足な解答には程遠いのですが、PART 1とPART 2に分けて私見を含めて述べてみます。
2.GDPが示すうわべの経済成長よりGPIで計る真の進歩で考える
経済成長を示すのに常用されるGDP (Gross Domestic Product、国内総生産)は、経済活動に伴ってやり取りされたお金の総額を示す量的指標で、人類の幸福や地球環境に正負いずれの影響を及ぼすかは区別されません。軍事支出はその際たるものでしょう。家庭や社会の崩壊と犯罪への対策、環境破壊的産業活動とその代償、武器の製造・売買などでやり取りされるお金も全てポジティブにカウントされます。ファーストフード産業や砂糖産業の利益と肥満対策に要する医療費も同様です。経済イコール貨幣経済と考え勝ちですが、経済の原義は家の管理にあります。地球規模で管理を考えると、市場で取引される丸太より生えている木の方が広い意味で経済価値が高く見えるように、経済の質的面を考えると見方が違ってきます。
アメリカのシンクタンク「リディファイニング・プログレス」は、上記を考慮に入れたGPI (Genuine Progress Indicator、真の進歩指標)を提唱しました。かいつまんで言うと、GPIでは人類の幸福や地球環境にネガティブに働く活動やその防除・修復に関わるお金のやり取りはマイナスにカウントします。一方、家庭での育児、老親の世話、地域のボランティア活動などお金のやり取りを伴わない本来生産的活動を、プロを頼んで支払った額としてカウントします。また、化石燃料のように再生不可能な資源の使用は、将来の世代からの借金としてマイナスにカウントします。図は米国人一人当りのGDPとGPIの推移を示しています。1970年頃からGDPが増えているのに、GPIは足踏み状態です。貧しい人ほど収入が増えると幸福感が増し、あるレベル以上に達すると消費が増えても幸福感の増加につながらず、所得配分の格差も拡大して、いろいろな問題が出てくると解釈されています。かつて日本は世界一安全な国と言われました。最近では通学中の子供達の安全が懸念されるなど様々な不安要因が増えてきましたが、昔より貧しくなったからとは言えないでしょう。社会や環境問題にかかる経費の査定法が煮詰められていないので、未だGPIが確立された指標とは言えませんが、持続可能な世界実現のために考慮すべき問題を提起しています。
参考資料:N. Myers & J. Kent, The New GAIA Atlas of Planet Management, p.252~255(Gaia Books 2005);http://www.redefiningprogress.org/;エコロジカル・フットプリントの活用 p.22~27(インターシフト 2005)。
3.期待されるバイオマスエネルギー
脱地球温暖化に向けて、化石燃料に替わる様々なエネルギーが求められており、バイオマスエネルギーにも期待がかかっています。簡略に言うとバイオマスは現存する生物由来の産業資源です。動物は植物由来の食物を食べて育ちます。それゆえ動植物由来の物質を燃やして生じた分の二酸化炭素は、植物の光合成で吸収されれば自然界を循環してくれるので、化石燃料を燃やして排出される二酸化炭素の増加分とは区別して考えるのです。2月18日のNHK土曜フォーラムで「どう生かすバイオマスエネルギー」が放送されました。岩手県南部の製材の町 住田町の工場団地では、産業廃棄物として捨てていた木屑用のボイラーを設置し、工場の暖房や木材の乾燥の熱源に利用しています。これで重油の使用量を従来の1/6に削減できたそうです。また、カンナ屑を圧縮して粒状の木質ペレットに整形し、燃料として出荷、販売しています。これは非常に燃焼効率が高く、保育園の床暖房用ボイラーや、町役場の暖房用ストーブで使われています。町では助成金を出して調理機能もついた家庭用ストーブの普及を図っており、住民の評判も上々でした。かつて岩手県山間部を日本のチベットと揶揄する向きもありましたが、このように時代を先取りした、聞くと元気が出る取組が行われているのです。
日本の山林は間伐などの手入れが行き届かず、荒廃が進んで土砂災害発生のおそれが高まっています。間伐された木も大部分放置されたままなので、木質バイオマスは国内で需給可能なエネルギー源なのです。山林を守ってくれる人達がやりがいを感じ、元気になってもらえるような社会環境の整備が大切です。但し、いくら環境に優しい燃料でも、木質ペレットを岩手県から東京へ取寄せるのは、輸送に多大なエネルギーを要するので得策とは言えません。エネルギーにせよ食料にせよ、地域社会ごとに地域に適した方法の開発と施策の展開で、需給率を高めてゆくのが良策です。
番組では上記のほかにも、間伐材を不完全燃焼さて出てきた一酸化炭素と水素の混合ガスを使った発電と、牛の糞尿を発酵させて出てきたメタンガスからの燃料電池用水素の製造(両方とも岩手県葛巻町)や、乳牛の糞尿由来のメタンガスを使った発電(北海道士幌町)も紹介されました。現在はバイオマス専用の施設や機器の導入に割高なコストが掛かりますが、将来的需要の増加や技術革新で低価格化が期待できます。枯渇のおそれがなく、廃棄物を出さない太陽光や風力などの自然エネルギーとともに、将来を見据えた政策展開によって可能性が広がるでしょう。
先日書き込んだ「成長の限界の回避と持続可能な世界実現への選択」の記事について、ある心あるご婦人から「事の重大さは伝わってくるが問題が大きすぎて、日常の生活に追われている人たちには今しか見えず、また今よければ将来のことまでは考えたくないとか、自分だけではどうにもならないとか、じゃどうすればいいの?等々、むしろ消極的な諦めに陥ってしまいそう」等々の私的コメントをいただきました。大変もっともなご指摘です。そういう大勢の方々が発想転換いただけるかどうかが、今後の時代にとても大切です。満足な解答には程遠いのですが、PART 1とPART 2に分けて私見を含めて述べてみます。
2.GDPが示すうわべの経済成長よりGPIで計る真の進歩で考える
経済成長を示すのに常用されるGDP (Gross Domestic Product、国内総生産)は、経済活動に伴ってやり取りされたお金の総額を示す量的指標で、人類の幸福や地球環境に正負いずれの影響を及ぼすかは区別されません。軍事支出はその際たるものでしょう。家庭や社会の崩壊と犯罪への対策、環境破壊的産業活動とその代償、武器の製造・売買などでやり取りされるお金も全てポジティブにカウントされます。ファーストフード産業や砂糖産業の利益と肥満対策に要する医療費も同様です。経済イコール貨幣経済と考え勝ちですが、経済の原義は家の管理にあります。地球規模で管理を考えると、市場で取引される丸太より生えている木の方が広い意味で経済価値が高く見えるように、経済の質的面を考えると見方が違ってきます。
アメリカのシンクタンク「リディファイニング・プログレス」は、上記を考慮に入れたGPI (Genuine Progress Indicator、真の進歩指標)を提唱しました。かいつまんで言うと、GPIでは人類の幸福や地球環境にネガティブに働く活動やその防除・修復に関わるお金のやり取りはマイナスにカウントします。一方、家庭での育児、老親の世話、地域のボランティア活動などお金のやり取りを伴わない本来生産的活動を、プロを頼んで支払った額としてカウントします。また、化石燃料のように再生不可能な資源の使用は、将来の世代からの借金としてマイナスにカウントします。図は米国人一人当りのGDPとGPIの推移を示しています。1970年頃からGDPが増えているのに、GPIは足踏み状態です。貧しい人ほど収入が増えると幸福感が増し、あるレベル以上に達すると消費が増えても幸福感の増加につながらず、所得配分の格差も拡大して、いろいろな問題が出てくると解釈されています。かつて日本は世界一安全な国と言われました。最近では通学中の子供達の安全が懸念されるなど様々な不安要因が増えてきましたが、昔より貧しくなったからとは言えないでしょう。社会や環境問題にかかる経費の査定法が煮詰められていないので、未だGPIが確立された指標とは言えませんが、持続可能な世界実現のために考慮すべき問題を提起しています。
参考資料:N. Myers & J. Kent, The New GAIA Atlas of Planet Management, p.252~255(Gaia Books 2005);http://www.redefiningprogress.org/;エコロジカル・フットプリントの活用 p.22~27(インターシフト 2005)。
3.期待されるバイオマスエネルギー
脱地球温暖化に向けて、化石燃料に替わる様々なエネルギーが求められており、バイオマスエネルギーにも期待がかかっています。簡略に言うとバイオマスは現存する生物由来の産業資源です。動物は植物由来の食物を食べて育ちます。それゆえ動植物由来の物質を燃やして生じた分の二酸化炭素は、植物の光合成で吸収されれば自然界を循環してくれるので、化石燃料を燃やして排出される二酸化炭素の増加分とは区別して考えるのです。2月18日のNHK土曜フォーラムで「どう生かすバイオマスエネルギー」が放送されました。岩手県南部の製材の町 住田町の工場団地では、産業廃棄物として捨てていた木屑用のボイラーを設置し、工場の暖房や木材の乾燥の熱源に利用しています。これで重油の使用量を従来の1/6に削減できたそうです。また、カンナ屑を圧縮して粒状の木質ペレットに整形し、燃料として出荷、販売しています。これは非常に燃焼効率が高く、保育園の床暖房用ボイラーや、町役場の暖房用ストーブで使われています。町では助成金を出して調理機能もついた家庭用ストーブの普及を図っており、住民の評判も上々でした。かつて岩手県山間部を日本のチベットと揶揄する向きもありましたが、このように時代を先取りした、聞くと元気が出る取組が行われているのです。
日本の山林は間伐などの手入れが行き届かず、荒廃が進んで土砂災害発生のおそれが高まっています。間伐された木も大部分放置されたままなので、木質バイオマスは国内で需給可能なエネルギー源なのです。山林を守ってくれる人達がやりがいを感じ、元気になってもらえるような社会環境の整備が大切です。但し、いくら環境に優しい燃料でも、木質ペレットを岩手県から東京へ取寄せるのは、輸送に多大なエネルギーを要するので得策とは言えません。エネルギーにせよ食料にせよ、地域社会ごとに地域に適した方法の開発と施策の展開で、需給率を高めてゆくのが良策です。
番組では上記のほかにも、間伐材を不完全燃焼さて出てきた一酸化炭素と水素の混合ガスを使った発電と、牛の糞尿を発酵させて出てきたメタンガスからの燃料電池用水素の製造(両方とも岩手県葛巻町)や、乳牛の糞尿由来のメタンガスを使った発電(北海道士幌町)も紹介されました。現在はバイオマス専用の施設や機器の導入に割高なコストが掛かりますが、将来的需要の増加や技術革新で低価格化が期待できます。枯渇のおそれがなく、廃棄物を出さない太陽光や風力などの自然エネルギーとともに、将来を見据えた政策展開によって可能性が広がるでしょう。












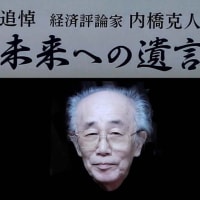


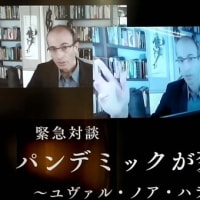










「バイオマス」「ホット・スポット」の用語はよく分かりました。
細かいことですが、マイヤーズ博士の綴り
は、Norman Myersであり、彼は「豊かさの環境への影響」について発言しており、とくに熱帯林の保全に努める一方、"biodiversity"という概念を提起しているようです。ご確認下さい。
それと、New GAIA Atlas of Planet Manage-ment (2005) は1993年版を書き改めたもののようですが、10年のうちに執筆の姿勢に顕著な変化は見られたでしょうか。この点もお教え願えたら幸いです。
マイヤーズ博士の英文綴りの初歩的誤りをご指摘有難うございました。本文を早速訂正しておきました。博士の活動は広範囲にわたり、ご指摘のように初稿ではイントロダクションが欠けていたので、博士の生物多様性の問題に関するパイオニア的活動や、環境と経済にわたる分野での活動を、PART 2に加筆しました。
GAIA ATLASについては、私は1993年版を見ていないので確答になりませんが、ウェブ上で見た目次等調べてみました。2005年版ではデータがアップデートされている以外に、消費、グローバル化、環境安全保障、難民、国際テロリズム、情報科学、中国台頭が加わったようです。大勢の著者達の執筆によるので、執筆姿勢を一概に比較できませんが、状況が好転したと見ていることはないでしょう。なお、2005年版の日本語版は未だ出ていません。
かつて第34代米国大統領アイゼンハワーは、旧ソ連に対する軍事的優位を重視しながら、「全ての武器が貧しい人々を飢え、凍えさせるとの言葉を残し」、軍産複合体の拡張に警告しました。ところが現米政権は国家の安全保障より、石油産業や軍産複合体の安泰を優先しています。水戸黄門の世界のように、「この紋所が目に入らぬか」で一件落着とは行きません。個人レベルから公的レベルへ発想の転換を伝えるのは確かに恐ろしいほど時間がかかりますが、究極的には米国の有権者がより賢明な選択をするような環境ができないといけないのでしょう。現在がマイヤーズ博士等の言うように重要なターニング・ポイントであると知りながら傍観者でいることは、博士の言葉を借りると今のままの推移を是認していることになります。実情をよく知らない人も大勢いるのでしょう。毎日歯を磨きながら何かできそうなことを考えてみてください。OxfamのHPから各方面に抗議のメールを送ることもできます。以下はマイヤーズ博士の講演の抜書きです。
科学者は、ある問題に対して自分たちが沈黙を守ることが、「大して心配することはないよ」という明確なメッセージを送っているのに等しいのだと認識すべきだと思う。問題に対して何も証言しないことは、「大丈夫だよ」という証拠をほのめかしているのと同じなのである。その結果、当然、政治家は行動を起こさず、しかしながら、急速に変化する世の中においては、行動しないこと自体が多くの行動を起こすのと同様の結果を招くことにもなるのだ。要するに、こうした状況下では、科学者の不当な沈黙が、結果的に無謀な事態につながりかねないのである。
私は北海道育ちなので、バイオマスエネルギーには以前から興味がありました。やはり、酪農が主幹産業の北海道では、次世代を担うべきエネルギーだと思います。確か、電力会社や大学がすでにモデル地区(これが士幌町なんでしょうかね?)において始めているというのを、何年か前の新聞で目にしました。
先生のような長年、研究に携わってきた方がこうして私たちにむけて情報を発信してくださるのは非常にありがたいことです。自分なりの意見を考えるきっかけにしたいと思います。
テレビ番組の内容を付記すると、乳牛1頭は1日に60kgの糞尿を排泄し、道全体で年間2000万トンに及ぶそうです。士幌町のバイオガス・プラントは国の補助金で設置され、320頭の乳牛の糞尿から発生するメタンガス(一日ドラム缶3000本分)を使って発電した電力の4割を内部で使用し、残りを売電(1月12万円)に回しています。以前は月10万円電気代を支払っていたそうです。発酵後の消化液も肥料として牧草地、飼料畑、地域の畑作農地で有効利用されています。バイオマス・プラントの設置にイニシアルコストが掛かりますが、放っておけば土壌や水質汚染を引き起こす糞尿を使ってエネルギー需給率が上がられるのですから、長期的視野で有効な選択肢だと思います。
これからも、どしどし応援のコメントを寄せてください。