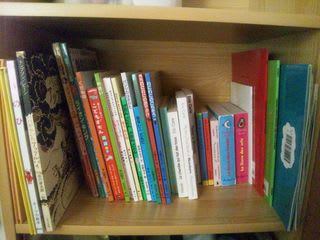べべちゃんの本棚(後編)
前編では日本語の絵本を紹介したので、後編では外国語の絵本を。
コチラの絵本は、ほぼ私の学生時代の趣味。
【英語】
「GUESS HOW MUCH I LOVE YOU」Sam McBratney
邦題は「どんなにきみがすきだかあててごらん」だったかな。
大きいうさぎと小さいうさぎの掛け合いがかわいらしいのだけれど。
べべちゃんはあまり...だったらしい。
「Today Is Monday」 Eric Carle
邦題は「月ようびはなにたべる?」
アメリカの童謡にイラストをつけたものらしい。
食いしん坊なべべちゃんは、いつも最後のみんなの食事シーンをながめてます。
「My Very First Book of Numbers」 Eric Carle
上下半分のところに切れ目が入っていて、別々に開ける仕組み。
上部の各ページには、数字と、その数だけ書かれた四角
下部は10種類の果物のイラストが、それぞれ1から10こずつかかれている。
上部の数字と、下部のイラストの数を合わせることによって、1から10までの数を学べる仕組み。
果物のイラストが好きなべべちゃんは、結構頻繁に眺めていました。
ただ、名前を聞かれても、日本ではあまり見られない洋ナシやプラムの説明が難しい...
「The Tiny Seed」 Eric Carle
邦題は「ちいさいタネ」
一時期かなりお気に入りで、一日に何回読まされたことか...
男の子が女の子に花をプレゼントするところが一番のお気に入り。
「Draw Me a Star」 Eric Carle
邦題は「おほしさまかいて!」
後半の絵描き歌みたいなところで、歌いながらべべちゃんの手を取ってなぞってあげたら、それがかなり気に入ったみたいで。
そのページを開けて持ってきては、指を持ってなぞれとせがまれる。
「Little Cloud」 Eric Carle
邦題は「ちいさなくも」
雲が形を変えて育っていき雨を降らせる話。
特にここが気に入っている!という箇所はなさそうだけれど、エリックカールつながりでよく持ってきた本。
「The CATERPILLAR and the POLLIWOG」 JACK KENT
青虫とおたまじゃくしの話。
「大きくなったら、違うものに変わる」と言いふらす青虫と、それに取り合わないほかの生き物たち。
おたまじゃくしだけが興味津々で...
蝶になった青虫と、かえるになったおたまじゃくし。ホントは蝶になれると信じていたのに。
でも、かえるの姿もまんざらではない様子。
まだ、内容を読んで欲しいわけではなさそうだけれど、一応パラパラとイラストを見て楽しんでいる様子。
べべちゃんは蝶とかえるが好きだから。
「Animals should not definitely not wear clothing.」 Judi Barrett, Ron Barrett
どうして動物が服を着てはいけないのかが、それぞれの動物の特徴を使っておもしろく紹介している。
べべちゃんはパラパラとイラストを見るのがおもしろいみたい。
【フランス語】
「Le livre des bruits」 Soledad Bravi
日本語で言うところの擬音語が見開きで1つずつイラストと言葉で紹介してある。
結構気に入っていて、好きなページを開いては眺めてみたり、実際のものと照らし合わせて確認してみたり、読んでと持ってきたり。
「Le livre des cris」 Soledad Bravi
いろいろな動物の名前と鳴き声が紹介されている。
上のbruitsと同じシリーズなんだけれど、こちらはイマイチ受けが悪いみたい。
「La chenille qui fait des trous」 Eric Carle
邦題は「はらぺこあおむし」
やはり食いしん坊のべべちゃん。穴が開いた食べ物のページを触ったり、眺めたり。気になるご様子。
「Petit Ours Brun et le pot」
こぐまがおまるを使う話。途中、座りながら遊んでみたり、お菓子まで食べて、最後はお母さんに見せに行く。
これに出てくるおまるも、うちのとおそろいの形。
でも、イマイチ触発されない...
「Petit Ours Brun dit Non」
こぐまが、お母さんに何を言われても「いやだ」を繰り返す。
最後にお母さんがこぐまに、「イヤだって言ってばっかりなの?」と聞くとこぐまは「いやだ!いやだ!」
最後はやっぱりお母さんの勝ち。
「La robe de Noel」 Satomi Ichikawa
森のもみの木がクリスマスツリーになることを夢見る話。
文はかなり長く難しいので、べべちゃんは途中で飽きてしまうのだけれど、
イラストがキレイで、気に入っているのか、クリスマスの頃はよく持ってきてひざの上でパラパラめくっていた作品。
前編では日本語の絵本を紹介したので、後編では外国語の絵本を。
コチラの絵本は、ほぼ私の学生時代の趣味。
【英語】
「GUESS HOW MUCH I LOVE YOU」Sam McBratney
邦題は「どんなにきみがすきだかあててごらん」だったかな。
大きいうさぎと小さいうさぎの掛け合いがかわいらしいのだけれど。
べべちゃんはあまり...だったらしい。
「Today Is Monday」 Eric Carle
邦題は「月ようびはなにたべる?」
アメリカの童謡にイラストをつけたものらしい。
食いしん坊なべべちゃんは、いつも最後のみんなの食事シーンをながめてます。
「My Very First Book of Numbers」 Eric Carle
上下半分のところに切れ目が入っていて、別々に開ける仕組み。
上部の各ページには、数字と、その数だけ書かれた四角
下部は10種類の果物のイラストが、それぞれ1から10こずつかかれている。
上部の数字と、下部のイラストの数を合わせることによって、1から10までの数を学べる仕組み。
果物のイラストが好きなべべちゃんは、結構頻繁に眺めていました。
ただ、名前を聞かれても、日本ではあまり見られない洋ナシやプラムの説明が難しい...
「The Tiny Seed」 Eric Carle
邦題は「ちいさいタネ」
一時期かなりお気に入りで、一日に何回読まされたことか...
男の子が女の子に花をプレゼントするところが一番のお気に入り。
「Draw Me a Star」 Eric Carle
邦題は「おほしさまかいて!」
後半の絵描き歌みたいなところで、歌いながらべべちゃんの手を取ってなぞってあげたら、それがかなり気に入ったみたいで。
そのページを開けて持ってきては、指を持ってなぞれとせがまれる。
「Little Cloud」 Eric Carle
邦題は「ちいさなくも」
雲が形を変えて育っていき雨を降らせる話。
特にここが気に入っている!という箇所はなさそうだけれど、エリックカールつながりでよく持ってきた本。
「The CATERPILLAR and the POLLIWOG」 JACK KENT
青虫とおたまじゃくしの話。
「大きくなったら、違うものに変わる」と言いふらす青虫と、それに取り合わないほかの生き物たち。
おたまじゃくしだけが興味津々で...
蝶になった青虫と、かえるになったおたまじゃくし。ホントは蝶になれると信じていたのに。
でも、かえるの姿もまんざらではない様子。
まだ、内容を読んで欲しいわけではなさそうだけれど、一応パラパラとイラストを見て楽しんでいる様子。
べべちゃんは蝶とかえるが好きだから。
「Animals should not definitely not wear clothing.」 Judi Barrett, Ron Barrett
どうして動物が服を着てはいけないのかが、それぞれの動物の特徴を使っておもしろく紹介している。
べべちゃんはパラパラとイラストを見るのがおもしろいみたい。
【フランス語】
「Le livre des bruits」 Soledad Bravi
日本語で言うところの擬音語が見開きで1つずつイラストと言葉で紹介してある。
結構気に入っていて、好きなページを開いては眺めてみたり、実際のものと照らし合わせて確認してみたり、読んでと持ってきたり。
「Le livre des cris」 Soledad Bravi
いろいろな動物の名前と鳴き声が紹介されている。
上のbruitsと同じシリーズなんだけれど、こちらはイマイチ受けが悪いみたい。
「La chenille qui fait des trous」 Eric Carle
邦題は「はらぺこあおむし」
やはり食いしん坊のべべちゃん。穴が開いた食べ物のページを触ったり、眺めたり。気になるご様子。
「Petit Ours Brun et le pot」
こぐまがおまるを使う話。途中、座りながら遊んでみたり、お菓子まで食べて、最後はお母さんに見せに行く。
これに出てくるおまるも、うちのとおそろいの形。
でも、イマイチ触発されない...
「Petit Ours Brun dit Non」
こぐまが、お母さんに何を言われても「いやだ」を繰り返す。
最後にお母さんがこぐまに、「イヤだって言ってばっかりなの?」と聞くとこぐまは「いやだ!いやだ!」
最後はやっぱりお母さんの勝ち。
「La robe de Noel」 Satomi Ichikawa
森のもみの木がクリスマスツリーになることを夢見る話。
文はかなり長く難しいので、べべちゃんは途中で飽きてしまうのだけれど、
イラストがキレイで、気に入っているのか、クリスマスの頃はよく持ってきてひざの上でパラパラめくっていた作品。