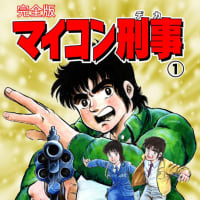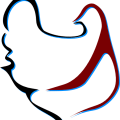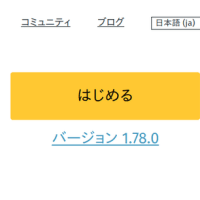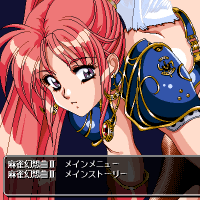教えて!gooにたまに次のような質問の類似質問が投稿される。
自分がおすすめするバトル漫画を教えてください
これだと思うものを一つだけお願いします。
う〜〜む・・・・・・。
ところでバトル漫画って何?
例えばWeblio辞書だと次のような事が書かれてある。
登場人物が戦い(バトル)を繰り広げる様子が中心的に描かれる漫画の総称および区分(ジャンル)。戦闘シーンの描写の迫力や、心理戦・頭脳戦の緊迫感、あるいはキャラクターの心身の成長などが主な醍醐味といえる。
バトル漫画におけるバトルは、必ずしも1対1の格闘を指すとは限らない。作品世界独自の特殊能力を駆使して戦う「能力系バトル漫画」はバトル漫画の下位区分(サブジャンル)として半ば確立している。また、料理対決を中心に展開されるグルメ漫画が「料理バトル漫画」と呼ばれることもある。
戦いが中心に描かれる漫画でも、極限の状況におけるバトルロイヤルを強いられてキャラクターが次々と脱落している様子を描いた作品は「デスゲーム系」と区分されることが多い。
しかし、これを読んでみても良く分からん。っつーか説明がおかしい。
「登場人物が戦いを繰り広げる様子が中心的に描かれる漫画の総称および区分」とか書いてるけど、だったら野球漫画はバトル漫画なのだろうか?いや、野球漫画は野球漫画だろう。
サッカー漫画はサッカー漫画だし、剣道漫画は剣道漫画である。要するに総称的にバトル漫画、なんて認識は我々はしてないのだ。
ピクシブ百科辞典なんかでもおかしな説明になっている。
漫画のジャンルの一つであり、手塚治虫以降の少年漫画で最も発展したジャンルの一つ。
主人公と敵との戦いを主軸に置いている作品のことを指す。
いや、んな事言っちゃうと少年漫画=バトル漫画だろうが。鉄腕アトムはバトル漫画なんだろうか?仮面ライダーは?全部バトル漫画のサブジャンル?
これらの説明はおかしいし、バトル漫画の説明に実はなっていない。
一体どういう事だろうか。
ハッキリ言ってやろう。
バトル漫画なんつージャンルは存在しないのだ。
少なくともかつては存在しなかった。
じゃあ、新しく出てきた新ジャンルなのか?と言うとそれも実は違うのだ。
どっちかっつーと説明がしづらいジャンルにバトル、と言う単語を当てはめた、って言った方が正しい。
今、漫画で・・・とか言ってるけど、例えば、ジャンルとしてはラノベなんかでもバトルものと言った体で定着している。これはむしろ小説と言うジャンルでは割に新形態ではある。っつーか、小説だと「アクション」を書くのが難しい・・・って思われてたわけだが、今のラノベ作家は頑張って新境地を開拓している。
で、彼らの脳内でのモデルはハッキリ言って決まってる。鳥山明のドラゴンボールだ。つまり、バトル漫画やラノベのバトルもの、と言われるジャンルが仮定しているモデルってのは要するにドラゴンボールであって、ドラゴンボールみたいなアクションがある話を暫定的にバトル漫画/バトルもの、って呼んでるんだな。従って、実はニュアンスだけ、であって厳密な定義ではない。
ところで、実は個人的にはドラゴンボールってのは一回も読んだことがない。すいません(笑)。
いや、正確に言うとドラゴンボールの初期だけ、は読んだ事があるんだけど、そもそもあんまジャンプを読んでなかった事もあって、結果本編がどんな話なのか、ってのは知らんのだ。ピッコロ大魔王、とか名前は聞いた事がある、って程度である。
っつーか、個人的には、鳥山明って言えばドラゴンボールよりDr. スランプなんだよなぁ。
とまぁ、その辺の話はさておき。
一応、ドラゴンボールを始祖とする・・・わけじゃないんだけど、いわゆるバトル漫画と言われるジャンルの歴史を紐解いてみよう。まあ、個人的見解だ、とか言われたらその通りなんだが、多分歴史に言及した人とかいねぇんじゃねぇか、とか思ったから、だ(上の2サイトの説明が説明になってない原因がその辺だろう)。
と言うわけで、曲がりなりではあるが、個人的にまとめておこうと思う。
まずバトル漫画のルーツとは。
これは実は大まかにはスポ根漫画、と言われるジャンルの一つであった、と考えて良いだろう。要するにさっき挙げた野球漫画の仲間だったのだ。
1970年代、スポ根漫画の全盛期に、当然、野球漫画以外のスポ根モノも存在した。具体的に言うと空手等の拳法系漫画だ。当時の有名な漫画の原作者に梶原一騎と言う人がいて、この人はスポ根漫画を大量生産してた。この人はあの有名な「巨人の星」の作者でもあり、ボクシング漫画の金字塔、「あしたのジョー」の作者でもある(著作者名は変名になってるが)。
この時代、彼が手がけた一番有名な拳法漫画はおそらく空手バカ一代だろう。

絵はつのだじろう。若い人はビックリするかもしれないけど、この当時の彼は別にオカルト/心霊漫画専門の作家じゃなかったのだ(他にも、知名度は低いが何と将棋漫画なんかも描いていた)。
ちなみに、この漫画は連載当時大人気で、アニメ化はもとより、実写映画化する程のコンテンツだった。
ところで、先程書いた通り、1970年代以前は良く知らないが、少なくとも70年代でスポ根もの、と言うと殆ど梶原一騎の独占状態だった。
と言うのも、原作者の梶原一騎は元々純文学志望者だったのだが、同時に物凄い肉体派で、スポーツ大好き、なおかつ本人も格闘技をやるほどの人間だった。要するにある種、彼のせいで、スポ根と言うのは「専門性がある漫画」だったのだ。
当時も今も変わらないが、基本的に漫画家志望の人間、なんつーのは青瓢箪である。国民的スポーツ、野球くらいはテレビで観たり、あるいは自らやった経験がある、と言う漫画家はそれなりにいたが、全方位的にスポーツに関心があって、かつ詳しい、なんつー人は殆どいなかったのだ。
結果、リアルな格闘の世界を知ってる梶原一騎は虚実織り交ぜた格闘の世界を描く事が出来たわけだが、そういう「リアルさ」は他の漫画家、あるいは漫画原作者が追従出来るクオリティではない。要するに殆ど、純文学志望のスポーツ新聞専門記者が漫画原作者になっちまったようなモンである。その領域に他の漫画家が入ってくるのは極めて難しい。そういうわけで70年代はこのジャンルに於いては梶原一騎一強時代だったのである。
ところが、80年代に入って、正確に言うと1982年だが、とんでもない革命的漫画が週刊少年マガジンに現れる。その名も「コータローまかりとおる!」と言う。

ハッキリ言おう。バトル漫画の元祖、と言うのはこの「コータローまかりとおる!」である。
「コータローまかりとおる!」の何が凄かったのか、と言うと、今までの専門性が高かった格闘漫画、を単なる漫画(つまりフツーの漫画家が描けるネタ)の領域に落とした、と言う辺りだ。
ポイントとしては
- 実在しない拳法(空手)を格闘の「軸」とした
- リアリティは追求しない
- 代わりにコメディ色を強めた
と言う辺り。事実上、梶原一騎が作り上げた「リアリスティックな」格闘漫画に真っ向から挑戦したのである・・・しかも梶原一騎の殆どお膝下であった少年マガジンで、である。
実際は作者の蛭田達也って人は梶原一騎の漫画の大ファンではあったのだろう。ところどころ、梶原作品の「形式」へのオマージュを入れている。しかし、蛭田は「空手のリアリティ」より話の面白さを重視して、かつ、面白ければ実在しない「拳法」を描いて良いのだ、と漫画界にメッセージを投げかけたのだ。
これはおそらく想像だが、「コータローまかりとおる!」はもちろん当時大人気の漫画だったが、同時に漫画界に投げかけた衝撃はこちらの想像を超えるモノだったのではないか。「あ、リアルさを追求せんでエエんだ」と。
これは漫画家にとっては福音だったんだよな、多分。漫画だ何だで結局一番メンド臭いのは「考証」作業である。梶原一強時代はスポーツモノ、そして特に格闘モノは「考証」が必要で、それが敷居を高くしていた。リアルで実現出来る実際のギリギリのテクニックにウソを混ぜる。その見極めはその範疇での実体験/知識を持ってないと不可能だったのだ。だから漫画のネタとしては二の足を踏まざるを得なかった。
しかし「コータローまかりとおる!」が指し示したのは、話が面白ければリアリティは必要ない、と言う盲点である。結果、格闘漫画に於いて「考証」は必ずしも必要ない、と言う事を示したのである。
事実、「コータローまかりとおる!」の登場以降、デタラメなオリジナル拳法モノが生えまくるのである。雨後の筍の如く。
- 北斗の拳(1983年)
- ドラゴンボール(1984年)
- ジョジョの奇妙な冒険(1986年)
- らんま1/2(1987年)
主だった作品は上の4作品だが、まだまだあるかもしれない。僕が覚えてないだけ、で。かつ皆ある意味お馴染みの漫画だろう。これらはハッキリ言って「コータローまかりとおる!」エピゴーネンである。
この中では、構造的に言うと「コータローまかりとおる!」のクソマジメ版が北斗の拳である。「コータローまかりとおる!」はコメディ色が強かったが、北斗の拳はシリアスに極振りした。が、登場時、「ひでぶ」「たわば」「あべし」と言った断末魔のセリフが大受けしてて笑いを誘ってたのは記憶に新しい。また、北斗神拳、なんつーのはデタラメの極みだった。「コータローまかりとおる!」で開拓された「やっていいんだ」デタラメ拳法を一歩進めた漫画だったのは事実である。
そして北斗の拳の成功が更なる後続を生み出すのだが・・・正直、当時の一漫画ファンとしてはあまりこのテの漫画は、オリジネーターの「コータローまかりとおる!」以外は感心せんかったのは事実である。
まず、ジャンプの鳥山明、サンデーの高橋留美子は、当時既にそれぞれ雑誌を牽引するビッグネームであった。鳥山明の「Dr.スランプ」、高橋留美子の「うる星やつら」それぞれのアニメはフジテレビ系の水曜7:00台で連続放映され、一世を風靡したもんだった。
そういう天才作家二人が、次にモティーフとしてデタラメ拳法モノを選ぶ、となった時、「そっちいくかぁ・・・」って失望したもんだった。正確に言うと、初期のドラゴンボールは違うカンジの漫画だったんだが、軌道修正して「そっち」に走ったのは個人的には凄く残念だったのである。「らんま1/2」もそうだったのね。安直な・・・そう、「コータロー方式」、つまり考証が要らない拳法モノ、と言うのはホント安直な解決策に見えて、「2匹めのドジョウ以降を狙う」ってのはなんだかなぁ、とか思ったモンだった。少なくとも既に人気ベテラン作家であったこの二人が手を出すべきジャンルだとは思えなかったのだ。
また、ここに「ジョジョの奇妙な冒険」を挙げた事を「え?」って思う人もいるだろう。だが、元々ジョジョの第一部と第二部と言うのは、間違いなく「コータロー以降の」拳法モノをその骨格としてる。波紋法、なんつーのは「コータロー方式」の拳法の変種である。
荒木飛呂彦と言う人はジャンプで連載を持っても、割に短命で終わる作家で、でも発想が物凄く良くって、ぶっちゃけ、「玄人受けする」漫画家だった。ハッキリ言えば、ジャンプをサッサと出た方が大成するんじゃないか、と言うカンジの漫画家だったのだ。ジャンプのアンケート方式で継続/打ち切りを決めるのではなく、もっとじっくりストーリーを育てられる雑誌に移るべきなんじゃないか、と言う評価だった。
ところが、荒木飛呂彦はジャンプにこだわった。そして最後に当てた金脈がジョジョの奇妙な冒険だったわけだが、ハッキリ言って、「玄人好みの」漫画家としてはやっぱ安易な方に行っちゃったな、って思ったモンである。
が、結果これが人気が出たお陰でジョジョはジャンプを代表する看板漫画の一つに成長するのである。かつ、荒木飛呂彦の本領発揮はなんて言っても第3部以降に登場する「スタンド」だろう。ここに於いてジョジョは「コータロー方式」から完全に抜け出して化けるのである(人によっては第一部と第二部を珠玉の傑作、とするが、個人的にはやっぱ第三部の「スタンド」以降の方が元々の荒木らしい作風だと思っている)。
とまぁ、ここまで見てきた通り、実の事言えば僕個人はそこまでバトル漫画は好きではない。と言うより、何度も繰り返すが「コータローまかりとおる!」がこのテの漫画のオリジナルかつ最高傑作であって、それ以降のバトル漫画はコータローの「焼き直し」にしか過ぎない、と思っている。
が。
世間の評判的にはむしろコータロー以降の漫画の方、特にドラゴンボールを高く評価していて、そういう意味では僕の目は節穴なのかもしれない。実際、そこまでドラゴンボールが人気が出て何年にも渡って愛される漫画になる、とは全く予想しなかったからだ。
ただ、歴史的な話をすると、ドラゴンボール「以前」に、まずは梶原一騎原作の作品群があって、そして「コータローまかりとおる!」があった、って事を記憶にとどめておいて欲しいだけ、である。
以降余談、である。
1. ラノベ、特になろう系ファンタジーだと、殆どのパターンから言って、作中に天下一武道会に影響を受けてるような「武術大会」が開催される。明らかにドラゴンボールを読んで育った世代がこのテの小説を好んで書いてるのを見受けられる。
2. 拳法漫画を軸として解題してみたが、もう一つの潮流としてはボクシング漫画がある。マガジンの「あしたのジョー」の後、少年サンデーでは「がんばれ元気」(1976年)、そして少年ジャンプでは「リングにかけろ」(1977年)が連載され、両者とも「最初は」本格ボクシング漫画としてスタートした。
が。
後者の「リングにかけろ」は、ブルワーカーやスペースアポロ等の、雑誌の広告に載るようなトレーニング器具を紹介しだしてからおかしな漫画になっていく。技名を大声で叫びながら必殺パンチを繰り出す「とんでもボクシング漫画」に変容していくのだ。もうそこには「リアルなボクシング」もクソもない。
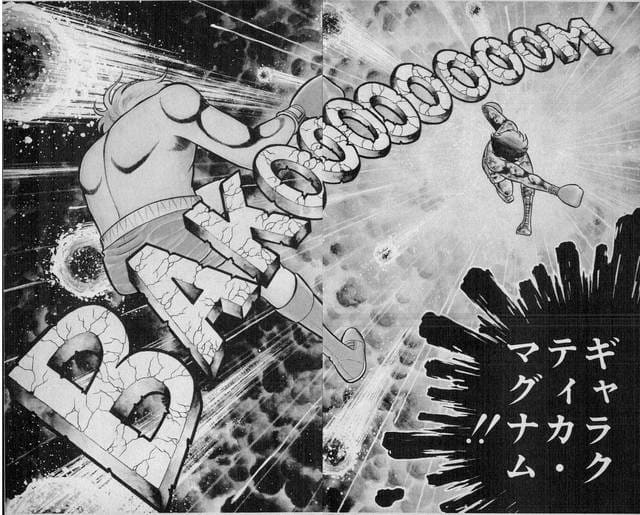
この漫画はコータローより先に出てるので、ある意味今のバトル漫画の元祖はこれだ、と言う見方も可能ではある。が、大ゴマを使った「必殺技」の応酬、と言う現代のバトルものの基礎っぽい展開があるにはあるが、特に後続するエピゴーネンを産まなかった、と思う。多分コータローと比すると一応「シリアス過ぎた」ってのがネックになって、またあらすじがシリアスな割には結構失笑対象になってた、からじゃなかろうか。
とは言っても後のバトルもののプロトタイプや雛形ではあった、とは言えるかもしれない。言いたくねぇけど(笑)。
3. そして第3の潮流として「剣道漫画」があるはずである・・・が、実はこのジャンルはそこまでバトルモノに影響を与えていない。リングにかけろ、のような「とんでも剣道漫画」ってのは多分いまだ出てない、と思う。つまり、後の異世界ファンタジーなんかの「剣術」は「剣道漫画の影響」と言うのはほぼ無い、と言って良い。
実際、必殺技を叫んで相手に打ち込む、ってのは剣道としてはあり得ないわけで(面、とか胴、とかは叫ぶが)、結果ファンタジーで言う「剣術」と言うのは、スターウォーズのへっぴり腰でライトセーバーを振るう、と言う剣道家から失笑を受ける構図の方がむしろ近いかもしれない。