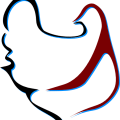坂本龍一が亡くなった。享年71歳。
何度か書いてきてるが、僕が大好き「だった」ミュージシャンだ。一番影響を受けた、って言って良い。
「だった」って書いてるのは、正直言うと、2000年代以降は追ってないから、だ。
かつての教授は攻撃的で、あらゆる音楽を「脱構築する」と言うのが彼の手法の面白いトコで、でもその深い知識に裏打ちされた作成物は、まさしく「音楽図鑑」って言って良かった。非常にエンサイクロペディア的なミュージシャンで、こういう人はホントいないんだよ。
ただ、90年代辺りから、アカデミー賞授与、の影響か、作風が保守的に変質する。極端に歌謡曲に寄せようと迷走したり、過去の作品をピアノを中心に「焼き直し」したり、とそれ以前の教授から見ると考えられないような方向へと向かう。
そんなこんなで僕は気持ちが離れちゃったんだよね。
Y.M.O.なんかも細野さんのアイディアで、「エキゾチックな、つまり東洋的なメロディラインをディスコに乗せる」と言う、当時は(今でも)イカれたアイディアだったんだけど、それを成せたのは坂本龍一の技術の貢献が大きいと思う。
彼の音楽で彼が一番影響を受けたのはドビュッシーなんだけど、ドビュッシー自身がインドネシアのガムラン音楽からインスパイアされていて、要はドビュッシーの「作曲技法」は「東洋音階と西洋音楽を貼り合わせる」「接着剤のような」方法論として編み出された側面がある(だから出来はともかくとして、日本のクラシック的な「合唱曲」なんかもドビュッシーの「方法論」を適用したりしてる)。
つまり、Y.M.O.の、少なくとも当初の音楽と言うのは、細野さんのアイディアを「クラシックに明るい」坂本龍一が、「ドビュッシー以降の編曲技法」を持ち込んで結実させた、と言える。ここでY.M.O.の音楽はクラシックから脈々と続いてきてる「音楽の歴史の流れ」の上にある意味ポジショニングされた、と言えるだろう。
こんな事、フツーの人なら「出来ない」んだわ。基本、「日本的/東洋的音楽」と言うと一般的には演歌だし、じゃなきゃポップス文脈だと「ギャグ」っぽいニュアンスになる。当時でも、そして今でも非常に「危うい」ネタだ。
ところが、Y.M.O.の場合、(ユーモラスではあっても)ギャグにならないギリギリの線を攻められたのは、ひとえに坂本龍一が「ドビュッシー以降の近代編曲技法」を持ち込んできたから、だし、そんな判断が出来たのも「Y.M.O.は遊びの場だった」、つまり、日本で強かった「歌謡曲ビジネス」の外側にいられた、と言う幸運のお陰だった。
いずれにせよ、技術的な面から言うと、言わずもがな、Y.M.Oの成功は坂本龍一の編曲に於ける「技術力」の貢献が大きかったと思う。
そしてこんな人は今後、多分50年間は世界レベルでも現れないだろう。
しかし、これでテクノ系のバンドはオリジナルメンバーだともう見れなくなっちまった、って事だ。
- テレックス: マルク・ムーランが2008年に死去。
- ディーヴォ: オリジナルメンバーだったアラン・マイヤーズ(ドラム)は2013年に死去。また、ボブ・キャサール(ギター)は2014年に死去。
- クラフトワーク: フローリアン・シュナイダーが2020年に死去。
そして今年、Y.M.O.のオリジナルメンバーのウチの二人が亡くなった。
一つの時代が終焉を迎えた、って事だろう。
さて、坂本龍一にはゲーム音楽作成がたった一つ、だけある。以前書いた事があるが、PCエンジンのRPG、天外魔境ZIRIAのテーマ曲がそれ、だ。
[GAME BGM] タイトル画面 - 天外魔境 ZIRIA (PCE)
僕が以前、「和楽器を導入しただけで和風になるワケがない」って書いたのは、そう、坂本龍一の影響からだ。と言うかこういう坂本龍一の音楽的な「ぶっ壊れ加減」が大好きだったんだ(笑)。異質なモノ同士のミクスチュア「こそ」に彼の才覚が現れる。
こういう彼の「作風」はこの時代、特徴的だった。
YMO - 以心電信 You've got to help yourself
「以心電信」なんかは後期Y.M.O.の曲らしく、その殆どはいわば「フツーのポップス」の範疇なんだけど(※1)、ブリッジで唐突に、それまでの文脈とまるで無関係な「和風の」フレーズが挿入される。ここも恐らく教授の仕事だろう。
別に和楽器を使うか使わないか、ってのは重要じゃないんだ。だから彼の「やり方」に慣れてると、「単に和楽器を使ってみました」って楽曲は浅く思慮に乏しく、クソに思えるわけ。
天外魔境の話に戻ろう。
実はこの時教授は、ゲーム音楽の仕事を請けたくなく、無茶を承知でハドソンに「ギャラに1億円要求する」と言う無茶振りをしたらしい。それで断るかな、と思ったら意外にもハドソンはその振りを受け、それで1億円で制作したテーマ曲が天外魔境ZIRIAに取り入れられた、と。まぁバブルな時代の話だよな(笑)。
本当かどうかは知らない。あくまでそういう噂がある、って話だ。そして実際問題、天外魔境ZIRIAだとテーマ曲以外は教授の仕事じゃないんだ(変奏曲を合わせても三曲程度だろう)。
このように、教授はなんだか良く分からん事もやってる。いわば「偉大な作曲家」ではあるけれど、性格的には難がかなりあったと思われるんだよな。例えばある映画Aに対して「映画音楽のテーマを書いてくれ」って言われて書くけど、そこで書かれた曲を映画Bに流用する、とか(笑)。フツーはそんな事「やっちゃいけないだろ」って思うんだけどやっちゃってる人でもあるんだ(※2)。
その辺、特に1990年前後の話だけど、岡田斗司夫のインタビューなんかを合わせて評されるべきだろうな、とは思う(※3)。ちょっとこの辺の話は、「音楽家としての評価」とはまた別で、多分今後色々とこぼれ出てくるんじゃないか(※4)。
ある意味、「ワガママ放題やりたい放題」が「才能を言い訳に」許された、最後の世代の人ではある。
さて、教授と言えば「戦メリ」と思われている。まぁ、一般的にはそうだし、教授の「ドビュッシー趣味」がモロに出てる曲だ(笑)。
でも、個人的に「どの教授の曲が一番好きか?」と問われたら、やっぱり「千のナイフ」がマイ・ベスト・フェバリット、だと答えよう。と言うか古今東西あらゆる曲の中でダントツで好きだ。
東洋音階を使ってながらワケの分からんメロディライン、東洋的な意味での牧歌的フレーズのブリッジ、そして現代音楽的な意味不明の調性が曖昧なフレーズでのブリッジ。どこを取っても完成度はサイコーだ。
と言うか、実の事を言うと、僕はいまだに「この曲が理解出来ない」。「理解出来ない」トコが魅力になる、なんつーのはフツーはないんだけど、「何だこれは」がいまだ続いてるわけだ。
なんつーんだろ、ある曲が「完全に理解出来る」ってのは、その作曲家がその曲を作った「過程」さえもシミュレート出来る事だと思うんだよな。「こういう意図だからこうしたんだろう」と。その結果が和声なんかで現れるわけでしょ。だから見様見真似で「真似する事」はある程度出来る筈なんだ。
ところが、「千のナイフ」はぶっちゃけ、いまだ分からん。何をどう発想すれば、特に「現代音楽的な意味不明の調性が曖昧なフレーズ」を思いつくんだかサッパリ分からんのだ。当然そこで使われてる和声も「何がどうなって」こうしたんだか全く見当が付かない。それくらい「凄い」部品でこの曲は構成されてるんだよ。
「なんだろ、なんだろ」ってのはいまだ継続している。教授でさえこのテの曲は(知ってる限り)3曲程度しか書けなかった。つまり、彼が若く、才気走ってた、まさに一時期にしか思いつけなかった珠玉の作品、だと思ってる。だから色褪せない。そして「解読できない」音楽としてそこに永遠に横たわり続けるんだ。
ちなみに、随分と前、あまりにこの曲が謎過ぎて好き過ぎて、積年の恨みを晴らすが如くコピーを試みた事がある(※5)。
【初音ミク】 Thousand Knives 【坂本龍一】
コピーはしたけど、やっぱいまだにこの曲は謎でフェバリットだ。
色々とありがとう、教授。
教授には「和声の面白さ」を教えてもらったよ。
本当にありがとう。
Rest in Peace!
※1: とは言っても、いわゆる「サビアタマ」のこの曲、以心電信の英詩での「世界がどう回るか見てご覧、自分で自分を助けなきゃ。世界がどう回るか見てご覧、そしたら誰かを助けられるだろう」の部分は「調性が曖昧」(長調なんだか短調なんだか良く分からん事)になっており、この辺の「無調性」っぽい仕事も坂本龍一が主導だろう。こういう「調性が曖昧」と言うのもポップス、と言うより現代音楽的な仕事となる。
※2: 契約がどうなってんだか分からんが、レーザーマン、と言う1988年の香港映画の話。このテーマ曲作曲が坂本龍一の仕事だが、何故かこの曲の別バージョンがハリウッド映画「ブラックレイン」の劇判に転用される。
香港側が作成した契約が甘かったのかどうかは知らないが、割に教授は「仁義を考えればやらんだろう」事をこうやってする。あるいは、発言と違って香港等を下に見ていたのか。
ゲームやアニメを「下に見てた」って事は割にあり得る話だ。
(ゲームに付いては、「シンセサイザー奏者」の割にはチープな電子音が嫌いだったらしいが)
※3: 本人の評がどうあれ、実は僕が一番好きな坂本龍一の映画音楽は「オネアミスの翼」だ。楽曲の完成度も高いし、「坂本龍一じゃないと成し得なかった」劇判になってると思う。
※4: Y.M.O.の「Behind the Mask」と言う曲は教授の(世界的な意味での)代表作、だと捉えられてるが、実は初出の「Solid State Survivor」と言うアルバムでは高橋幸宏との共作、としてクレジットされている。
誤植なのか、と思われたが、実はそうではないらしく、後年高橋幸宏がその辺を音楽関係者にインタビューされた時、「あれはもういいんです」と歯にモノが引っかかったような返しをしていた。
つまり、実際は「高橋幸宏が関わっていて」、そしてその「権利」に付いては二人で揉めた上に「高橋幸宏が引いた」と言う事だろう。
また、「子猫物語」と言う映画の映画音楽を担当した際、「これからはグループで(映画音楽)プロジェクトを請ける」と発言してて、実は実際は「ラストエンペラー」まではその体制になっていて、日本側音楽スタッフでは当時、教授の回りにいたMIDIレコードのアーティストである野見祐二や上野耕路がいた。
ところが、ラストエンペラーでアカデミーを獲った時、彼らの名前はまるで出ず、あたかも教授単独で音楽を作ったような扱いになっていて、サポートした二人の名前は全く出なくなり、また、その後は単独で映画音楽をやるようになっていく。
なんか、性格的には一種「ジャイアニズム」な人だったんだろう。
※5: なんか「千のワイフ」って言うギャグは理解されてないみたいだ(謎