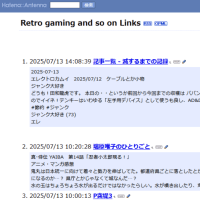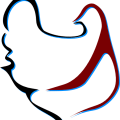「goo blog 終了」を受けて、こういう事を書いてる人たちが多い。
- 親しくなった皆さんとお別れになるのがツラい
と。
要は「goo blog」と言うコミュニティの消失を嘆いているわけだ。
いや、気持ちは分かる。
ホント、思い入れが強い事が書かれている記事ばっかで、涙溢れて読めない・・・・・・・(泣

なんてな(笑)。
いや、ホント、「goo blogを二十年も使ってきて・・・」って書いてたりする記事も散見するんだけど、ゴメン。マジで二十年もブログを使ってきてブログってのはどういう機能を持ってるのか全く知らない、って事にビックリしてる。
学ばない貴方が悪いのか、それともユーザーの囲い込み戦略を立ててたgoo blogが凄いのか。
あれだよな、goo blogが親で貴方が子だとすれば、goo blogって殆どネグレクト状態なんだよ。親が子供に充分な情報を与えず、囲い込んで閉じ込めて、外部を見せない、とかどんな虐待なんだ、って話であって。
そして意外な事に、「虐待を受けた子供」ってそれでも親に信頼と親愛の情を持ち続けるんだよな。
人間って哀しい存在だ。
さて、「ブログで知り合った知人」とかコミュニティ、とか一体何を指してんだろう。
例えばこれの事なんだろうか。

ここで互いに知り合ったブログ同士でやり取りして、それが無くなるのが悲しい、とか?
いや、ハッキリ言うと、僕がgoo blogを始めた時、
「ナニコレ?goo blog内の情報しか受け取れないの?ダサッ!」
ってのが感想だったんだ(笑)。
え、こんな貧相な機能の実装を提供なんてあり得ないだろ、と。
確かに、ブログに貼っつけられた「フォロー」ボタンとか?便利って言えば便利ではある。
しかしもっと本質的な問題があるんだ。
それを説明していこう。
例えばテキトーなブログを閲覧してみよう。

ブラウザのスナップショットだが、敢えてマウスポインタも撮影している。
ブラウザのアドレスバーの右側にマウスポインタがあるのが分かるだろうか?
そこが指してるアイコンは、色の違いとかデザイン差がビミョーにあるが、基本はこういうモノだ。

あ、見た事ある、とか覚えがある、って人もいるだろう。これをRSSアイコン、って言う。
RSSとは何か、と言うのはおいおい説明していく。
僕はVivaldiってブラウザを使ってるんだけど、VivaldiだとRSSアイコンをマウスオーバーすると、次のような「説明」が表示される。

フィードってのが何か、ってのも後述しよう。
RSSアイコンをクリックすると、次のようなメッセージボックスが表示される。

うん。なるほど、と。
で、ナニコレ?って言うのは皆思うだろうな(笑)。
とりあえず、その疑問に答える前に、だ。
皆も・・・各々が、ブラウザとしてMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefoxとか、どれを使ってるか知らんけど、テキトーなブログ(友達のブログでもいいし、芸能人のブログでもいい)を開いて、アドレスバーの右側を見てご覧。恐らく同じような「RSSアイコン」があって、マウスオーバーしたり、クリックする事が出来るだろう。
試してみて欲しい。
さて、RSS及び(RSS)フィードと言われるモノを説明していく。
と言うか、根本的かつ一般的な、ブログの性的静的Webページに対する優位性に対する説明だ。
一般的に静的Webページが出来ない(※1)事で、(殆どの)ブログ(と言うかCMS)がやってのけてる事に記事の更新通知機能がある。
そう、新しい記事が上がった時に、「新着お知らせ」的な情報を送信する機能だ。
RSSはそういう送信機能の総称で(※2)、その情報を受信する為にコピペする一種のコードをフィード、と呼ぶ(※3)。
さて、RSSの機能が定義されたのは1990年代末、から2000年代初頭にかけて、だ。そしてブログがそれを取り込んだ。
一方、RSSが「流行った」のは2010年前後、なんだ。意外に思うかもしんないけど、「新しい技術」が浸透するのって大体10年くらいかかるんだよ。そしてRSSリーダーってのが流行ったのがこの頃なんだ。
しかしながら、RSSリーダーはその後衰退を見せる。何故か、っつーと、RSSリーダーを使いまくってたのは技術者とかIT技術にキョーミがある人前提、で残念ながら一般認知度は然程高くなかった、てのが理由だ。言っちゃえばこの時初めて、ブログと言うソフトウェアに詳しい人とブログが何だか良く分かってない層の二極化が起こった。当然ながら前者は後者より数は少ない。
この頃、例えばRSSリーダーを使う事を駆使してた人は、エロ動画紹介ブログ、エロアニメ紹介ブログ、エロ漫画紹介ブログ、から送信されるRSSを一本化して最新エロ情報を読む、とかやってたんだよな(笑)。
いや、俺はやってないけど(言い訳臭い?・笑)。
このRSSリーダーは技術的な事が大好きな人には大ウケで、RSSリーダーはアチコチで作られてたんだ。有名ドコではGoogle Readerとか米Yahoo!のYahoo! Pipesなんかがあった(※4)。それらサービスは熱狂的なファンを獲得したが、大体2015年前後でそれらサービスを終了したトコが多い(※5)。「熱狂的なファン」は一般的ではない、って言いかえる事が出来るからね。一般人はこれらの「技術者系がアツくなった」ブツを殆ど知らないんだよ。
RSSリーダーブーム(技術者向けだけど)は収束したんだけど、一方、別にRSSの「送信」機能自体が廃れたわけじゃない。ブログはほぼRSS送信機能を実装してるし、貴方が好んだ任意の情報は依然と受信可能なんだ。
ハッキリ言えば、goo blogの「フォローしているブログの新着記事」なんかも、内部的にRSSリーダーだろう。ただし、goo blog限定、っておかしな制限をかけてるのが問題なんだ。ホントだったら、他社のブログの更新情報も読み取れないとおかしい、んだ。このおかしさに関しても後述しよう。
いずれにせよ、例えば貴方が「はてなブログ」を選んで、貴方の、goo blogで知り合った人がAmebaやその他のブログに移動したとしても泣く必要はない。
貴方は彼らの更新情報をRSSで入手出来るから、だ。
「はてな」自身も過去、RSSリーダーのサービスをやっていた。
一方、RSSリーダーはXMLをコピペする、と言う、ちょっと素人目には怖いことを要求するんだよな(笑)。
そこで「はてな」では。RSSのフィードではなく、ブログのアドレスを入れれば自動的にRSSフィードを入手するサービスに軸足を移した。それをはてなアンテナと言う。
Amebaに似たような機能があるかどうかは知らんが(多分、goo blogと同じようなコンセプトだから無いかもしんない)、一方、「はてな」を使う限り、goo blogから去って他社ブログへと移動した、「購読対象」を随時追っかけるのは充分可能だ。
是非とも「はてなブログ」に移動した人は、goo blogのような「読者」機能もあるけど、同時に、「はてなアンテナ」も活用して欲しい。
じゃあ、Amebaはどうなのか。
いや、個人的にはAmebaはHTMLを制限してるって事で引っ越し候補から外してるんで全く、って言う程調べていない。恐らくAmebaもgoo blog同様に囲い込みしかしてないんとちゃうんか。従って、Amebaに、はてなアンテナに比するサービスがあるかどうかも知らん。
ただ、次のような代替策は考えられる。結構goo blogだと使ってるヤツが多そうなんで、Ameba引っ越し組も使い続けるヤツが多いんじゃないか。にほんブログ村とか人気ブログランキングとかだ。
ここでは「にほんブログ村」を取り上げてみよう。
そもそも、にほんブログ村、とかブログランキング(順位付け)システムだと思ってるだろ(笑)?
にほんブログ村とか人気ランキングに参加してるブログに付けられたボタンの例
まぁ、当然そういった側面はある。否定はしない。
もっとも、俺はgoo blogに来てからこのテのボタンをクリックした事はねぇけどな(爆
ところで、だ。上のRSSの説明を理解した人はある程度予想は付いてると思う。
実の事を言うと、にほんブログ村ってのは実質的にRSSリーダーなんだ。
にほんブログ村ではブログ登録者のブログのRSSを受信してそれらの情報を一本化する。こういうサービスをマッシュアップと呼んだりする。
実の事を言うと、にほんブログ村みたいなサービスは、ブログランキングをユーザーへの呼び水にしてるだけ、であって、実質的にはRSSのマッシュアップサービスなんだ。そして登録されてるブログを閲覧して貰って、色んな会社の各個人ブログを統一的に扱って、簡単に読んでもらおう、ってサービスなんだよ。

「にほんブログ村」の登録ユーザーは、同じく「にほんブログ村」登録ユーザーの作ったブログの「読者になる」事が可能だ。解説はここから。
繰り返すが、実の事を言えば「にほんブログ村」の人気ブログランキング、って催しは本懐じゃないんだ(笑)。知らんかったろ(笑)。
そうじゃなくって、むしろ「にほんブログ村」の目的は、ブログ関連のポータルになる事なんだ。要はブログ界のGoogleになる、って事だ。
にほんブログ村から検索すれば、どんなブログだろうと簡単に見つけられる、一種の検索サイトになる事を目的としていて(※6)、そのために呼び水としてブログランキングを行ってるに過ぎない。
いずれにせよ、Amebaに行った人で「Web上での知人がはてなや他のサービスに移動した」で悲しんでる人は、その"知人"がにほんブログ村利用者なら、にほんブログ村の貴方のアカウント上で彼らの更新情報を追う事が出来る。
何も問題はない、んだ。
ところで、「はてなアンテナ」にせよ「にほんブログ村」にせよ、ある意味独立したサービスなんで、ブログの管理画面上で状況が確認出来ない、って辺りで不満に思う層もいるかもしんない。一々ログインして観なければならないのか、と。
まぁ、はてなブログは僕もまだ手を付けてないから分からん。ひょっとして「はてなブログ」の管理画面から「はてなアンテナ」にすぐ移れるかもしんないし、あるいは、ブログパーツとして「はてなアンテナ」を組み込めるのかもしんない。
この辺の事に関しては龍虎氏のブログや、zio氏のブログの続報を待ってよう、とか思ってる(笑)。まぁ、他人任せ、って事だが(笑)。恐らくだが、はてなブログなら「はてなアンテナ」をブログパーツとして搭載可能なんじゃないか、とは思っていて、goo blogのような古典的なブックマークより利便性が高い事になるんじゃねぇの、とか予想してる。
それはさておき、一般的に言うと、「はてなアンテナ」や「にほんブログ村」のログインが面倒くさい、とか思うのなら、単純にブラウザにピン留めしときゃ済む話だ、とか思ってる。それどころか、ブログの管理画面でさえピン留めしときゃエエだろう、と。
- Microsoft Edgeのタブ操作(ピン留めと複製とタブの切り替え)
- ピン留めされたタブ(Mozilla Firefox)
- 【Google Chrome】タブをピン止め(固定)して、よく使うページを常に表示する
あるいは、Windowsなら、ブラウザの「タブ」をピン留する代わりに、スタートメニューやタスクバー(Windowsの画面下方にあるエリア)で「特定のページ」をピン留めする事さえ可能らしい。
- ウェブページをスタート画面やタスクバーにピン留めする方法(Microsoft Edge)
- Windows 10 のタスクバーに Firefox をピン留めまたは解除する方法
- ChromeでタスクバーにWebページをピン留め Part 1
- ChromeでタスクバーにWebページをピン留め Part 2
「ピン留めくらい知ってるよ!バカにすんな!」って人もいるだろう。
いや、本当の事を言うと、そういう人が多い事をむしろ望んでるんだ。
しかし、実際のトコ、以前書いたが、世の中、パソコンにデスクトップ撮影の機能が実装されてる事さえ知らない人間が結構多いんだ。
彼らはパソコンのデスクトップ写真を撮るためにわざわざスマホでパソコンのモニタを撮影する。
そういうタイプの人は、貴方が思うより多いんで、当然、ブラウザのピン留め機能を知らん人間も一定数いるだろう、と仮定してるに過ぎない。
だから「知ってる人が多い」事を望んでるのは本音、なんだよ。
さて、ブログが下火なんでgoo blogは閉鎖する、とか書いてる人が散見するが、ハッキリ言ってそれは事実ではないと思う。人は爆発的にユーザーが増えてる時、それを「流行ってる」と言う。ただし、安定期に入った時、軽々しくオワコンって言うんだよな。
事実は違うでしょ。大体、ブログがマジでオワコンなら、それこそにほんブログ村みたいなサイトは真っ先に潰れる筈だ。
にほんブログ村が潰れてない、って事は貴方が思うよりブログはオワコンではない、って事なんだ。結果、オワコンだとしたらそれは単にgoo blogがオワコンだ、って事なんだよ。
僕がgoo blogに来た時(多分2020年頃?)、単純にgoo blogって閑散としてんな、って印象だったんだ。殆どgoo blogの性質だ。他のブログと混同は出来ない。
要は新規ユーザーが増えてないんじゃねぇの?って印象だったんだよ。精力的に新規ユーザーを獲得しよう、って動きが全くない、って思った。
原因はハッキリしている。囲い込みをやろう、ってのが間違ってただけだ。
ブログのサービスって、要はSNSの登場にビクついてたんだよね(笑)。皆mixiとか覚えてるだろ(笑)?会員制で、外から何が成されているか全く分からない。招待制で簡単にアカウントは取れない。言わば選民思想的なサービスが一斉を風靡した。
んで、ブログによってはそういうSNSのサービスをブログに取り入れようとした、んだよな。goo blogもそういった間違った方針を持ったサービスなんだ。
そもそも、ブログを使うヤツってのは公開Web日記を書きたい、って欲求が大きいわけじゃない。非公開にしたい、ってヤツはそもそもブログを使わない。
ところが、その辺勘違いして、旧NTT レゾナントとか、管理画面をSNS化する、ってバカな事をやったんだよな。それは公開されているブログ側で行うべき事なんだ。何度も書いてるけど、マルシェルみたいなサービスをブログ管理者側に於いてのみ行う、とか間違った方針に過ぎない、んだよ。
結果、goo blogってのは周りから見るとちっとも盛り上がってるように見えない。だから新規ユーザーを獲得出来ないわけだ。
大体、非公開が前提の機能を公開が前提のブログに取り込もう、なんつーのはおかしいだろ。コンセプトが真逆なんだ。真逆のモノを取り込もう、なんつーのはアタマのおかしい決定に過ぎない。
結果、goo blogが盛り上がらないのはブログユーザーのせいじゃなくって、NTTレゾナント及びNTT docomoの単なる失策、だ。そして繰り返すが、結果goo blogがオワコン化したのはユーザーのせいでもないし、ましてやブログ全般がオワコンになってるわけでもない、んだ。
「はてなブログ」へと移る人たちはこれから「本物のブログサービス」で「ネットの自由」を満喫する事となる。そして如何にgoo blogで「色々とネグレクトを受けていた」事実を実感する事となるだろう。
言える事はこうだ。「はてなブログで幸あれ」と。
※1: 実際は「出来ない」んじゃなくって、古き良きWebサイト構成だと実装してないって言った方が正しい。
いわゆる「古典的な」Webサイトだと、単純にHTMLを表示するだけ、と言う簡単な仕組みになってるから、だ。
※2: 厳密には、定義が曖昧。Wikipediaでも参照してくれ。
※3: 大体はXMLで記述されている。
※4: 反面、日本のYahoo!では提供されなかった。ハゲの決定だろう(謎
実のことを言えば、米国Yahoo!と日本のYahoo!はほぼ別会社だ。日本のYahoo!はソフトバンクが半分前後株式を持っていて、結果、米国Yahoo!の日本のYahoo!への決定権はそれほど高くない。
※5: しかし、いまだ、feedlyとか、良質なRSSリーダーのサービスを行っているトコロも存在する。
※6: こういう「登録型」の検索サイト、と言うのは、大昔のYahoo!のようなスタイルだ。覚えてる?大昔のYahoo!はロボット検索を採用してなく、自作WebページをYahoo!に登録して、そこからコンテンツを探す、と言ったかなり限定的なポータルサイトだった。
しかし、現実的な話をすると、ロボット検索でフツーのWebサイトなのかブログなのか、を判別するのは難しい。2つにはHTML的に違いがない、んだ。従って、「ブログユーザーに登録してもらう」ってのは合理的な判断、となる。
かつて、Googleも、ブログやSNSの類が検索スパム(つまり検索結果の質が悪い情報)になり得る事を危惧して、ブログ等は専用の検索エンジンに分け、切り離そう、とした事がある。Googleブログ検索、だな。
ただ、端的に言うとGoogleブログ検索は結果失敗したんだよ。要は、HTMLの仕組みから言うと「ロボット検索がブログだけを抽出する」ってのが難しかったから、だ。
結果、我々は、例えば技術情報で「確実な情報を探したい」のに、曖昧なQiitaの検索結果が上位を占める、とか(笑)。そういう検索スパムだらけの世界に住まなアカンくなってるわけ(笑)。