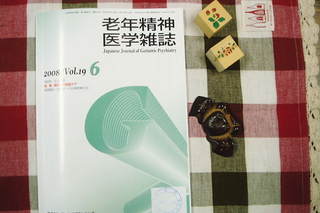
老年精神医学雑誌
の最新号(第19巻第6号、2008年6月)
を勤務する図書館で借りました。(写真はその表紙)
特集として、「最新の認知症ケア」を組んでいます。
この目次が
日本老年精神医学会の事務局である
ワールドプランニング
に掲載されています。
7本の特集論文は、認知症の専門職養成に関するもの3本、認知症ケアの実践に関するものが3本で、いずれも重要なものですが、今日は、冒頭の
加藤伸司(東北福祉大学教授)氏の
「認知症ケアはここまで進んだ」pp.629-635
の要点を紹介します。
【発展の歴史】
○ 1963 老人福祉法の制定
○ 1972 有吉佐和子『恍惚の人』
○ 1980 呆け老人をかかえる家族の会→認知症の人と家族の会
○ 1997 認知症看護認定看護師
○ 2000 介護保険法(グループホームが位置づけられる)
○ 2003 「2015年の高齢者介護」(厚生労働省、高齢者介護研究会)
○ 2004 「痴呆」→「認知症」への呼称変更
【概念の変化・・キーワード風に】
○ 当事者 Christine Borden (邦訳、2003)
○ Kitwood, T. 1997
Demantia reconsidered:The person comes first. Open University Press.
→全人的ケア、生活支援型ケア
パーソンフッド(その人らしさ、個別性)
○ 非薬物的アプローチ
○ バリデーションテラピー
○ BPSD
○ 国際老年医学会(IPA)の功績
*私も知らない用語・概念が多かったです。
→専門分野の方は、サーチエンジンで検索しましょう。
【思い出】
加藤先生(専門は心理学)は、私が北海道に勤務していた頃、同じ「看護福祉学部」の同僚で、お世話になりました。
この論文の歴史で
1984年 「痴呆性老人処遇技術研修」は、私が老人福祉課長のときに大蔵省(当時)と相談して始めたものです。地味な政策ですが、この論文に出ていて懐かしい限りです。
*当時の、大蔵省主計局の厚生省担当主査は、身内に認知症の方がおられたとかで詳しく知っておられた。
の最新号(第19巻第6号、2008年6月)
を勤務する図書館で借りました。(写真はその表紙)
特集として、「最新の認知症ケア」を組んでいます。
この目次が
日本老年精神医学会の事務局である
ワールドプランニング
に掲載されています。
7本の特集論文は、認知症の専門職養成に関するもの3本、認知症ケアの実践に関するものが3本で、いずれも重要なものですが、今日は、冒頭の
加藤伸司(東北福祉大学教授)氏の
「認知症ケアはここまで進んだ」pp.629-635
の要点を紹介します。
【発展の歴史】
○ 1963 老人福祉法の制定
○ 1972 有吉佐和子『恍惚の人』
○ 1980 呆け老人をかかえる家族の会→認知症の人と家族の会
○ 1997 認知症看護認定看護師
○ 2000 介護保険法(グループホームが位置づけられる)
○ 2003 「2015年の高齢者介護」(厚生労働省、高齢者介護研究会)
○ 2004 「痴呆」→「認知症」への呼称変更
【概念の変化・・キーワード風に】
○ 当事者 Christine Borden (邦訳、2003)
○ Kitwood, T. 1997
Demantia reconsidered:The person comes first. Open University Press.
→全人的ケア、生活支援型ケア
パーソンフッド(その人らしさ、個別性)
○ 非薬物的アプローチ
○ バリデーションテラピー
○ BPSD
○ 国際老年医学会(IPA)の功績
*私も知らない用語・概念が多かったです。
→専門分野の方は、サーチエンジンで検索しましょう。
【思い出】
加藤先生(専門は心理学)は、私が北海道に勤務していた頃、同じ「看護福祉学部」の同僚で、お世話になりました。
この論文の歴史で
1984年 「痴呆性老人処遇技術研修」は、私が老人福祉課長のときに大蔵省(当時)と相談して始めたものです。地味な政策ですが、この論文に出ていて懐かしい限りです。
*当時の、大蔵省主計局の厚生省担当主査は、身内に認知症の方がおられたとかで詳しく知っておられた。

























