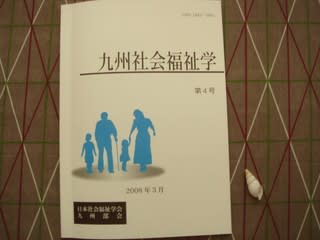
【事務局は、鹿児島に】
社会福祉学を代表する学会は、日本社会福祉学会です。
その学会誌は、『社会福祉学』で、最近では、年4回刊行されています。
今日、ご紹介するのは
日本社会福祉学会九州部会が毎年1回刊行しているものです。
編集委員がおかれ、査読も行われている。
2008年3月20日発行で、これが第4号です。A4版で110ページ。
編集事務局は、鹿児島国際大学福祉社会学部田畑研究室です。
【社会的ひきこもり】
第4号では、論文が5点、研究ノートが2点掲載されています。
そのうち、
笠野恵子「社会的ひきこもりにおける家族支援への一考察」p101-p110
を読みました。
*著者は、この3月、鹿児島国際大学大学院(修士課程)を卒業しました。この論文は、その修士論文の核となる部分をまとめています。
このテーマをGoogleすると、3万点もヒットする大問題です。
「社会的ひきこもりとソーシャルワーク」で検索すると485点でだいぶ絞られてきます。
日本社会福祉学会の学会誌『社会福祉学』では、検索システムが整備されていますが、第47巻第2号(2006年8月)までのところは、「社会的ひきこもり」をテーマとした論文は掲載されていません。
【家族会】
著者は、鹿児島における「ひきこもり」の家族会へ参与観察した結果をまとめています。先行研究は少ないのですが、斉藤環(精神科医)などの研究を手がかりに、ひきこもりの問題の広がりと、その対応を考察しています。
「ひきこもり」は、社会的ひきこもりであり、日本を除いては、これほど社会現象として顕われている国はないようです。
著者は、家族の会との交流を通じて、社会的な問題である以上、社会的な対応が迫られている、という筋道を持っているようです。
その研究姿勢に、私は、いまの日本の社会福祉学が忘れているものを感じるのです。
【研究は遊びではない】
このようなテーマは、いわゆる量的な研究にはなじみにくく、また家族も研究の対象となること自体に抵抗があります。私は、調査法にはとんと暗いのですが、「社会福祉学」など高い評価を得た雑誌に最近掲載される論文には、「いま解明を迫られている問題」よりは「量的調査で精緻な分析で(論文の採択を)差別化する」という研究態度のほうが強いように感じています。それは、アメリカにおけるソーシャルワーク研究の悪しき側面を真似ているようなのです。
*調査は、大事です。でないと、社会から、単なる評論や感想としてしか受けとめられませんから。
社会福祉学を代表する学会は、日本社会福祉学会です。
その学会誌は、『社会福祉学』で、最近では、年4回刊行されています。
今日、ご紹介するのは
日本社会福祉学会九州部会が毎年1回刊行しているものです。
編集委員がおかれ、査読も行われている。
2008年3月20日発行で、これが第4号です。A4版で110ページ。
編集事務局は、鹿児島国際大学福祉社会学部田畑研究室です。
【社会的ひきこもり】
第4号では、論文が5点、研究ノートが2点掲載されています。
そのうち、
笠野恵子「社会的ひきこもりにおける家族支援への一考察」p101-p110
を読みました。
*著者は、この3月、鹿児島国際大学大学院(修士課程)を卒業しました。この論文は、その修士論文の核となる部分をまとめています。
このテーマをGoogleすると、3万点もヒットする大問題です。
「社会的ひきこもりとソーシャルワーク」で検索すると485点でだいぶ絞られてきます。
日本社会福祉学会の学会誌『社会福祉学』では、検索システムが整備されていますが、第47巻第2号(2006年8月)までのところは、「社会的ひきこもり」をテーマとした論文は掲載されていません。
【家族会】
著者は、鹿児島における「ひきこもり」の家族会へ参与観察した結果をまとめています。先行研究は少ないのですが、斉藤環(精神科医)などの研究を手がかりに、ひきこもりの問題の広がりと、その対応を考察しています。
「ひきこもり」は、社会的ひきこもりであり、日本を除いては、これほど社会現象として顕われている国はないようです。
著者は、家族の会との交流を通じて、社会的な問題である以上、社会的な対応が迫られている、という筋道を持っているようです。
その研究姿勢に、私は、いまの日本の社会福祉学が忘れているものを感じるのです。
【研究は遊びではない】
このようなテーマは、いわゆる量的な研究にはなじみにくく、また家族も研究の対象となること自体に抵抗があります。私は、調査法にはとんと暗いのですが、「社会福祉学」など高い評価を得た雑誌に最近掲載される論文には、「いま解明を迫られている問題」よりは「量的調査で精緻な分析で(論文の採択を)差別化する」という研究態度のほうが強いように感じています。それは、アメリカにおけるソーシャルワーク研究の悪しき側面を真似ているようなのです。
*調査は、大事です。でないと、社会から、単なる評論や感想としてしか受けとめられませんから。

























