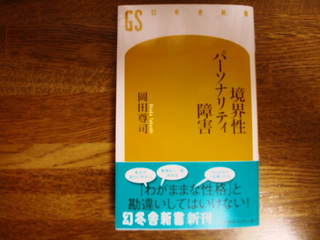
これまでだったら、本屋さんの新刊コーナーでも手に取ることはなかったようなものにも関心がいきます。
というのも、土曜日の、新入院生歓迎パーティの二次会での臨床家たちの話を聞いて触発されたからです。
←第2947号(5/31)
岡田尊司『境界性パーソナリティ障害』(幻冬舎新書123.2009.05.30)を買いました。(写真)
「境界」とは、神経症と精神病の境界のことだという。1938年、アメリカの精神分析家アドルフ・スターンによって初めて使われた。
私自身は、臨床家ではないし、社会福祉や精神医学、心理学を学んだことはないのでごく普通の市民として読んだのですが、本書は、この病気が増えているのは社会のありかたにも深い原因がある・・というメッセージに満ちています。
症例の紹介、原因の究明、対処方法・・と書いてあります。
○ ヘルマン・ヘッセ
○ ジェームス・ディーン
○ 中森明菜
○ 飯島 愛
といった人たちを例にして話を進めています。
年を取ってから、臨床事例に関心を示すようになったのは、この病気の場合のように、
「境界性パーソナリティ障害は、まさに、人が生きるということは何か、何によってそれが可能になるのかという、人間にとっての最も根本的な問題を突きつけてもいる」(p.6)からですね。
うまく伝えられませんが、新書版と言うこともあり、これまで政策系の勉強をしてきた人にも読んで欲しいです。
著者の岡田尊司は、1960年生まれ。東大哲学科を中退して、京大医学部を卒業した精神科医。現在は、京都医療少年院に勤務する。
というのも、土曜日の、新入院生歓迎パーティの二次会での臨床家たちの話を聞いて触発されたからです。
←第2947号(5/31)
岡田尊司『境界性パーソナリティ障害』(幻冬舎新書123.2009.05.30)を買いました。(写真)
「境界」とは、神経症と精神病の境界のことだという。1938年、アメリカの精神分析家アドルフ・スターンによって初めて使われた。
私自身は、臨床家ではないし、社会福祉や精神医学、心理学を学んだことはないのでごく普通の市民として読んだのですが、本書は、この病気が増えているのは社会のありかたにも深い原因がある・・というメッセージに満ちています。
症例の紹介、原因の究明、対処方法・・と書いてあります。
○ ヘルマン・ヘッセ
○ ジェームス・ディーン
○ 中森明菜
○ 飯島 愛
といった人たちを例にして話を進めています。
年を取ってから、臨床事例に関心を示すようになったのは、この病気の場合のように、
「境界性パーソナリティ障害は、まさに、人が生きるということは何か、何によってそれが可能になるのかという、人間にとっての最も根本的な問題を突きつけてもいる」(p.6)からですね。
うまく伝えられませんが、新書版と言うこともあり、これまで政策系の勉強をしてきた人にも読んで欲しいです。
著者の岡田尊司は、1960年生まれ。東大哲学科を中退して、京大医学部を卒業した精神科医。現在は、京都医療少年院に勤務する。


























『境界性パーソナリティ障害』、私も購入しました。まだほとんど読み進めていませんが、隙間時間をみて読んでいこうと思っています。
以前、私の勤務校にも境界性パーソナリティ障害(以下、「境界性」とさせて頂きます)ではないかと思われる学生がいて、担任の教員など対応に苦慮していました。(職員室で大声を上げたり、担任の携帯電話に1日数十回かけてくるなど)人に対する好意と敵意がハッキリしています。
境界性の方は、見た目儚げで手をさしのべたくなる人間的な魅力があるようです。(担任の教員も1時間も2時間も話を聞くなどかなり熱心に最初はかかわっていたようです。)しかし一度親切にすると、要求はエスカレートしていき、それを相手がかなえられなかった時、その相手に敵対的態度と攻撃的行動が出てきます。
勤務校の学生の例でも、同級生や高校時代の教員に「(担任に)見捨てられた」というようなことを言ったりしていたようです。
また、表面的な部分では、統合失調症や解離性同一性障害とも見られるようなところもあるようです。(実際、担任は統合失調症を疑っていました。)
10年ほど前は聞いたこともない症状名ですが、最近はかなり頻繁に耳にするようになりました。
おそらく、今後、高機能自閉症や学習障害など発達障害とともに精神保健福祉分野でも対応を迫られることになるのではないかと考えています。
同書は精神保健福祉士や社会福祉士も一読しておくべき書籍だと思います。
実にタイムリーな紹介だと感心した次第です。
コメントありがとうございます。
私の場合、ずばり境界性パーソナリティ障害の方には出会っていないと思われすが・・
この本を購入したのは、
同僚の先生達の議論を少しは理解したいという想いでした。
私のブックマークにある
「想い・思い・おもい」のどりーむ さんが
今朝、本書を注文したとの記事がありました。
最近は、新しく出る本の感想のようなブログも多く不思議な読書体験ができそうです。
また一人のワーカーとして,このような方に出会った時に,適切に対応することが求められますので,その時の参考にしたいと思います。
とても参考になった紹介です。ありがとうございました。
お役に立てて嬉しいです。
ソーシャルワークも
心理学や精神科の最新の知見を学ぶ必要がありますね。