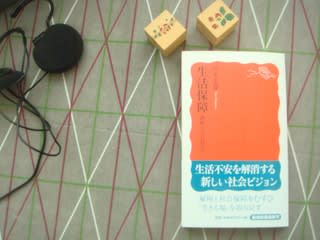
【きっかけ】
昨日、田近先生(経済学)の小論文を読み、スウェーデンの税制についてモデル的に書かれていました。(第3346号)
宮本先生(政治学)も、スウェーデンの政策を随所に参考にして書かれています。
【概要】
岩波書店のサイトに、編集者の推薦と目次がでています。
生活保障
【特色】
日本の最近の事情が国際比較の視点で紹介されています。
巻末の文献リストを見ると、最近話題となった本や古典となった本などがあげられていて参考書として優れています。
日本の各地の優れた実践に目配りされている。
(p.160,p.200)
【疑問点】
「生活保障」とはなにか?
という定義がはっきりしません。
これまでも幾つかの提案(大沢真理)があるようですが、学会では市民権はえてないのでは?
国際的にはどのような概念と近いのでしょうか?
それはそれでいいのですが、「私はこう思う」という人ばかりで、概念についての共通の理解がないのでは、ジャーナリズムの論法と同じではないかな?
という初歩的な疑問が残ります。
「社会保障と雇用を連携した政策」という意味のようでもありますが、それだと「社会政策」(武川正吾)ということでよいのでは?
国際的に長く使われているSocial policyということとどう違うのか?
この分野の一番の問題点は、
日本では、旧国立大学に、「社会福祉」や「社会保障」が単独の学問としては認められずに、経済学や政治学の先生方が「私はこう思う」といろいろの説明をしているころですね。
社会福祉学では、古川孝順先生が「生活支援」という概念で説明しています。
大先生たちがいろいろな概念をいっていて社会的な発言が拡散してしまっているように感じています。
本書のもう一つの鍵概念である「アクティベーション」は、スウェーデンの用語のようですが、これも新鮮ではありますが、「活性化」という日本語とどのように違うのか?
全体に、概念や用語がよくわからないのが残念です。
昨日、田近先生(経済学)の小論文を読み、スウェーデンの税制についてモデル的に書かれていました。(第3346号)
宮本先生(政治学)も、スウェーデンの政策を随所に参考にして書かれています。
【概要】
岩波書店のサイトに、編集者の推薦と目次がでています。
生活保障
【特色】
日本の最近の事情が国際比較の視点で紹介されています。
巻末の文献リストを見ると、最近話題となった本や古典となった本などがあげられていて参考書として優れています。
日本の各地の優れた実践に目配りされている。
(p.160,p.200)
【疑問点】
「生活保障」とはなにか?
という定義がはっきりしません。
これまでも幾つかの提案(大沢真理)があるようですが、学会では市民権はえてないのでは?
国際的にはどのような概念と近いのでしょうか?
それはそれでいいのですが、「私はこう思う」という人ばかりで、概念についての共通の理解がないのでは、ジャーナリズムの論法と同じではないかな?
という初歩的な疑問が残ります。
「社会保障と雇用を連携した政策」という意味のようでもありますが、それだと「社会政策」(武川正吾)ということでよいのでは?
国際的に長く使われているSocial policyということとどう違うのか?
この分野の一番の問題点は、
日本では、旧国立大学に、「社会福祉」や「社会保障」が単独の学問としては認められずに、経済学や政治学の先生方が「私はこう思う」といろいろの説明をしているころですね。
社会福祉学では、古川孝順先生が「生活支援」という概念で説明しています。
大先生たちがいろいろな概念をいっていて社会的な発言が拡散してしまっているように感じています。
本書のもう一つの鍵概念である「アクティベーション」は、スウェーデンの用語のようですが、これも新鮮ではありますが、「活性化」という日本語とどのように違うのか?
全体に、概念や用語がよくわからないのが残念です。

























