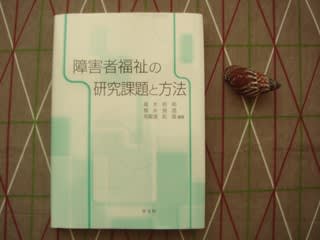
【知的障害のある人が高齢化したら】
高木邦明他編著
『障害者福祉の研究課題と方法』(学文社、2007)を読んでいます。
今日は、その第3章
「知的障害のある人の高齢化と『生活の質』
ー家族と暮らす人の事例を通してー」です。
(p32-p48)
著者は、
西山廣志氏。(共生館福祉医療専門学校専任教員)
【60歳以上の知的障害者】
全国で 23,900人。(2000年)
これは、知的障害者総数 459,000人の5.2%に相当する。
「生活の質」の概念の形成
生活を全体的・多面的にとらえる方向へ転換する役割
先行研究:
河東田博他の「知的障害者の生活の質に関する日瑞比較研究」(1998年)
【調査の実施】
肝属保健福祉圏を対象とした。
この圏域の人口は、2005年で166,381人
(1985年 178,829人)
この圏域の高齢化率は、34%(鹿児島県平均:24.7%)
おおむね50歳以上の5人。調査に同意を得た5世帯。
調査項目
・環境的側面
・内的側面
家族からの聞き取り
・生活史
・本人の満足度
・家族としての苦しみ・悩み・課題
・障害のある人の将来の生活への希望
・身近に相談できる専門職・専門機関
・利用しているサービスの状況、今後必要とする福祉サービス
【調査結果から見た「生活の質」】
・同居する親自身も疾病や介護を要する状態にある
・女性の方が就労できない人が多い
・いずれも障害基礎年金を受給(年金の管理は親または兄弟)
・通所施設やデイサービスなどが身近に準備されていない
*5人の母親のうち3人が介護保険の要介護認定を受けている。
【これからの課題】
・高齢化への一般的な対応である介護保険制度に比較して、知的障害者の場合の対応は遅れている。
・相談支援事業が必須事業として法的に位置づけらたことは前進。
*肝属保健福祉圏において、2006年11月から、職員6人体制で三障害に対応した総合拠点が発足した。
・高齢者の場合に動き始めた「小規模・多機能」型サービス拠点の構築は障害者福祉の分野においても共通の課題。
高木邦明他編著
『障害者福祉の研究課題と方法』(学文社、2007)を読んでいます。
今日は、その第3章
「知的障害のある人の高齢化と『生活の質』
ー家族と暮らす人の事例を通してー」です。
(p32-p48)
著者は、
西山廣志氏。(共生館福祉医療専門学校専任教員)
【60歳以上の知的障害者】
全国で 23,900人。(2000年)
これは、知的障害者総数 459,000人の5.2%に相当する。
「生活の質」の概念の形成
生活を全体的・多面的にとらえる方向へ転換する役割
先行研究:
河東田博他の「知的障害者の生活の質に関する日瑞比較研究」(1998年)
【調査の実施】
肝属保健福祉圏を対象とした。
この圏域の人口は、2005年で166,381人
(1985年 178,829人)
この圏域の高齢化率は、34%(鹿児島県平均:24.7%)
おおむね50歳以上の5人。調査に同意を得た5世帯。
調査項目
・環境的側面
・内的側面
家族からの聞き取り
・生活史
・本人の満足度
・家族としての苦しみ・悩み・課題
・障害のある人の将来の生活への希望
・身近に相談できる専門職・専門機関
・利用しているサービスの状況、今後必要とする福祉サービス
【調査結果から見た「生活の質」】
・同居する親自身も疾病や介護を要する状態にある
・女性の方が就労できない人が多い
・いずれも障害基礎年金を受給(年金の管理は親または兄弟)
・通所施設やデイサービスなどが身近に準備されていない
*5人の母親のうち3人が介護保険の要介護認定を受けている。
【これからの課題】
・高齢化への一般的な対応である介護保険制度に比較して、知的障害者の場合の対応は遅れている。
・相談支援事業が必須事業として法的に位置づけらたことは前進。
*肝属保健福祉圏において、2006年11月から、職員6人体制で三障害に対応した総合拠点が発足した。
・高齢者の場合に動き始めた「小規模・多機能」型サービス拠点の構築は障害者福祉の分野においても共通の課題。

























