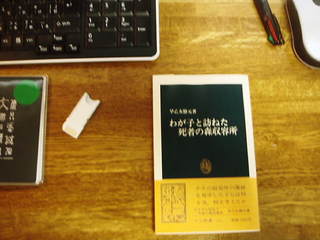
【早乙女勝元】
早乙女勝元『わが子と訪ねた死者の森収容所』(中公新書、1983年)。購入した日付が1983年7月はじめになっていますから、発行されてすぐ求めたことになります。何度か繰り返し読んだのでバタバタになっています。(写真は、その表紙)
私が、この本で紹介されているブ-ヘンバルト強制収容所跡を訪ねたのは、1979年の夏、ドイツに赴任して最初の夏休みのことでした。30年前のあの夏の日のことは、今でも鮮明に覚えています。
*Buchenwald:
Bucheは、ブナの木、Waldは、森 の意味です。ドイツ語読みでブッヘンバルト。英語読みで、ブーヘンワルト。
「死の森収容所」は、この収容所の通称Toden Waldの訳。
【オバマ訪独】
この本のことを書棚から出してきたきっかけは、つい最近このブログで書いた2つの記事からです。
・オバマ大統領がドイツ訪問の際に、ここを訪問したというオンラインニュースを読みました。このブログでも短く紹介しました。
*第2961号(2009.06.07) Spiegel Onlineの写真が数枚アップされています。
・福島智東大教授が、爆笑問題の番組で、アウシュビッツの強制収容所の体験を書いたフランクルの『夜の霧』について触れていました。
*第2969号(2009.06.10)
【3人の子供達と】
早乙女勝元は、1932年生まれ。東京大空襲に関する記録作りで知られる。
この本は、3人の子ども
早乙女 愛
早乙女 民
早乙女 輝
と、ブーヘンバルトを訪問した記録です。
アウシュビッツについては、良く知られていますが、ブーヘンバルトについて知る日本人は少ないでしょう。
本の目次:
序章 旅の始まり
1章 無差別攻撃の町ドレスデン
2章 ワイマル、その光と影
3章 ブーヘンワルトの警鐘
4章 1945年4月11日
5章 丘の上にたつ11人の男
アンネみたいなやさしい子に 早乙女 愛
ぼくたちは油断できない 早乙女 民
ブーヘンワルトで考えたこと 早乙女 輝
【記念館】
ワイマールからバスで30分ほどだったか。ブナの木の深い森が開ける。
ガス室。毛髪や靴などを保存した部屋。
ブーヘンバルト強制収容所は、1937年から1945年までの8年間で、25万の人が収容され、7万人が死亡したという。(p.106)
人間の皮膚をはいで作られた電気スタンドの傘は、収容所長の妻イルゼの指示によって作成されたという。(早乙女、p.130)
私のつたない文章では、うまく伝えられないです。
「1945年4月11日」とあるのは、この日入所者のうち850名の抵抗集団が戦闘の末2万1000人を解放した日です。(p.107)
早乙女さんの子ども達の感想文は、子どもらしく率直です。
「何故、こんなことがおきたのだろうか・・なぜ、みんなでだめだといえなかったのだろう」(p.208)
早乙女勝元『わが子と訪ねた死者の森収容所』(中公新書、1983年)。購入した日付が1983年7月はじめになっていますから、発行されてすぐ求めたことになります。何度か繰り返し読んだのでバタバタになっています。(写真は、その表紙)
私が、この本で紹介されているブ-ヘンバルト強制収容所跡を訪ねたのは、1979年の夏、ドイツに赴任して最初の夏休みのことでした。30年前のあの夏の日のことは、今でも鮮明に覚えています。
*Buchenwald:
Bucheは、ブナの木、Waldは、森 の意味です。ドイツ語読みでブッヘンバルト。英語読みで、ブーヘンワルト。
「死の森収容所」は、この収容所の通称Toden Waldの訳。
【オバマ訪独】
この本のことを書棚から出してきたきっかけは、つい最近このブログで書いた2つの記事からです。
・オバマ大統領がドイツ訪問の際に、ここを訪問したというオンラインニュースを読みました。このブログでも短く紹介しました。
*第2961号(2009.06.07) Spiegel Onlineの写真が数枚アップされています。
・福島智東大教授が、爆笑問題の番組で、アウシュビッツの強制収容所の体験を書いたフランクルの『夜の霧』について触れていました。
*第2969号(2009.06.10)
【3人の子供達と】
早乙女勝元は、1932年生まれ。東京大空襲に関する記録作りで知られる。
この本は、3人の子ども
早乙女 愛
早乙女 民
早乙女 輝
と、ブーヘンバルトを訪問した記録です。
アウシュビッツについては、良く知られていますが、ブーヘンバルトについて知る日本人は少ないでしょう。
本の目次:
序章 旅の始まり
1章 無差別攻撃の町ドレスデン
2章 ワイマル、その光と影
3章 ブーヘンワルトの警鐘
4章 1945年4月11日
5章 丘の上にたつ11人の男
アンネみたいなやさしい子に 早乙女 愛
ぼくたちは油断できない 早乙女 民
ブーヘンワルトで考えたこと 早乙女 輝
【記念館】
ワイマールからバスで30分ほどだったか。ブナの木の深い森が開ける。
ガス室。毛髪や靴などを保存した部屋。
ブーヘンバルト強制収容所は、1937年から1945年までの8年間で、25万の人が収容され、7万人が死亡したという。(p.106)
人間の皮膚をはいで作られた電気スタンドの傘は、収容所長の妻イルゼの指示によって作成されたという。(早乙女、p.130)
私のつたない文章では、うまく伝えられないです。
「1945年4月11日」とあるのは、この日入所者のうち850名の抵抗集団が戦闘の末2万1000人を解放した日です。(p.107)
早乙女さんの子ども達の感想文は、子どもらしく率直です。
「何故、こんなことがおきたのだろうか・・なぜ、みんなでだめだといえなかったのだろう」(p.208)

























