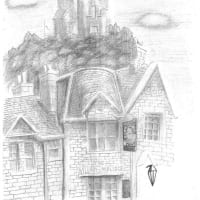インターナショナルな社会主義の政治的試みは、各々の国において特権を持った優福層と多数派の庶民層など2分化した社会階層の解体し無条件に資源や財産を共有しあう万人の融和を目指し、国境を越えて世界の人々が博愛の精神をもって助け合い平和に生きることであった。
しかし、社会主義の欠点は、個人がそれぞれ自発的にそれぞれの適性と労力を高める手段と環境を整えられなかったことと、一人の自己中心的で強欲な個人がその政治制度を動かす権力者となった場合についての考慮について怠っていたことだ。 社会主義制度は、人ひとりひとりが常に他人のためにつくすだけ貢献しあうことの力量を過大視するとともに、その財産共有し中央統制によって制御する計画経済が博愛の精神の無い人間に乗っ取られた時に社会主義の理想とは全く違う結果を生み出してしまう可能性を過小評価していた。
その一方で、経済における生産手段の分業と私生活における個人的快楽の追求を原動とする資本主義の拡張は止まらなかった。 殆どの近代化された国民国家は国民の福祉と国家防衛力、外交における影響力を確保するだけの国力を得るための手段として資本主義を導入した。
資本主義が有するマーケットメカニズムが個人間において必要なもの欲しいものを交換条件をもとに取引させた。 この制度が人間個人の欲求を満たしていくと同時に、その交換条件に応じるための適格を鍛え努力するようになり、その人間個人の性ともいえよう果てしない欲求が資本主義をさらに拡張させた。 そして、そのマーケットにおける個人間の取引が小さな共同体規模から国家規模へ、そして国家の枠を超えた世界規模へと発展していった。
更に、資本主義の政治経済制度は一人個人や一組織によって権力が統一されておらず、それぞれ分裂した組織によって構成され、権力は分散されている。 かつ数多の大小の取引が複雑に絡み合っているマーケットメカニズムによってなりたっているため権力の所在は常に変動している。 故に、この政治経済制度は、激しく変動しつつ混沌としていながらも、保たれ成長し続けてきた。
すると、資本主義は成長し拡張し続け、国家間どうしの貿易頻度が増してくると、国家が資本主義を利用していた立場から、国家の政策が国家間を跨いで拡張した資本主義制度に合わせなけばいけない立場に逆転するほどとなった。
なぜ社会主義が期待する博愛に満ちた人間同士の自主的な利他的奉仕活動を中心に世の中を動かしていくことが難しい。その原因は人間の心理とそれに基づいた行動にある。 苦痛な思い出は楽しい思い出よりも強く残る。 そして、その苦痛からくる人の物事そして他人に対する憎しみは人の心を支配しやすく、相互不信の種はいとも簡単に育ち広まる。 より憎しみが強大な個人は他人よりも強い動機を持つ傾向にある。 故に、人間すべてが善なる存在であることは難しく残念なことに、より寛容で幸福かつ思いやりのある他人よりも、より憎しみを抱いた相互不信的な個人がいっそう活動的に行動する傾向にある。
もちろん、人間個人は他人を思いやることは可能であり、自分の時間と余力をある程度そそぎ万人にとって住み良い世界を作るための貢献を行えるぐらい博愛的になれる。 しかし、一個人には他人のために貢献する限度があるし、時に堕落行為への誘惑も同時に強く、常に利己的かつ短期的な欲求を抑えられるほど人間は強くはない。 もっと他人を思いやり助け善徳に生きるだけの余裕を確保するには、人間個人は自分だけでなく他人へ施しができるだけの物理的にも精神的にも裕福である必要がある。 物理的にいえばある程度自分の富を犠牲にしてまで他人を助けられるだけの資源が必要であり、精神的にいえば自分自身がすでに俗世で自分自身が堪能できるだけの至福を満足しきっただけの人生の余裕が必要である。 そして、それだけ人生に余裕がある個人はこの世の中では少数派であろう。
しかし、社会主義の欠点は、個人がそれぞれ自発的にそれぞれの適性と労力を高める手段と環境を整えられなかったことと、一人の自己中心的で強欲な個人がその政治制度を動かす権力者となった場合についての考慮について怠っていたことだ。 社会主義制度は、人ひとりひとりが常に他人のためにつくすだけ貢献しあうことの力量を過大視するとともに、その財産共有し中央統制によって制御する計画経済が博愛の精神の無い人間に乗っ取られた時に社会主義の理想とは全く違う結果を生み出してしまう可能性を過小評価していた。
その一方で、経済における生産手段の分業と私生活における個人的快楽の追求を原動とする資本主義の拡張は止まらなかった。 殆どの近代化された国民国家は国民の福祉と国家防衛力、外交における影響力を確保するだけの国力を得るための手段として資本主義を導入した。
資本主義が有するマーケットメカニズムが個人間において必要なもの欲しいものを交換条件をもとに取引させた。 この制度が人間個人の欲求を満たしていくと同時に、その交換条件に応じるための適格を鍛え努力するようになり、その人間個人の性ともいえよう果てしない欲求が資本主義をさらに拡張させた。 そして、そのマーケットにおける個人間の取引が小さな共同体規模から国家規模へ、そして国家の枠を超えた世界規模へと発展していった。
更に、資本主義の政治経済制度は一人個人や一組織によって権力が統一されておらず、それぞれ分裂した組織によって構成され、権力は分散されている。 かつ数多の大小の取引が複雑に絡み合っているマーケットメカニズムによってなりたっているため権力の所在は常に変動している。 故に、この政治経済制度は、激しく変動しつつ混沌としていながらも、保たれ成長し続けてきた。
すると、資本主義は成長し拡張し続け、国家間どうしの貿易頻度が増してくると、国家が資本主義を利用していた立場から、国家の政策が国家間を跨いで拡張した資本主義制度に合わせなけばいけない立場に逆転するほどとなった。
なぜ社会主義が期待する博愛に満ちた人間同士の自主的な利他的奉仕活動を中心に世の中を動かしていくことが難しい。その原因は人間の心理とそれに基づいた行動にある。 苦痛な思い出は楽しい思い出よりも強く残る。 そして、その苦痛からくる人の物事そして他人に対する憎しみは人の心を支配しやすく、相互不信の種はいとも簡単に育ち広まる。 より憎しみが強大な個人は他人よりも強い動機を持つ傾向にある。 故に、人間すべてが善なる存在であることは難しく残念なことに、より寛容で幸福かつ思いやりのある他人よりも、より憎しみを抱いた相互不信的な個人がいっそう活動的に行動する傾向にある。
もちろん、人間個人は他人を思いやることは可能であり、自分の時間と余力をある程度そそぎ万人にとって住み良い世界を作るための貢献を行えるぐらい博愛的になれる。 しかし、一個人には他人のために貢献する限度があるし、時に堕落行為への誘惑も同時に強く、常に利己的かつ短期的な欲求を抑えられるほど人間は強くはない。 もっと他人を思いやり助け善徳に生きるだけの余裕を確保するには、人間個人は自分だけでなく他人へ施しができるだけの物理的にも精神的にも裕福である必要がある。 物理的にいえばある程度自分の富を犠牲にしてまで他人を助けられるだけの資源が必要であり、精神的にいえば自分自身がすでに俗世で自分自身が堪能できるだけの至福を満足しきっただけの人生の余裕が必要である。 そして、それだけ人生に余裕がある個人はこの世の中では少数派であろう。