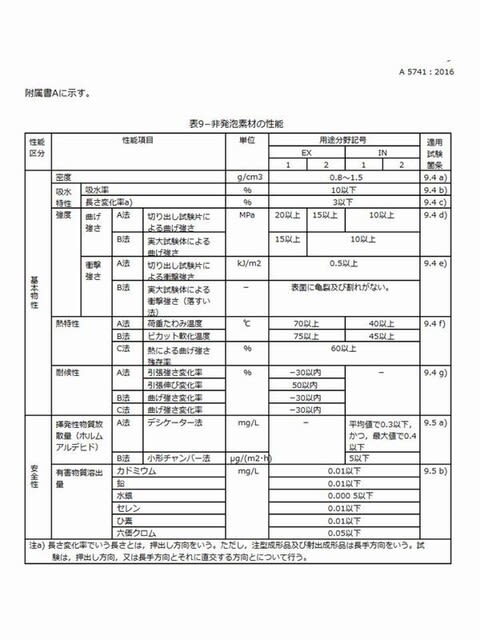弊社は、過去大阪の某テーマパークの屋外木製施設の多くを設計施工しました。
花博の時も多くの施設を施工しただけでなく、木製クラフトの展示コーナーの運営も行いました。
でも今回の万博は恐らくからむことはないだろうと思っていました。
理由はウッドデッキは以前と比べるとありふれた商品になっていますので、弊社が設計施工しなくても、
一般のゼネコンさんの下請け工務店で材料調達から施工までができるようになったことと、
建物にからむ木材については、弊社の範疇外だからです。
ところが今回設計事務所さんから依頼されて、一部のイベント用デッキを万博協会に提供することになりました。
どうせ提供するなら、新しい試みをしたいと思って設計事務所さんと打ち合わせ中です。
万博が始まりましたら、詳しくご説明をさせて頂きます。

花博の時も多くの施設を施工しただけでなく、木製クラフトの展示コーナーの運営も行いました。
でも今回の万博は恐らくからむことはないだろうと思っていました。
理由はウッドデッキは以前と比べるとありふれた商品になっていますので、弊社が設計施工しなくても、
一般のゼネコンさんの下請け工務店で材料調達から施工までができるようになったことと、
建物にからむ木材については、弊社の範疇外だからです。
ところが今回設計事務所さんから依頼されて、一部のイベント用デッキを万博協会に提供することになりました。
どうせ提供するなら、新しい試みをしたいと思って設計事務所さんと打ち合わせ中です。
万博が始まりましたら、詳しくご説明をさせて頂きます。