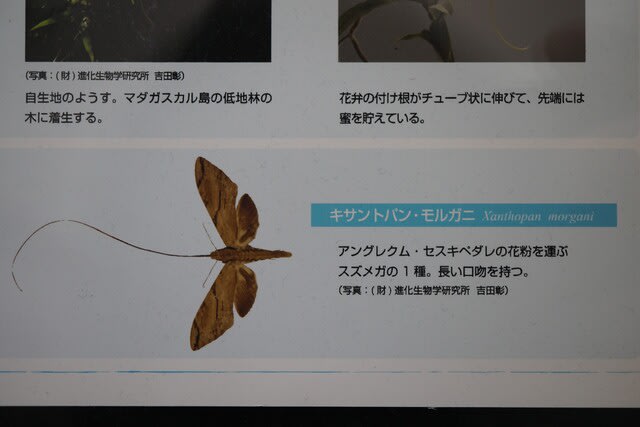先日、※スプリング・エフェメラルの一つ「セツブンソウ(節分草)」を取り上げました。
追録で「キバナセツブンソウ(黄花節分草)」もUPしましたのでご覧ください。

2月上旬の「福寿海」。 まだ咲き始めたばかりでした。
今回はキンポウゲ科の※「フクジュソウ’フクジュカイ’(福寿草’福寿海’)」(学名:Adonis 'Fukujukai' )です。

「フクジュカイ」は「フクジュソウ」と「ミチノクフクジュソウ」の雑種起源の園芸品種で草勢が強く不稔性(種子が出来ない)。
「福寿海」は八重咲きの黄花で最もポピュラーな品種。一般に「福寿草」といえばこれをさします。
これまで、「福寿草」は1種類と思われてきましたが、現在4種類に分類されています。
北海道に分布する「キタミフクジュソウ」(A. amurensis)、 本州と九州に分布する「ミチノクフクジュソウ」(A. multiflora)、 四国と九州に分布する「シコクフクジュソウ」(A. shikokuensis)と「フクジュソウ(別名:エダウチフクジュソウ)」(A. ramosa)です。(A.はアドーニス(Adonis)の略)
産地と萼の長さや色、花びらの数や色、茎が中空かどうかなどで判別可能とのことです。

落葉樹林の下に生える草丈10~25 cm位の多年草。
当初は茎が伸びず、苞に包まれた短い茎の上に花だけが付くが、3月の満開の頃には次第に茎や葉が伸びます。

名板では単に「福寿草」となっていましたが、こちらも園芸品種の’福寿海’かもしれません。

「福寿草」は、旧暦の正月(2月)頃に咲き出すことから、「元日草(ガンジツソウ)」や「朔日草(ツイタチソウ)」という別名もあります。
花は陽が当たると開き、日暮れや夜間、曇天は閉じてしまいますが、暗黒下でも15~20℃の温度で完全に開く。
「福寿草」には、代表的な品種「福寿海」の他、緋色や緑色の花をつけるものなど多数の品種があります。

’080315 「三段咲き」:はじめ黄花八重で、咲きすすむにつれて中心の緑色花弁が羽毛状に伸び、最後に奥の黄花弁が開く。花径4~5cm

’210220 うすい銅赤色でナデシコのような花弁の「フクジュソウ’紅撫子’」(Adonis ’Beninadeshiko')

’210220 「フクジュソウ’秩父紅’」(Adonis ’Chichibubeni’)咲き始めが銅赤色の一重咲き。

’210220「フクジュソウ’金鵄’」(Adonis ’Kinshi')
なお、毒性が大変強く、危険なため注意が必要。
<追録>

'230223「フクジュソウ’爪折笠’」(Adonis ’Tsumaoregasa')

'230223「フクジュソウ’白宝’」(Adonis ’Hakuhou')
<筑波実験植物園>のHPには以下のような解説があります。
*園内にあるのは「フクジュカイ(福寿海)」という園芸品種。
栽培が容易で“福寿草”として栽培されているものの大部分はこの品種(福寿海)のようです。(松本定先生)
*林床に十分光が入るこの時期に葉を開いて花を咲かせ、初夏までの間に養分を蓄えたのち、翌年の春まで姿を消してしまう植物を「スプリング・エフェメラル」と呼びます。
地上部が短命であるようすから、「春のはかない命」と訳されます。