
SPカード×AI活用 不登校支援サポーター講習会 要綱
【講習名】
SPカードとAIを活用した不登校児・保護者支援サポーター育成講座
【目的】
-
子ども用SPカード(33枚)とAI解析を活用し、不登校児の内面理解と支援の実践力を養う
-
保護者への成熟(治療)的関わりと、安心を育む対話支援スキルを習得する
-
サポーター自身がSPの視点を用いて関係性を再構築する力を身につける
【対象者】
- 学校関係者(担任、養護教諭、SC)
-
保護者支援団体スタッフ
-
子育て支援NPO/行政関係職員
-
不登校支援に関心のあるカウンセラー・教育関係者
- 不登校児の保護者
【日程】2025年8月24日(日) 10時~16時 昼食自弁
【会場】神戸市元町 県庁山側徒歩7分
兵庫県立のじぎく会館
TEL:078-242-5355 神戸市中央区山本通4-2-
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf06/documents/noji_tirashi.pdf
【講座構成】(全3部)
◉ 第1部:SPカードと子どもの心の可視化
-
SP(サブパーソナリティ)とは?
-
不登校に現れやすい欲求が脅かされたときの防衛的SPとその特徴
-
SPカードを使った子どもの「こころの言語化」ワーク
-
実践:7枚カード選び&共有練習
◉ 第2部:AIフィードバックで見る子どもの内面
-
AIによるSP傾向解析の仕組み
-
欲求バランスと成長段階(防衛→意志→充足)の読み取り方
- 学校は行っていないものの子どもの成長プロセスの理解
-
AIレポート活用ワーク(支援ヒントの読み取り)
-
保護者との共有方法と留意点
◉ 第3部:保護者支援と成熟(支援)的SPの活用
-
保護者に現れるSPとその意味(例:心配屋さん、頑張り屋さん)
-
成熟(支援)的SPの関わり方(例:思いやりさん、冷静さん)
-
「子ども主導」を支える親のSP変容支援
-
ワーク:SPふりかえり×子どものSP対応チャート
【講習時間・形態】
-
1日コース(10時~16時) 計5時間
-
対面(別途オンラインでも随時開催しています)
-
スライド・SPカード・AI分析ツールを使用
【必携品】
- 筆記道具
【会費】
27,500円(税込)
会費に含まれるもの 子ども用のSPカードまたは一般向けのSPトランプもついています。
また親ならびに子どものSPの分析(AIによる診断)1回分
サポータへのフオローアップ(個別相談)ZOOM
【講師】
八尾芳樹 YAO教育コンサルタント・エンパワーメントカウンセリング研究所 代表
今日まで不登校児家族200家族以上の支援、親と子供の合宿「海塾」を42回実施、不登校児の家族を支援するファミリーサポー
ト協会設立。
*ファミリーサポート協会は臨床心理学者・東山紘久氏(大阪教育大学教授・京都大学副学長)指導の下、不登校や非行などの問題
を抱える子どもとの関係改善を目的とした「母親ノート法」という支援法を採用。母親が子どもとの日常会話をノートに記録し、それ
を専門家と一緒に振り返ることで、親子のコミュニケーションの質を高めていく方法です。
【お問合せ・お申し込み】
エンパワーメントカウンセリング研究所 ecl@yao-ec.co.jp
、
参考
子どもが自分で「ぴったりくるSPカード(サブパーソナリティのイラストカード)」を遊び感覚で選ぶ――そしてその選び方や変化をAIが読み解くことには、不登校児への支援において非常に高い効果が期待されます。以下にその効果を整理します。

SPカード(サブパーソナリティカード)は不登校児の面接のとき、上記の子どもが表現したSP(えたいのしれないお化けさん)をヒントに制作されました。不登校・行き渋り・情緒支援などの現場、また多くの子ども自身が自分の気持ちや行動を「見える化」し、言語化することを支援する目的で設計されています。
不登校児によく見られるSPカード(心理傾向) AIによるインターネット調査
以下は、不登校の子どもによく見られる傾向や背景に照らし合わせて、該当する可能性が高いSPです(特に防衛的SPや自己保護傾向に注目):
|
SP名 |
傾向・背景 |
|
心配屋さん |
「学校に行ったら不安」「失敗が怖い」などの不安感・予期不安 |
|
臆病さん |
人との接触や刺激を避けたい回避的傾向 |
|
内気さん |
人前に出たくない、人との交流が苦手 |
|
いじけさん |
自己否定感・「どうせ自分なんて」という思考 |
|
我慢さん |
周囲に合わせて自分を押し殺す傾向(限界で爆発) |
|
言い訳さん |
本心を隠して「行きたくない理由」を構築する |
|
ソワソワさん |
注意集中が困難で環境への過敏反応 |
|
恥ずかしがり屋 |
視線恐怖、他者の評価への過敏 |
|
泣き虫さん |
感情が揺れやすく、ストレス時に涙になる |
|
わがままさん |
本来の「主張の強さ」ではなく、支配的環境への反動表現として現れる場合あり |
|
お化けさん |
自己の内面を外に出せず、「漠然とした不安」に取り憑かれているような状態 |
|
頑固さん |
柔軟性のなさではなく、自分のルールでしか動けない防衛的パターン |
|
几帳面さん |
失敗や間違いを極端に恐れ、完璧を求めて動けなくなる |
|
甘えん坊 |
安心できる人・場所でしか行動できない依存傾向 |
|
人見知りさん |
初対面や環境の変化に対する強い不安・警戒 |
|
寂しがり屋さん |
一人は寂しいけど、集団には入れないジレンマ |
|
おこりん坊 |
不安や恐怖の裏返しで、怒りという形で出る |
小学生高学年以上には一般向けのSPトランプ(52枚)があります。親の自己理解、子どもの自己理解のツールとしてお役立てください。

」🌈 1. 【自己理解の入り口】
🎴カード選びは「感覚ベースの自己表現」
- 言葉では語れないモヤモヤした内面を、イラストやキャラの「感覚」で表現できる。
- 「これ、自分っぽいかも…」という小さな気づきが、自己理解と承認の出発点になる。
🔍AI分析で「見えない傾向」が見える
- 子どもが選んだカードの傾向をAIが分類(防衛的・充足的・内向/外向…)
- 言葉にできない心理状態を見える化し、保護者や支援者と共有できる。
🧩 2. 【“安全な遊び”としての自己開示】
- 子どもにとって「不登校」は自己開示=危険と感じている場合が多い。
- SPカードを通すことで「直接的な質問なし」で、心理的安全を守った表現ができる。
例:「学校に行きたい?」ではなく「この中で今日の気分に近いのは?」という問いかけ
📈 3. 【変化の兆しをAIが早期キャッチ】
- 選ぶカードが「防衛的SP → 意志的SP → 充足的SP」と移行していく過程を可視化。
- 本人すら気づかない回復のサインをAIが感知できる。
🔁 例:「お化け→泣き虫→わがまま→負けず嫌い→チャレンジャー」と変化する流れ
👪 4. 【親や支援者との“橋渡し”になる】
- AI分析結果をもとにした親へのフィードバック(共感的なアドバイス)が可能。
- 子どもはカードで表現、親は文章で理解――ツールが親子をつなぐ通訳役となる。
🧠 5. 【認知行動療法的な効果】
- 自分の状態を「カードで客観視」→「自分で選び直す」という流れにより、
- 思考の柔軟性
- 自己効力感の回復
- 感情のラベリング能力
を高める効果がある。
🌟 6. 【総合的支援ツールとしての意義】
|
項目 |
従来の面談 |
SPカード+AI |
|
表現のしやすさ |
△ 言葉に頼る |
◎ 絵と感覚で表現 |
|
心理的安全性 |
△ 試される感覚あり |
◎ 遊び感覚で安心 |
|
状態の可視化 |
△ 面談者の主観依存 |
◎ 客観的にデータ化 |
|
親子の共有 |
△ 情報が届きにくい |
◎ レポート化で共有 |
|
継続支援 |
△ 曖昧になりがち |
◎ AIで経過追跡可 |
不登校への理解を深めるための意識啓発資料
▶ 今々の日本の不登校をささえるデータ
-
小中学生の不登校子は 2023年で約30万人、過去最多
-
中学生の1割弱が不登校状態
-
原因:人間関係、教室環境、自己否定感、発達特性など
▶ 正しい理解と反対観
| 当たり前の考え | 悪応しやすい認識 |
|---|---|
| 学校は行くのが当たり前 | 行かないのは悪いこと |
| 不登校は子どものわがまま | 教育失敗の結果 |
| 適応したものだけ生きられる | 社会性を失う |
▶ 正しい理解:子どもは "たたかっている"
-
不登校は逃げではなく「生き残ろうとするサバイバル」
-
学校が安定した場所ではなくなったとき、自分を守る決断
-
無理に戻すのではなく、「他の道」を探すことが気力につながる
▶ 正しい関わり方:対応から「反応」へ
-
最初に必要なのは「認めること」
-
話す、聞く、受け止める「感情の安定基盤」作り
-
子どもが「働きたい」と思えるような「心の自立」を待つ
-
学校に戻ることは目的ではない:「学びの内容」「生きる力」の復旧が本質
▶ 正しい知識:武器は「認め」と「空間」
-
不登校は一人ではなく「人と一緒で現れるサイン」
-
従来のコミュニケーション、教育観がもたらすストレスに慎重に
-
大人の成功モデルに子どもを合わせない
-
子どもが「これでいいんだ」と思えるような人間関係が本当の学びを再生させる
▶ サポーター、支援者の道筋
-
実態をしる
-
聞く / 同じ感情になる
-
「このままでいい」を一緒に体感
-
「次はどうしたい」を問う
-
子どもが動きたくなる空気を大人が作る
「行きたくない」は「生きたい」のさけび 不登校は「生き方を見つけ直す」旅のサイン
ご家庭の方、支援者の方へ。この資料が、不登校の子どもたちのまなざしや人間関係を見直す、一緒に揺れるための手がかりとなれば幸いです。
エンパワーメントカウンセリング研究所 ecl@yao-ec.co.jp


















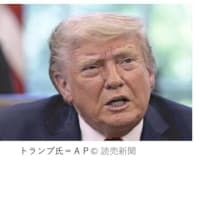






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます