
2013年04月02日15時21分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
日本放送業界が激変している。
30年間にわたり2強構図を形成してきた
フジテレビと日本テレビの勢いが一段と弱まった。
その代わりに
下位圏だったテレビ朝日が先頭に立った。
1日に発表された日本民放5局
(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ東京)と
公営放送NHKの2012年度 (2012.4.2~2013.3.31)の平均視聴率で、
テレビ朝日は
プライムタイム(午後7時~午後11時:12.7%)とゴールデンタイム
(午後7 時~午後10時:12.4%)でトップとなった。
プライム、ゴールデンタイム、全日(午前6時-0時)の3部門で
角逐し、2部門で1位となったのだ。
テレビ朝日が1部門でも1位なったのは1959年の開局以来初めて。
テレビ朝日は全日部門でも7.8%と、
日本テレビより0.1ポイント低い2位となった。
下半期(2012年10月~2013年3月)で見ると
全日を含む3部門ですべてトップとなった。
「よくて3位」といわれたテレビ朝日が1位になった半面、
03年から8年連続で3冠王となり“永遠の第1人者”のように君臨して
きたフジテレビはTBSと3、4位争いをする
ことになった。
日本放送業界も衝撃を受けている。
週刊東洋経済は最新号のメディア特集で、
「フジの没落は筋肉疲労によるもの」と指摘した。
首位を守 ることに集中するあまり、
新しい挑戦ができなかったという分析だ。
新鮮さと面白さが最優先の芸能番組の現場でも、
官僚組織のように細分化された上部組織に 書類を提出する
のに時間がかかり、
他局に先を越されるケースが多かった。
社長と編成責任者の「Go」という一言で一線組織が不乱に動いた
全盛期の雰囲気が消 え、ドラマも大物俳優に大きく依存し、
新しい流れを対応できなかったという分析も出ている。
主要視聴層だった10、20代と若い職場女性が
モバイルなど ニューメディア側に移動していることへの対策が
十分でなかった
という指摘もある。
2011年7月のデジタル化によるチャンネル変更も変数として作用した
従来の「10」から「5」に変わったテレビ朝日がプラスの影響を受け
「8」のフジテレビが一番最後のチャンネルになって
マイナスの影響を受けたという側面がある。
しかし日本放送業界は
絶えない挑戦精神をテレビ朝日の躍進の原動力に挙げている。
テレビ朝日は
ワールド・ベースボール・クラシック (WBC)、
ワールドカップ(W杯)サッカー予選、
フィギュアスケートなどのスポーツ中継権を積極的に獲得し、
チャンネル認知度を高めた。
また若いプロ デューサーを果敢に登用し、
新鮮な芸能番組やドラマを連続でヒットさせる好循環構造を構築した
この結果、昨年、
東京など関東地域の視聴率「トップ10」 番組のうち5つをテレビ朝日
が占めた。


















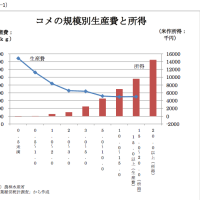

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます