紛争の「世俗的理解」を試みる
ジョルジュ・コルム
元レバノン財務大臣
『紛争の「世俗的」理解をめざして』(未邦訳)著者
Georges Corm, Pour une lecture profane des conflits,
La Découverte, Paris, 2012.
訳:仙石愛子 ル・モンド
広大なサハラ砂漠に住んでいる部族民の困難な生活ぶりに
思いをはせないで、マリでの戦争を理解できるだろうか?
反徒の旗がイスラム過激派の旗に 立て替えられても、
それで何も変わらない。世俗的、経済的、社会的、さらに
政治的な現実は従来のままであり、そうした現実が
レバノン、イラク、イラン、あ るいはパレスチナ同様、
この地にもただ対立と危機の土壌を形成している
のである。[フランス語版編集部]
« 原文 »
東西冷戦に替わる紛争
時代が変わった。
西側ではソヴィエト連邦に煽られる共産革命が非難され、
東側では階級闘争と反帝国主義が賞賛されていた時代は終わり、
これを引き 継いだのは、
宗教的、民族的、さらには部族的なグループ同士の対立を
引き起こす時代である。
このような新しいものの見方が
特別な影響力を持つようになった のは、アメリカの政治学者
サミュエル・ハンティントンが20年以上前に《文明の衝突》
という概念を広めてからである。
彼は、
数多くの危機の根底には文化 的、宗教的そして道徳的な
価値観の違いがある、と説明した。
しかし、それは以前からあった人種主義的二分法に息を
吹き返らせたにすぎない。19世紀にこの 理論を広めたのは
エルネスト・ルナンである。彼はアーリア人の世界は
文明化して洗練されていると考え、
セム族の世界は
無政府主義的で粗暴とみなし、両者の 対比を説くものであった。
このように、「価値観」に依拠することは、
原初的アイデンティティへの回帰を促すことになった。
原初的なアイデンティティは、
相次ぐ近代化の大波 によって後退していたが、グローバル化や、
生活・消費形態の画一化、新自由主義によって
引き起こされた大きな社会変動、その犠牲になった幅広い階層の
人々、こういったもののおかげで逆説的にも蘇ってきた。
このように特定の価値観に依拠することは、
紛争当事者のいずれかに有利な国際世論の動員が可能とな る。
言ってみれば、植民地主義的思想を受け継ぎ文化本質主義
[特定の国、地域の文化は変わることがないという考え方――訳注]
の影響を受けて永続する大学 の伝統に、
強力に後押しされるのである。
ヨーロッパ風の非宗教的リベラリズムと社会主義思想は、
ヨーロッパ外に伝播した挙げ句、
両方とも消え去ったように思われる。
紛争は人類学的、文化 的次元のものに限られてきている。
今や古典政治学的な分析手法を維持するジャーナリストや学者は
ほとんどいない。しかしこの学問は、
人口統計学、経済、地 理、社会、政治、歴史そして地政学に
関わる要因を考察対象に加えているだけではなく、
指導者の野心、世界の新帝国主義的構造、
そして影響力拡大をめざす地 域権力の思惑をも、
考慮に入れている。
ありきたりの空虚な議論
概して、紛争について説明するにあたって、
その勃発に数多くの要素が絡んでいるということが考慮に
入れられない。ただ《善人》と《悪人》を分け、
問題点を単純化するだけで終る。
主役たちは、民族、宗教あるいは地域共同体つながりで
グループ分けされる。ご指名を受けたグループ内部では
意見や行動が皆 同じはずだ、ということになる。
この種の分析方法の兆しは、冷戦末期には既に現れていた。
1975年から1990年までの長期にわたるレバノン内戦では、
多様な当事者たちが「キ リスト教徒」か「イスラム教徒」か
で分類された。前者は
全員が《レバノン軍団》という名の再編成グループ
もしくはキリスト教右派の《ファランジスト党》の 支持者とみなされ、
後者は
《パレスチナ進歩党》、後に《イスラム進歩党》と改名した連合グループ
にまとめられてしまった。こういった漫画的な分類で
想像す らされなかったことがある。それは、
数多くのキリスト教徒が反帝国主義と反イスラエルの連合グループに
属していたこと、パレスチナ人の対イスラエル作戦を
レバノンから指揮する権利をキリスト教徒が支持していたこと
一方、多くのイスラム教徒はそれに反対していたことである。
さらに、武装パレスチナ・グルー プがレバノンに駐留したこと、
それに対しイスラエルが激烈で大規模な報復攻撃を行なって
民間人に被害が及んだこと。このような事件を通して
レバノンにもた らされた問題は、
宗教とは全く関係のない性質のものであり、
レバノン内の諸グループの出自とも全く無縁のものだった。
同じ時代に、
宗教的アイデンティティに対して別の作為が行なわれたが、
これを批判した専門家アナリスト、マス・メディアは全くいなかった。
1979年12月のソ連侵略によって引き起こされたアフガニスタン戦争
でのことである。この時こそ、
無神論者の侵略に反発する「イスラム教徒」を大動員 し、
国家レベルでの抵抗を隠蔽することとなった。
アラブ諸国をはじめ様々な国籍の若きイスラム教徒たちが、
アメリカ、サウジアラビア、パキスタンで
訓練を 受け先鋭化していた。
イスラム聖戦主義のインターナショナルが永続的に発展する
ための有利な状況はこのようにして創り上げられたのである。
欧米列強の大誤算
さらに、1979年1月から2月にかけてのイラン革命は、
重大な地政学的誤解の端緒となった。西側列強が考えたことは、
イラン国王失脚後の新政府 を、
ブルジョワ民族主義、社会主義、あるいは
反帝国主義に染めさせないための最善策は
(1950年代初頭にモハンマド・モサッデクが
もたらした苦い経験に 学んで)
権力の座には宗教指導者を就かせる、
ということだった。というのは、
非常に宗教色の強いサウジアラビアとパキスタンの2か国が
アメリカと密接な 同盟関係にあったので、
イランもまた断固たる反共国家になり、
自分たちの忠実なパートナーになるだろうと踏んでいた。
それ以降、政治とメディアは一斉に、
イラン、イラク、シリアそしてレバノンのヒズボラがつくった
「シーア派」の三日月危険地帯を引き合いに出す ようになった。
こうした国々・グループはスンニ派の不安定化をはかり、
テロを起こし、イスラエル国家を殲滅しようとしているという
のだ。
一部のイラン人が イスラム教シーア派に転向したのは
やっと16世紀のことであることを誰も指摘しようとはしない。
それはオスマン帝国の膨張主義に対してもっと強く抵抗する
ためにサファヴィー朝が促したものだった(注2)。
イランが常に主要大国であることや、
その体制は新たな虚飾で飾り立てて、「偉大なシャー」政策を
ひたす ら追い求めていたことなどは、
誰も触れない。
シャーは
自らペルシャ湾の憲兵になることを願い、
フランスに刺激されて核兵器に強い関心を持っていた。
宗教と は関係のない
こういった歴史的な事実があるにもかかわらず、以降、
中近東ではすべてのことが「スンニ派とシーア派」という発想で
分析されている。
理解されないイスラム組織
2011年初頭にアラブ世界で民衆の怒りが爆発して以降も、
単純化の動きは続いている。
バーレーンでは、
デモ参加者は「シーア派」であり、
スンニ 派支配に反対するイランが操っていると言われている。
これは反体制派の主張に共感するスンニ派市民がいるだけではなく、
現政権を支持するシーア派市民がい ることをも無視する行為
である。
イエメンでは、この国を長きに渡り支配した王朝の支持党派の流れ
を汲むホウシー派の反乱(注3)があったが、これは
「シー ア派」的現象、すなわち専らイランの影響としてしか
見られていない。
レバノンでは、《ヒズボラ》が、シーア派内部で対立を起こしたり
あるいは逆に数多くのキリスト教徒やスンニ派を含め様々な宗派の
イスラム教徒の 間で支持を集めてきた。
にもかかわらずこの組織は、
イランの野心に操られる単なる道具とみなされているのだ。
レバノンは1978年から2000年までの 間、
住民の大半がシーア派である南部の広大な土地をイスラエルに占領
されていて、ヒズボラがこれに抵抗して生まれた組織だという
ことが忘れ去られている。
確かにこの占領は、ヒズボラの執拗な抵抗がなければ
長く続いたことだろう。
反面、ガザの《ハマス》は純粋に「スンニ派」の所産であり
《ムスリム同胞団》パレスチナ支部を母体として結成されたのだが、
「中道」スンニ派支持 のアナリストたちの中に
このことを気にかけるものはあまりいない。
このハマスが
彼らからみて批判されるべきなのは、
武器を供給しているのがイランだからで あり、
その武器でイスラエルによる領地封鎖を破ろうとしている
からである。
要するに、いたるところ微妙な差異は無視されている。
社会経済的な抑圧や疎外状況は故意に伏せられる。
諸党派の権力闘争も存在しないことになって おり、
善の力と悪の力が存在しているだけなのだ。
多様な意見を持ち多様な行動をとる社会共同体は、
空虚な人類学的理論とステレオタイプ化した文化本質主義 の助けを
借りて性格規定されている。
そういった共同体は
何世紀にも渡り、社会・経済・文化の強い相互影響の下で
生きてきたのだ。
新しい概念が諸言説のなかに進入してきている。
西欧では、
「ギリシャ=ローマ」時代の根底にあった無宗教性が
拠りどころにされていたが、その後
「ユダヤ=キリスト教的価値」がそれを継承した。
それと同様に、
世俗的発想を持つアラブ民族主義が主張する反帝国主義、社会主義、
「産業化優先」などが地 域の政治に長いあいだ影響を及ぼしてきた
が、これを継承したのが、
「イスラム主義的な価値、特性、慣習」すなわち
「アラブ=イスラム主義」だった。
相手が仏教徒でも……
こうしたことから、オリエントの「家父長的あるいは部族」的な
総合価値観は
西欧社会が自認する個人主義、民主主義的価値観と相容れない
と考えられ るようになる。かつてヨーロッパの大社会学者たちは、
仏教社会は産業的資本主義に達することが決してないだろう、
と考えたことがあった。というのは、
産業 資本主義はプロテスタンティズムという固有の価値観を礎としていた
からだという。
同じような着想から、
パレスチナ問題も、もはや民族解放をめぐる戦争として認識されてはいない。
この問題はパレスチナ解放機構(PLO)が長い間 要求してきたように
国を一つだけ建設し、そこで
ユダヤ教徒、キリスト教徒そしてイスラム教徒が対等に暮らすことで
解決できるはずだからである(注4)。
と ころがパレスチナ問題は今や、
ユダヤ人のパレスチナ居住に反対するアラブ=イスラム的拒絶
とみなされている。それゆえ、
多くの良識ある人々が、
PLOは処 罰すべき根強い反ユダヤ主義の象徴だと捉えているのだ。
それでも、少々の分別があれば理解できたであろうと思われるのは
たとえパレスチナを占領したのが 仏教徒だったとしても、
あるいは、
オスマン後のトルコがパレスチナを再征服しようとしたとしても、
抵抗運動は全く同じように恒常的かつ過激になっていただ ろう、
ということだ。
チベット、新疆ウイグル自治区、フィリピンで、さらに
ロシア支配下のコーカサスで、その後ビルマで、
仏教徒である隣人と紛争を起こしていたイスラ ム教徒の存在が
最近明らかになった。また、
共同体と共同体の境界線に沿って分割された前ユーゴスラヴィア
(カトリック教のクロアチア、正教会のセルビア、
イスラム教のボスニア)でも、さらに
アイルランド(カトリックとプロテスタントに分割され)でも
……。こういった様々な宗教において、
紛争は本当に宗教的 価値観の衝突だと言えるだろうか?
それとも逆に、紛争は宗教とは関係なく、
つまり社会的現実の中にその根源があるが、
誰もその力学を分析しようとはしな くなり、
その間に共同体の指導者を自認する多くの者たちが、
そこに野望実現の機会を見ているのではないだろうか?
規模の差こそあれ、覇権争いにおいてアイデンティティを利用する
のは昔からの常套手段である。フランス革命以来、
政治の近代性と共和主義的信条は 世界中に広がり、
国際社会と外交に政教分離の理念を継続的に根づかせてきた……
と誰もが信じていた。ところが、
全然そういうふうにはならかなった。いくつ かの国が、
複数の国々にまたがる宗教を代表するのは自分の国だ
と主張する。そういう国が、特に3つの一神教
(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)に関し て、増えている。
権利の歪曲化
こういった国々は宗教をつかみ、権力政治、影響力ある政治、
拡張政策に宗教を利用しようとする。国連の謳う人権という原理を遵守
していないことを これで正当化するのである。
欧米諸国が、
1967年以来パレスチナ人の土地が占領され続けていることを承認している一方で、
一部のイスラム大国は、鞭打ち 刑、投石刑、断手刑を容認している。
国際的人権侵害に適用される制裁は、これもまたばらばらである。
たとえば、
一部の国々(イラク、イラン、リビア、セル ビア他)では
「西欧諸国」が厳しい懲罰を科している一方で、
別のケース(イスラエルによる占領、米軍のグアンタナモ収容所における拘禁刑)では
戒告すら行 なわれていない。
地域の紛争を収拾しようと望むならば、
特に中近東において緊急にやらなければならないことは、
宗教の手段化をやめさせ、紛争の非宗教的な実態を隠蔽する
単純な分析方法をやめさせることである。これが緊急に必要なのである。
注
(1)Seymour M. Hersch, «The redirection», The New Yorker, 5 mars 2007, http://www.newyorker.com
(2)サファヴィー朝は1501年から1736年までペルシャを統治した。初代君主のイスマーイール1世(1487年~1524年)は臣民のシーア派改宗に着手した。
(3)Pierre Bernin, «Les guerres cachées du Yémen», Le Monde diplomatique, octobre 2009.
(4)特に、1974年国際連合総会でヤセル・アラファトが演説し、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒が一つの国に対等に暮らす意義を訴えたことは有名である。
(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2013年2月号)


















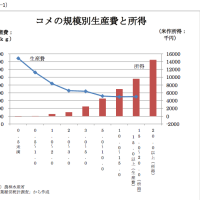

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます