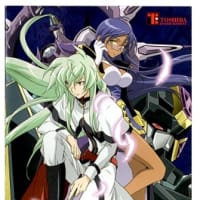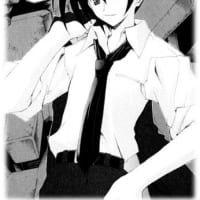暇さえあれば、猫の動画や写真をあさってみたくなる管理人です。
そうそう、こんな動画を拾いました。
歌にあわせてよく編集されてますよね。
そういえば去年は猫なべ(猫を煮て食す料理のことではない(笑))がはやったそうで。動画サイトでも猫のおもしろムービーがよく投稿されていますね。
そんな猫は、文学界でも大人気。
作家が取りあげる動物は犬よりも猫が人気なのだそうです。その理由は、犬はブルドッグやダックスフンドなど種類によって違いがあるのでその良さをひと口ではいえないが、猫ならほとんど顔かたち大きさはかわらず、どれも「かわいい」の形容詞ですんでしまうからとのこと。またある作家の弁によれば、猫のとる突拍子もない行動がひとの心をとらえてはなさいのだといいます。
第一の理由は生物学的な分析でちょっとおもしろかったのですが。第二の心理的な理由を補足しますと、人間の奥底にひそむ自由願望につながるのではないでしょうか。たとえば、「〇〇の犬」といえば、権力者や組織におもねった忠実な人間を卑下するようないい方につかわれる。猫は飼いつながれておらず、好き勝手に気の向くままにどこにでもいくし、好きなだけ昼の光りを毛布にしてあたたかく眠ることができる。それはまさに作家の望みそのものでありましょう。
あるいはまた、仕事や家庭やなにかの義務にしばられている犬人間ほど、じつは猫をうらやましがるのかもしれませんね。
キティちゃんも〇五年に二十年ぶりの再ブームが到来したなめ猫もそうですが、
動物キャラクターグッズでも猫のほうが人気が高いようです。ちなみに私は子どものころ、「タマ&フレンズ」のグッズをよく集めていました。(あれは犬もいますけどね)
猫の文学といえば、『我が輩は猫である』
猫の目から分析すればお偉い美学者も、ただのひまつぶしの男にしかみえません。このタイトルは、語り手の猫自身の名乗りであると同時に、書き手である漱石の、猫のように自由に物書きしたちという意欲のあらわれとうけとれます。
猫の小説といえば、むかしよく読んだのが赤川次郎の「三毛猫ホームズ」シリーズ。ひとのいい刑事の兄としっかり者の妹の飼い猫ホームズが迷宮入り事件の解決の糸口をみつけだすというストーリーです。
作家にせよ、学者にせよ、探偵業にせよ、自由業。まさに猫のおしごとといえるのかもしれませんね。
ところで、少女漫画の巨匠大島弓子が愛猫との日々をつづった、大ロングセラーエッセイ漫画『グーグーだって猫である』が映画化されるそうです。
このタイトルもなんだか、漱石ももじりっぽいですね。
やはり締切に追われる人間は、猫にいやされるのでしょうか?
【参照サイト】
「文学やネットの世界ではなぜ猫の支持率が高いのか?」(R25.jp)
大人の女性に観て欲しい「グーグーだって猫である」
(Garbo 〇八年九月五日)
 「ネコナデ」DVD発売
「ネコナデ」DVD発売
そうそう、こんな動画を拾いました。
歌にあわせてよく編集されてますよね。
そういえば去年は猫なべ(猫を煮て食す料理のことではない(笑))がはやったそうで。動画サイトでも猫のおもしろムービーがよく投稿されていますね。
そんな猫は、文学界でも大人気。
作家が取りあげる動物は犬よりも猫が人気なのだそうです。その理由は、犬はブルドッグやダックスフンドなど種類によって違いがあるのでその良さをひと口ではいえないが、猫ならほとんど顔かたち大きさはかわらず、どれも「かわいい」の形容詞ですんでしまうからとのこと。またある作家の弁によれば、猫のとる突拍子もない行動がひとの心をとらえてはなさいのだといいます。
第一の理由は生物学的な分析でちょっとおもしろかったのですが。第二の心理的な理由を補足しますと、人間の奥底にひそむ自由願望につながるのではないでしょうか。たとえば、「〇〇の犬」といえば、権力者や組織におもねった忠実な人間を卑下するようないい方につかわれる。猫は飼いつながれておらず、好き勝手に気の向くままにどこにでもいくし、好きなだけ昼の光りを毛布にしてあたたかく眠ることができる。それはまさに作家の望みそのものでありましょう。
あるいはまた、仕事や家庭やなにかの義務にしばられている犬人間ほど、じつは猫をうらやましがるのかもしれませんね。
キティちゃんも〇五年に二十年ぶりの再ブームが到来したなめ猫もそうですが、
動物キャラクターグッズでも猫のほうが人気が高いようです。ちなみに私は子どものころ、「タマ&フレンズ」のグッズをよく集めていました。(あれは犬もいますけどね)
猫の文学といえば、『我が輩は猫である』
猫の目から分析すればお偉い美学者も、ただのひまつぶしの男にしかみえません。このタイトルは、語り手の猫自身の名乗りであると同時に、書き手である漱石の、猫のように自由に物書きしたちという意欲のあらわれとうけとれます。
猫の小説といえば、むかしよく読んだのが赤川次郎の「三毛猫ホームズ」シリーズ。ひとのいい刑事の兄としっかり者の妹の飼い猫ホームズが迷宮入り事件の解決の糸口をみつけだすというストーリーです。
作家にせよ、学者にせよ、探偵業にせよ、自由業。まさに猫のおしごとといえるのかもしれませんね。
ところで、少女漫画の巨匠大島弓子が愛猫との日々をつづった、大ロングセラーエッセイ漫画『グーグーだって猫である』が映画化されるそうです。
このタイトルもなんだか、漱石ももじりっぽいですね。
やはり締切に追われる人間は、猫にいやされるのでしょうか?
【参照サイト】
「文学やネットの世界ではなぜ猫の支持率が高いのか?」(R25.jp)
大人の女性に観て欲しい「グーグーだって猫である」
(Garbo 〇八年九月五日)
 「ネコナデ」DVD発売
「ネコナデ」DVD発売