文部科学省による文書(〇七年七月十一日発表)による、教員免許更新制の概要がまとめられています。その問題点を洗いだしてみましょう。
(1)免許状の有効期限は十年。
正確に記すれば、資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで。「普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は有効期間の満了の日のうち最も遅い日まで」とするとされている。つまりよくいえば、有効期限中に新たな免許を取得した場合その有効期限となるので、更新期間は延期されるが。逆にいえばそのいちばん新しい免許の更新を怠った場合、当然ながらすべての免許状をうしなう羽目になる。
なお更新講習は校内での人員配置等も考慮して、免許満了の二年前から受講可能、とあります。これはたとえば、前年度の合格科目を免除できる税理士資格試験のように、二年間で講習を修了すればいいというのであれば納得がいきます。また、家族の介護や本人の傷病など予期しえないやむをえない事由で修了できないのであれば、期限を延期するという温情措置が図られてもいいと考えます。
(2)更新講習対象者は、現職教員および雇用予定者。
二年前の審議では、現職者は対象外とされていたようです。すなわち今後の教員予定者を想定していたのです。おそらく指導改善研修でこと足りるとみていたのでしょう。しかし、更新講習をうける者とうけなくていい者とがおなじ現場ではたらくことへの不満が生じるのを鑑みて、教員全員に義務づけたものと思われます。
そして問題なのは、ペーパーティーチャーの人びと。教員と違って講習の参加は任意です。が、更新講習をうけなければ、資格を剥奪されてしまいます。せっかく学生時代に苦心して取得したのに国に奪われるなんて納得がいかないと憤懣(ふんまん)やる方なしなひとも多いのです。たしかに履歴書に書くためだけに資格をとったようなひとには、これは功を奏することではありますが。じっさい、教職に就かず他の職種で働いている人は、教員よりもさらに講習参加時間の確保がむずかしいのではないでしょうか。私の大学の先輩にも教員免許を有しつつ、美術館学芸員をされている方がいますが、展示の準備や研究活動にいそがしくとても更新に参加できないのではと心配しております。さらに有効期限間近に教員に採用された者は、まだ学校現場になじんでもいないのに、更新講習に駆り出されなければならない。経験がなく指導力も身についていないのに、少し酷なのではと思います。
(3)更新講習はおよそ三十時間程度。費用は個人負担で三万円。
この制度をめぐっていちばん論争をよんだのがこの部分でしょう。放課後の児童とのふれあいや部活動指導、研修参加など授業時間外の活動や教材研究や準備でとかく多忙を極めている教育現場。三十時間とは、けっして短い時間ではないでしょう。土日祝日、夏期休業期間であってもクラブ顧問や研修に参加している先生にとっては時間を確保するのは容易ではありません。
そして、そのあいだ現場を離れる教員の代替者の補充が必須となります。これはうまくいかないと教育サービスの質の低下をまねくおそれがあるのです。
また費用が個人負担であること。以前の審議では、公務員であるから経費は税金投入と目されていました。おそらくパブリックコメントをかさねた結果、国民におもねったのでしょうが、受講者側からしてみればかなり痛い出費。教職員の給与というのは、大学新卒の初任給としてはいいほうに思えますが、私は休日も夜も仕事に追われる教職員の給料としては、けっして高すぎるものだとは思えません。
(4)講座の開設は教職課程認定大学の他、各自治体の教育委員会が大学や大学院との連携によって設置することも可能。講座の設置許可は文部科学省が行う。
さて、ここで問題になるのはこの講座の講師の資質でしょう。要するに、都合の悪い思想の持ち主を排除する誘発剤にならないかということです。
そもそも、いまの教師のモラリティや指導力不足の問題については、元をただせば各都道府県に教育学部のある大学を設置した旧文部省、学生確保のため就職の受け皿は限られているのに教員免許の資格を乱発した大学側にこそあるのではないでしょうか。
ですから、更新講習を大学ないしは教育委員会に委ねるのなら、その講習内容についてつねに監査するシステムも必要ではないかと思います。私の懸念は、アカデミックハラスメントまがいのことが行われ、職を奪われる教師がでることです。
また、教員の教育実践や自主的な研鑽活動が目立って優秀であると判断される場合には、講義の一部または全部の受講を免除することも可能。更新講習を基準時間以上に受講するなどした場合、処遇にも反映させる方策も検討されています。その判断には公正な基準があるのでしょうか。顔色うかがいをして講習逃れする教師が想定されます。
それに、ここでいう教育実戦や研鑽活動とは、果たしてなんなのでしょう。たとえば教員が在職中に、大学院に進学し専修免許を取得するケースが増えていますが、それは教育現場を離れたいがための休暇目的であったり、じっさい教育として反映されにくい修士号獲得目的の研究(管理職になるには専修免許が必要とされるため)であったりします。(誤解のないようにいっておきますが、修士号を得て現場復帰し、その研究成果をいかんなく実践していらしゃる先生も、とうぜんいます。)
そして、資格を授与するのも、更新講習にあたるのも、教育現場の空気をほとんど知らないアカデミズムの牙城でふんぞりかえっている大学教官。大学でさえ学生を講義に集中させるのに難儀している先生方が多いのに、そんな方々が教育者の模範となり指導者となれるものなのでしょうか。
この制度の一番の問題は、現今の教育問題を教師の責任として蓋然的に押しつけていることです。いちばん困っているのは他でもない善良な多くの教師。なんの非もなく熱心な教育活動をつづけてきたのに、突然の負担を強いられたひとたちです。全国には幼稚園から高等学校まで、いま百万人以上の教員がいらっしゃいますが、問題行動をおこすのはごくわずかです。凶悪な子ども像とおなじように、あまりにもおもしろおかしくマスコミに煽りたてられて、教師が悪職だと印象づけられてしまっているのです。前回語ったように、私はたしかに一部のいやな教師のせいで教育者はおおむね好きではありませんが、私の知っているすべてが世界の実態であるとまで思ってはいません。そして、これまで出会ったなかで、学校をはなれても生涯、先生とお呼びし私淑しつづけたい恩師にも廻り会うことができました。それは、ここで語られている作品とおなじ、たいせつな、私の人生を変えてくれたと言っていい出会いでありました。その恩師は県有数の進学校につとめていたにもかかわらず、進学指導に熱心ではないので職員室でも異端視されていました。こうした先生が、この更新制によって排斥されるのではなかいと危惧しているのです。
この更新制は、いわば雑草を引き抜く手間を惜しんで、健康な青い苗のならんだ水田に除草剤を散布してしまうもの。ただしく実りをつける若い稲穂まで痛めてしまう。それはかえって、教育の土壌を疲弊させる結果におわるのではないかと思うのです。ゆとり教育のスローガンのもと導入された週五日制にしろ、授業内容の過密化をすすめてしまい、逆効果をうんでしまっていました。その完全撤廃がうちだされたのも、今年になってから。たびかさなる文科省の政策転換に、現場の教員は右へ左へと振り回されているのです。
そして、そもそもこの更新制だけで満足していては、ほんとうの教育再生などできやしない。これが抜本的な教育改革なのだと過信してしまわないことです。たとえば教員がこころを病むのはなぜか。家庭でお粗末なしつけをされた子ども、身勝手な保護者、そして派閥がある職員室、または本人の家庭状況。いろいろな要因がそこにからんでいます。私は、熱意にあふれて教職を選んだ者ほど、荒んだ現場に揉まれて、情熱をうしなっていくのではないかと思えるのです。
教員資格の重みを知らしめ、ひとを教えることの厳しさを浸透させることはもちろん重要ですが。教師というのはいわば一国一城の主。先生、先生と呼ばれつづけたら、慢心したくもなろうというもの。おなじ学校職員でも横どうしの交流がなく、孤立しやすいのではないでしょうか。同僚や上司に悩みを相談しやすい職場環境づくりを推進したり、また保護者も教育現場に参加させて教えることのたいへんさを実感してもらうことも肝要なのです。学校に預けっぱなしにしておけばいい時代ではなくなった。それは正しいあり方です。学校と託児所は違うのですから。
教育の歪みは、学校というせまい揺籃のなかでのみ起こった事柄ではないのです。たとえば子どもに関する問題といえば、児童虐待。夫は仕事、妻は家事という分業意識が育児の全責任を負わされた母親のストレスを深め、暴発させた悲劇とされています。子どもに関わるひとすべてが社会全体が同床異夢のままでは、ほんとうの教育改革は実現されえないでしょう。
「育児は育自」「教育は共育」という言葉がありますが、教師は資格によって先生になるのでない。親が子を生んだからといって、かならずしもふさわしい保護者であるとはかぎらないのと同様に。子どもによって育てられ、そして子どもといっしょに学びつづけるものなのです。
最後に付言しますと。こうした資格の更新制は、ややもすると今後、教員免許だけでなくほかの資格にもおよぶのではないかということです。私は法曹界と医療現場にも、ぜひ導入するべきではとも思います。ただし以上に考察したような問題があらかじめ予想されますので、その効果のほどはじゅうぶん検証されなければならないでしょう。
【参照サイト】
教員免許更新 広がる不満 県教委「技術向上の機会」
(河北新報) - goo ニュース















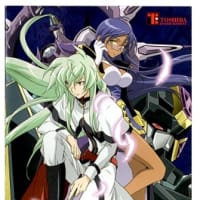



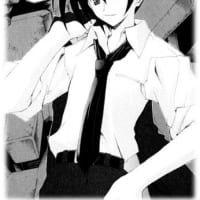










私も、2人の子供の親として、考えなければならない問題で、大変興味深く読ませて頂きました。
私も子供の頃、なんでこの人が「先生」なんだと、思うような教師に出会いまして、学校という場所に対してトラウマのようなものがあります。
ですが、私は親であり、いずれ義務教育によって子供を学校に預ける立場となりますので、それではいけないと思い、子供対して熱心に勉学を教えている方々のブログを見に行って、教職に立ち、どんな風に子供のことを考えているのかを知ろうとしています。
教員免許更新制は、ゆとり教育と同じで、複雑になった教育現場・教師の成長を妨げる制度となるかもしれませんが、子供の教育を、塾や学校、国に丸投げしておいて、あとで文句を言うような親にだけはなるまいと思います。
健康で青い苗に除草剤をまかれたら、その中和剤となれるよう、子供や先生とともに悩む、人間でありたいと思います。
また、もともと不健康な苗に出会ってしまったときの対処法も子供に教えなければなりません・・・が、
こちらは、まだよい解決策が見つからずにいます・・・。
教育者の意識と質の向上は大変大きな問題だと思いますのでとても興味深く拝見しました。
決して教職者を非難するつもりはないのですが、特に義務教育である小学校・中学校の教諭・教師はあまりにも世間知らずであることも根本問題ではないかと思います。
学校という砦にこもり、特殊な価値観に同化させられてしまうだけでなく、生徒という圧倒的に優位に立てる存在があり、ともすれば「圧政」できる立場でいられることから生じる、自分の考えを疑わない傲慢さ等々・・・
せっかくの熱意ある人でさえ気がつけば独りよがりで相手の気持ちが理解できない教師になってしまう要素があまりに多いのが今の教育現場だと思います。
※政治的思想は人それぞれですが、特に、税金をもらっている公立の教師に限って日教組や共産党系の活動ばかりして子供に偏った思想を平気で垂れ流すことを疑問にも思わない糞ったれが多いのは、全く困ります。
全く、なんですかね。有給とって授業なくして、今は無き社会党の決起大会に参加した挙句生徒にまで選挙に「土井先生を応援するように」と親に言えと喚く中学教師ってやつは。
30時間も要する更新制度よりも、一定期間過ぎた教師は、たとえば半年とか3ヶ月程度、教師の立場を離れて強制的に「民間企業」(ここがポイント)に出向させて、お客様に頭を下げてすいませんといわせるとか、そういうほうが効果がありそうですし、本当に腐った教師を見つけてあぶりだすこともできそうな気がします。
好き勝手言いましたが、私のいた公立中学校には平気で嘘を教え、ことあるごとに国を批判し、赤旗新聞を生徒に読ませる教師ばかりでしたので。
ちなみに私の父は歴史学の教授であり、事実の検証方法だけはしっかりと叩き込まれましたので、中学教師の唱える独りよがりな「歴史教育」が、いかにいい加減でソースも史料も無い捏造であるか、中学生ながらいやでも目に付いてしまい、さらにそれを指摘したところ教師にいじめられるという結果になりました。
いやあ、たいしたものです。本当に言い方が悪いですが、近代史を専門としている大学教授の父のほうが間違っていて、国際法の意味も知らず、ろくすっぽ史料も呼んだことない自分のほうが正しいと平気で主張できる馬鹿教師って奴は。
そういうわけで、私自身、「公立の左思想系の教師ほど知識も品性も教養もない存在は無い」という偏見を持ってしまっています。
教師がだめだと、生徒までこんなになってしまい負の螺旋が続くという、まさに「反面教師」として、あえて過激なコメントをさせちただきました。
まったく、こんなことなら幼稚舎から大学までリリアンに通ったほうが100倍ましってもんです。
それではごきげんよう。
ごきげんよう、eminamoti様。
こちらへ、お越し下さって感謝しております。
私がこの記事を書くにあたり、予想されたコメントは教師に好意的ではなく免許更新制には諸手をあげて大賛成な方々です。私自身も先の記事で書いてしまいましたが、過去の学校でのおぞましい記憶をただぶつけて、その怒りを制度の導入への無批判的に喜びとして昇華せしめてしまう思考のパターン。自身がその制度の対象者でなければ、実害を想定することができず、いくらでも蚊帳の外から大ナタをふるうことができますね。私はしばしばこの徹をふみ、読者様のコメントによって愚考を反省することしきりであります。
ですから、じっさいに教育現場に携わる方、もしくはその予定者の方に、冷静なご意見をいただけてうれしく思います。
>子供対して熱心に勉学を教えている方々のブログを見に行って、教職に立ち、どんな風に子供のことを考えているのかを知ろうとしています。
まず、この態度に感服します。批判をするならいくらでもできます。でも、それに対し、自分はなにができるだろうかと動き出せるひとは少数です。自戒をこめて、そう思うのです。
>教員免許更新制は、ゆとり教育と同じで、複雑になった教育現場・教師の成長を妨げる制度となるかもしれませんが、子供の教育を、塾や学校、国に丸投げしておいて、あとで文句を言うような親にだけはなるまいと思います。
そのとおりですね。そもそもゆとり教育にしろ、提唱したのは教育専門家か政治家なのかもしれませんが、受験勉強やお稽古ごとで子どものゆとりがないと騒がれすぎた世論の声をうけて導入したもの。学校で教えられない部分をカヴァーする、安価な教育システムが外部として受け皿にあれば、学力低下も招かなかったでしょう。結果としてお勉強熱心でかつ経済的に余裕のある子どもほど高い学力を身に着けられる、学力格差をも招いているのではないかということです。
一部の教師の問題行動のせいで教育レヴェルが悪化している、だから教師全員を締めつければいいというのではありません。たとえば、児童虐待が後をたたない。では、日本の育児をしている親がすべて悪い。そう決めつけるようなものです。
>健康で青い苗に除草剤をまかれたら、その中和剤となれるよう、子供や先生とともに悩む、人間でありたいと思います。
ひとりの苦しみも大勢で分けあえば苦しくない。何ごとも、いっしょに問題を考える姿勢というのがだいじですね。個性の尊重とか問題の自己解決能力の向上とか言葉だけが空回りして、ひとりで問題をかかえこもうとする先生が多いのではないかと思います。子育てについても、それはいえそうですね。
>もともと不健康な苗に出会ってしまったときの対処法も子供に教えなければなりません・・・が、こちらは、まだよい解決策が見つからずにいます・・・。
もともと不健康な苗、すなわち不良教師が、更新制によって駆逐されればよいのですけれどね。教師にしたら免状をとりあげられたら、食い扶持をうしなうわけですから、意識改善にはなるではありましょうが。
ただ、そこまでにいたるまでに、そのふできな苗を正常な苗にもどすことが大切なのですが。それがいわば、更新講習の目的であって、よくいえば教師の学びなおしの機会なのですが。
具体的な対策にはならないかもしれませんが。もし学校の先生が自分のお子さんをだめにすると判断された場合、(子どもといっしょになって一方的に教師を批判せずに)自身で教えられることはおしえる、ないしは学校外でかわりの先生を見出す、でしょうね。
この制度のよい面は、短期ですが講習期間中の教師の代替要員として臨時教員の需要がみこめるということでしょう。(その代理者がうまく穴を埋められるかはさておき)多くのひとが教育に携わるというのは、よいことです。
この記事は多くの方に関心をもっていただいたようで、いろいろコメントをいただきました。海外在住生活が長い教免所持者で、はじめてこの事実を知った方もいらっしゃったようです。教職についておらず、教育とは無縁な業界で多忙を極めていれば、知っていらっしゃらない方もいるのではと思います。
なお、ご存じかと思いますが、「資格取得日の翌日から十年」とありますので、〇九年時点で十年以上経過しているひとは更新措置をしないかぎり、自動的に資格を剥奪されてしまうわけですね。ただし、有効期限を過ぎたあとでも講習を修了すれば復活します。しかし、介護実習を義務づけられた教免保持者の場合、いったん資格をうしなうと再度介護実習までうけなおさないといけないようです。
誰かが過ちを犯したとする。そしてそのひとを追い払うのは、教育ではなく刑罰なのです。この更新制、先生をさばく(捌く、裁く)のでなく、なおすもしくは教えるという意識で機能してくれたらと思います。
子どもに最高の教育をうけさせてやりたい。いい人生を歩ませるために。そう願わない親はいないでしょう。
とりあえず、この制度によって全面解決すると安堵せずに、これはただ全人的に教育の再生を考える契機にすぎないものだと認識しておくことですね。eminamoti様のように、おおくの保護者の方が教育の問題をじぶんの懐にかかえこんで、あたためてくださることを願っています。
では、コメントありがとうございました。
ごきげんよう、名無し様。なんとなく一見様でないように感じられるのは気のせいでしょうか…?(微笑)
なかなか刺激的なするどい論弁のコメントをいただき、ありがとうございました。
教室は教師の砦。自由教育の名のもとに、ほかのおとなは立ち入りできない聖域。教室で多くのいたいけな瞳をしたがえている慢心が、彼らをして殿様気分にさせる。私はむしろ、大学教育のほうにそうした専横さを感じましたが、ひとによっては小中学校時代にそれを体感した方もいるでしょうね。
ちなみに、悪しき教師の例なら私も事欠きませんよ。
たとえば高校受験で、市外の有名商業高校を志望校に選んでいた女の子がいた。その担任は彼女の内申書から合格ラインぎりぎりだと判断し、受け持ちのクラスから不合格者をだすまいと必死に市内のランクの低い高校を勧めていた。しかし少女が志望を頑として曲げなかったので、その願書を受験先へ届けなかったのです。期日ぎりぎりになって別の教師に発見されたので事なきを得ましたが。彼女はその志望校の推薦を得て大手企業に就職、いいパートナーにも巡り会えて幸せな生活をおくっています。一歩間違えば、彼女の人生はおおきく狂わされていたことでしょう。その担任はただ忘れていただけだと軽く謝罪しただけ。いまでしたら、お咎めなしではすまされぬ話です。
また、こんな話もあります。校長先生の娘なので採用試験で優遇された。精神病といつわって給料をもらいながら長期休暇をとっている。その影で、採用試験が受けられる年齢制限を超えてしまったので、すばらしい力量をもちながらも社会保障のない臨時雇用に甘んじなければならない人びともいる。もちろんこの話は、部外者として私が知る限り聞く限りの教育界の悪い例です。しかし狭くて曲がりのはげしいレンズに近づいて映しこまれたものほど大きくみえてしまうもの。その見え方で糾弾してばかりはいられないということですね。
>政治的思想は人それぞれですが、特に、税金をもらっている公立の教師に限って
私は家の経済事情もあり、また私立の高校が少ない地域でしたので、ずっと公立でしたので。公立の教師、ありていにいえば公務員だから傲慢だとは思いませんでした。かえって私立のほうが創立者もしくは学園長の思想のために妙な宗教教育が、おこなわれていると思うのですが。にしても、それって八九年のマドンナ旋風のころの話でしょうか?いろいろ突拍子もないことをしでかす先生もいるもんですね(苦笑)
>一定期間過ぎた教師は、たとえば半年とか3ヶ月程度、教師の立場を離れて強制的に「民間企業」(ここがポイント)に出向させて、お客様に頭を下げてすいませんといわせるとか、そういうほうが効果がありそう
この更新講習の三十時間でも確保できるか嘆いているというのは、現職教員の声なんです。そしてじっさいわずかな時間にせよ、教育現場をはなれると支障がでるのは、子どもたち、ひいてはその保護者です。問題教師の更生という名目では、現在、指導研修制度があります。おっしゃるように勤続年数が長きに渡る教師すべてをやみくもに教育現場から三箇月もひきはなしたら、現場に混乱が生じるのは目にみえております。
なお民間企業にて再教育というのは、以前に飲食店で教師を研修させたという話を耳にしたことがあります。けっきょく効果のほどがあったのか、さだかではありません。たしかに奢りたかぶった教師の頭を低くさせるにはいい手段かもしれないですが、私は安易すぎると思いますね。れっきとした企業で社内講師をしているベテラン営業マンに指導を仰ぐのならばまだしも。そもそも時給アルバイトで高校生でも誰でもできるような接客レベルと、学校の教師にもとめられる対人折衝能力とは雲泥の差です。(誤解されないでほしいですが、職業差別発言ではありません。教師の仕事のほうが時間や労力を考えると、まじめに時給に換算したら割にあわないほどたいへんだということです)塾や資格スクールなど教育産業は、生徒を顧客と見なし最善のサービスを提供しようとつとめますが、その教育のしかたは、学校とはことなります。学習意欲のない子どもの興味をひきたて、いかに数十分の授業に集中させるか、ひとりひとりの能力をみきわめ悩みに応じて指導する。悪い行いにはきびしく叱る。そういった教育テクニックはすぐには教育現場で身につかないし、ましてや他に場を移してどうなると反論したくなります。
私は逆に、少子化や高齢出産のせいで子どもを希少化し甘やかしている風潮、体罰教師の過大報道が、保護者側を増長させ教師を萎縮させているのではないかとも思うのです。そしてはたして現場のたいへんさを日々実感していない、実践指導でなく文献学で教育論をかたって資格をばらまいてきた感のある教員養成大学の教官に、更新講習をゆだねて大丈夫なのかと案じているのです。
>本当に腐った教師を見つけてあぶりだすこともできそうな気がします。
火に紙の裏側をかざして、不穏分子な模様をあぶり出すという更新制。しかし、不要な文様どころか、精白な紙そのものまで灰にしてしまわねばよろしいのですがね。
ところで、その社会科教師の件ですが。お父上の教育法を冒涜されたことで腹立たしいお気持ちはよくわかります。先生が生徒をいじめるなどはもってのほか。私も高校の担任に家の職業を賎しめるような発言をされたことがありますから。そのことも含めて現在の私の教師否定にはなっておりますが、すべて根こそぎで疑わしきものは刈り取ってしまえばよいとの見解には、同意しかねるのですね。
それから、すこし出過ぎたもの言いをお許しいただきますと。「大学の専門研究としての歴史学」と、「教科教育としておしえる歴史」には隔たりがあります。後者のほうは検定を経て数年に一度しか改正されない教科書をもとにしているのですから、多少なりとも最新の研究成果が集積されている大学人の知見と異なるのは当然ではないかと思うのです。こういってはなんですが、大学の研究とは学者の数だけ学説があるような世界。一般に流布しているようなテキストの解釈をつねに懐疑し、否定しながら仕事をする大学人の教えが、学校現場との教育内容から離れていってしまうのは常なのです。さらには日本史学科でまともな研究論文を書いて卒業した人間と、教員養成課程の社会科教育を出た人間(教職に就くのを目的としているため卒業研究の質が問われない)、ないしは地理学や政治経済など歴史が専門ではなく社会科教諭の免状を得た人間とでは、おなじ歴史を教えるにしても差が出るのは無理からぬことです。学問と学習とは違うのです。
それは美術の分野でもいえることでして。教育学部で美術科を修めた者よりは、おおむね芸大・美大出身者のほうがはるかに石膏デッサン力もあり斬新な絵を描きます。ですが、児童の美術教育では、うまく描くかではなく、あくまで市販の教材などを用い児童の表現意欲をださせるかに注進しているように思えます。アーティスト気取りな表現者、研究者肌な先生では、とても子どもの目線とおなじになって、ものを感じ世界をながめての指導などおぼつかない。
大学で更新講習をうけさせるとしても、最悪、教官たちが自説の宣伝目的と著作テキスト販売のために利用するだけが関の山ではなかろうかというもの。(私の在学時は資格取得のための講義はこうした類のものが多かった)ほんとうに、現場に応用できるように教師を再教育できるのかと疑問なのです。これは教育問題のみならず、ひろく社会一般の職業につきましてもいえることでありますけれど。
話題がずれましたが。要するに学校教育とはおしなべて特殊な能力を必要とされるもの。けっして成績のよい者がすぐれた先生になれるのではないのと、おなじ理屈です。
少子化にあたり定員割れで生き残り対策に必死な大学はいま、社会人の再教育機関として再編成をされようとしており、企業と共同プログラムを開発したり、教官も教育現場を見学したりしてアカデミズムと実業との空気の隔たりを埋めようとされているようですね。
>まったく、こんなことなら幼稚舎から大学までリリアンに通ったほうが100倍ましってもんです。
いや、さすがにそれは無理です。あんな絵に描いたような華々しい学園ライフなんて、この世にありえませんから(笑)
いろいろ興味深いお話をありがとうございました。ただ名無し様とはいえ、個人が特定できそうなこと、しかも中傷めいたことを、他所であまり書かれないほうがいいと思います。私はこのHN名義で発言したことには責任をとる所存ですが、某匿名掲示板のような無責任な発言に類するもの(元社民党党首の差別的話題からしてそこの吹聴には目に余るものがあります)には対処いたしかねますので。
しかし、私の記憶から掘り起こしましても、たしかに社会の先生は妙な思想の持ち主が多かったです。でも、良心的な先生ばかりでしたので五科目のなかではいちばん興味を惹かれるものになりました。学校ではであえなくとも、今後の社会で名無し様が生涯の師と仰げる御仁にめぐりあえる機会はあるのではないでしょうか。それはひとではなく、書物のなかのいち章節や一幅の絵画であってもいい。いい指導者にであえなくても嘆く事なかれ、自分で学びつづければよい。自身が師としたものに更新も期限も関係なし。私はそう思うのですね。
では。
教員の免許更新制度、これもお立場によって見方が分かれる一つかもしれませんね。導入の理念を歓迎しつつも中身が駄目だと言われる方、理念も内容もまったく駄目だと憤慨される方が各方面にそれぞれいらっしゃる。教員の方たちの中にも制度の問題点を指摘し撤回を求める方たちがおられる一方で、制度を歓迎される方もおられる。
教員とは立場が異なる管理職や教育委員会の中にも、制度の運用への不安を口にされる方、効果を疑問視される方がいらっしゃる一方で、制度を理念に沿った形で運用すべく奔走しておられる方たちもいらっしゃいます。
政治日程の都合と、官邸の思惑と中央教育審議会を有する文部科学省の思惑とのせめぎ合いの中で、いつしか枝葉の議論ばかりが飛び交うようになった教育再生会議でしたけれど、再生会議の目玉の一つとして導入が決まったのが教員の免許更新制度でした。当然中身は、背景からしても中途半端な妥協の産物とならざるを得ず、万葉樹さんのように心から教育を憂えておられる方にとっては納得がいかない点も多々おありでしょう。
当事者の立場、特に免許を更新するために努力しなければならなくなった第一の当事者となる教員の方々のお立場に立たれた上での問題点の指摘は、とても説得力がございました。
当事者の立場に立って考えるということ、なかなかできることではありません。大変難しいことです。自分の思いがあればあるほど、難しい。立場や考えを異にする相手であれば、その相手の立場に立って考え理解を深めるということは、時に至難の業です。
教育は、誰もが一家言の持ち主になるテーマなだけに、よけい難しい。
教員、先生の立場になれば、Aだと言えることでも、生徒の立場になれば、どうか。保護者の立場になればBになるかもしれない。管理職の校長からみれば、Cと思えることでも、組合活動をしておられる方にとってはXになる。
大学で教育研究していらっしゃる方にとってMであって欲しいことが、教育行政を司る文部科学省の官僚にとってはSであって欲しいことだったりします。
だからこそ、集まって論議を尽くすことが求められるのですけれど、そこで相手の立場に立って問題点や解決策を考えるという姿勢を持つことは一層難しくなります。自説の応酬となり、自説に拘泥する。信念があればあるほど、拘泥する。
感情も波立ち収拾が付かなくなる。そのような中でそれでも妥結点を図らなければ、一歩も解決に向けて前進できない。
革命ではなく改革だから、前進するには妥協の産物とならざるを得ないけれども、それでもそれが第一歩。
立法サイドでも、教育熱心な議員の示す解決策が同じテーマでありながらABCDさまざま。政治は不介入と言いながら、教育ほど政治化しやすいものはなく、教育ほど政治介入させてはいけないものも、またない。
なのに政治主導でやらなければどうにもならないと多くの方が思ってしまったほどに、教育現場では問題が山積。この国の教育は荒廃しているというのが多くの国民の共通認識となりました。
それもまた、教育改革にとっての第一歩。
(こうしたことが国民の共通認識となる不幸を、いったいどれだけの方が認識していらっしゃるでしょう。)
そうした気の遠くなるような営為の果ての第一歩ですもの、それを踏み出したのですから、この教員免許の更新制度も前向きに支援していきたいと思うわたくしです。
駄目なところは、また皆で知恵を出し合って修正していけばいいのです。そういう方向を向いておられる限り、万葉樹さんが一個人としてご指摘になられた今般の教員免許更新制度の中身に対するご懸念は、このブログをご覧になられた方たち、真摯な思いで教育を憂えておられる方たちにリアルに受け止められるのではないでしょうか。そう期したいと思うわたくしです。
教育は現行法においては、地方分権の最たるものなのですから、自分の住み暮らす自治体でいかようにも工夫し解決策を見出していけるハズなので、ハズを現実のものとしていくためにも、当事者として自分の住み暮らす町の教育行政をチェックし、自分の出来る形でいいので町の教育改革に参画する意志を一人でも多くの方に持っていただけたらなあと期す次第です。
このコメント、ブログの日記で万葉樹さんがご指摘になられた論点への賛否やコメントではございませんけれど、
ゆっくりと読んでいただけたら幸いです。
万葉樹さんの教育に対する熱い思い、
十分に伝わるブログ日記でした。
ご寄文感謝いたします。
記事執筆中でありましたため、気づくのが遅れ、返信が間に合いませんでした。まことに失礼ながら、後日あらためて回答させていただきます。ご理解下さいませ。
では、本日も佳き一日を過ごされますよう。
ごきげんよう、月光院様。こちらにお越しくださいまして、光栄に思います。優雅な文体で語られるきじ猫のマルコくんと黒猫桜子ちゃんの日常と、名画講説が楽しみな万葉樹です。
このたび私的都合によりレスが遅れまして、申し訳ありません。
私がこの記事でめざしたことは、自身が教免所持者でないからといって、傍観者のような気分で安易に制度を後押ししないことです。降りかかる火の粉からとおい高見櫓から、批判の矢をそそいで混乱をたのしむような態度はけっしてしまいと。おそらく、数年前の私なら若気の至りでそのような怒りに任せた暴論をここに吐き連ねていたことでしょう。
おっしゃるように、この制度の導入にあたってはいろいろな立場から賛否両論悲喜こもごもあったことと窺えます。
ちなみに、私が今夏に成立したこの制度をいまどきになって取りあげておりますかといいますと。恥ずかしながら、その時期、いやここ数年の教育改革なるものの動きを見定めてこなかったからなのです。この記事を書くにあたって、文科省の該当HP、ベネッセコーポレーションの教育広場、教育問題にくわしい某議員のブログなど、手当たり次第に読みました。ネット上でこの制度成立までの経過を遡及的にたどってはみたものの、やはり当時の声を知らない物言いのせいか、いささか片手落ちで説得力にかける論理であったようにも思えます。
ですので、月光院様のように、リアルタイムで教育再生会議のなりゆきを見守られていたであろう方のご意見を拝しますことは、このうえなくありがたきお言葉添えなのです。制度の問題点を行政側から問いただされた論説、拙所ではあたらしい観点で、とてもうれしく思いました。
私としても、この教育制度が国民のためというよりは、政治家の形式的な業績づくりのために利用されたのではないか、という疑念は拭いきれません。
文科省HPに掲載された諮問のやりとりなど眺めておりますと、口当たりはまろやかですが論点をはぐらかすような生ぬるいやりとりに、いささか呆れる始末です。とりあえず、この制度を導入して教育の不満を現場の教師へ向けさせればよい、あとの結果はしったこっちゃない。どこかしらそんな無責任めいた心持ちが透かしみられたようで。そんないい加減な態度ではじめられる制度、はたして信用してよいものだろうかと。不安に駆られたものです。
>当事者の立場に立って考えるということ、なかなかできることではありません。大変難しいことです。自分の思いがあればあるほど、難しい。立場や考えを異にする相手であれば、その相手の立場に立って考え理解を深めるということは、時に至難の業です。
この相手の身になって考えるというのは、いわば教育者として必要な素養なのではないでしょうか。教育といいますのはいっぽうてきに指導をすればよいものではありません。耕作にたとえますと「教える」は水や肥料や太陽の恵みを与えられることですが、「育てる」はその者のもっている力を伸ばしてあげるようにあれやこれやと算段することです。けっして伸びが悪いからと苗をひっぱって長くすればいいということではなく。理解力と思いやり、なによりそれを必要とされる職種に、現場を理解しない配慮に欠けたうえからの指導をする。これほど矛盾したことがありましょうか。
>自説の応酬となり、自説に拘泥する。信念があればあるほど、拘泥する。感情も波立ち収拾が付かなくなる。
恥ずかしながらもこの、自説にこだわり話手の揚げ足をとるという手法は、私がここのコメント欄においてしばしば陥っている過ちであります。そして自分の方針に相手を引き込み、自分のととのえた鋳型にはめこんだ人格を大量生産しようという教育者と、本質的にかわるところないでしょう。私自身はこうした教育家としての資質に欠けていることは自認していますので、教育に関し自論をさしはさむことはすまいとここ数年かんがえていたのですが。教育関係者様のブログを拝見するうちに、なにか発言しておかなければと思い立った次第なのです。
>政治は不介入と言いながら、教育ほど政治化しやすいものはなく、教育ほど政治介入させてはいけないものも、またない。
とくに初中等教育は憲法にさだめられた国民の義務でありかつ無償が保証されているのですから、政治が関与せざるをえない部分はあるかと思います。しかし、地方公務員である教員に国の指導がどこまで許されるのか。今回の制度導入にあたっても、更新講習のカリキュラムは文科省の監修のもと旧国立大学で作成される。講習を各都道府県教育委員会にゆだねるという案もあったそうですが。しかし、だからといって裁判員制度のように評価と裁定を市民に丸投げしてよいものでもない。難しいところですね。
またいちばん恐ろしいことには、更新制成立の前提として戦後初めて教育基本法が改正されてしまったこと。日本国憲法改正の前段階なのではないかともっぱら噂されているのですね。東国原宮崎県知事の徴兵制奨励発言もありましたけれど、これを機に日本がふたたび軍事国家の道を歩みはじめるのではないかと案じてしまうのです。そこまで考えいたるのは杞憂かもしれません。ですが、そこにはなにがしかのシステムを導入しさえすれば、形式を整えさえすれば万事解決する。そのような浅はかさが感じられるのですね。原因をふかくとらえようとせずに、うちたてた対策は逆にトラブルをふかめることになりかねないのです。
この制度で危惧していることは、教員志望者が減るのではないかということです。数年前に新規採用をひかえたがため、小中学校には中高年の教師ばかりでフレッシュなエネルギーに欠けたと報道されていました。私の回りでも教員免許を取りながら教師は割にあわない仕事だからと教職に就かない例が多かったのです。ある意味教師は聖職であるという神話が、職業的誇りをたかめ優秀な人材を集めていたといえる。教師を卑しめはずかしめ、ますます教師の自信を奪う結果になっては逆効果です。更新制は資格の信頼性をたかめるものであってほしいのです。
>そうした気の遠くなるような営為の果ての第一歩ですもの、それを踏み出したのですから、この教員免許の更新制度も前向きに支援していきたいと思うわたくしです。
駄目なところは、また皆で知恵を出し合って修正していけばいいのです。
ほんとうにそのとおりですね。「悪法もまた法なり」という言葉があります。法というのはしばしばひとを網にかけて捕らえる倫理的な罠。しかしその網の目すべてがひとしい大きさとは限らず、緩んだり破れ目もあったりする。それに盗みを働いた者を罰するのは法律ですが、それを更生するのは人為です。
導入がきまってしまった以上、それをもはやくつがえす術はありません。だからといってお上のお達しだからと暗黙裡にしたがうのではなく、これを好意的に利用して改善してゆくのが目下もとめられるべき道行きなのです。教員免許更新制は、いたらない教師をいかにおおく摘発する取り締まり法ではない。心構えとしては、いかにその更新制にひっかかって教師の道を閉ざされる者を少なくするかにあるのです。つまり先生がたが教育者としての情熱をうしなったり、心身をむしばまれたり、個人ではどうにもならない学級運営の問題をかかえた場合、いかに支えの手をさしのべられるか。悪い制度を敷かれたならば、なおのことそれをのりこえる人間力のみせどころなのではないでしょうかと。
>当事者として自分の住み暮らす町の教育行政をチェックし、自分の出来る形でいいので町の教育改革に参画する意志を一人でも多くの方に持っていただけたらなあと期す次第です。
抽象的な図式化で恐縮ですが、教育という領域にあっては、「家庭」「学校」「行政」の三権分立が図られてよいのではないかと思います。私はこの三者にあってもとりわけ家庭の役割がおおきいかと思います。核家族化がすすんだせいか、家庭問題に干渉しない風潮がよしとされてはいますが。個々人のプライバシーを犯さない範囲において、家庭も学校も開かれたテリトリーで、誰もがエントリーできるのが理想です。
教育のみならず、総じて行政問題にいえることですが、参加者意志をもつことがだいじなのでしょうね。オピニオンを寄せることはたしかに大切。さりとて実行力をともなわない論士の言葉ほどやすいものはない。月光院様のお言葉を胸にいだきまして、自分がなにをできるのかは、考えつきつめていきたく思っております。
それにしても、うちのようなとんちきブログに美文をお寄せくださり夢の極致であります。
では、コメントありがとうございました。