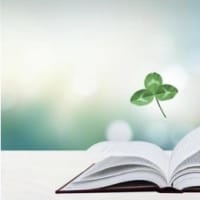そのロープから数段歩いた頃だろうか。
ちょうどふたりの間にある、階段の中央を照らした明かりのうちに奇妙なものが飛び込んできた。
「『ア』…?」
「『ヒ』…『ヒ』?!」
階段に置かれた「もの」を口にして、ふたりは顔を見合わせた。
ふたりのライトが照らし出したもの、それは階段の一段ごとに盛られた白い「文字」だった。
白い砂のようなものが美しい勘亭流で、文字をかたどって積まれていたのだった。真琴はしゃがみこんで、それを指先につけてねぶってみた。ざらりとしたその砂粒は、舌の上で塩味を残しながらうっすらと融けていった。
「お。こりゃ、しょっぱい」
真琴が、ほれ、とさしだした指先を、姫子もおそるおそる舐めてみた。食わず嫌いをする姫子の舌も、それがなんら変哲もない塩であることを確かめたのだった。
「これ、なにかのおまじない?」
「そうかもな。塩はお清めにつかうって言うし」
「だったら、これ以上歩いたらまずいんじゃないかな」
ライトをさらに横にかざしていくと、闇の底に『白』が浮かんだ。そのさらに上には、『小』がほの見える。
一段につきひと文字というのではないらしい。光りの輪を滑らせてみれば、『小』のある左右には『ヌ』があり、『土』があるのだった。漢字もあれば、片仮名もある。いったいこれはなにを語るのだろうか。
「何かのメッセージかな?」
「さあね。それにしても、みごとな文字だなぁ。こりゃ、芸術の域に達してる」
腰に手をあてがいながら、感心しきりで真琴は、盛り塩の文字を照らした。
粗塩なのだろうか、宝石を砕いたかのように、光りの粒子がきらめいている。しかし、先ほどのロープといい、いたずらにしては手が込んでいるではないか。
「どうするの、マコちゃん?」
「姫子はそこで待ってな。どこまで続いてるのか確かめてくる」
『ま』の段に姫子を残したまま、真琴はいきおいよく階段をかけあがっていった。
そして、ゆっくりと文字を辿りながら、光の輪だけが階段の段差を這うようにして降りてきた。
「マコちゃ~ん、どお、読めた~?」
「姫子もあがってきなよ」
上階から、やや遠く呆れた声が降りてきた。
言われたとおりに、下から順に目にした文字を口に含みながら、姫子は上っていった。だが、それが無駄だと気づいたのは文字の先頭に辿り着いてからだった。各段にある文字はやはりさっぱりと意味をなさない。『干』、『シ』、『言』、『ノ』の四つが同じ段に並べられているかと思えば、『糸』『十』『ワ』のグループがあり、一部がなんとも判じがたい文字のようなものまである。『エ』『日』『一』とおなじ列にある『π』は、あの数学でつかう円周率のことなのだろうか。いずれにせよ、それらはさしずめ、粘土を棒状にして並べたような形状であり、より高校生らしい類推にあてはめるとすれば、姫子がさんざん悩まされている生物の教科書で見かける、細胞分裂中に現れるあの紅い染色体のようなものだ。線だけがだらしくなく絡み合ったような文字だった。上の段にいくほど、夜の湿気に融かされて、輪郭があいまいになっているらしい。融けくずれた雪のように、文字はどろりと石段に積もっていて、ここにも夜の底に散り散りになりながらも、なお地熱として潜む、炎暑の名残りを感じずにはいられない。
その文字段はしめて十四段はあっただろうか。
最後の段にあったのは、『二』、『九』、『申』という三文字であった。なんとなくそう見えただけで、ひょっとしたら、他の文字であったのかもしれない。いや、そもそも、文字などではなくして、なにかを意味する記号であったのかもしれない。さらには灯りで追えていないだけであって、闇のふもとにはいまだ知らぬ文字がそこかしこ潜んでいるのかもしれない。