石舟斎の館の中には資料室と柳生家所縁の肖像画が本堂に並んでいる。裏山には歴代の墓所がある。柳生の隆盛だった時代を偲んでみる。剣豪小説・講談本など、わくわくしながら読んだ本の世界がここにあった。
この史料室から隣の本堂に繋がっている。展示物の一つ一つは剣術家相伝の活き活きとした品物ばかりである。宮本武蔵とか塚原卜伝とかも出てくる。


剣術の奥義を伝える巻物。
免許皆伝の時はこれらの内容がすべて伝授されたのである。箱の蓋の上書きの中に「新陰流奥法」「新陰流絵目録」の文字が見える。

どうもこれは新参者の剣術の心得が書いてある巻物のようだ。
右の三か条以って、初学の門として、これから勉強をしていきましょう、などと書いてある。

剣術の型の絵が描いてある。正眼の構えとかの図解が書いてある巻物だろう。人物の描き方が面白い。

左:柳生新陰流2代当主である柳生宗矩(むねのり)
右:当時親交のあった沢庵(たくわん)和尚


左:ちょっと見えにくいが、三面六臂の仏は麻利支天である。いつも猪の上に乗って姿を見せる。武士の守り本尊である。姿を隠して障難を取り除く。護身・勝利などを祈る。戦国武将前田利家は兜の中に、麻利支天の絵を貼っていたという。
右:柳生家の4代までの系図である。いずれも剣豪小説に出てくる剣術家である。


本堂の裏手の窪んだ土地を越えると、柳生家累代の墓所がある。格式のありそうな墓石が並んでいる。小さな領主であったが立派な大名である。


最も小説によく出てくる柳生但馬守宗矩がここに眠っている。子連れ狼はなかったが、烈堂はあったような気がする


この史料室から隣の本堂に繋がっている。展示物の一つ一つは剣術家相伝の活き活きとした品物ばかりである。宮本武蔵とか塚原卜伝とかも出てくる。


剣術の奥義を伝える巻物。
免許皆伝の時はこれらの内容がすべて伝授されたのである。箱の蓋の上書きの中に「新陰流奥法」「新陰流絵目録」の文字が見える。

どうもこれは新参者の剣術の心得が書いてある巻物のようだ。
右の三か条以って、初学の門として、これから勉強をしていきましょう、などと書いてある。

剣術の型の絵が描いてある。正眼の構えとかの図解が書いてある巻物だろう。人物の描き方が面白い。

左:柳生新陰流2代当主である柳生宗矩(むねのり)
右:当時親交のあった沢庵(たくわん)和尚


左:ちょっと見えにくいが、三面六臂の仏は麻利支天である。いつも猪の上に乗って姿を見せる。武士の守り本尊である。姿を隠して障難を取り除く。護身・勝利などを祈る。戦国武将前田利家は兜の中に、麻利支天の絵を貼っていたという。
右:柳生家の4代までの系図である。いずれも剣豪小説に出てくる剣術家である。


本堂の裏手の窪んだ土地を越えると、柳生家累代の墓所がある。格式のありそうな墓石が並んでいる。小さな領主であったが立派な大名である。


最も小説によく出てくる柳生但馬守宗矩がここに眠っている。子連れ狼はなかったが、烈堂はあったような気がする


















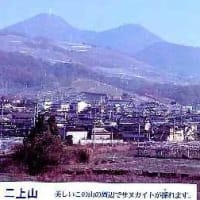
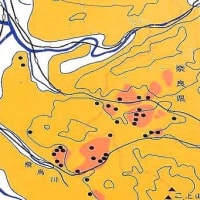


剣術の型の描かれた巻物はとても面白いです
一番左の人物は刀を二本持ってますね
見て、嬉しいショットばかりでした。
特に、剣術の型の絵が描いてある人物の描き方に、惹かれました。
面白いですね。
とても、珍しいショットの数々、ありがとうございました。
免許皆伝の証しに巻物を貰って、それがあれば何でも出来るような気もしていましたよ。
上手く描いていますね。それに二刀流と言うのは宮本武蔵だけではありませんね。
特に興味を引かれたものだけ撮ったのですが、ほかに武器の鎖鎌のようなものとか、鉄で出来た索とか、書画・掛け軸・木彫・陶磁器などが多数ありましたよ。
さすがに、剣術で身を立てた柳生だと思ったものでした。
剣術も奥義を伝える巻物・・貴重な資料を拝見出来るなんて思いもしませんでした。
剣術の型の図解、一見象形文字を思わせる様でとっても良く解り楽しく拝見できました。
剣道に関わりの有る大徳寺大仙院の「七世沢庵和尚」の像を此方で拝見出来た事も感激です・・
目録なんですね。これより後は口伝とかになるのが普通でしょうか。
図解までしてあるとは、これは教授用の虎の巻でしょうか。
沢庵さんによろしく。
男なら知らない者はいない「柳生十兵衛」の名前でも、故郷が何処なのか知らない人は多いのでは無いでしょうか。
実は私も「柳生の里」の名前は知っていましたが、現実、何処に有るのか知りませんでした。江戸の話が多いので、まさか此処にあったとは
菩提寺や貴重な巻物など見せて頂き有難う御座いました。
豆本とか、少年倶楽部とか、戦後は宮本武蔵とか、近くは子連れ狼とか、幕府隠密とか、柳生一族の達人ぶりは、随所に出てきますね。
芳川英治の宮本武蔵で、彼の訪問を、柳生は座敷の木の枝を刀で切った一枝を持たせて断りますね。
その切り口を見て、その剣の道の達人振りを理解する武蔵など、わくわくものでしたよ。