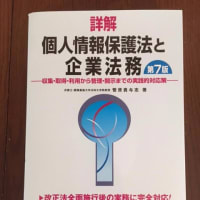新・落語で読む法律講座 第26講
石町二丁目の越中屋では、若い奉公人が大勢いてちょっかいを出すため、なかなか女中が居つかない。そこで、さがしだしてきたのが、とてつもない醜女のお染。さすがに店の奉公人も手を出さない。
ところが、ある晩のこと、番頭の身寄りで若党の佐造が、酒に酔って、お染に手をつけた。さんざん金品をせびったあげく、妊娠までさせてしまうが、お染から夫婦になってほしいと迫られ、佐造は困ってしまう。店の者のてまえはあるし、世間体もあり、また、主人に顔向けもできない。
とうとう佐造はお染を殺害しようと企てる。
加賀の屋敷内の友だちに預けるのだと偽り、お染を五斗俵に押し込んで、和泉橋から神田川に突き落とした。夜釣りから帰るところの二人連れが、米俵だと思って開けて驚く。
翌日、河原に様子を窺いにきた佐造が召し捕らえられ、時の町奉行・遠山左衛門尉の裁きを受けることになる。

この噺、『遠山政談』と題してはいるが、かんじんの遠山金四郎が登場してくるわけではない。もし遠山の金さんが出てきたならば、おなじみの悪代官と町娘が対決するお白州の場面となるだろう。
悪「お奉行様、私にはまったく心当たりのないことで」
娘「ちがうんです!わたし、見たんです。この人たちがお染ちゃんを……」
悪「よもやこんな小娘の世迷言をお信じになるつもりじゃ……おい、小娘。そこまで言うのなら証拠をここに出してみなさい」
娘「証拠と言われても……あっ……そ、そうだ金さん……お奉行様、金さんが全部知っています。遊び人の金さんを探してください」
悪「あっはっはっは。ええ呼んでもらおうじゃありませんか、その金さんとやらを」
悪人たち「そうだそうだ、金さんをここに呼べ! おおい、金さんはどこだあ」
奉行「…オイ、うるせえなあ…ちったあ静かにできねえのか。おうおう悪党ども、そんなに見てえ証拠なら見せてやる…冥土の土産に目ン玉ひんむいて、よおく拝みやがれ…あの日、見事に咲いた遠山桜…ウヌら…この桜吹雪、よもや見忘れたとは・・・・・・言わせねえぞ!」

ここでの遠山金四郎は、「遊び人の金さん」として事件を内偵・捜査し、「遠山左衛門尉」の立場から、悪人どもに厳罰を下す。つまりは、裁判官であるとともに、警察官であり、また検察官でもあるのだ。
しかし、現代の刑事訴訟は、そのような仕組みになっていない。
裁判が公平であるべきことは、いわば裁判の生命である(憲法37条1項参照)。そこで、訴訟手続の面での公平な裁判を担保するために、裁判官と検察官は、まったく別個の組織に属し、その機能を分化している。
また、検察官と被告人の両当事者ともに、十分な主張と立証ができるような平等の機会を与える建前となっている(当事者対等主義)。
さらには、公判がはじまるまで、あらかじめ裁判所が事件の内容にタッチすることなく、白紙の状態に保つようにも配慮されている。これを予断排除の原則という。
たとえば、起訴状には、裁判官に事件についての予断を生ぜしめるおそれのある書類などを添付できないし、その内容も引用してはならない(刑事訴訟法256条6項)。公訴提起には、起訴状一本をもってしなければならないのである(起訴状一本主義)。
戦前の旧刑事訴訟法当時には、遠山の金さんほどではないにせよ、起訴と同時に一切の捜査書類と証拠物が裁判所に提出され、裁判官はあらかじめその内容を精査していたから、事件に対する十分な心証を抱いて公判に臨んでいた。このようなやり方は、検察官には有利だが、すでに裁判官が有罪の予断をもっているおそれがあるため、被告人の側にとって不利な場合が多い。そこで、現行法においては、起訴状一本主義を中心とする予断排除の原則を採用したのである。

ところで、この「この桜吹雪が目に入らぬか」という大いなるワンパターンこそが、いまだ根強い時代劇人気の秘訣である。「善いモンはいい、ワルイ奴は悪い」との徹底した勧善懲悪。この分かりやすさが見ている側に心地よい安定感となって伝わるのだ。しかし、現実の世の中、そんなに単純ではない。
都内のある駐車場で傷害事件が発生した。駐車料金を精算する出口付近で、先行車両の運転手が、後続ドライバーの顔を数発殴ったのである。加害者は無職の若い男。被害者は青年歯科医。新聞の社会面をかざるほどの事件とはいえないが、もし記事風に書くとこうなるのだろう。
「警視庁某署は、東京都板橋区○○、無職甲野太郎容疑者(24)を傷害の疑いで逮捕した。調べによると、甲野容疑者は今月17日午後5時ごろ、練馬区○○の遊園地「○○ランド」の駐車場で、横浜市鶴見区○○、歯科医乙野次郎さんの顔面を数回殴打し、全治一週間のけがを負わせた疑い。」
この記事をみれば、「人様に手をあげるなど、とんでもない。そんな粗暴な奴にはキツイお灸をすえてしかるべき」との感想をもつのが普通ではなかろうか。これだけを読めば、である。しかし、事実はそう単純ではない。
植木職人として修業中だった甲野は、この不況のために失職。病弱な若い妻と4歳になったばかりの娘をかかえて、失意のまま郷里へ帰ることにした。苦しいばかりで、なにひとつ楽しいことのなかった東京での生活。この街の最後の思い出にと、甲野は、元の職場の先輩からオンボロの軽自動車を貸してもらい、家族を連れて遊園地に出かけた。1枚のフリーパス券を交互に使って娘を乗り物にのせ、3人でやきそばやソフトクリームを食べる。この貧しい一家にとっては、ささやかにぜいたくな一日を過ごした。


帰路につくために甲野が軽自動車を駐車場から出すとき、その事件は起きた。甲野の車が徐行して直進中、突然T字路の横から頭を出してきたのが白いベンツである。この運転手(乙野)が、クラクションを鳴らし、「薄汚い車で、私の前を横切るんじゃない!」と大声で神経質そうに叫んだ。しかし、一時停止を無視したのは乙野のほうだ。その後ベンツは、甲野を威嚇するように、ぴったりと後続追跡してくる。
駐車場の出口ゲートのところで2台が停車したとき、乙野はベンツを降りて、甲野の軽自動車の窓ガラスをドンドンと叩き、「おい、出てこい! お前ら、私の高級車をキズつけても弁償なんかできんだろう」
と血相を変えて怒鳴りつづけた。
助手席では、妻のひざの上に抱かれた愛娘が、おびえたように父親を見上げている。
今日の思い出を台無しにされてはならない……小さくうなずきかえし、甲野は車外に出た。
乙野は、車内の幼児に一瞥をくれた後、真正面から甲野を見据えた。
「こらっ、サル!車を運転するなんぞ、百年はやいんだ」。小柄な甲野は、猿顔といえなくもなかったが、妻子の面前で「サル」呼ばわりされ、堪えがたい屈辱感におそわれた。
乙野は、自分のあごを突き出すようにして、「なんだ、私を殴るのか?殴れるものなら、殴ってみろ。お前のようなチンピラになめられてたまるか。サルめ!」と挑発するように言った。
車内の娘が泣きだしたと同時に、甲野のなかで何かがプツンと切れた。次の瞬問、甲野の握りしめた拳が乙野の顔面にとんでいた。
乙野は、警察署でも、横柄かつ高飛車で一方的であった。「さっそく歯科医師会の顧問弁護士と相談する。ただでは済まない。私は被害者だ」。そう言い放った乙野は、甲野の行状を悪しざまに申し立て、彼には多額の損害賠償を要求し、かっ、警察には厳罰に処することを強く求めた。取調べにあたった警察官さえも、加害者の甲野に同情したという。


殴った甲野が正しいなどと一言うつもりは毛頭ない。しかし、しかしである。妻子の面前で「サル」呼ばわりされた甲野の気持ちはいかばかりであったろう。だれがこの家族のささやかな思い出を奪えるというのだろうか。
このケースでもそうであるが、事件の多くは、一方(加害者)だけによって引き起こされるわけではない。事実を解明し、真実をみきわめるためには、他方当事者(被害者)にも目を向け、彼が事件発生にいかなる影響を与えたかもさぐる必要がある。ただ「善いモンはいい、ワルイ奴は悪い」だけでは、名奉行はつとまらないのだ。
さて、『遠山政談』に話を戻すと、お染を俵に入れ川に捨てる場面などは、落語らしからぬ(?)凄惨な筋立てになっている。しかし、人間の性を表現するのが落語なら、こうした噺があることも仕方ないと思う。
【楽屋帖】
昔ながらの因果モノ仕立ての「お白洲もの」で、遠山金四郎の裁きの中にあった実話をもとに、四代目三遊亭圓生が作った噺といわれる。舞台は現在の日本橋本石町。