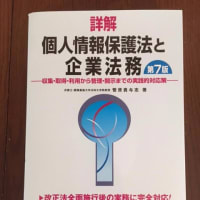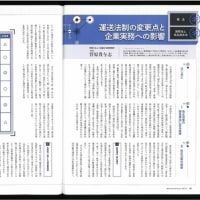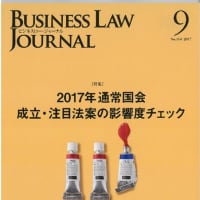新・落語で読む法律講座 第24講
わが国の根本法、日本国憲法が制定されてから、70年になろうとしている。
最近では、総選挙が実施されたこともあって、護憲だ、改憲だ、論憲だと、憲法論議も喧しい。現行憲法が、大日本帝国憲法(明治憲法)73条に定める改正手続を通じて制定されたことは、よく知られているところだ。
ところで、現行憲法にあって明治憲法時代にはなかった人権規定が二つあるが、ご存じだろうか。ひとつは「学問の自由(23条)」、もうひとつは「思想・良心の自由(19条)」である。
この思想・良心の自由は、人の内心領域における自由を保障するものであり、精神的自由(表現・信教・学問の自由)の母体をなすものとして機能している。内面の自由そのものまで統制した戦前の苦い経験から規定されたものだ。そして、これは「沈黙の自由(内心を外部に表すことを強制されない自由)」をも要求する。
上方落語には、この沈黙の自由を侵害された男の噺がある。

うたた寝をしている亭主を、女房がひょいっと見ると、うなされるような声を出したり、ニターツと笑ってヨダレを垂らしたり。
「ちょっとあんた、起きなはれ。えらいうなされて、いったいどんな夢見たん?」
「夢なんか見てない」
「ほな、なにか、女房の私に言えんような夢見たんか」
「アホ言え! 見てたら言うわい」
……夫婦喧嘩になる。
隣の男が飛び込んで、「アホな喧嘩するな」と仲裁するが、
「ほんまはどんな夢、見たんや?」
「ほんとにオレ、夢なんか見てへんのや」
「兄弟分やと言うてるオレにも、夢の話できんのか!」
……また喧嘩である。
ここへ家主が飛び込んできて、
「アホなことで喧嘩するな。ところでおまえ、かなりおもしろそうな夢らしいな?」
「いや家主さん、ほんとに夢なんか見てえしまへんねん」
「親子も同然の家主に夢の話できんのか。そんなやつ、ほかの店子のしめしがつかん。今日限り家あけてもらおう」。
仕方がないので、町奉行に訴えでる。
奉行もあきれて、
「店子の見た夢の話を聞きたがって、店立てを申しつけるとは不届き千万。ところで、夢の話、奉行にならばしゃべれるであろう」
「いや、ほんとに私、夢なんか見てえしまへん」
「できんと申すか、この者に縄をうて!」
……奉行所の松の木にぶらさげられてしまう。
これを僧正ケ谷の大天狗が助けてくれ、
「わしは聞きとうない。が、その方がしゃべりたいというのなら、聞いてやってもよい」
「いえ、ほんとに夢なんか、見てえしまへん」
「天狗をあなどるとどのようなことになるか、存じおるか。五体は八つ裂きにされて、杉のこずえにかけられる」と、爪の伸びた指が、体にかかった。
「助けてくれ! あー、あー。あー」
……女房が「ちょっとあんた、起きなはれ。えらいうなされて、いったいどんな夢見たん?」。

この男、言いたくないことを言わないのではない。何も話すことがないのに、話をしろと言われているのだ。沈黙の自由に対する侵害もはなはだしい。
ところで、この『天狗裁き』。めぐりめぐって話がもとに戻っている。要するに、噺全体が循環構造になっているのだ。こういった噺のサゲ方を「廻り落ち」という。
循環構造といえば、現行憲法の予定する統治システムも循環構造である。主権(憲法1・15条)。国者・国民は自分たちの代表者(国会議員)を選挙で選ぶ民の代表者は議会(国会)を通じて政府(内閣)を組織し(議院内閣制、67・68条)、この政府が国民に福利を提供する(64・25条)。
そこでは、徹底した多数決民主主義が貫徹されているのである。この国民→議会→政府→国民という循環構造が、憲法の予定した統治システムなのだ。通常ならば、これで国民みんなの幸せは確保されるだろう、まさに「最大多数の最大幸福」である。
ところが、この多数決民主主義による循環システムも万能ではない。うまく機能しない場合がおおむね二つある。ひとつは循環システム自体に欠陥がある場合、もうひとつは多数決では救われない少数派の人権保護が問題となる場合である。
このような場面では、もはや民主主義による循環システムの自浄作用を期待することはできないから、循環構造の外にいるものの力を借りざるをえない。ここに「憲法の番人」の役割を果たす裁判所(司法権)の存在意義がある。
循環システム自体に欠陥があるとは、表現の自由(思想や情報を発表し伝達する自由、21条)に対して不当な制限がされている場合である。表現の自由は、もともと「話す」自由、「書く」自由として観念されてきた(「送り手」からの表現の自由)。言いたいことが言えないようでは、この世も真っ暗闇である。一方、この表現の自由を別な角度、すなわち「受け手」の側からみれば、「聞く」自由、「読む」自由、そして「知る権利」となる。
民主主義においては、この知る権利がきわめて大切だ。民主主義は「国民による政治」を標榜する。
しかし、国民にさまざまな事実や意見を知る権利を認められなければ、自らの意見を正しく形成することはできない。もし表現の自由に対する不当な制約が加えられたら、もはや投票箱を通じてそれを修正することも不可能だ。
知る権利なくして、国民の真意を反映した政治など期待できないのである。これが「表現の自由はきわめて重要な基本的人権」といわれる所以である。

【楽屋帖】
この『天狗裁き』や『夢金』など、人々が見る夢を題材にした落語は数多い。「僧正ケ谷の大天狗」の僧正ケ谷は鞍馬山の奥にあり、かの牛若丸(義経)が天狗僧正坊から武芸を習ったところである。
ところで、表現の自由といえば、落語も立派な表現である。明治憲法下の一時期、この落語という表現の自由にも受難の時代があった。昭和16年10月30日、浅草寿町三丁目(現在の台東区寿二丁目)の本法寺境内に鷲金亭金升題字の「はなし塚」が建立され、廓噺や艶笑噺など53題が禁演落語として埋葬されたのである。重要産業指定規則が公布され、鉄鋼・石炭・セメント・自動車など12業種に統制会が設立されたのも、この日のことだ。
終戦から1年を経た昭和21年9月30日、これら禁演落語の復活祭が行われた。日本国憲法が公布されたのは、そのおよそ1月後の11月3日のことである。

わが国の根本法、日本国憲法が制定されてから、70年になろうとしている。
最近では、総選挙が実施されたこともあって、護憲だ、改憲だ、論憲だと、憲法論議も喧しい。現行憲法が、大日本帝国憲法(明治憲法)73条に定める改正手続を通じて制定されたことは、よく知られているところだ。
ところで、現行憲法にあって明治憲法時代にはなかった人権規定が二つあるが、ご存じだろうか。ひとつは「学問の自由(23条)」、もうひとつは「思想・良心の自由(19条)」である。
この思想・良心の自由は、人の内心領域における自由を保障するものであり、精神的自由(表現・信教・学問の自由)の母体をなすものとして機能している。内面の自由そのものまで統制した戦前の苦い経験から規定されたものだ。そして、これは「沈黙の自由(内心を外部に表すことを強制されない自由)」をも要求する。
上方落語には、この沈黙の自由を侵害された男の噺がある。

うたた寝をしている亭主を、女房がひょいっと見ると、うなされるような声を出したり、ニターツと笑ってヨダレを垂らしたり。
「ちょっとあんた、起きなはれ。えらいうなされて、いったいどんな夢見たん?」
「夢なんか見てない」
「ほな、なにか、女房の私に言えんような夢見たんか」
「アホ言え! 見てたら言うわい」
……夫婦喧嘩になる。
隣の男が飛び込んで、「アホな喧嘩するな」と仲裁するが、
「ほんまはどんな夢、見たんや?」
「ほんとにオレ、夢なんか見てへんのや」
「兄弟分やと言うてるオレにも、夢の話できんのか!」
……また喧嘩である。
ここへ家主が飛び込んできて、
「アホなことで喧嘩するな。ところでおまえ、かなりおもしろそうな夢らしいな?」
「いや家主さん、ほんとに夢なんか見てえしまへんねん」
「親子も同然の家主に夢の話できんのか。そんなやつ、ほかの店子のしめしがつかん。今日限り家あけてもらおう」。
仕方がないので、町奉行に訴えでる。
奉行もあきれて、
「店子の見た夢の話を聞きたがって、店立てを申しつけるとは不届き千万。ところで、夢の話、奉行にならばしゃべれるであろう」
「いや、ほんとに私、夢なんか見てえしまへん」
「できんと申すか、この者に縄をうて!」
……奉行所の松の木にぶらさげられてしまう。
これを僧正ケ谷の大天狗が助けてくれ、
「わしは聞きとうない。が、その方がしゃべりたいというのなら、聞いてやってもよい」
「いえ、ほんとに夢なんか、見てえしまへん」
「天狗をあなどるとどのようなことになるか、存じおるか。五体は八つ裂きにされて、杉のこずえにかけられる」と、爪の伸びた指が、体にかかった。
「助けてくれ! あー、あー。あー」
……女房が「ちょっとあんた、起きなはれ。えらいうなされて、いったいどんな夢見たん?」。

この男、言いたくないことを言わないのではない。何も話すことがないのに、話をしろと言われているのだ。沈黙の自由に対する侵害もはなはだしい。
ところで、この『天狗裁き』。めぐりめぐって話がもとに戻っている。要するに、噺全体が循環構造になっているのだ。こういった噺のサゲ方を「廻り落ち」という。
循環構造といえば、現行憲法の予定する統治システムも循環構造である。主権(憲法1・15条)。国者・国民は自分たちの代表者(国会議員)を選挙で選ぶ民の代表者は議会(国会)を通じて政府(内閣)を組織し(議院内閣制、67・68条)、この政府が国民に福利を提供する(64・25条)。
そこでは、徹底した多数決民主主義が貫徹されているのである。この国民→議会→政府→国民という循環構造が、憲法の予定した統治システムなのだ。通常ならば、これで国民みんなの幸せは確保されるだろう、まさに「最大多数の最大幸福」である。
ところが、この多数決民主主義による循環システムも万能ではない。うまく機能しない場合がおおむね二つある。ひとつは循環システム自体に欠陥がある場合、もうひとつは多数決では救われない少数派の人権保護が問題となる場合である。
このような場面では、もはや民主主義による循環システムの自浄作用を期待することはできないから、循環構造の外にいるものの力を借りざるをえない。ここに「憲法の番人」の役割を果たす裁判所(司法権)の存在意義がある。
循環システム自体に欠陥があるとは、表現の自由(思想や情報を発表し伝達する自由、21条)に対して不当な制限がされている場合である。表現の自由は、もともと「話す」自由、「書く」自由として観念されてきた(「送り手」からの表現の自由)。言いたいことが言えないようでは、この世も真っ暗闇である。一方、この表現の自由を別な角度、すなわち「受け手」の側からみれば、「聞く」自由、「読む」自由、そして「知る権利」となる。
民主主義においては、この知る権利がきわめて大切だ。民主主義は「国民による政治」を標榜する。
しかし、国民にさまざまな事実や意見を知る権利を認められなければ、自らの意見を正しく形成することはできない。もし表現の自由に対する不当な制約が加えられたら、もはや投票箱を通じてそれを修正することも不可能だ。
知る権利なくして、国民の真意を反映した政治など期待できないのである。これが「表現の自由はきわめて重要な基本的人権」といわれる所以である。

【楽屋帖】
この『天狗裁き』や『夢金』など、人々が見る夢を題材にした落語は数多い。「僧正ケ谷の大天狗」の僧正ケ谷は鞍馬山の奥にあり、かの牛若丸(義経)が天狗僧正坊から武芸を習ったところである。
ところで、表現の自由といえば、落語も立派な表現である。明治憲法下の一時期、この落語という表現の自由にも受難の時代があった。昭和16年10月30日、浅草寿町三丁目(現在の台東区寿二丁目)の本法寺境内に鷲金亭金升題字の「はなし塚」が建立され、廓噺や艶笑噺など53題が禁演落語として埋葬されたのである。重要産業指定規則が公布され、鉄鋼・石炭・セメント・自動車など12業種に統制会が設立されたのも、この日のことだ。
終戦から1年を経た昭和21年9月30日、これら禁演落語の復活祭が行われた。日本国憲法が公布されたのは、そのおよそ1月後の11月3日のことである。