先日書いた「日本企業の苦しみを25年前から味わっていたアメリカ企業」という記事には、
2日間で2万人以上のアクセスがあり、あちこちで記事にもしていただいた。
復活した企業はあるの?日本はどうすればいいの?続きが読みたい、という希望も頂いた。
では、新しい技術などに押され、崩壊しつつある大企業は、どうやって復活すれば良いか。
個別企業が具体的にどうするかは企業によって異なるが、総論としてどうすべきか、という解の仮説は、私には一応ある。
(それを実証する理論的サポートとして、産業のダイナミクスを描いてるのが今の私の修士論文。)
でもこのブログでは、理論的な小難しい話ではなく、分かりやすく事例で迫りたいとおもうんで、
これから次のような内容の記事を書いていく予定。
- IBMやGEなど見事復活を果たした企業は、どうやって復活したのか
- 仮に日本企業が日本で復活しようとした場合、受け皿の日本社会に必要なのは何か
- a) 大企業の中央研究所が持つ技術資産を、ベンチャーなどが使って生かしていく素地を作る
- b) 人的資産の流動化。専門・経営職含めた労働の流動性を高める
1は総論としては、企業が持っている強み、すなわち、人的資産、文化、事業の考え方など企業に根付いている強みで、まだ使えるものを活かしながら、対応していくという話になる予定。
この強み、とは、MBA卒の人とかが横文字で「コアコンピタンス」と呼んでるやつ。
つまりコアコンピタンスの多くを活かしながら、企業は変革をすべきだ、という話だ。
どーでもいいけど、この内容で、「コアコンピタンス企業変革」とかいう本書いたら売れそうじゃない?(笑)
まあ私はブログで書くけど。
それはともかく、仮に1で他社・他国事例を研究して、参考にしようと思っても、
結局2の日本の問題が解決しないと、日本では意味ないんじゃないかと私は思うのだ。
特に2-b)で「労働の流動化を高める」なんて書いたら、書いた矢先から炎上しそうで、
だからこそ現実とあるべき姿のギャップが大きいということなので、解決するのは大変ってことだ。
というわけで、その話から書いてみようと思う。(前置き長し)
新しい技術とか、新興国から競合が出てきて、旧技術に依拠する大企業が潰れそうになってるとき、
その企業を変革しようとしたら、何にせよ、組織や事業形態を大きく変えることが求められる。
その時、もちろん社員には新しい組織や事業に移動してもらって、馴染んでもらうようにしたいのだけど、
全ての人が変わっていけるとは限らないだろう。
変われなくてお荷物になる人、変革自体を阻止しようと抵抗勢力になる人が、結構な数出てくる。
こういう人には会社を去ってもらわないと変革できず、結局「技術はあるのに組織が変えられない」結果になってしまう。
要はリストラが必要になる。
企業としては変革する際に、自社の大事な人的資産である社員を、できるだけ活かした方が、
より強い事業ができるはずなのだが、必ずしも全ての人は維持できないのである。
すなわち、追い上げられた企業が大きく変革をする場合、どうしてもリストラは避けられない。
こういう話をすると「従業員をリストラするくらいなら変革しない方がいい!」と反論する人が必ずいるが、
そういう人は、前に書いたコダックの例を思い出してみよう。
変革しないとフィルムカメラ市場がどんどん小さくなって、会社が潰れ、全員解雇になるだけである。
あるいはIBMはどうか?
自分たちが生み出したPCサーバによって、メインフレームの価格破壊が起こり、市場が縮小している。
システムインテグレーションというサービスに全社を移行しなければ、生き残れなかった。
一部の人が犠牲になるとしても、別事業にシフトするとか、ビジネスモデルを全く変えるとかして生き残ることは、残りの人たちを救うのに重要になるのだ。
更に言うと、企業が分断されて崩壊されると、企業が今までに蓄えた技術、スキル、暗黙知は失われてしまう。
社会全体でみても、大企業を単に崩壊させるよりは、変革して、強くして、生き残らせる方が社会のためになると私は思っている。
実は、企業の経営者は出来る限りリストラはしたくないと思っている。
特に家長的性質の強い日本企業は、従業員の生活を守るのが企業の使命だと考える人は未だ多い。
例えば、どう見ても別事業にシフトすべき事業から、撤退できない大企業がたくさんある。
これは、撤退したら、その事業で働いてる社員はどうなるか、と思って踏みとどまってしまうのだ。
実際には、事業撤退→新事業参入でリストラされるのは一部だけだが、その人たちの生活を考えると、決断できない。
だったら、まだ少しはお金が入ってくるのだから、何とか今の事業にとどまって、頑張って回復しよう、という話になる。
モトローラが何故1G携帯電話から2Gにシフトできなかったか?
1Gは、多くの特許と技術をモトローラが所有し、じゃんじゃんお金が入ってきた事業だ。
そのおかげで、研究開発に大幅にお金をかけられたし、研究者・技術者もいっぱい雇えた。
2Gに行ったら、その人たちを抱えるほど儲からないから、リストラするか、別事業に異動してもらうことになる。
出来るだけそんなことはしたくないので、モトローラは
「1Gのままじゃ帯域に制限がありすぎて、加入者数を増やせない」という問題に対し、
2Gへの移行ではなく、1Gの技術革新や、1Gへの莫大な設備投資で、何とかとどまろうとしたのだ。
(そのおかげでアメリカ全体の2Gへの移行が遅くなったことは以前書いた)
そのせいで2Gへの参入が遅くなり、ノキアに大負けして、売上げが大幅に落ちた。
モトローラはアメリカだからまだ良い。
アメリカは、人々が転職したり、ベンチャー企業に入って仕事したり、自分で起業したり、ということが割と普通に起こる世の中だ。
人材の流動性が非常に高い。
私の米国での友人にも、もともとモトローラのエンジニアでした、なんて人は何人かいて、
彼等は例えば、リストラを機にMBAとかに入り、「この間にMBA取っちゃおう」みたいに前向きである。
家族がいるのに工学博士に入り、ワンクッション置いて別の携帯電話メーカーに就職した人もいる。
あるいは、携帯電話向けアプリを作る企業に転職して、割と成功しちゃった40代のエンジニアもいる。
全部が上手くいくはずはなく、中には悲惨な例もあると思うが、上手くいく例が多くある。
だからこそ、モトローラはそれでもその後は何度もリストラを進めることができ、企業自体は存続出来る状況が15年ほど続いた。
ところが、日本ではどうか。
日本の一流企業といわれるところに正社員として勤めている、管理職やエンジニアを、変革に対応できない結果リストラ、ということが出来るか?
転職市場が非常に小さいこの国では、正社員でなくなったとたん「負け組」と言われる憂き目にあう。
同レベルの一流企業に転職するなんて、相当優秀な人でないとまずありえない。
そうでない場合は、一流企業に勤めてたパパが、翌日から中小企業やベンチャーに勤めるパパになるのだが、
これが余り日本では歓迎されない。
ていうか、一度そっちに行くと、後は転落人生になってしまうように思われている。
「起業したら?」なんて無責任に言う人は多いけど、VCも起業家ネットワークも発達していない日本で、
まとまったお金も技術もないのにどうやって起業するのか?
要するに、日本の場合、大企業が少しでもそういう管理職やエンジニアをリストラ、ということになると、
その人たちは転落人生決定みたいになっちゃうのだ。
第二新卒レベルの若さならまだ良いが、30代前半とか結構若い人でもそうなっちゃう。
外資系や海外の企業に行けば「転落」せずに済むが、英語が話せなければ話にならない。
これでは、社員を大切にする大企業は臆病になる。
そんな可能性がある変革だったら、今の(儲からない)事業のまま何とか頑張ろう、と。
で「ユデガエル」になっていく。
私はこの、大企業に勤めてるような人たちの人材の流動性を高めないと、大企業が抜本的に変革するのに、臆病になってしまうと思うのだ。
米国にいるモトローラですら変革が大変だったのに、況や日本企業をや、なのだ。
もう一度まとめると、
・大企業が大きな変革を行うと、リストラはしたくなくても必ず起こる。
・ところが、日本はそういうリストラされた人たちが転職する術がほとんどない。あっても「転落」とみなされる。
・企業がそういう決断をするのは非常に難しいので、少しはお金が入る今の事業に何とかとどまって頑張ろう、という安易な決断になって変革が遅れ、ゆでがえるになる。
で、米国でどうして人材の流動性が高いかというと、大企業間の転職が必ずしも大きいわけではなく、
人々が、ベンチャーとか、中小企業に転職するのに、そんなに抵抗がないこと、
MBAや社会人修士など、転職するための手段がいろいろ整っている、というのが大きいと思う。
こういう世の中になると、人々が起業を選択する、というのもだんだん可能になってくると思うのだ。
日本では、起業しようにも、お金も、技術も、人材も流通してないので、正直難しいことが多い。
ベンチャーに優秀な人たちが入ってくる環境、大学や大企業から技術を持った人材がどんどん流入してくる環境じゃないと、起業家社会を作るのは難しい。
そういうわけで、私は日本社会において、管理職・技術職レベルでの人材の流動性を高め、
転職へ人々の抵抗感をなくすこと-間違っても中小のベンチャーに勤めることが転落にならないように変える。
これが、大企業の変革にも、起業社会にするにも、大事なことだと考えている。
どうでしょうか?
(今後もこの続きで、IBM/GEなどの事例研究や、もうひとつの日本の問題を書いていこうと思ってます)











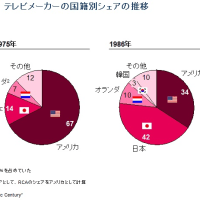
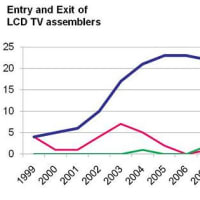
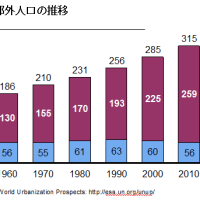
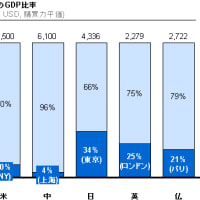

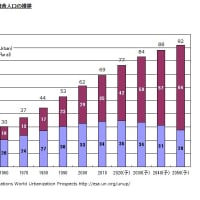
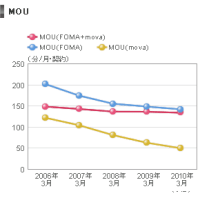
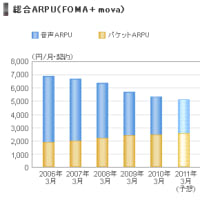
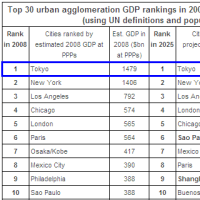
日本でも能力に見合った給与がどの事業規模でも得られるなら人材の流動化も進みそうですが。
あと、中小から大企業への転職の敷居も日本は高いですが、アメリカは如何でしょう?
あと、日本ではこれまでは能力がさほどなくても勤続年数でエスカレーター式に給与と地位があがっていったので、転職を考えた際に能力の応用が効かない人材が多いのでアメリカほど転職が盛況(?)でないのかな、とも思います。
細かい点なのですが
>実際には、事業撤退→新事業参入で養えなくなる社員は一部の管理職・技術職
と言う場合、
技術職は専門性が高いから分かるものの、
管理職が転用できない理由はどこらへんにあるのでしょうか?
先日、アントレの教授に相談したら
「日本は起業するには最低の国だ」と
言い放たれてしまいました。
とほほ。
中間管理職は企業の一部の組織を熟知しているというだけの組織「専門職」である場合が多く、かなり能力が高い人でなければ転用が難しい。また彼等は一般に転職も難しいことが多い。
>一部の人が犠牲になるとしても、別事業にシフトするとか、ビジネスモデルを全く変えるとかして生き残ることは、残りの人たちを救うのに重要になるのだ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC
にもあるように、この考え方は日本人にとって合理的だと感じられないのではないですかね。
一部を切って他が生き残るより、全員で共倒れを好む人が多そう、という意味です。
教育しないと スキルがないのにに起業や
転職は難しいと思う
市役所のHPの隅に職業訓練校の紹介があるが
短い期間でだったり人数が決められてたり
講師は素人だったり 市はアリバイ作りのためにやってるだけで 本気じゃないんだよな
公民館みたいなところ短い期間借りて職業訓練やってるといわれてもね
労働者の教育、失業者の教育しないと流動性なんてうまれないとおもう 会社じゃやらないだろうし
正直どんなに講師が優れていたとしても、ベースがない人間に教えるのはハードルが高いですね。
ハローワークといい教育訓練といい、官が民と全く違うフレームワークで動いていることも日本をだめにしている理由ですね。
> これは、撤退したら、その事業で働いてる社員はどうなるか、と思って踏みとどまってしまうのだ。
従業員を路頭に迷わせたくない、というのは多少はあるとは思いますが、
その事業を開始した先代の顔を潰せない、というのが最大の理由でしょう。
特に、自分を今の地位に押し上げてくれた人が始めた事業ならなおさら。
だから、社外の人間でないと退治できない。
> 私はこの、大企業に勤めてるような人たちの人材の流動性を高めないと、大企業が抜本的に変革するのに、臆病になってしまうと思うのだ。
今の日本の政策だと、潰れるのを阻止するので、次の産業が起こってこなくてジリ貧。
サンクコストは無視して国全体でのパイを増やすことを考えて欲しいのです。
> 人々が、ベンチャーとか、中小企業に転職するのに、そんなに抵抗がないこと、
アメリカだと、大企業とベンチャーとで給与水準に大きな差が無いのもでかいとおもいます。
大企業だと安定性とブランドが優れているけど、ベンチャーだとストックオプションとかでリスク・リターン関係にバランスがある。
日本の中小企業は、経営者のためにある組織であって、従業員を向いている組織じゃないから、敬遠されるのは当然ではないでしょうか。
批評家的な人間は退職金を渡すからと首を切られます。
あと社長は、学級委員みたいな雑な扱いをされてますよ。経営者の為の企業ではなく、本当に野望が高いのだと思います。
>人的資産の流動化
本当に流動化して欲しいです。
流動化したほうが、みな幸せになれると思うのです。
そんなことになったら、働かなくても金が貰える、今のおいしい地位が無くなってしまいます。
私以外の日本人の流動化は進めてもらってもいいですが、私だけは今の地位と年収を保証してもらいたい。
日本の将来とか、他人なんてどうなっても知ったことではありません。
みんな、口じゃあ、立派なことを言っても、本音はこれなのでしょう。
私も、そう思っています。