アメリカに暮らし始めて一番びっくりしたのは、この国ではコネが非常に重要だ、ということ。
何か、公明正大で機会均等の国だと思っていたイメージが全く覆された。
日常生活でも、「知り合いからの紹介」だと、提供されるサービスの質や早さが全く違ったりする。
就職活動でも同じ。
就活の最初の面接で会ってもらえるか、から、最後に誰を採用するか、というところまでコネは重要な役割をもたらす。
その会社の人たちがたくさんいるコミュニティに出入りして知られている、とか、
MBAの出身校が同じ、とか、
パーティであったことあるとか、
そういう理由だけで、普通は会ってもらえないものも会ってもらえたりするし、「実はこのポジションが空いてるよ」情報を教えてもらえたりするし、最終的な採用にも影響する。
知り合いの知り合いの知り合いが、狙ってる企業の採用担当者だったりして、わらしべ長者的に内定ゲットすることだってまれじゃない。
驚くことに、これってスタートアップやベンチャーキャピタルみたいな中小企業だけじゃなく、IT企業や製薬業界などにある、大企業・有名企業への就職でも同じだということ。
(ただし、アメリカでもAT&Tとか商業銀行とか航空会社みたいな、昔から確立した大企業だと別かも。このあたりに就職を試みる人が少ないので良く知らず)
日本だと、「研究室採用」やわずかに縁故採用が存在するくらいで、例えばOB訪問が採用の可否に大きく影響したりってことは余りないだろう。
何でアメリカでこれだけコネが重視されるのか。
ひとつは、それだけ多民族・多文化の国であり、同じ学歴・職歴でも、仕事に対する価値観、それに伴うスキルなどが全く異なるからじゃないだろうか。
これは、ビジネススクールにいると実感する。
すごくいい大学出身で、一流企業に勤めて、履歴書はピカピカなのに、
「仕事の責任の考え方」とか「仕事の進め方」が全く違い、全く一緒に仕事できない人、というのは存在する。
(別にその人が悪い、って事じゃなく、文化の違いかもしれない。向こうも同じことを思ってるだろう)
以前のエントリで書いた、「○○大卒」「○○会社勤め」という情報だけで、大体どのような考え方やスキルを持つ人かわかってしまう日本とはかなり違う。
ある意味で、私たちが、良い歯医者や病院を選ぶときに、自分の知り合いが薦めるかで選ぶのに似ている。
この国では、仕事の能力に「○○大卒」「○○勤め」などの情報は余り役に立たない。
かといって他に選択する基準がない。
だから口コミ・紹介が、より重要になるんじゃないか。
もうひとつは、特にIT・ハイテク、製薬、メディア、新エネルギーなど、この10年・20年で大きくなった業界では、業界人たちが持っているコミュニティっていうのがある。
コミュニティって言っても、「○○の会」みたいな明確な線引きがあるのではなく、業界の重要人物を中心としたゆるいつながりである。
で、業界人は、このコミュニティでの評価や人脈を大切にするのだ。
だから、そのコミュニティの知り合いから紹介された学生には会ってくれるし、時には採用につながることもあるのだ。
例えば、Googleの割と偉い人とかベンチャーキャピタルなどが参加してるシリコンバレーのコミュニティがあるよ、と言われれば、想像できるんじゃないか。
で、実際にそういうコミュニティは存在し、そういうところで、新しい会社が起業されたりするのだが、このコミュニティに属する人に高く評価されれば、その人の紹介というのは非常に意味がある。
他にもいろんなコミュニティがある。
例えば、ノバルティスやジェンザイム(遺伝子治療薬大手)など、有名製薬企業が集まっているボストンには、製薬コミュニティがあるそうだ。
そういう企業の中堅以上の人たちや、大学や病院の教授・研究者、製薬に関するベンチャーキャピタルや法律事務所、アントレプレナーなどがゆるくつながっている。
学生は、大学の先生や卒業生でこのコミュニティにいる人の紹介を通じて、ここに入り込んでいくことができる。
具体的には、そういう人たちが開く立食パーティに参加したり、セミナーに参加したり、単にメールで紹介してもらったり。
こういうコミュニティでネットワークを広げると、米国企業への就職できる確率は高くなる。
大学卒業生のコミュニティも大きい。
MITの場合、スローン単体より、MIT全体の卒業生コミュニティの影響力が強く、MIT卒業だというだけで、就活の際に会ってくれる担当者がいる。(人にもよるが)
米国では「MIT卒はネットワーキングが弱い」という悪評があるが、日本の大学なんかよりよっぽどつながりが高い。
ボストンだけでなく、シリコンバレー、シアトルなどさまざまなに存在し、IT、エネルギーその他いろんな業界につながっている。
そんなわけで、エントリが前後してしまったが、米国における就活において最初に進めるべきは、ネットワーキングだと思っている。
じゃあ具体論。
渡辺千賀さんがブログで何度も何度も書かれているように、アメリカで就職したいなら、前提としてまずは留学をするのは王道だ、と私も思う。
その上で、日本人留学生がどうやって狙っている業界のネットワークに入り込み、就職を有利に持っていくか。
色々書くけど、全部やると大変なので、自分の性格にあった方法で入り込むのが良い。
1) 業界関連のセミナー・パーティ・トレックには積極的に参加 (影響度:中~大、難易度:小~中)
大学にいると、この手の機会はたくさんある。
多くは、大学の先生が知り合いの業界人を呼んでセミナーを開いているとか、学生主催のセミナーとか。
その手のセミナーのあとは、立食パーティがあったりして、そういうところに、業界の要人が結構いたりする。
そういう人に会ったとき、自分の興味や能力を短時間でアピールできるよう、事前に多少練習しておくのが良い。
そこで相手が興味を持って、話が盛り上がれば、15分以上話をして、自分の興味やスキルをアピールできることもできる。
必要に応じて他の人を紹介してくれたりもするし、いきなり面接に呼ばれちゃうこともあるのだ。
私の場合、今年の1月に学校の授業の一環で行った、「シリコンバレートレック」の夜のパーティで、今年の夏のインターン(自分がやったのも含めて)先候補を複数見つけた。
うちひとつは(結局ここでは仕事をしなかったのだが)、日本の企業や大学との連携を模索しているところだった。
私と話して興味を持ってくれ、1週間後に会社に呼んでくれた。
この会社は、もともとサマーインターンを取ることは全く考えていなかったのだが、検討したい、ということで早速面接。
結局予算がつかなくて、誰も採用しないことになり、私も別企業で働くことが決まってしまったので、そこで終わりになってしまった。
けれど、こういうパーティに参加していると、本当に就職につながるような機会がある、と実感した。
ちなみに、この手のパーティでの「礼儀作法」については、以前書いたこちらのエントリが面白いと思う。
2)大学の先生を活用する(影響度:大、難易度:中~大)
研究室で担当教授がいる場合は、教授のネットワークを活用すべし。
でも、つながりは複数あったほうが良い。
MBAの学生も同様だけど、授業で「この先生は業界に影響力もあるし、いい先生だな」と思った先生には積極的にアプローチすべし。
まずはその授業の課題は、必要以上にしっかりやり、授業も積極的に参加して、先生に良い印象を持ってもらうことが大切。
あと、自分から先生のオフィスアワーに質問に行ったり、相談をしに行ったりする。
そうやって先生と仲良くなると、先生がやってるセミナー企画に混ぜてくれたり、重要人物を紹介してくれたりする。
自分の担当教授がいる場合は、カニバラないように注意が必要だけど。
日本でもそうだけど、業界に影響力のある教授の推薦は強力なパワーを発揮する。
3)大学の業界関連のクラブで、自分でセミナー・パーティを企画する(影響度:大、難易度:大)
日本もそうだけど、大学には「○○業界研究会」的なノリのクラブがたくさんある。
そういうところに入ると、自分と同じ興味を持った人と、業界人を呼んでのセミナーやパーティを企画することになるので、重要なつながりがたくさんできる。
例えば、私は100KというMITのビジネスコンテストの主催を今年の6月までやっていた。
ここでは、ボストン周辺のベンチャーキャピタル(VC)やシリアルアントレプレナー(複数企業を起業してる人)など、主要人物を呼んでのセミナーやパーティを企画。
そういう人たちにスピーカーなどをお願いするので、当然知り合いになれるし、イベント以外の自分の興味などについてアピールできる機会がある。
私は、別にボストンで起業やVCに興味があるわけじゃないって気づいたので、やめちゃったが、
本当に起業しようと思っている人なら、自分のアイディアをVCにアピールして起業につなげる一番の近道だろう。
VCに勤めたいなら、直接VCの重要人物にアピールできる。
すごい影響力のある手段だけど、ネイティブの学生と対等に仕事をしていかないとならないので、語学・文化の壁は結構大変。
あと、イベント企画とかが好きな人じゃないと続かない。
4)学会やビジネスコンテストに参加する(影響度:大、難易度:中~大)
研究してる人なら、学会に参加して、そこで業界人に自分の研究をアピールすることで、就職につなげるチャンスは多いだろう。
そうでない、ビジネススクールの学生や学部生も、大学で多々開かれているビジネスコンテストに参加して、自分のアイディアや能力をアピールすることができる。
ちなみにビジネスコンテストは、本当に起業したいひとだけでなく、その業界の大手企業に就職したい人にも意味がある。
例えば、私がやっていた100Kビジネスコンテストには、ジェンザイム、マイクロソフト、フィリップスなど、バイオテック、エネルギー、IT、コンシューマプロダクトなどの分野でたくさんのスポンサー企業がいる。
この人たちはベンチャーへの投資目的ではなく、その分野の優秀な学生を採用したい、と思って来ているのだ。
学生が考えるアイディアなんて、余程の物を除いて、事業化は難しいことを彼らは知っている。
けれど、そういうことを考えて、ビジネスモデルを作ることができる能力を持った優秀な学生がほしいのだ。
こういうコンテストでは、別に優勝しなくても、ノミネートしただけで、こういったスポンサー企業の採用担当者がたくさん来るパーティへの参加権が手に入る。
相手も、難しいコンテストを潜り抜けた人だと知っているから、最初からある程度の信頼を置いて付き合ってくれる。
ここで出来たつながりは、就職だけじゃなく、非常に大きなネットワーク財産になるだろう。
5)大学の卒業生を活用する(影響度:小~大(人による)、難易度:小~中)
卒業生の性格などによって違うけれど、OB/OG訪問は、一般に日本よりも威力を発揮する、と思ってよいと思う。
例えば今年みたいに景気の悪い年は、大企業でも「サマーインターンをやるかどうか」すら決まっていないということが多々ある。
大学の卒業生に会いに行くだけで、この手の情報が手に入ったりする。
直接採用権がある人につながればラッキーだが、そうでなくても、OB/OG訪問(別に本当に訪問しなくても、電話やメールで話すのでも良い)がきっかけで、重要人物につないでくれたり、そういう人たちが集まるパーティとかに呼んでもらえたりする。
そういうところでちゃんと自分をアピールすれば、「こういう人材がいるよ」と紹介してもらえる。
こういうのの積み重ねが重要。
6)日本人で米国企業への就職した人を活用する(影響度:中、難易度:小~中)
彼らが直接採用権を持っているわけではないが、就職に成功した人なら、それなりのネットワークは築いてきているはずだ。
こういう人たちに、自分の興味のある業界の人を紹介してもらったり、コミュニティに呼んでもらったりする方法は常にある。
日本人同士なら、こういった日本人を呼んでのセミナーを開いたり、パーティを企画したりっていうのは、そこまで難しいことじゃないだろう。
就職するに当たってのコツなんかも直接聞けるので、米国企業へのネットワークへの足がかり以上の意味がある。
ポイントは、「日本人のよしみ」だけを頼りにして甘えないこと。
中には「日本人だ」と言うだけで協力してくれる親切な人もいるかが、皆さん忙しいわけで、タダ日本人だからという理由で会ってくれる人は少ないと思う。
その人にとっても自分とつながるメリットをちゃんとアピールし、日本のビジネス常識はちゃんと守ること。
7)ネット上のコミュニティを活用する(影響度:小~中、難易度:小)
私自身は余りちゃんと使ってないけど、Linked InやFacebookのようなネット上のつながりがきっかけで、コミュニティに入っていくこともできるらしい。
Facebookよりは、ビジネス上のつながりを重視したLinked Inの方が影響力大。
Linked Inの人がMITで説明していたところによると、
・自分が本当に尊敬している、ネットワーク上意味があると考えている人とだけ友達になること。
(きびちーが、たいしたこと無いと思っている友人は自分のネットワークに入れない)
・相手が自分を知らない重要人物に送る場合は、どこであったか、自分は何者かを端的にアピールする文章を添えること
・セミナーやパーティであったら、その日のうちに礼状を送るとともに、Linked Inへの登録願いを出す
これで、Linked Inを使って就職をゲットする確率は5割増しだそうだ。
以上、米国での就職に大きく影響する「業界コミュニティ」に入るための7つの方法でした。
要約すると、
・アメリカでの就職活動では、事前に業界の人たち複数とネットワークしておくことが重要。
・理由はアメリカ人は日本と違って、仕事能力を測る共通物差しがないので、採用において同僚や自分が属している業界コミュニティの意見を重視するから
・日本人学生が、このコミュニティに入る(複数の重要人物に推薦してもらえるくらいのつながりを作る)には次の方法があり、自分の性格や好みでやれるところをやればよい
1) 業界関係のセミナー・パーティ・トレックに積極的に参加する
2) 大学の先生を活用する
3) 大学のクラブなどで、自分でセミナー・パーティを企画する
4) 学会・ビジネスコンテストに参加する
5) 大学の卒業生を活用する
6) 日本人で米国企業に就職した人を活用する
7) ネット上のコミュニティツール(Linked Inなど)を活用する

Two by twoにしたものの、あまり軸が切れてないのう。(意味なし)。
まあ「世の中近道は無い」「負担が大きいけど影響力小さい方法は書いてない」ってことで。
すごく長くなっちゃった(書くのも3時間近くかかった)けど、役に立てばいいなぁ。
米国就活シリーズ
1. 2009/08/05 MBA生が夏のインターンを獲得するには
2. 2009/08/10 アメリカ就職面接を突破する-MBA面接のコツも含めて
3. 2009/08/12 アメリカ就職面接その2-想像力を働かせて準備する
4. 2009/08/13 アメリカ就職面接その3-自分の能力を論理的に説明
5. 2009/09/04 アメリカ就職面接を突破する その4-雑談力の重要性
6. 2009/09/06 コネが重要な国・アメリカ-就活でのネットワーキング











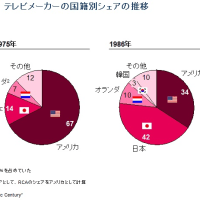
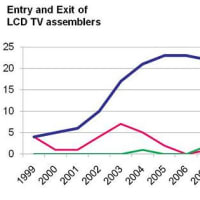
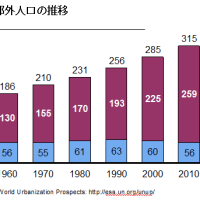
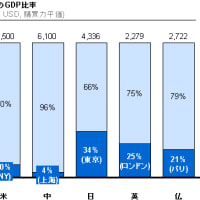

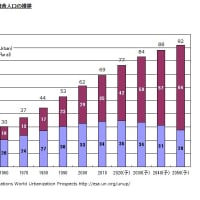
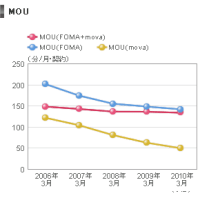
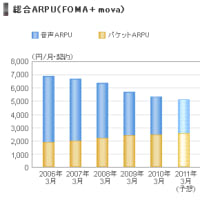
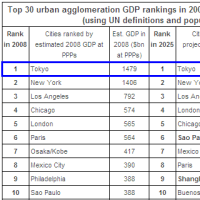
ただ日本でも OB/OG 訪問はとても重要だと思いますよ。特に古い大企業だと、まだリクルーター制度があって、OB/OG に会えないとそもそもそこから先に進めないこともあります。自分は情報系、弟は銀行業界で就職活動しましたが、どちらも同じで OB/OG と話すことが先に進むために必要なステップだった気がします。
LinkedIn の使い方、まだよく分かってないのですが、ネットワークのリクエストして断られることもあるってのは、そういうことだったんですね。今後活用していきたいと思います!
していました。
内定とっていました。かなり昔の話です。
私も、受講していた講座の教授のコネで
外資系証券会社面接は受けることが出来ました。落ちました。
「公」になっている採用窓口を通じて、
誰かに会うといっても採用担当者の人から
みたら、「この人何者?」
という不安感は消えないですよね。きっと。
昔むかし、「縁故」というもので、ものごとが
きまることに嫌悪感があったのですが。
採用側が、いい人材を採るという目的を
設定したとき、「縁故・コネ」にはそれなりに
合理性があるのだろうなと思います。
今回のLilacさんのエントリを読んで、そう思いました。
だって、「縁故・コネ」のビジネス関係が、
ある意味「リクナビ」より強力に整備されているように見えますもん。
うーん。そういっちゃっていいのかな。
どれだけこういったネットワークが強力に
なっても、「外」からみたら・・・・・。
「仲良しクラブ」の洗練された独占か・・。
というより、「チャンス」を見つけ出して、
どんどんアクションを起こしていこうという
人間のネットワークそのものが小さいものなのかな。
そういったネットワークの埒外に
いるので、好き勝手、コメントしてもいいかなと思い、書いてしまいました。
邪魔だったら、削除してください。
ありがとうございます。
なるほど、考えたら私は日本では、まともな業界への就職活動をしたことが無かったので知らなかったのです。
日本の大企業でもOB/OG訪問は大切で、そこから開けてくることはあるんですね。
勉強になります。
確かに、研究者採用などだと、日本の大手メーカーとかでもコネとか大切だったりしますね。
ただ(mamorukさんもそこを否定してるわけじゃないとは思いますが)それでも日本よりずっとコネ・ネットワーキングが重要ってのは事実だと思うのですよ。
「アメリカは機会均等の国」と思ってる日本人は多いはずで、日本よりコネが効くなんて思ってない人も多いんじゃないかなあと。
それでネットワーキングを軽視して、もったいない結果に終わってしまってはダメだよ!という警告のつもりで書きました。
>通りすがり関西人様
なるほど。「仲良しクラブの独占」って確かにそうですね。
それで思い出したんですが、私の知り合いで、昔、日本の銀行の投資部門にいてアメリカで働いてた人がいました。
私もこの業界はよく知らんのですが、一番儲かる部分って、ユダヤ系とか、アメリカの一部の小さいネットワークとかに独占されてて、日本の銀行が入る余地とか無い
そうです。
でも、日本でエクイティに投資してるより儲かるので、アメリカに支店を構えているものの、
アメリカで本当に一番儲かるところには「コネが無くて」入り込めず、弱者のまま。
プライドの高い日本の銀行マンとしては、歯がゆい思いをし続けたそうです。
ただ、就職市場においては、私たち日本人のような「外」にいる人間でも、中に入るチャンスがある。
ビジネスコンテストとか、大学の先生経由とか。
そういう意味では、アメリカは「機会均等」なのかな、と思いました。
ただ、正しい戦い方を知っていることが重要なのですが。
日本の話をもう少し書くと、大企業だと「そこから開ける」どころか、コネがないと門前払いだったりしますよ。「どの大学からも受け付けます」と言いつつ募集要項は東大一橋早慶くらいにしか送らないとか、説明会をオンラインで予約させても出身大学の欄によって「申し訳ないですが満席になりました」と出る人と、それより後でも予約できる人とか。
あと銀行だったら学閥がかなり強いそうで、大学のリクルーターにコンタクトを取る(リクルーターに会って話をする)のが一次面接(いや、そういうリクルーターがいないような大学では、他の面接とか試験を受けないといけないので、本当は一次ではないらしいですが)なので、そこで同じ大学出身の結束力が活かされるみたいですね。
理系はそこまで露骨じゃないですが、Google も一次選考は書類ですが、東大京大とか一部の大学以外は説明会レベルで落とされるようですね。
日本とアメリカの違いだと、新卒の価値が異様に高いのは日本では仕事の流動性が低いせいだろうなと思うのですが、アメリカほど高い(明日から来なくていいよ、と言われたり)のもなんだかなと思いますし、なにがいいんだろうなぁ、と悩みますね。
>「どの大学からも受け付けます」と言いつつ募集要項は東大一橋早慶くらいにしか送らない
なるほど、学歴門前払いがあるという話ですね。
で、コネがあればそれを押しのけていける、と。
米国でも、学歴アシきりはありますよ。
MBAトップ校しか採用情報のメールは送らない、とか学校別の説明会とかね。
今年なんか、ボストンに採用担当者が来ても、「ハーバードでは説明会やるけど、MITには来ない」みたいな企業があります。
へー、そういうことするんだー、とMITの人は思ってますが。
企業の論理からすると、採用活動の効率性を重視したいので、いわゆる学歴アシきりがあるのは、仕方ない。
逆に、そういう一部の大学以外にすごい人がいるかもしれないのを、採用できないリスクがあるのもわかった上で、敢えてやってるわけですからね。
ただ、学生側から見ると「どの大学からも受け付けます」なんて奇麗事言わなきゃいいのに、と腹立つでしょうね。