広島で「子どもの権利条例」に反対の署名活動(産経新聞)
広島市が制定を検討している「子どもの権利条例(仮称)」に反対しようと、24日、市民団体のメンバーらが同市の中心部で街頭署名活動を行った。また、市側も同日、同市北部で説明会を行い、地元住民らに条例制定の必要性を訴えた。
開発途上国での人身売買などから子供を守るため、国連総会で「子どもの権利条約」が採択され、日本も批准。これを受け、国内の一部自治体で、虐待などから守るため、子供のプライバシー権や意見を表明する権利などを保障する内容の条例制定が進んでいる。
広島市では現在、同様の内容の骨子試案を作り、説明会を開くなどして市民の意見を募集しており、平成21年度中に骨子案をまとめる方針。制定時期は未定だが、保護者や学校関係者から「指導しづらくなる」などと懸念の声が上がっている。
署名活動には約40人が参加。「制定されれば子供たちがわがままになり、学校や家庭が崩壊する」などと呼びかけ、約350人の署名を集めた。
「児童の権利に関する条約」(以下「条約」とする。)は日本国内においては1994年5月22日から効力が発生している。今回はこの問題だらけの「子供の権利」を糾してみよう。
まず、国際法学者であった波多野里望先生は、「この条約は、そもそも、発展途上国における人権環境を改善することを『主たる』目的としている。この条約は、けっして、国内法体系のバランスを崩してまで、子どもの権利を突出させることを締結国に要求しているものではない。」(『逐条解説 児童の権利条約』有斐閣、1994年)と述べている(なお、この本への批判的見解として、平野裕二氏の「逐条解説 児童の権利条約」を挙げておく。)。
文部省(当時)が当時各都道府県の教育委員会等宛てに出した事務次官通達においても、「学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理解させることは極めて重要であり、この点に関しても日本国憲法や教育基本法の精神にのっとり、教育活動全体を通じて指導すること。」、「意見を表明する権利、表現の自由についての権利等の権利について定められているが、もとより学校においては、その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対し、指導や指示を行い、また校則を定めることができるものである」、「学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒等が自国の国旗・国歌の意義を理解し、それを尊重する心情と態度を育てるとともに、すべての国の国旗・国歌に対して等しく敬意を表する態度を育てるためのものであること。その指導は、児童生徒等が国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を身につけるために行うものであり、もとより児童生徒等の思想・良心を制約しようというものではないこと。今後とも国旗・国歌に関する指導の充実を図ること。」と現場に求めている。
そして、同条約の効力を国内において反映させる際にしばしば挙げられる条文は12条「意見を表明する権利」であると思われるが、12条では「児童の権利とは、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」という条件が付いていることを指摘しておきたい。つまり、児童の年齢や成熟度に関係なく全児童を対象に網羅的に児童の権利を保障することは、条約自身が留保をつけて戒めているのである。
ここまでは児童の権利条約の国内における効力について論じてきたが、ここからは視点を変え、子供をいかにして捉えるべきかということについて議論をしてみる。
子供の権利を声高に主張する人々がその拠り所とするのは、19世紀のイギリスの哲学者(こう呼称するのが適切かどうかはさておき。)であるJ.S.ミルであろう。ミルは主著『自由論』において個性(individuality)の擁護を展開している。ミルによれば人間とは、自己の個性を涵養することによって自身を発展させ、自己完成できる存在ということになる。そのことは、「個性の育成のみが十分に発展した人間を生むことができる」(『自由論』第3章)と述べていることからも窺える。要するに、ミルにとって人間が幸福であるには個性の発展が不可欠であり、個性を抑圧するようなものは「専制主義」ということになる。
このようなミルの主張を聞けば、一見すると子供に対して何かしらの制約を課すことは不可能のように思われるが、ミルは決してそのようには解していなかった。
ミルは同じ『自由論』の中で、「自己の意見に基づいて行動する自由」すなわち「行為の自由」についても述べており、そこでミルは、人間の行為を「自己に関わる行為」と「他人に関わる行為」に分け、論じている。そしてミルは自己に関わる行為については干渉は許されないとするが(もっとも、その人の判断を助けるための警告や助言までも否定していない。)、後者の「他人に関わる行為」については有名な「他者加害原理(harmprinciple)」によって制限をかけている。
ミルによれば「他人に関わる行為」の領域で自由が保障されているのは、あくまでも他人に害を及ぼさない限りであって、他人の幸福や利益を損なうような行為には当然、制限や処罰が行われてよいとしている。したがって、ミルにおいてさえも、自由は無制限であるとはしていなかったのである。
そしてミルはこのような自由は、成人した当事者のみが享受できるものとしていた。ミルにとって子供とは、「いまだ他の人々の世話を受ける必要のある状態」なのであって、子供は「外からの危害」から保護されるべき存在であって、子供が自己決定の主体になることはない。つまり、ミルの主張に拠ったとしても、子供はあくまでも保護の対象であって、大人と同じ「権利の主体」になることはないのである。にもかかわらず、子供を大人と同じ権利の主体と把握し、自己決定権を付与しようとするのは、ミルの理論からすれば明らかに無理が出てくる。
仮に、子供を大人と同じように「権利の主体」として扱うのならば、そもそも子供だからといって特別扱いをする必要はないということになるはずだ。まず手始めに民法上の未成年者取消権(民法5条2項)を削除するべきだ。そして少年法も不要(もちろん実名報道)。児童虐待防止法の即時廃止。この他にも廃止ないしは削除されるべき法律、条文が多数存在する。
それでは子供がどうしてこのように様々な法律等によって特別扱いされているのかといえば、ミルの言うように、子供はいまだ未成熟で判断能力等も乏しいため、他の人たちの支えがなければ生きていけない状態であるからだ。あくまでも子供は「権利の主体」ではなく、保護の対象なのである。
ところで、日本国憲法においては、子供の権利についてどうだろうか。これは権利や自由に対するパターナリスティックな制約に関する議論にも関係してくる。憲法上、パターナリスティック(家父長主義的)な制約をすることは可能であるという見解が、関連する裁判例も含めれば支配的な見解であると言える(人格的利益説。この見解によれば、子供の人格的自律の助長・促進いとって必要である場合には、パターナリスティックな制約は許されることになる)。
裁判所が自己決定権の可否について判断する際に用いる基準として「社会通念」というものがある。つまり、主張されている権利ないし自由が、常識的に考えて認められるかどうかということを基準としているのである。よって、たとえば、「制服着用義務は子供の権利を侵害している」と主張したところで、そのような主張は(よほどの理由でもない限り)間違いなく認められることはない(最高裁平成3年9月3日判決(バイクの3ない運動に関するもの)等を参照)。
憲法に明文をもってそのようなことが書いてないのは確かだが、憲法の番人と言われる裁判所が社会通念を基準にして判断している以上、これが正当な憲法解釈である。つまりはこれこそが「憲法」であって、こうした憲法観であるにもかかわらず、たとえば「子どもの権利条例」が制定されている神奈川県川崎市において、授業中に教室で騒いだ小学校児童を担任の教師が注意したところ、同市の人権オンブズマンから、「行き過ぎた指導があり、教育的配慮に欠けている」と指摘され、謝罪を求められたケースなどというのは、憲法の下位法である条例が憲法に違反していると言うこともできるのではないか。
子供を虐待をはじめとした危害から保護しようという活動を否定するものではないし、それは当然のことと言える。しかしながら、たとえば刃物の使い方の分からない人に、刃物を渡したらどうなるだろうか。もしかしたら人に向かって使うかもしれないし、自分自身を傷つけてしまうかもしれない。本来刃物はそのように使うものではなく、美味しい料理を作るためであったり、何かモノを作るために使うのである。
権利についてもこのことと同じことが言えるのではないか。つまり、権利といっても、それは実は諸刃の刃なのであり、使い方を誤れば子供自身にとってマイナスになることだってあり得るということだ。
精神的にも肉体的にも未成熟な子供に、「子どもの権利」と称して扱いきれない猛獣を与えることは、子供にとっても大人にとっても、そして社会全体にとってもマイナスとなることは間違いないだろう。
広島市が制定を検討している「子どもの権利条例(仮称)」に反対しようと、24日、市民団体のメンバーらが同市の中心部で街頭署名活動を行った。また、市側も同日、同市北部で説明会を行い、地元住民らに条例制定の必要性を訴えた。
開発途上国での人身売買などから子供を守るため、国連総会で「子どもの権利条約」が採択され、日本も批准。これを受け、国内の一部自治体で、虐待などから守るため、子供のプライバシー権や意見を表明する権利などを保障する内容の条例制定が進んでいる。
広島市では現在、同様の内容の骨子試案を作り、説明会を開くなどして市民の意見を募集しており、平成21年度中に骨子案をまとめる方針。制定時期は未定だが、保護者や学校関係者から「指導しづらくなる」などと懸念の声が上がっている。
署名活動には約40人が参加。「制定されれば子供たちがわがままになり、学校や家庭が崩壊する」などと呼びかけ、約350人の署名を集めた。
「児童の権利に関する条約」(以下「条約」とする。)は日本国内においては1994年5月22日から効力が発生している。今回はこの問題だらけの「子供の権利」を糾してみよう。
まず、国際法学者であった波多野里望先生は、「この条約は、そもそも、発展途上国における人権環境を改善することを『主たる』目的としている。この条約は、けっして、国内法体系のバランスを崩してまで、子どもの権利を突出させることを締結国に要求しているものではない。」(『逐条解説 児童の権利条約』有斐閣、1994年)と述べている(なお、この本への批判的見解として、平野裕二氏の「逐条解説 児童の権利条約」を挙げておく。)。
文部省(当時)が当時各都道府県の教育委員会等宛てに出した事務次官通達においても、「学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理解させることは極めて重要であり、この点に関しても日本国憲法や教育基本法の精神にのっとり、教育活動全体を通じて指導すること。」、「意見を表明する権利、表現の自由についての権利等の権利について定められているが、もとより学校においては、その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対し、指導や指示を行い、また校則を定めることができるものである」、「学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒等が自国の国旗・国歌の意義を理解し、それを尊重する心情と態度を育てるとともに、すべての国の国旗・国歌に対して等しく敬意を表する態度を育てるためのものであること。その指導は、児童生徒等が国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を身につけるために行うものであり、もとより児童生徒等の思想・良心を制約しようというものではないこと。今後とも国旗・国歌に関する指導の充実を図ること。」と現場に求めている。
そして、同条約の効力を国内において反映させる際にしばしば挙げられる条文は12条「意見を表明する権利」であると思われるが、12条では「児童の権利とは、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」という条件が付いていることを指摘しておきたい。つまり、児童の年齢や成熟度に関係なく全児童を対象に網羅的に児童の権利を保障することは、条約自身が留保をつけて戒めているのである。
ここまでは児童の権利条約の国内における効力について論じてきたが、ここからは視点を変え、子供をいかにして捉えるべきかということについて議論をしてみる。
子供の権利を声高に主張する人々がその拠り所とするのは、19世紀のイギリスの哲学者(こう呼称するのが適切かどうかはさておき。)であるJ.S.ミルであろう。ミルは主著『自由論』において個性(individuality)の擁護を展開している。ミルによれば人間とは、自己の個性を涵養することによって自身を発展させ、自己完成できる存在ということになる。そのことは、「個性の育成のみが十分に発展した人間を生むことができる」(『自由論』第3章)と述べていることからも窺える。要するに、ミルにとって人間が幸福であるには個性の発展が不可欠であり、個性を抑圧するようなものは「専制主義」ということになる。
このようなミルの主張を聞けば、一見すると子供に対して何かしらの制約を課すことは不可能のように思われるが、ミルは決してそのようには解していなかった。
ミルは同じ『自由論』の中で、「自己の意見に基づいて行動する自由」すなわち「行為の自由」についても述べており、そこでミルは、人間の行為を「自己に関わる行為」と「他人に関わる行為」に分け、論じている。そしてミルは自己に関わる行為については干渉は許されないとするが(もっとも、その人の判断を助けるための警告や助言までも否定していない。)、後者の「他人に関わる行為」については有名な「他者加害原理(harmprinciple)」によって制限をかけている。
ミルによれば「他人に関わる行為」の領域で自由が保障されているのは、あくまでも他人に害を及ぼさない限りであって、他人の幸福や利益を損なうような行為には当然、制限や処罰が行われてよいとしている。したがって、ミルにおいてさえも、自由は無制限であるとはしていなかったのである。
そしてミルはこのような自由は、成人した当事者のみが享受できるものとしていた。ミルにとって子供とは、「いまだ他の人々の世話を受ける必要のある状態」なのであって、子供は「外からの危害」から保護されるべき存在であって、子供が自己決定の主体になることはない。つまり、ミルの主張に拠ったとしても、子供はあくまでも保護の対象であって、大人と同じ「権利の主体」になることはないのである。にもかかわらず、子供を大人と同じ権利の主体と把握し、自己決定権を付与しようとするのは、ミルの理論からすれば明らかに無理が出てくる。
仮に、子供を大人と同じように「権利の主体」として扱うのならば、そもそも子供だからといって特別扱いをする必要はないということになるはずだ。まず手始めに民法上の未成年者取消権(民法5条2項)を削除するべきだ。そして少年法も不要(もちろん実名報道)。児童虐待防止法の即時廃止。この他にも廃止ないしは削除されるべき法律、条文が多数存在する。
それでは子供がどうしてこのように様々な法律等によって特別扱いされているのかといえば、ミルの言うように、子供はいまだ未成熟で判断能力等も乏しいため、他の人たちの支えがなければ生きていけない状態であるからだ。あくまでも子供は「権利の主体」ではなく、保護の対象なのである。
ところで、日本国憲法においては、子供の権利についてどうだろうか。これは権利や自由に対するパターナリスティックな制約に関する議論にも関係してくる。憲法上、パターナリスティック(家父長主義的)な制約をすることは可能であるという見解が、関連する裁判例も含めれば支配的な見解であると言える(人格的利益説。この見解によれば、子供の人格的自律の助長・促進いとって必要である場合には、パターナリスティックな制約は許されることになる)。
裁判所が自己決定権の可否について判断する際に用いる基準として「社会通念」というものがある。つまり、主張されている権利ないし自由が、常識的に考えて認められるかどうかということを基準としているのである。よって、たとえば、「制服着用義務は子供の権利を侵害している」と主張したところで、そのような主張は(よほどの理由でもない限り)間違いなく認められることはない(最高裁平成3年9月3日判決(バイクの3ない運動に関するもの)等を参照)。
憲法に明文をもってそのようなことが書いてないのは確かだが、憲法の番人と言われる裁判所が社会通念を基準にして判断している以上、これが正当な憲法解釈である。つまりはこれこそが「憲法」であって、こうした憲法観であるにもかかわらず、たとえば「子どもの権利条例」が制定されている神奈川県川崎市において、授業中に教室で騒いだ小学校児童を担任の教師が注意したところ、同市の人権オンブズマンから、「行き過ぎた指導があり、教育的配慮に欠けている」と指摘され、謝罪を求められたケースなどというのは、憲法の下位法である条例が憲法に違反していると言うこともできるのではないか。
子供を虐待をはじめとした危害から保護しようという活動を否定するものではないし、それは当然のことと言える。しかしながら、たとえば刃物の使い方の分からない人に、刃物を渡したらどうなるだろうか。もしかしたら人に向かって使うかもしれないし、自分自身を傷つけてしまうかもしれない。本来刃物はそのように使うものではなく、美味しい料理を作るためであったり、何かモノを作るために使うのである。
権利についてもこのことと同じことが言えるのではないか。つまり、権利といっても、それは実は諸刃の刃なのであり、使い方を誤れば子供自身にとってマイナスになることだってあり得るということだ。
精神的にも肉体的にも未成熟な子供に、「子どもの権利」と称して扱いきれない猛獣を与えることは、子供にとっても大人にとっても、そして社会全体にとってもマイナスとなることは間違いないだろう。











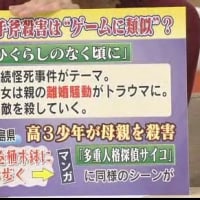
日教組の組織率も今では2割程度と言われていますが、2割といっても影響力は決して過小評価できないのであって、今後とも警戒をしていくことに越したことはありませんね。
そういえば、朝日新聞が3億円以上の所得隠しをしていたようですね。
普段は捏造までして他人の非を論って叩く朝日ですが、自分たちには相当甘いようで、
http://news.google.co.jp/news?hl=ja&ned=jp&ncl=1277124523&scoring=d
では、全社が「所得隠し」と報じているのに、朝日だけは「申告漏れ」。
日教組も朝日も、サヨクという生き物は自分に甘く他人に冷たい、典型的な駄目な大人の姿を晒してくれていると、つくづく思いましたね。