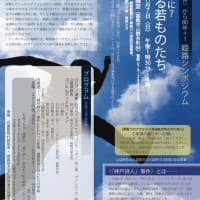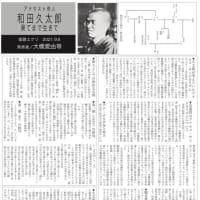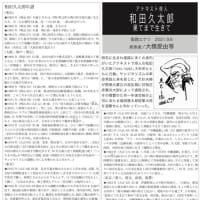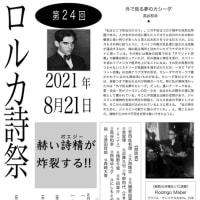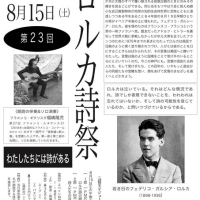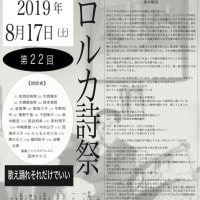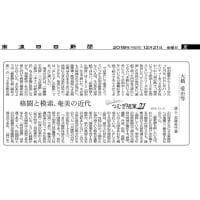『Melange』同人のみなさん ならびに 誌友のみなさんへ
大橋愛由等@『Melange』同人より
詩誌『Melange』の第27回読書会・合評会のお知らせです。11月25日(日)に開催しま
す。
今回は、岩成達也さんをゲストにお招きします。「詩論の方へ」というタイトルでお話し願います。以下、岩成氏制作のメモを本文貼り付けします。とワード添付をします。また、「現代詩手帖」に岩成氏が書いた詩論も2篇、富氏から預かっています。
まだ渡していない方は至急大橋まで連絡してください。maroad@warp.or.jp
詩論の世界で大きな問題提起をし続ける岩成氏のお話しに期待しています。
岩成さんのお話しを、第二部〈午後3時~〉にしますので、詩の合評会を第一部といたします。開始時間も30分早くなっていますので、ご注意下さい。
第一部の詩の合評会について、
詩稿の締め切りは、11月22日(木)とします。
今回も意欲的な作品、実験的な作品をお寄せ下さい。
お待ちしています。
ちなみに、詩稿は毎回小詩集に仕立てて、製本しています。出席されない方でご希望ので、大橋まで請求してください。さて、今月も聞いて学ぶだけでなく自作品を携えて参加するわれらの読書会・合評会にみなさん参加してください。
11月10日(土)に、甲南大学(神戸市東灘区)で「第15回島尾文学研究会」が開かれ、「島尾敏雄と神戸」というタイトルのシンポジウムが開かれ、わたし(大橋)は、パネラーとして出席。〈奄美と神戸をつなぐもの〉というタイトルで発言してきました。
会の様子は、私が記事送稿した文章が、南海日日新聞に掲載されていますので、当日お配りいたします。島尾伸三氏(敏雄の長男)の講演が特に興味深いものでした。神戸で一家をなした島尾家の最後の一人となってしまった伸三氏が語り部として語り始めた感があります。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
◆日時=11月25日(日)午後0時30分から第1部。午後2時30分まで。詩の合評会。(いつもより開始が30分早いのでご注意ください。)
午後3時00分から第2部。岩成達也さんのお話。「詩論の方へ」
◆会場=神戸・三宮のスペイン料理カルメンで行います。
(カルメンの場所は以下のサイトを参照してください。阪急三宮駅西口の北へ徒歩2分
の場所にあります。 http://www.warp.or.jp/~maroad/carmen/
)。
◆第1部=詩誌の合評会/詩稿締め切りは、11月22日(木)締め切りは必ず守ってください。送稿された作品は24日(土)朝に、みなさんあてにメール発信します。ではみなさん、積極果敢に詩稿を送ってくださいね。
◆第2部=読書会=岩成達也さんのお話。「詩論の方へ」
なお、申しわけありませんが、岩成氏をお呼びするため、若干のカンパを要請しのすので、ご了承ください。
大橋愛由等
//////////////////////////////////////////////////////////////////
詩論の方へ(メモ) 07・11・25(sun)
岩成達也
( 0 ) 詩は要請(定義)できるか・・・・二、三の例
R・ヤーコブソン : (発信者/受信者間の)メッセージそのものへの指向、メッ
セージそのものへの焦点合わせが、言語の詩的機能である。[『一般言語学』P192]
藤井貞和 : 《詩のことば》なんか存在しないかもしれない。きわめ
て意識的な言語体験が重ねられるだけではないか。[『詩的分析』の帯]
瀬尾育生 : 言語とはほんらい、いまだ対象でないものが自らを
開き、対象としてはじめて姿をあらわす場所のことである。詩的言語は、意志体・情
熱体がそこで開示される場所そのものを直
接的に実在のものとする。一方非詩的言語は、意志体・情熱体を遠近法のなかへ移し
置き、そこで関係のなかの主体へと翻訳する。この二つの言語は互いに「逆立」する。
[『戦争詩論1910-1945』P312]
岩成達也 :(イ)詩的関係においては〈表現:内容〉という関係において言語
(構造)が充足しない。
(ロ)あるテキストが詩(作品)であるためには、関与者の宣言を必
要とする。[『詩的関係の基礎についての覚書』p72p90]
( 1 ) 第二要請
1) 私(達)の世界を定義し構成するものは言語である。
2) 詩とは、言語でもって私(達)の世界を超出(/脱在-excendance)しようとする営為
である。
(註)ヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」論による「世界」の漂流性
( 2 ) 規範の侵犯―言語関係の異常
0) 詩=「規範の侵犯」という見方:第二要請との関係,その見方の問題点
1)言語構造に係わる異常
(イ)従前の主流詩観―行分けと抒情(感情/感慨の表出)中心主義
(ロ)音韻の前面化による異常
→記号表現(視聴覚イメージ)の異常増殖(関係錯綜:『フィネガンズ・ウエ
イク』)
(ハ)喩/アレゴリーの前面化による異常
→記号内容(概念等)の異常増殖(多義性/過剰解釈/ヘルメス定義:『フー
コーの振り子』)
2)言述(discours,わ話)に係わる異常
(イ)ディスクール:「だれかが(わたし)、なにかを(意味)、なにかについ
て(指示)、だれかに(あなた)、語る」こと。
(註)ラングの現働化、ラングの内在性(意味)とディスクールと超越性(指
示、人称)
(ロ)一人称の異常―P・リクールのテクスト論(杉村靖彦『ポール・リクールの
思想』)
a)「わたし」の匿名化/抹消―指示の逆転/世界の逆転
b)言述=出来事から意味への乗り超え(疎隔―distanciation)
→発語に対する書記の優位
→テクスト論;「テクストにおいては指示は「世界」に向かうのではな
く、そこで開かれた指示の総体が世界である。(テクストは指示を直示的な指示の限
界から解き放つ)」
(参考)リクールの言語観
・ いかなる言述も出来事として生起するが、意味として了解される。
・ この〈出来事から意味への乗り越え〉、〈言うことの、言われるものにおける疎
隔〉という見方が、リクールの言述論の核芯を成す。(杉村)
・ 言述に注目することによって,出来事から意味が湧き出す瞬間に立ち会うことが重
要なのであって、(この意味では)〈疎隔〉とはむしろ言葉の意味産出の条件であり、
言述が出来事として孕んでいた力は、出来事を乗り越えたときに初めて解放され、以
降ますます強くなっていく反響のように、絶えざる意味の探究へと引き継がれていく。
(杉村)
(ハ)二人称の異常―E・ レヴィナスの他者論(コリン・デイヴィス『レヴィ
ナス序説』)
a)「あなた」の絶対化/把握不能―指示の無効/ディスコミュニケー
ション
b)語ること(le Dire)と語られたこと(le Dit)との「相差」
→「あなた」が絶対の「他者」の場合、出来事は意味へと回収さ
れない。
→この場合、語る「私」は専ら「他者」にあますところなく暴い
て(暴かれて)いる。
(註)詩とは(絶対の)「他者」との遭遇である。(第二要請
―2)
(参考)レヴィナスの言語観
・〈語ること〉と〈語られること〉とは言語活動の二つの相である。
・〈語ること〉は〈語られること〉に「前―起源的」(先行的)であり、しかも「離―
時性(単一の時間のなかに走る亀裂)としてみれば、両者は(分離不能で)同時的に生
起し、かつ相克しない。(デイヴィス)
・〈語ること〉は、姿をみせないまま言説の語り手あるいは聴き手としての〈他者〉
に私が曝露されているような状況、構造、あるいは出来事におけるあらゆる発語を基
礎づけている。(デイヴイス)
(補足)思考するとはディスクールにおいて「わたし」が
「わたし」に語ることである。
(P・ヴァレリー『カイエ』)
( 3 ) 言語系の限界―特異な言語関係 cf.他者との遭遇の様
態
0) 三つの問題(言語哲学的)・・・論者にとってまだ十分な決着はみていない。
(イ)知と言語の関係
(ロ)身体と知/言語の関係
(ハ)「私」と知/言語の関係
(参考)バンヴェニスト『一般言語学の諸問題』
特に「6.思考の範疇と言語の範疇」「17.ことばにおける主体性について」
1) 触知―知の下部(基礎)限界の突破
・触知はドリフト(漂流)する。
・触知を捉えるのは、多くの場合、言語の周辺部分(意味的、視聴覚像的に非中心部
分)によってであって、その場合の言語運動も通常の(言語)組織化運動から逸脱する。
(仮説) ・・ ( 断片化、 物語の破綻、等)
(註)言語の連合(パラディグマティック)関係→多義性、中心/周辺
2) 分節―知/言語の分節/未分節(分節以前)と もの/ことのそこへの現われ
例;a.logosがratioとoratioとに分節されたとき何が生じたのか
b.アウグスティヌスの「聞く言葉」と「光る(見る)ことば」
(註)知/言語の分節化の増大と知(特に科学知/理性知)-散文―の精密化
の増大
3)超越(志向)―知の上部限界の突破
・知/言語は常にその根源を求めてやまず、更にそれを超えようとする。
-知/言語の志向性/逆流
・神学、特に聖トマスの言語観モデル
(参考)聖トマスの言語観―discomunicationの克服
・ 稲垣良典『神学的言語の研究』
_ アナロギア;同語同義と同語異義 との中間 (語;nomen/義:
ratio)
_ 二つの言語とその方向性の一致
「表示の様式」(modus significandi):感覚から出発する
人間理性に固有の認識
「表示されたもの」(res significata)
「因果性の道」による推論⇒「表示された完全性そのもの_
恩寵(の言語)
・澤崎幸子『内なることばの研究』
外なることば
ことば 表象において:表象像(phantasma)
内なることば ↓※
知性において:可知的形象
(
※)能動知性が受動(可能)知性の中に可知的表象象を
つくる。これは更に概念形成(直知/定義)から
判断形成(判断/言表)を経て存在把握にいたって
究極点に辿りつく。
4)信憑性/断片集積の自己同一性の問題(独白)
「私」がもはや「個」であることが疑わしいとき、「私」が係わる、この分裂し、
断片化し、相矛盾す
る言葉や言表を自己同一的な関係として、「私」に「開く」ものは何か。
→書く/話す(読む/聞く)という身体性を伴う営為それ自体ではないか(
「私」/「開く」)
(註)書くということのありようは、「いま(ここに殺到する無数の過
去)」のありように似ている。
つまり「私」=「いま」

大橋愛由等@『Melange』同人より
詩誌『Melange』の第27回読書会・合評会のお知らせです。11月25日(日)に開催しま
す。
今回は、岩成達也さんをゲストにお招きします。「詩論の方へ」というタイトルでお話し願います。以下、岩成氏制作のメモを本文貼り付けします。とワード添付をします。また、「現代詩手帖」に岩成氏が書いた詩論も2篇、富氏から預かっています。
まだ渡していない方は至急大橋まで連絡してください。maroad@warp.or.jp
詩論の世界で大きな問題提起をし続ける岩成氏のお話しに期待しています。
岩成さんのお話しを、第二部〈午後3時~〉にしますので、詩の合評会を第一部といたします。開始時間も30分早くなっていますので、ご注意下さい。
第一部の詩の合評会について、
詩稿の締め切りは、11月22日(木)とします。
今回も意欲的な作品、実験的な作品をお寄せ下さい。
お待ちしています。
ちなみに、詩稿は毎回小詩集に仕立てて、製本しています。出席されない方でご希望ので、大橋まで請求してください。さて、今月も聞いて学ぶだけでなく自作品を携えて参加するわれらの読書会・合評会にみなさん参加してください。
11月10日(土)に、甲南大学(神戸市東灘区)で「第15回島尾文学研究会」が開かれ、「島尾敏雄と神戸」というタイトルのシンポジウムが開かれ、わたし(大橋)は、パネラーとして出席。〈奄美と神戸をつなぐもの〉というタイトルで発言してきました。
会の様子は、私が記事送稿した文章が、南海日日新聞に掲載されていますので、当日お配りいたします。島尾伸三氏(敏雄の長男)の講演が特に興味深いものでした。神戸で一家をなした島尾家の最後の一人となってしまった伸三氏が語り部として語り始めた感があります。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
◆日時=11月25日(日)午後0時30分から第1部。午後2時30分まで。詩の合評会。(いつもより開始が30分早いのでご注意ください。)
午後3時00分から第2部。岩成達也さんのお話。「詩論の方へ」
◆会場=神戸・三宮のスペイン料理カルメンで行います。
(カルメンの場所は以下のサイトを参照してください。阪急三宮駅西口の北へ徒歩2分
の場所にあります。 http://www.warp.or.jp/~maroad/carmen/
)。
◆第1部=詩誌の合評会/詩稿締め切りは、11月22日(木)締め切りは必ず守ってください。送稿された作品は24日(土)朝に、みなさんあてにメール発信します。ではみなさん、積極果敢に詩稿を送ってくださいね。
◆第2部=読書会=岩成達也さんのお話。「詩論の方へ」
なお、申しわけありませんが、岩成氏をお呼びするため、若干のカンパを要請しのすので、ご了承ください。
大橋愛由等
//////////////////////////////////////////////////////////////////
詩論の方へ(メモ) 07・11・25(sun)
岩成達也
( 0 ) 詩は要請(定義)できるか・・・・二、三の例
R・ヤーコブソン : (発信者/受信者間の)メッセージそのものへの指向、メッ
セージそのものへの焦点合わせが、言語の詩的機能である。[『一般言語学』P192]
藤井貞和 : 《詩のことば》なんか存在しないかもしれない。きわめ
て意識的な言語体験が重ねられるだけではないか。[『詩的分析』の帯]
瀬尾育生 : 言語とはほんらい、いまだ対象でないものが自らを
開き、対象としてはじめて姿をあらわす場所のことである。詩的言語は、意志体・情
熱体がそこで開示される場所そのものを直
接的に実在のものとする。一方非詩的言語は、意志体・情熱体を遠近法のなかへ移し
置き、そこで関係のなかの主体へと翻訳する。この二つの言語は互いに「逆立」する。
[『戦争詩論1910-1945』P312]
岩成達也 :(イ)詩的関係においては〈表現:内容〉という関係において言語
(構造)が充足しない。
(ロ)あるテキストが詩(作品)であるためには、関与者の宣言を必
要とする。[『詩的関係の基礎についての覚書』p72p90]
( 1 ) 第二要請
1) 私(達)の世界を定義し構成するものは言語である。
2) 詩とは、言語でもって私(達)の世界を超出(/脱在-excendance)しようとする営為
である。
(註)ヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」論による「世界」の漂流性
( 2 ) 規範の侵犯―言語関係の異常
0) 詩=「規範の侵犯」という見方:第二要請との関係,その見方の問題点
1)言語構造に係わる異常
(イ)従前の主流詩観―行分けと抒情(感情/感慨の表出)中心主義
(ロ)音韻の前面化による異常
→記号表現(視聴覚イメージ)の異常増殖(関係錯綜:『フィネガンズ・ウエ
イク』)
(ハ)喩/アレゴリーの前面化による異常
→記号内容(概念等)の異常増殖(多義性/過剰解釈/ヘルメス定義:『フー
コーの振り子』)
2)言述(discours,わ話)に係わる異常
(イ)ディスクール:「だれかが(わたし)、なにかを(意味)、なにかについ
て(指示)、だれかに(あなた)、語る」こと。
(註)ラングの現働化、ラングの内在性(意味)とディスクールと超越性(指
示、人称)
(ロ)一人称の異常―P・リクールのテクスト論(杉村靖彦『ポール・リクールの
思想』)
a)「わたし」の匿名化/抹消―指示の逆転/世界の逆転
b)言述=出来事から意味への乗り超え(疎隔―distanciation)
→発語に対する書記の優位
→テクスト論;「テクストにおいては指示は「世界」に向かうのではな
く、そこで開かれた指示の総体が世界である。(テクストは指示を直示的な指示の限
界から解き放つ)」
(参考)リクールの言語観
・ いかなる言述も出来事として生起するが、意味として了解される。
・ この〈出来事から意味への乗り越え〉、〈言うことの、言われるものにおける疎
隔〉という見方が、リクールの言述論の核芯を成す。(杉村)
・ 言述に注目することによって,出来事から意味が湧き出す瞬間に立ち会うことが重
要なのであって、(この意味では)〈疎隔〉とはむしろ言葉の意味産出の条件であり、
言述が出来事として孕んでいた力は、出来事を乗り越えたときに初めて解放され、以
降ますます強くなっていく反響のように、絶えざる意味の探究へと引き継がれていく。
(杉村)
(ハ)二人称の異常―E・ レヴィナスの他者論(コリン・デイヴィス『レヴィ
ナス序説』)
a)「あなた」の絶対化/把握不能―指示の無効/ディスコミュニケー
ション
b)語ること(le Dire)と語られたこと(le Dit)との「相差」
→「あなた」が絶対の「他者」の場合、出来事は意味へと回収さ
れない。
→この場合、語る「私」は専ら「他者」にあますところなく暴い
て(暴かれて)いる。
(註)詩とは(絶対の)「他者」との遭遇である。(第二要請
―2)
(参考)レヴィナスの言語観
・〈語ること〉と〈語られること〉とは言語活動の二つの相である。
・〈語ること〉は〈語られること〉に「前―起源的」(先行的)であり、しかも「離―
時性(単一の時間のなかに走る亀裂)としてみれば、両者は(分離不能で)同時的に生
起し、かつ相克しない。(デイヴィス)
・〈語ること〉は、姿をみせないまま言説の語り手あるいは聴き手としての〈他者〉
に私が曝露されているような状況、構造、あるいは出来事におけるあらゆる発語を基
礎づけている。(デイヴイス)
(補足)思考するとはディスクールにおいて「わたし」が
「わたし」に語ることである。
(P・ヴァレリー『カイエ』)
( 3 ) 言語系の限界―特異な言語関係 cf.他者との遭遇の様
態
0) 三つの問題(言語哲学的)・・・論者にとってまだ十分な決着はみていない。
(イ)知と言語の関係
(ロ)身体と知/言語の関係
(ハ)「私」と知/言語の関係
(参考)バンヴェニスト『一般言語学の諸問題』
特に「6.思考の範疇と言語の範疇」「17.ことばにおける主体性について」
1) 触知―知の下部(基礎)限界の突破
・触知はドリフト(漂流)する。
・触知を捉えるのは、多くの場合、言語の周辺部分(意味的、視聴覚像的に非中心部
分)によってであって、その場合の言語運動も通常の(言語)組織化運動から逸脱する。
(仮説) ・・ ( 断片化、 物語の破綻、等)
(註)言語の連合(パラディグマティック)関係→多義性、中心/周辺
2) 分節―知/言語の分節/未分節(分節以前)と もの/ことのそこへの現われ
例;a.logosがratioとoratioとに分節されたとき何が生じたのか
b.アウグスティヌスの「聞く言葉」と「光る(見る)ことば」
(註)知/言語の分節化の増大と知(特に科学知/理性知)-散文―の精密化
の増大
3)超越(志向)―知の上部限界の突破
・知/言語は常にその根源を求めてやまず、更にそれを超えようとする。
-知/言語の志向性/逆流
・神学、特に聖トマスの言語観モデル
(参考)聖トマスの言語観―discomunicationの克服
・ 稲垣良典『神学的言語の研究』
_ アナロギア;同語同義と同語異義 との中間 (語;nomen/義:
ratio)
_ 二つの言語とその方向性の一致
「表示の様式」(modus significandi):感覚から出発する
人間理性に固有の認識
「表示されたもの」(res significata)
「因果性の道」による推論⇒「表示された完全性そのもの_
恩寵(の言語)
・澤崎幸子『内なることばの研究』
外なることば
ことば 表象において:表象像(phantasma)
内なることば ↓※
知性において:可知的形象
(
※)能動知性が受動(可能)知性の中に可知的表象象を
つくる。これは更に概念形成(直知/定義)から
判断形成(判断/言表)を経て存在把握にいたって
究極点に辿りつく。
4)信憑性/断片集積の自己同一性の問題(独白)
「私」がもはや「個」であることが疑わしいとき、「私」が係わる、この分裂し、
断片化し、相矛盾す
る言葉や言表を自己同一的な関係として、「私」に「開く」ものは何か。
→書く/話す(読む/聞く)という身体性を伴う営為それ自体ではないか(
「私」/「開く」)
(註)書くということのありようは、「いま(ここに殺到する無数の過
去)」のありように似ている。
つまり「私」=「いま」