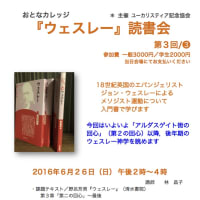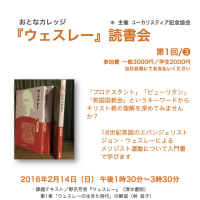正直のところ、この本について述べることにあまり気乗りがしない。いわゆる世間で言われるように、この本がキリスト教を冒涜しているからでは、全くない。
ミステリー小説の場合、余程心が震えるようなガツンとくる要素――たとえばロバート・パーカー氏のハードボイルド的味付けとか――がないと楽しめないという私の性質ゆえなのだろうが、ミステリー小説としてこの本を眺めた場合、展開が平板すぎる、要するに、つまらないのだ。
うんちく本としてはどうだろう。自然界に存在する黄金比の話や、レオナルドの絵に込められた仕掛けについての解説のうちのいくつかは、素直に「おお!そうだったのか」と楽しめたことは事実だ。しかし、だ。これは私の職業に由来すると言ってよいかもしれないが、言い方を変えれば、専門家の端くれから言わせてもらえば、ことキリスト教はじめ宗教的な話題になると「どこかで読んだ・聞いたことのある話」のオンパレードだ。『レンヌ・ル・シャトーの謎』の著者がイギリスで、『ダ・ヴィンチ・コード』の出版元に対し、盗作だと裁判に訴えたという報道がなされていたが、その気持ちは理解できる。『…謎』の著者だけでなく、他の研究者たちにとっても、本人が真面目に研究した結果をおいしいトコ取りされて、その上薀蓄として披露されては敵わない、と考えるのも納得できる。
そのようなわけで、私は『ダ・ヴィンチ・コード』に関して、うんちくの点で多少楽しみ、ミステリー小説としてはあまり堪能できなかったのであるが、全体的な読後感として最大の興ざめだったのは、どうも著者であるブラウン氏自身が、この話がキリスト教の存在意義を失わせるほどのセンセーションに満ちた事実であると考えているらしいことが、ヒシヒシと伝わる点である。
私は、この本に書かれていることが嘘っぱちだ、と言っているのではない。嘘っぱちどころか、相当程度、そのとおりであることも多いかもしれないと思っている。この歴史研究的な側面について私は、これまでの、そしてこれからの成果に大いに期待しているし、私自身、その進展を大変喜んでいる者である。
「歴史とは蓋然性に過ぎない」と考えるのは、歴史を語る人々にとって、もはや当たり前のことだと私は思っていたが、私が憶測するブラウン氏の皮相的な歴史理解は、私には滑稽にさえ映る。キリストの血を受け継ぐ末裔が現実にいるとしても、それがキリスト教信仰にとって何の意味があるのか。少なくとも、私には無意味としか思えない。なぜなら、聖書が書かれた時代にキリストと言われた男が苦しみを受け、神の愛を人々に伝えたという「事実」(=蓋然性)にこそ、キリスト教の土台を求めるべきだからだ。
仮にこの小説に書かれていることがすべて事実だとして(=蓋然性)、「だから、どうした」という部分が「キリスト教の存在意義が失われる」という理解につながるならば、ブラウン氏は、あるいはそのような危機感を抱く全ての者たちは、キリスト教についてその本質的な部分において、大きな誤解をしていると言わざるを得ないと思う。
ミステリー小説の場合、余程心が震えるようなガツンとくる要素――たとえばロバート・パーカー氏のハードボイルド的味付けとか――がないと楽しめないという私の性質ゆえなのだろうが、ミステリー小説としてこの本を眺めた場合、展開が平板すぎる、要するに、つまらないのだ。
うんちく本としてはどうだろう。自然界に存在する黄金比の話や、レオナルドの絵に込められた仕掛けについての解説のうちのいくつかは、素直に「おお!そうだったのか」と楽しめたことは事実だ。しかし、だ。これは私の職業に由来すると言ってよいかもしれないが、言い方を変えれば、専門家の端くれから言わせてもらえば、ことキリスト教はじめ宗教的な話題になると「どこかで読んだ・聞いたことのある話」のオンパレードだ。『レンヌ・ル・シャトーの謎』の著者がイギリスで、『ダ・ヴィンチ・コード』の出版元に対し、盗作だと裁判に訴えたという報道がなされていたが、その気持ちは理解できる。『…謎』の著者だけでなく、他の研究者たちにとっても、本人が真面目に研究した結果をおいしいトコ取りされて、その上薀蓄として披露されては敵わない、と考えるのも納得できる。
そのようなわけで、私は『ダ・ヴィンチ・コード』に関して、うんちくの点で多少楽しみ、ミステリー小説としてはあまり堪能できなかったのであるが、全体的な読後感として最大の興ざめだったのは、どうも著者であるブラウン氏自身が、この話がキリスト教の存在意義を失わせるほどのセンセーションに満ちた事実であると考えているらしいことが、ヒシヒシと伝わる点である。
私は、この本に書かれていることが嘘っぱちだ、と言っているのではない。嘘っぱちどころか、相当程度、そのとおりであることも多いかもしれないと思っている。この歴史研究的な側面について私は、これまでの、そしてこれからの成果に大いに期待しているし、私自身、その進展を大変喜んでいる者である。
「歴史とは蓋然性に過ぎない」と考えるのは、歴史を語る人々にとって、もはや当たり前のことだと私は思っていたが、私が憶測するブラウン氏の皮相的な歴史理解は、私には滑稽にさえ映る。キリストの血を受け継ぐ末裔が現実にいるとしても、それがキリスト教信仰にとって何の意味があるのか。少なくとも、私には無意味としか思えない。なぜなら、聖書が書かれた時代にキリストと言われた男が苦しみを受け、神の愛を人々に伝えたという「事実」(=蓋然性)にこそ、キリスト教の土台を求めるべきだからだ。
仮にこの小説に書かれていることがすべて事実だとして(=蓋然性)、「だから、どうした」という部分が「キリスト教の存在意義が失われる」という理解につながるならば、ブラウン氏は、あるいはそのような危機感を抱く全ての者たちは、キリスト教についてその本質的な部分において、大きな誤解をしていると言わざるを得ないと思う。