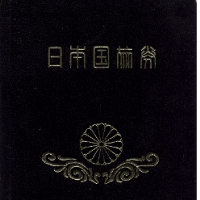香港島や九龍半島の地下は花崗岩の塊なんです。
山が海に迫って、急激に水深が深くなる、所謂ドン深の良港なのもそのせいでしょうね。
水が染み込まんから一旦台風などで豪雨が降ると、すぐに山津波が起きます。
「スージーウォンの世界」で描かれた難民バラックを押し流した山津波なんかはしょっちゅうだったそうです。
今でも激しい夕立の後などでは、長い階段を滝のように水が流れ落ちる光景を見ることが出来ますね。
折角降った雨がアッと言う間に海に流れてしまうので、特に香港島は近年まで飲料水に苦労してきました。
中共の文革に影響された香港暴動の時などは、大陸からの給水を政治の駆け引きに使われて、当時の香港政庁は相当苦労したようですね。
その教訓と新界での急激な住宅建設もあって、大埔、沙田などの湾の淡水湖化が進められて、街の性格や景観が激変したんです。
その代わり、岩盤が確りしていて地震の心配が無いので、あんな高層ビルを立てる事が早い時期から可能やったんでしょうね。
実際、何処も彼処も一寸掘ったら花崗岩に行き当たるんですよ。
西区警察署の前で信号待ち(撮影:カミさん) さて、石塘咀へはトラム(路面電車)に乗ってドンドン西へ、上環、西港城を経て西営盤の西区警察署の所で降ります。
さて、石塘咀へはトラム(路面電車)に乗ってドンドン西へ、上環、西港城を経て西営盤の西区警察署の所で降ります。
西営盤一帯は乾物問屋が多いのでトラムの中にも干物の匂いが漂って来ます。
トラムは全線同一料金ですから、もっと西の屈地街まで行っても良いんですが、歩くのが好きなんですよ。
警察署の東側を山に向かって伸びているのが西邉街。
ここには香港でおそらく最古(約100年前に建設)と思われる公衆浴場が有ったんですが、今でも有るんやろか?
警察署の近くは手職の職人の店がチラホラとある下町なんですが、山へ向かってゆくと段々小奇麗になってきて、英皇書院(キングズ・カレッジ)の角に出ます。
等高線に沿って走っている般咸道(ボンハム・ロード)を右に曲がるとすぐ左の山側には香港大学の広いキャンパスが見えてきます。
右には聖保羅書院(セントポール・カレッジ)。
この周辺は、優秀な学生が通う進学校が香港でもっとも多い地区です。
般咸道(ボンハム・ロード)は香港大学の所で下から来た扶林道(ポックラム・ロード)と交差して、少し先で扶林道と右へ行く山道(ヒル・ロード)に分かれます。
ここから海へかけての山道(ヒル・ロード)を中心とした一帯が石塘咀(セットンチュイ)。
香港島の中でも、ここ石塘咀(セットンチュイ)は、極早い頃から集落が在ったと言われています。
花崗岩の石切場で働く石工の村が始まりやそうです。
なるほど、石塘咀=石で出来た水溜りのある嘴(クチバシ)のような岬という地名は、石切場と積み出しの港そのまんまですなぁ。
香港の年配者にとっては石塘咀というのは特別な響を持った地名やそうです。
というのも昔はこの一帯に大遊郭があったんやそうです。
それも半端や無い、娼妓2,000人以上、娼館50軒以上、大型酒楼18軒の南中国最大規模といわれた大遊興地区やったんですね。
イギリスが区画整理をするのに、ここより少し東の水坑口辺りにあった娼館を、山道の近辺に強制移動させたのが始まりやそうです。
公娼制度は30年ほどして廃止されるんですが、廃止されたから、禁止されたからといってなくなった験しはありません。
表から裏の商売に変って、逆にいわゆる黒社会の格好の稼ぎ場になっただけ。
その上一箇所にまとまっていたのがバラバラになったので、かえって増殖したようです。
私なんぞは、石塘咀の大遊郭が出来てから、無くなるまでの時代に生まれもしてません。
公娼制度廃止の年に生まれた人でも70歳、実際に経験した人は90歳前後の筈です。
日本の占領時代には、石塘咀の遊郭が少し息を吹き返したそうですが、終戦でポシャったようですね。
不動産屋の前で一休み。 日本の旧遊郭地域は、今でも歓楽遊興、またはウッフン街のところが多いんですが、此処には全くそういう雰囲気が残ってません。
日本の旧遊郭地域は、今でも歓楽遊興、またはウッフン街のところが多いんですが、此処には全くそういう雰囲気が残ってません。
大学は変わらずに在るものの、赤いランタンは今は勿論完全に姿を消して、どちらかといえば、他の香港の下町よりもアットホームな感じがする、香港にしては静かな街に変貌しています。
しかし、未だに人々の意識の中に、そういう印象が残っているというのは、相当凄かったんでしょうなぁ。
香港大学は創立されたのが20世紀初頭(1911)、その後100年近く香港のNo.1エリート大学として今も健在です。
香港大学創立の5年前には、敷地の海側に隣接したと言ってもいいほど近くに、娼館の立ち並んだ紅燈区(ホンダングォィ=紅灯の巷)、石塘咀の大遊郭街の建設が始まっていたというから、いくら香港は狭いとはいえ、一体何を考えてここに大学を建設したんでしょうね。
そろそろお昼になったけれど、食べ物屋が溢れている香港に珍しく、この界隈はこれといって飯屋が見当たりません。
飯は帰りに上環でで食べる事にして、山道からトラムの走る徳輔道へ出て東へ少し行くと、山側に喫茶店というのも恥かしいような小さな店が有ります。
パイプ椅子が並んだ店の中は中学、高校生くらいの女の子だらけ、といっても10人も入ればぎっしり。
この店の愛玉(ンゴイユッ)は、私の知る限り香港一。
石塘咀にやって来た理由の一つは、カミさんにここの愛玉を食べさせたかった事もあるんです。
最近は日本でもたまにお目にかかりますが、あれはどうやら缶詰、ツルリン感が微妙に違いますなぁ。
愛玉というのは台湾が本場で、実は私も初めて食べたのは台湾の屋台なんです。
ソフトボールよりも二回りくらい大きな、イタビの仲間の実を裏返しにして、バケツに張った水の中で揉むと透明なゼリーみたいなのが出来るんです。
それを集めて固めて、レモンジュースを掛けて、何故かカキ氷をチョコット盛るんですね。
いたって安手の、なんて事の無い食べ物なんですが、若い時の基隆での思い出やら何やらがあって、私にとっては別格の食べ物なんですわ。
この店には「本物ですよ」と言わんばかりに、その実が置いて有るんです。
オッサンとオバサンが入るには少々場違いな店。
若い女の子に混じって愛玉を食べてるのを珍しそうに店のおっちゃんが見てました。
帰りがけに、「台灣人(トイワンヤン)?」「ンーハイ(いいや)、日本人(ヤップンヤン)」
怪訝そうに首を振ってたけれど、日本人が愛玉好きでもええやんか・・。
この路地、夜にはよう来んなぁ・・。 帰りは、路地から路地へアミダ籤風に歩いて行くと、いかにも危なげなビルの隙間の小さな公園に出た。
帰りは、路地から路地へアミダ籤風に歩いて行くと、いかにも危なげなビルの隙間の小さな公園に出た。
これはイカンと逆戻り。
少し広い道に出ると歩道に沢山の人が集まってます。
何事かいな?と思ってたら、ビルの扉が開いて子供がワラワラッと出て来た。
そうか、学校なんですねぇ!
香港島市街地のほとんどの学校は校庭が無いから、すぐ傍を通っててもちょっと気付きません。
山側に曲ると道が途中で階段になっている所が多くなります。
小さな廟がポツポツあって、60センチくらいのプロペラが置いてあるのは車公さんの出店かいな?
車公さんについてはココ。
葬式やら、墓参りに使う紙の飾りを扱う店が並んでいる通りを過ぎて、今度は海側へ向かってそこいら中の路地をのたくり回って、再び西区警察署の傍に出ました。
さて、トラム(路面電車)で上環に出て、街市の上の熟食中心(フード・センター)で遅い昼飯にしますか。
2004/02/22
喜愛香港-034 香港仔-01
喜愛香港-目次