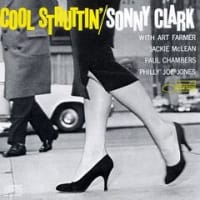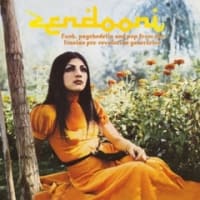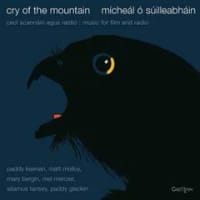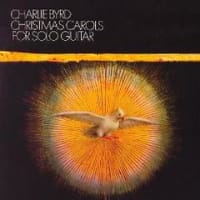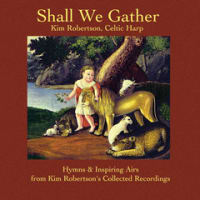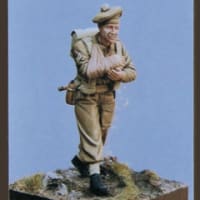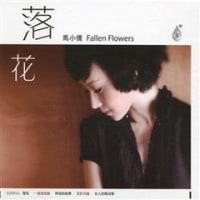さて昨日の続き、人種・国境をどこかズレて行く音楽の話なのだけれど。
あれは誰だったかなあ?ゲイトマウス・ブラウンだったっけ。ともかく来日した黒人ブルースマンが、連れてきたバンドのメンバーに若干の白人ミュージシャンが含まれていることを指摘され、「お前は人種差別をするのか。彼らも立派なミュージシャンだ」とか言い返される、なんて一幕があったらしい。
まあ、それは確かに「ただ黒人なだけ」みたいなミュージシャンもいるのだからね、そりゃそうなのだが、来日したブルースマンを聞きに行って、ステージに並んでいるバンドのメンバーのほとんどが白人、というのは、なんか騙されたみたいな気分になるだろう。
などといっていると、昔懐かしい「黒人以外にもブルースは演奏可能なのか?」なんて論争を思い出してしまうが、あれの結論って出たのだろうか。いや、結論なんてないのだろうが。
こちらの都合で言えば、外人の歌う演歌はどうなんだ?最近ではジェロと言ったっけ、黒人の演歌歌いが出てきたが、私としては彼の歌っている歌が、先日批判したばかりの”フォーク演歌”の典型みたいな奴だったので相手にする気にはなれない。
昔、”インド人・チャダ”って歌手がいたなあ。日本に農業を学びに来て演歌にはまってしまい、ついにプロ・デビューしてしまった。彼などは時代のせいもあり、正統派演歌と言える楽曲をあてがわれていたが、ちょっと歌い口が明朗過ぎて、演歌らしい陰影が感じられない気がした。むしろ彼が日本の演歌のどこに惚れたのか、その過程にワールドミュージック的興味が出てくるくらいで。
そういえばいつぞや、さすらい日乗さんから、ジョアン・ジルベルトやスタン・ゲッツらの共演盤、初期のボサノバのヒット作である”Getz/Gilberto”を取り上げたおりの文章について、下のような書き込みを頂いた。
~~~~~
昔、ブラジル語の先生に聞きましたが 彼女は、ブラジルにいたとき、アストラッド・ジルベルトの『イパネマの娘』を聞いたことがなく、日本に来て、大ヒット曲と知り、大変驚いたそうです。
この『ゲッツ・ジルベルト』もブラジルで発売されたかどうかは知りませんが、多分されなかったと思います。
~~~~~
ブラジル人は誰も聞いていないかのようだ、つまりは、あの盤はリアルなブラジル音楽とは言えない、と日乗さんはおっしゃられたいのだと推察するのだが、実はそれがリアルな音楽かどうか、については私はあんまり興味はない。
ブラジル音楽を利用して世界マーケットで売れようと意図した音楽を、ブラジル人が聴いたことなくても、そりゃそうでしょうと言うしかない。ポップ・ミュージックなんて、そんなもんでしょ。逞しく良いも悪いもゴタ混ぜで飲み込んで流れて行くのが大衆音楽でありましょう。
その話のついでに言えば、たとえば”久保田麻琴プロデュースの日本の音楽”を聞いたことのない日本人など山ほどいるわけでね。
その一方、あちこちの音楽を漁り歩いて聴いている私だけれど、自国の、日本の民謡できっちり歌える物って一曲もありません。さらにその一方、これはマイミクの神風おじさむさんから指摘いただいたのだけれど、テレビののど自慢番組で出演者が歌っている演歌が、聴いたことのないようなものばかりだ。しかもそれらは”我々の共有の財産”という認識のもとに当たり前のように歌われ、聞かれているようで、まるでもうひとつ、別の日本社会があるかのようだ。
これは私もそう思う。カラオケの現場なんかでも、全く知らない曲が朗々と歌い上げられ、しかも他の人たちはイントロを聞いただけで「待ってました!」てなノリの歓声でもってそれを迎える。皆は、その歌を知っているのだ。
これは、なにが起こっているのだろうか。まるでプリズナーNo6の”村”に住んでいるみたいな気分になってくるのだが。
さらに。ツイッターでみつけた発言。「ヒットしてしまっているけれど、AKB48の歌みたいなものが日本の音楽だと外国人に認識されるのは面白くない」と。
しかし。それじゃそれにかわって、誇りうる、どんな音楽がこの日本に今、存在すると言うのかね?AKBなんぞの肩を持つ気はさらさらないが。