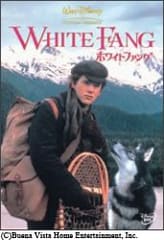”SALTADOROS”by MICHALIS JENITSARIS
やあ、CDを整理していたらこんなものが出てきてしまった。これは、ギリシャの大衆音楽を聴き始めたばかりの頃の愛聴盤だった。
第1次世界大戦とその後の混乱期におけるギリシャとトルコの領土分捕り合戦の結果、さまざまに両国間の国境線は引き直された。この辺の事情は何度解説を読んでもややこしくて良く分からないので私に詳しい解説など求めないで欲しいものだが、ともかくその結果、突然トルコ領となった土地を追われギリシャ本国に強制帰国(?)させられた大量の人々が発生した。
トルコの文化の強い影響下で生きて来た人々が、住みなれぬ”祖国ギリシャ”にほとんど難民として流入するに当たってはさまざまな混乱があったろう。特に私などが興味を惹かれるのが、そこで拮抗したトルコの文化とギリシャの文化。しかも舞台は、たとえば大都会アテネの底辺の悪場所。
で、そのハザマに生まれたのが、このレベーティカなる音楽という次第であります。
はじめて聴いたレベーティカは、かのジャンルの初期の名演を収めたという”Funf Griechen in der Holle”なるアンソロジーでだった。
タイトルが示すようにドイツ盤で、解説もドイツ語しか付いていなかったので、いまだに詳しいバックグラウンドも分からないままなのだが、地を這いずり回るような重心の低いリズムと、濃厚に粘りつきながらかき鳴らされるギリシャの民族楽器ブズーキの調べ、そしてまるでブルースシンガーみたいな歌声にすっかり魅了されてしまったものだった。
先に大都会アテネの悪場所、なんて書いたが、なにしろ発祥したばかりのレベーティカが演奏されていた場所にはハッシシを吸わせる店などが居並び、ヤクザや売春婦が横行するあたりだそうで、たしかに、そのアンソロジーに収められた音楽には、いかにもそんな雰囲気が溢れていたものだった。
「他人事と思って呑気な事を言うな」とか叱られそうだが、都市の底辺に立ち込めるヤバいヤクザな雰囲気の中へ身を沈めてこのような音楽を生み出して行く、その痺れるような快感というもの、たまらなかったろうな、なんて空想してしまうのです。いや実際、もの凄く面白かったろうと思うのですよ。その時代、その場に生きていたら。
で、今回の盤は、そのアンソロジーでも強烈な印象を発していた、レベ-ティカ界のボス、みたいな人物なのでしょう、MICHALIS JENITSARISの1990年度のライブ盤であります。
カイゼル髭というんでしょうか、ピンと跳ね上がった立派な髭でブズーキを抱えてポーズを決めたそのお姿は、なんだかスターリンに良く似ていて、そういえばかの独裁者氏はソビエト連邦はグルジアの出身だったし、レベーティカ発祥を巡る小アジアの国際関係の舞台とそう遠くはない生まれだ。血の連鎖としてまったく関係なくもないんでは?などと思うと、こいつもちょっと血が騒ぐのだけれど。
この盤もドイツ盤で解説は全然読めないのだが、なんとなく分かる部分を拾い読んで行くとどうやら JENITSARIS の生年は1917年のようで、この盤はかなり歳がいってからの演奏といえるのだろう。
実際、彼の1940年代の演奏が収められていたアンソロジーでは、エレクトリック・ブズーキの爪弾きも妖しく、非常にギトギトした手触りの生臭い歌を聞かせていたのだが、この盤ではずいぶんと枯れた印象を受ける。とはいえ、悪場所のおっかないボスの貫禄はむしろ増していて、ブルースシンガーっぽさはますます濃厚となっているのだが。
音楽的にはブルースとはまるで似てはいないんだけどね。なぜかブルースを引き合いに出したくなる、その音楽的濃さ、根深ささが魅力であります。この辺の間合いが面白いねえ。重々しく繰り出されるリズムなんかは、まるで「お控えなすっておくんなせえ」と、ヤクザが古典的仁義を切っているみたいでね。