のヴァイオリン協奏曲。
前回のグルックとは打って変って、激情が溢れだすかのような演奏。
さすがに北欧、フィンランドの作曲家だけあって、寒さのピークを迎えた冬、にこそ似合います。
1:30あたりの、淡々としながら厳しい寒さを感じさせるようなオケのうえで、
ヴァイオリンが狂おしくうねって官能的ですらあります。。
ベートーベンやチャイコフスキー、ブルッフやブラームスなどの有名なヴァイオリン協奏曲、
美しい小品とは異なった、ある意味ロックより激しい楽章があったりします。
Sibelius Violin Concertin Mov.3 by wei wen
(↓)前にも、チャイコフスキーの狂気を感じさせるようなドラマチックなやつ 取り上げました。
http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/f785525ce4311ea0b365ec6a9377a488
(↓)狂気の演奏といえば、ルービンシュタインの月光ソナタの第3楽章、
ピアノ演奏ですが、やはり凄まじいものを感じます。
http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/b84483637f9c9726e5c3faf0f75cef0b
ちょっと難しく聞こえますが、一部引用です。
グローバリズムというのは「誰にでもわかるもの」を基準にして、すべての価値を考量すること。
「わかる人にはわかるが、わからない人にはわからない」ようなものは、
グローバリズムの風土では存在しないし、存在してはならない。
だから、そのようなものを感知する能力をいくら高めても、社会的能力としては評価されない。
であれば、そのような能力の開発にリソースを注ぐ人間はいなくなるのが道理である。
その結果、私たちの社会では、家庭でも学校でも企業でも、「人を見る目」の涵養プログラムには指一本手を動かさなくなった。
あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。
数値をもって示すことのできない「知」は知として認知されない。
けれども、evidenceで基礎づけられないものは「存在しない」、と信じ込むのは典型的な無知のかたちである。
私たちが「客観的根拠」として提示しうるのは、私たちの「手持ちの度量衡」で考量しうるものだけになる。
著者は、逆説的に、人間はそんなにバカじゃないのだ、と言っているのです。
~ 私はものが「収まるところに収まる」ということが あらゆる場合にベストのソリューションだとは考えていない。
「収まりの悪いものは そのへんにごろごろしている」し、そんなのは気にしなくていいのです。
こういう、ある意味"収まりの悪い"音楽、が心をえぐるように感じられたら、
それは、手持ちの度量衡(モノサシ)を超えたものを持っていることの証(アカシ)のように思えます。
超えてる方がいい、というわけでもないですが。
前回のグルックとは打って変って、激情が溢れだすかのような演奏。
さすがに北欧、フィンランドの作曲家だけあって、寒さのピークを迎えた冬、にこそ似合います。
1:30あたりの、淡々としながら厳しい寒さを感じさせるようなオケのうえで、
ヴァイオリンが狂おしくうねって官能的ですらあります。。
ベートーベンやチャイコフスキー、ブルッフやブラームスなどの有名なヴァイオリン協奏曲、
美しい小品とは異なった、ある意味ロックより激しい楽章があったりします。
Sibelius Violin Concertin Mov.3 by wei wen
(↓)前にも、チャイコフスキーの狂気を感じさせるようなドラマチックなやつ 取り上げました。
http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/f785525ce4311ea0b365ec6a9377a488
(↓)狂気の演奏といえば、ルービンシュタインの月光ソナタの第3楽章、
ピアノ演奏ですが、やはり凄まじいものを感じます。
http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/b84483637f9c9726e5c3faf0f75cef0b
 | 邪悪なものの鎮め方 (木星叢書)内田 樹バジリコこのアイテムの詳細を見る |
ちょっと難しく聞こえますが、一部引用です。
グローバリズムというのは「誰にでもわかるもの」を基準にして、すべての価値を考量すること。
「わかる人にはわかるが、わからない人にはわからない」ようなものは、
グローバリズムの風土では存在しないし、存在してはならない。
だから、そのようなものを感知する能力をいくら高めても、社会的能力としては評価されない。
であれば、そのような能力の開発にリソースを注ぐ人間はいなくなるのが道理である。
その結果、私たちの社会では、家庭でも学校でも企業でも、「人を見る目」の涵養プログラムには指一本手を動かさなくなった。
あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。
数値をもって示すことのできない「知」は知として認知されない。
けれども、evidenceで基礎づけられないものは「存在しない」、と信じ込むのは典型的な無知のかたちである。
私たちが「客観的根拠」として提示しうるのは、私たちの「手持ちの度量衡」で考量しうるものだけになる。
著者は、逆説的に、人間はそんなにバカじゃないのだ、と言っているのです。
~ 私はものが「収まるところに収まる」ということが あらゆる場合にベストのソリューションだとは考えていない。
「収まりの悪いものは そのへんにごろごろしている」し、そんなのは気にしなくていいのです。
こういう、ある意味"収まりの悪い"音楽、が心をえぐるように感じられたら、
それは、手持ちの度量衡(モノサシ)を超えたものを持っていることの証(アカシ)のように思えます。
超えてる方がいい、というわけでもないですが。














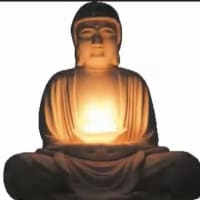
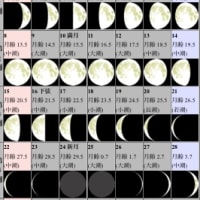
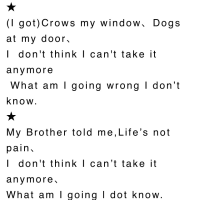
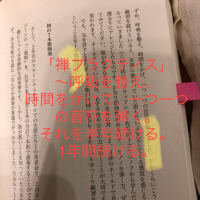
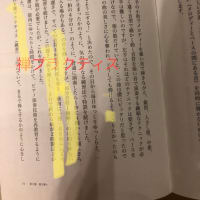
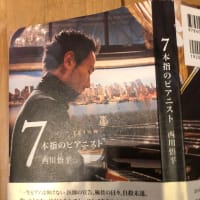









粘っこい演奏で好き嫌いがあるとは思いますが
若い頃、カラヤンに夢中でした。
「クラッシック音楽友の会」の会員になって週に一度はコンサートに出かけていた時期がありました。
1979年10月19日(金曜日)、普門館での演奏会は「昭和54年台風第20号」のため交通機関が乱れ、開演時間が遅れたのでよく覚えています。
・ドヴォルザーク:交響曲第8番
・ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」
同じ1979年10月、カラヤンが早稲田大学・名誉博士号授与式で学生のオーケストラ・早稲田大学交響楽団を指揮してリハーサルを行いました。
シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」
忘れられない出来事でした。
思い出話、失礼いたしました。
好きな曲ばかりです(除く、頭に浮かばないオイレンなんとか…)!
こんなプログラム、でカラヤンだったら
それはひと財産のような思い出に違いない。。
展覧会の絵、よく響いた演奏だとすごくいいですよね~。
ドヴォルザークも郷愁のあるメロディが交響曲にまで入ってきて好きです。
8番て、たしかサントリーウイスキー響のCMで使われてたやつですね、たぶん。
そうかドヴォルザーク、だ!って感じ。
ぼくの頭の中はヘンで
時々ドヴォルザークとブラームスを取り違えていたります。
カラヤンはモーツァルトの40番をこのブログでも取り上げました。
端正で明快な演奏の印象がありますが、
粘っこいのもあるんですね。
また情報交換させてください。(^O^)/
迷惑コメント、削除しました。