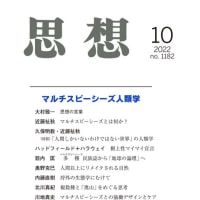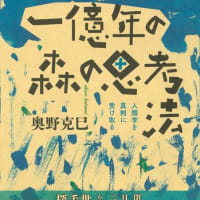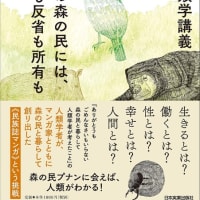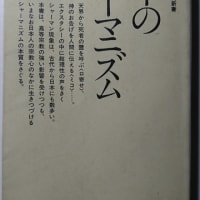下の写真は、これまで撮ったビデオのなかで、プナン人に、サイチョウ(rhinocero hornbill)の鳴き真似をやってもらっているシーンである。それは、たんなる鳴き真似ではなく、ポクウォ(pekewe)と呼ばれる、動物の鳴き真似などで動物をおびき寄せて狩る「たぶらかし猟」でもある。
これまで、プナンのトリ(juit)については、折に触れてずいぶん調べてきた。というよりも、動物の方名、別名、動物譚、狩猟方法などを調べるなかで、必然的に、聞きなしを含めて、トリについてもデータが蓄積されてきた。
カーンカプット(ka'an kaput)と呼ばれる、動物譚に頻繁に登場するトリがいる。ある本では、カッコーのようなトリだと説明されている。そのトリは、ほとんど目撃されたことがない。鳴き声だけが、果実の季節になると聞かれるという、不思議なトリである。神話を聞きたいと言って教えてもらったなかに、いま一つ意味が呑み込めない話があった。そこには、カーンカプット、オジロドリ、イノシシだけでなく、「しおれた木」が出てくる。
カーンカプットは、果実の季節にやって来る。カーンカプットの鳴き声を聞いて、しおれた木は、果実の液を吸う。しおれた木が川の下流からやって来ると、イノシシは、今度は、花の匂いがしだいに漂ってくるのを知るようになり、ブラガ川やバルイ川にやって来た。そのようにして、イノシシは、しおれた木について行くようになり、果実を食べ、太りはじめた。オジロドリは、イノシシの後をついて行った。イノシシについて行くと、果実のたくさんある場所に辿り着くことができたからである。
ここで語られていたのは、<カーンカプット>⇒<しおれた木>⇒<イノシシ>⇒<オジロドリ>という、果実をめぐる捕食に関わる森の生態学に他ならない。プナンは、トリの渡りを知っている。そして、エドゥアルド・コーンふうに言えば、人間は、この「形式」を知って、イノシシ狩りをするのだ。
コーン『森は考える』(近刊予定)のなかにも、トリの話は、たくさん出てくる。フウキンチョウ、リスカッコウ・・・。菅原和孝『狩り狩られる経験の現象学』のなかにも、民族鳥類学の分厚い一章がある。菅原は、トリの聞きなしとは、私たち外部者にとっては「信仰」のように見えるが、現地の人たちにとっては、事の次第を見せてくれる「指標記号」なのだ、というようなことを言っている。おっ、それは、パースの記号過程のインデックス(指標記号)ではないか。旗が揺らめいているのは、風が吹いていることを指差する。トリの聞きなしとは、それと同じようなものだ、と言うのだ。カーンカプットの鳴き声が、果実の季節の訪れを告げるのは、指標記号なのである。一考の価値がある。
ここ一月ほどは、私のなかで、しだいに、トリのテーマが大きく膨らんだ。池袋の12階のオフィスで、風の強い日に窓の外を眺めていたら、窓のすぐ傍を、巨大なトリが、風に煽られないように流線型に体を絞り込んで、西を目指して、飛んで行った。動物園にも、猛禽類やカワセミなどを見に行った。トリのカタチは、他の動物に比べて、飛ぶという点で、際立っていることに、今更ながら気づいたのだった。トリの本をずいぶん買って読んだ(見た?)。小説も読んだ。梨木香歩『渡りの足跡』を読んだ。加藤幸子『心ヲナクセ、体ヲ残セ』も読んだ。それは、トリの視点からというか、作者がトリになって書いたとしか思えない小説だった。戸川幸夫『爪王』は、日本の鷹匠と角鷹の物語だった。
それでいま、プナン語のトリの方名の学名について調べている。今日は、双眼鏡も手に入れた。今回の一年ぶりのプナンの短期調査は、前半では、トリについて、いろいろ聞いてみたいと思う。
トリは、狩猟民にとって、ある場所から別の場所へそこからまた別の場所へ渡るという特質の点で、手本であり、憧れでもあるのではないだろうか?