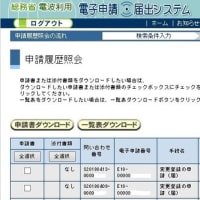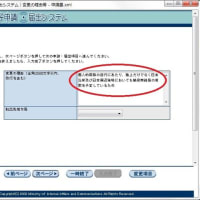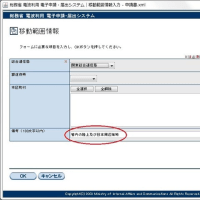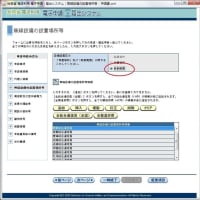昨年(2010年)のハムフェアで買ってきたグラスファイバー製5.4mの釣り竿をそろそろ活用しようと決意し、部品屋に材料を調達しに行った。

用意したモノは、ネジ・圧着端子・自在ブッシュ・ミノムシクリップ・スズメッキ線1.2mm径10m、直径60mmの塩ビ管である。
おなじみ局との会話の中では、「塩ビ管なんかで作ったら重くなるじゃね~か」とのことだが、カットアンドトライをするにも試作品から作らないと…という訳で、インダクタンス計算云々は棚に上げ、とりあえず巻いてみることにする。
参考になりそうなサイトをぐるぐる回っていたら、便利な計算ツールが載っているサイトを発見したのでメモ。
Helical Coil Calculator ヘリカルコイル計算機
線の太さと直径と長さ、巻線数や間隔等を入力するとインダクタンスを計算してくれるものだ。
さて、完成はいつになることやら。
---
11/06/14 追記
この手の工作ではおなじみの百円均一のお店(私はセリア派)では、あらゆる用途で筒状のケース的なものが在庫している。本来はお茶や味噌、粉モノなど、密閉して保存したいもの用なのだが、無線脳は何でもコイルの材料に見えてきてしまうのが不思議だ。


ありがたいことに、セリアで売っているこうした筒モノは日本製が多く、某大陸産でありがちな刺激臭やプラスチック臭、そして"やっつけ仕事感"は見られない。先日調達したスズメッキ線はこちらの入れ物を使用するコイルにすることにし、とりあえず手持ちのカラー線(テレビアンテナのステー線の余り)を持ってきて自在ブッシュを貼り付けた塩ビ管に適当に巻いてみた。(参考まで、巻数は43.5回です)
ついでに、物干し竿用洗濯ばさみ(何とポリカーボネート製、3個100円byセリア)で釣り竿にコイルを取り付けてみると、何となくアンテナらしく見えてきたぞ。コイルをクリップ式にしておけば、周波数毎のコイルを必要に応じて差し替えることも出来るし、調整もしやすいだろう。この後、コイルには陸軍端子を取り付け、エレメントにはバナナプラグか圧着端子を取り付けることにする。今の段階で運用目標は、3.5MHz帯と7MHz帯だ。

今まではこれで満足して放置モードに突入していたのだが、次はうまくマウントを作って実際に取り付け、調整・・・するかなあ。
-----
2011/6/17 追記
釣り竿アンテナのエレメント長が約4mで、今回作ったコイルがどこの周波数に乗ってるか確認してみた。

3.5MHz帯に乗れば御の字ってなもんで、アンテナアナライザを追い込んでいくと・・・

ん?3.82MHz付近でVS1.2?
惜しい!!
今回の調整で使った竿は、ローカル局から借りたトップの竿が抜いてある4.5M物だから、実質のエレメント長は約4m。(ローカル局曰く、18MHz帯の1/4λの釣り竿アンテナだぞーとの話)
今後は自前の5.4mの竿(実質5m弱になる)を使ってエレメント長やコイルを調整すればすんなり3.5MHzはイケそうだ。
今回作ったモノのまとめメモ
・直径60mmの塩ビ管
・自在ブッシュ
・1.2mm径のカラーワイヤ(被覆無くても良いと思う)
・43.5回巻
次は7MHz帯のコイル巻に突入予定。(いつかは未定)

用意したモノは、ネジ・圧着端子・自在ブッシュ・ミノムシクリップ・スズメッキ線1.2mm径10m、直径60mmの塩ビ管である。
おなじみ局との会話の中では、「塩ビ管なんかで作ったら重くなるじゃね~か」とのことだが、カットアンドトライをするにも試作品から作らないと…という訳で、インダクタンス計算云々は棚に上げ、とりあえず巻いてみることにする。
参考になりそうなサイトをぐるぐる回っていたら、便利な計算ツールが載っているサイトを発見したのでメモ。
Helical Coil Calculator ヘリカルコイル計算機
線の太さと直径と長さ、巻線数や間隔等を入力するとインダクタンスを計算してくれるものだ。
さて、完成はいつになることやら。
---
11/06/14 追記
この手の工作ではおなじみの百円均一のお店(私はセリア派)では、あらゆる用途で筒状のケース的なものが在庫している。本来はお茶や味噌、粉モノなど、密閉して保存したいもの用なのだが、無線脳は何でもコイルの材料に見えてきてしまうのが不思議だ。


ありがたいことに、セリアで売っているこうした筒モノは日本製が多く、某大陸産でありがちな刺激臭やプラスチック臭、そして"やっつけ仕事感"は見られない。先日調達したスズメッキ線はこちらの入れ物を使用するコイルにすることにし、とりあえず手持ちのカラー線(テレビアンテナのステー線の余り)を持ってきて自在ブッシュを貼り付けた塩ビ管に適当に巻いてみた。(参考まで、巻数は43.5回です)
ついでに、物干し竿用洗濯ばさみ(何とポリカーボネート製、3個100円byセリア)で釣り竿にコイルを取り付けてみると、何となくアンテナらしく見えてきたぞ。コイルをクリップ式にしておけば、周波数毎のコイルを必要に応じて差し替えることも出来るし、調整もしやすいだろう。この後、コイルには陸軍端子を取り付け、エレメントにはバナナプラグか圧着端子を取り付けることにする。今の段階で運用目標は、3.5MHz帯と7MHz帯だ。

今まではこれで満足して放置モードに突入していたのだが、次はうまくマウントを作って実際に取り付け、調整・・・するかなあ。
-----
2011/6/17 追記
釣り竿アンテナのエレメント長が約4mで、今回作ったコイルがどこの周波数に乗ってるか確認してみた。

3.5MHz帯に乗れば御の字ってなもんで、アンテナアナライザを追い込んでいくと・・・

ん?3.82MHz付近でVS1.2?
惜しい!!
今回の調整で使った竿は、ローカル局から借りたトップの竿が抜いてある4.5M物だから、実質のエレメント長は約4m。(ローカル局曰く、18MHz帯の1/4λの釣り竿アンテナだぞーとの話)
今後は自前の5.4mの竿(実質5m弱になる)を使ってエレメント長やコイルを調整すればすんなり3.5MHzはイケそうだ。
今回作ったモノのまとめメモ
・直径60mmの塩ビ管
・自在ブッシュ
・1.2mm径のカラーワイヤ(被覆無くても良いと思う)
・43.5回巻
次は7MHz帯のコイル巻に突入予定。(いつかは未定)