かれこれ4年以上前からの個人的なお知り合いで、
2人のお子さんと日本からカナダに家族で留学に向かわれた、
Iさんという方がいらっしゃいます。
Iさんの娘さんのA子さんには、学習障害がありました。
小学校の頃、大変な苦労をされ、
親子で話し合った結果、中学校はインターナショナルスクールへ転学。
そして高校はカナダへ。
先日、娘さんの成績が「生まれて初めてのオールA」だったと
喜びのメールを頂き、
「素晴らしい~~」とわたしも大変嬉しく思いました。
以前、チャレンジ教室に来てくれたエイジ君のときにも感じましたが、
日本で「LDがある」ということは非常に重く、受け止められます。
高校の進学すらためらわれる環境のなかで、
そして実際,高校への進学率が非常に低い現実のなかで、
学習障害は、「学業的にも社会的にも不成功」
というレッテルを貼られるに近いのです。
エイジ君やA子さんの成功例は、
決してそうではなくて
「LDがあっても教え方や環境次第で、学業の成功は可能なんだ」
ということを示してくれます。
「なぜ欧米でできて日本でできないんだろう」
先が見えない気分になったり絶望的な気持になるたびに、
「できないはずはない」、と思い直します。
幸い、最近は日本でも、
民間では専門家と一緒に支援するスタイルの学習塾などが増えています。
また、フリースクールも、
「参加していたらよし」という所ではなく、
もっと子供の学習の「質」を重視した学校が増えてくると思います。
LDの子どもたちの指導方法も、工夫や改良が少しずつですが、進んでいます。
ICTの導入も含め、
子どもたちの選択肢が増えることが、まずは大切だと思います。
カナダやイギリスには行けなくても、
がんばっている子供の気持ちを受け止める場所に出会えますように。
少し長くなりますが、
わたしのリクエストにIさんが応えて書いて下さった手記をご紹介します。
小学校で苦労されていた時代、何に困っていたのか、どういう様子だったのか。
そしてカナダ留学に行ってからどう変化したのか。
Iさんの手記を読みながら、何度も胸に来るものがありました。
同じ苦労をされている子供や親はたくさんいらっしゃいます。
「できないのは子どもたちの努力不足ではない」ということは、特別支援教育では良く聞くことなのですが、
Iさんのような事例を知ることで、
指導側の視点を変えていくこと、
保護者や子どもたちが希望をもって進んで行くことができるのではないかと思っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A子さん 16歳 (10年生/高校生)
カナダBC州 に滞在
滞在ステイタスは留学生
村上:小学校の頃の様子や、困っていたことをお聞かせ下さい。
Iさん:算数が全般的に理解できませんでした。
数がわからないので、『計算』の意味が分からなかったようです。
数が増えると量が増えると言う事も理解できなかったし、
単位が理解できません。
長さと重さの違いなど、時計が読めなかった。
(中学生になっても読めませんでした)
文章問題は文章の意味は理解しても数字が理解できなかったため、
解けませんでした。
不思議と図形だけは出来きたが、
これも数字で計算するような問題は出来ませんでした。
図形を写す、同じ図形を見つける、などは出来きたが、
角度を求めるようなものは出来ませんでした。
算数は全体的にこのような感じだったので、
宿題の問題をひとつひとつ図式化し、
図で描いたものを指でなぞりながら数える、という事が精一杯でした。
その為、同級生が30分で終わらせるような計算問題が
3時間、4時間かかりました。
例えば、かけ算で9×9=81 と
普通は暗記でこなすような問題を方眼用紙に9個丸(○)を描き
それを9列描き、
ひとつひとつ数えていきました。
「努力していて、怠けているわけではない」と言う事を先生にお伝えしたく、
必ず家で宿題をする時に図にしたものは全て持たせましたが、
6年間、
それを見て、意見をくださった先生は一人もいまませんでした。
「こうやってひとつひとつ描き出して、数えないと娘は分からないので、宿題の量を調整したい」
そう何度も申し入れましたが、
「学習の基礎だから」
「努力すれば」
とおっしゃるだけで、
「ではどうすれば良いのですか?」とお尋ねしても答えていただけませんでした。
その当時の教頭先生が算数の専門でいらっしゃると言う事でご相談いたしましたが、
具体的に「なにをどうすればいい」という話ではなく、
「協力しますよ、お母さん。頑張りましょう」と繰り返されるだけで、
メソッドやアプローチは一切お話しされませんでした。
算数のテストの点数はいつも一桁でした。
国語は文章を理解する力はありましたが、
漢字を覚える事が出来ませんでした。
漢字は文章の中にあれば読めたが、
単体で漢字だけ出されたら読めなかった。
書き取りテストは、ほとんど出来ませんでした。
家では歌いながら書き順を指でなぞったり、
大きく拡大したものを色塗りしたり、
習う漢字を使って文章を作ったり、
ありとあらゆる方法で記憶できるように努力しました。
寝る前にも一度書き、
朝学校に行く前にも書き、
テストの前にも書けるように準備を持たせました。
それでも忘れてしまうのです。
10問の書き取りテストで間違えた数の倍数だけ家で書いてくる、
という宿題をされる先生もいらっしゃいました。
7問間違えたら、7つの漢字を7回ずつ。
9問なら9×9で81回。拷問のようでした。
これも家で練習したものを証明として持たせ、
先生に理解を求めました。
「家でこれだけ努力してやっています。でも覚えられないのです。」
「書くのは難しいので、読めるだけで良い事にしてもらえませんか?」と。
でも算数と同じ返答しか頂けませんでした。
「学習の基礎ですから」
「将来困りますよ」
「努力しかありません」
娘は努力をしていないわけではない、
決して頭が悪いわけではありません。
夏休みなどは毎年自主的に「研究課題」を提出しました。
植物園の植物の観察、コアラの研究、ペンギンの乱獲と自然保護、花火の炎色反応、ピクトグラムと標識、氷の温度の実験 ・・・・
「算数が出来なくても、漢字が覚えられなくても、学ぶ事は好きなのです。」
とお伝えしたかったのですが、
娘が動物園や科学館に行って、調べ、まとめあげた事を理解してくれる先生は
残念ながら一人もいらっしゃいませんでした。
こういったものを諦めずに提出してきましたが、
「計算も出来ないような子が」
「漢字も書けないくせに」
という反応に親子で傷つきました。
小学校も高学年になると覚える事が更に増え、
地図記号、都道府県や県庁所在地、歴史年表や事柄。
理科の実験道具の名称、百人一首まで。
低学年より、連絡帳が書けないため、
宿題や提出物がわからなくなり、
忘れ物が多く、
だらしないと言われ続けました。











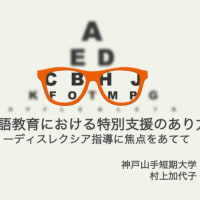



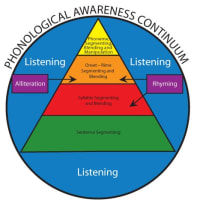
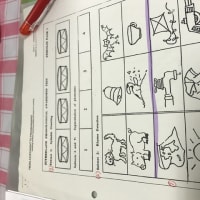



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます