
サブタイトル:大地震・大津波があなたの町を襲う。
帯:古い地名は災害の履歴書。
著者は30年以上地名の事ばかり考えていたという人。
古い地名を全国から調べて、先人の残した地名による危機のリスクを追及する。
3.11以来、まあまあその位でといういい加減(適切)な災害予想でパニックを
避けたり、経済的実害を避けるなどを優先してきたこの国でも現実を直視する雰囲気が
高まり、想定災害規模の大幅な見直しとその対策が検討されている。
この本には、先人が地名として残した津波の痕跡、山崩れ、水害などを実例を挙げて
提示する。通読すると日本列島はどこもかしこも危険地帯だということがよくわかる。
問題はそれがいつ起きるかだ。数千年とか数万年とかの単位であると、一人の人生の
尺度に合わず、ほとんど無視してもたいていの人は問題ないのだが、昨年の3.11は
現実にそれが起きてしまった訳である。
たとえば三浦半島西岸から湘南と呼ばれる地方は関東大震災でも東京都心以上の
建築物の被害が大きかったところであり、人口集中は危険だと断言している。
著者も元々横浜に住んでいたが、この地名調査を進める中であまりのリスクの大きさに
埼玉県へと転居している。
富士山噴火も伊豆半島を乗せたフィリッピンプレートが本州に乗り上げていく過程の
造山運動で出来上がった若い火山であり、いずれ歴史の中であの山容も崩れる
時が来るのだろう。
3.11の津波被害の場所の地名にもまさにそのような先人の残したメッセージが読み取れると
訴えている。問題は色々あるが、古くは奈良時代に時の政権は地名の漢字の見直しを
指示して、危なそうな字を同音の印象の良い漢字で書き換えたということだ。
人為的にリスクを伝える意味が見えにくくなっているという場合も多いと言う。
今も、合併によって古い由緒ある地名が、東西南北を著名な地名に変えてしまう愚が大流行で
「西東京」等のような奇天烈な市名が多数存在する。この著者は湘南という地名も嫌悪している。
中国の名所の名前を軽々に引用して地名にすることの浅薄さを指弾する。
確かに同じようなもんだなと共感もする。
この手の名前の推定にはどうしても強引なものが出てくるので全部が全部その通り
でもないかもしれないが、津波や山崩れの跡としてのリスクをきちんと検証する
きっかけとして役に立つことは間違いない。また、関西の浪速の意味も通常の早い波ではなく
津波の時の猛烈な速度を見てつけられたのではないかと推察する。
全般に大阪も相当に危険なようだ。
こういう事実もあるのだと、この手の本も読んでみる価値は高いと思う。
自分はこのために転居までしないが、孫たちには何か言っておきたいという
感覚でもある。
写真:散歩の山道にある日突如現れた百合の花。びっくり。












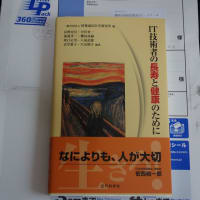







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます