園芸友の会オンライン例会(サイバーサロン)は、下記の通り、7月25日午後2時から始まりました。 北海道(札幌)の中澤会員から「ここ数日36℃を記録している」などの発言があるように全国的な猛暑が続いています。
コロナの以前は、品川の教養室での例会でしたが、現在はオンラインでやっていて、暑い中出かけて行く必要がなく自宅で参加できる利点は勿論、ネットを通じて遠く離れた会員同士が園芸関連のほか、自然や旅行、趣味などの話題をサロン風に交換して楽しむことが出来ています。 今回から、九州の安永正志さんが会員として初参加されました。
第204回例会
日時 :2025年7月25日(金) 14:00~
場所 :各自自宅より(オンライン)
発表 :「農業事業・・米作を中心として」(寺山会員)
参加者:生駒憲治、中澤雅則、土師克己、寺山幸男、安永正志、
本多孝之、中島汎仁(敬称略)
今回のメンバー(関東×3、札幌×1、福岡×2、関西×1)

今回のテーマは、「農業事業・・米作を中心として」を、市街地で米作の他、野菜、果樹などを趣味(事業としてでなく)で長年やっている寺山会員から、自身の経験に基づいて大胆な仮定の下に試算したデータを添えてその実態の発表がありました。
昨今、大きな話題となっている「コメ」について、なぜこのような事態に陥ったか、どうして短期間に価格が倍ほどにも高騰したのか? など、我々が知らない米作の実態の一端なりとも解明したいとの要望から発表をいただいたのです。
寺山会員は、1300㎡(1反強)の耕作地を市街地に4面所有していて、うち3面を稲作(米作)に、残る1面は野菜作りに充てられています。米作の3面は、稲刈り後、次の田植え迄の間、二毛作として、野菜やイチゴなどの栽培をし、イチゴやジャガイモなどは近隣の児童の収穫体験に提供されるボランティア活動も実施されています。
会社を退職した後、これらの作業を趣味を兼ねて1人でやっておられるのですね。
寺山会員の水田(部分) 順調に育つ稲


古代米を使って文字を書く

裏作のイチゴを園児たちが収穫

(写真はいずれも寺山会員提供)
で、発表は、自作されている3面の稲作を基に、数値化をしてそれを大規模耕作に適用した場合の事業性を検討された内容でした。

今、耕作規模を3反、5反、1町(10反)、10町を仮定して、経費を算定すると、費用要素として、
*材料代(苗、肥料、農薬等)は耕作規模に比例して増加(反当りは一定)し、
*逆に機械代(トラクター、コンバイン、田植え機、乾燥機、籾摺り・選別機等)は、固定費なので、耕作規模が大きくなるにしたがって使用効率が向上し、反当り経費は減少します。
また、ある程度の規模以上になれば、使用機械は大型化するなどの変化はあります。
(参考ですが、アメリカの小麦地帯は、緯度によって収穫時期がずれていき、刈り取り専門業者が機械を保有し、南から北へ順々に移動して刈り取りしていき、農場主は刈り取り機械を保有していないようです。)
*ここで、人件費も規模に比例して増加し、雇用すれば明確になりますが、自作特に兼業(サラリーマンや、野菜が専業)で、土、日曜日など遊び感覚で米作すると、人件費=ゼロという考えもあります。
これを簡単に、下表にまとめてみました。
経費について

以上のことを念頭に置いて、現実に行っている 寺山会員のモデルで試算してみると、
〇3~4反規模では、所有機械類の使用効率が悪く、機械に余裕があり、機械代を使いきっていないこととなります。所有機械類の効率は、5反規模でもまだ余裕がありますが、人件費をゼロとすれば、その場合、反当りの費用は、約20万円(人件費を含まず)となり、反当りの収入とバランスすることから、お米5㎏換算では約1700円/5 ㎏が得られます。
ここで、人件費を0としましたが、寺山会員の場合は、退職後、1人で趣味的に、そして野菜や果樹栽培などを楽しみながら実施されていますから、この1700円が原価?扱いと見なせば、仮にこれを市場経由で食卓に上る場合の費用は、1700円に人件費、流通・輸送費、保管費、精米費、利益が加味されると考えられます。
寺山会員の場合で、米作に係る日数を試算すると、年に僅か反あたり10日余りとなり、3反で年間30日(1日弱/週)、後は自然の作用で稲が生長するのですね。
昔は人手で田植えをしていましたが、今では田植え機に代わり、肥料も、時間差効果を発揮する肥料が田植え機で同時に施肥され、除草も専用の除草剤(枯らすのではなく、発芽を抑える)を散布することで、手間暇がかからないようになっているのです。ですので一人でやって行けるのですね。今や米作には手がかからない。
〇1町(10反)規模では、所有機械類の効率が丁度良く、収支トントンですが、事業としては、所得(給与)ではなく、売り上げ約200万円となり、事業になりません。数町規模に規模拡大しないと、専業農家として事業にならないようです。

米作を事業として捉えると、上で見て来たとおりある程度の規模を確保し、効率を高める必要のあることが分かりますが、水田は水をためる必要があるため水平でなくてはならず、また底辺土壌には粘土質が要求され、八郎潟、有明海等の干拓地、区画整理地を除けば、日本の農地は中山間地(棚田)が大半で、規模の拡大、特に連続した広大な土地を確保することが困難な場合が多く、ここが大問題のようです。
寺山会員の場合は、大都市近郊農地で、水田が3面ありますが、少し離れているためトラクターの使用時に水田を移動する度に、一旦清掃し(泥を落として)市街地の舗装道路を移動しなければならず、大幅な時間的ロスが生じているとあります。

以前には、コメ余りを解消するために減反政策がとられてきましたが、そうではなく、コメは作れるだけ作り、余剰分は輸出するという案も聞こえてきていますが、輸出は価格競争にさらされ、楽観できません。それより、政府が買い上げてODAの一環として、食糧難の地域(国)に提供すれば、政府の買い上げ価格が、生産者価格の目安にもなり、生産者価格も安定するメリットもあると寺山会員は提案されています。(土地の集約化、広大化不可、後継者不足、遊休地増で、コメ余りにならないのでは?という意見もありました。)

発表後、各自から多くの質問や意見が出て、活気に満ちたサロンが展開されました。最近スーパーに行っても「備蓄米」が並んでいるのが見られ、売れ残っているのでは?などの発言もあるほか、備蓄米が2000円/5㎏で販売されているが、備蓄米を放出する場合には、精米、流通などの費用がプラスされているわけで、そもそも政府が買い上げた価格はいくらなのか?
さらには、小規模生産者にとっても、口コミ等で試食され気に入られれば、直販による販売も可能かもしれない・・その場合、送料を低減するための集約配送業の出現も考えられるかもしれないなど、新しい事業化へのヒントなども飛び出したりしました。
活気に満ちた議論はまだまだ続き、16時を過ぎてようやくお開きとなりました。
お疲れ様でした。
*お問い合わせなどお気軽にどうぞ・・中島まで。
メルアド: h.naka@crocus.ocn.ne.jp










































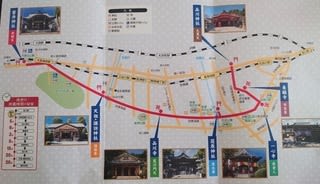



 (農水省より)
(農水省より)
 (宝徳寺HPより)
(宝徳寺HPより)




