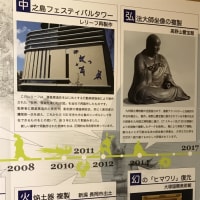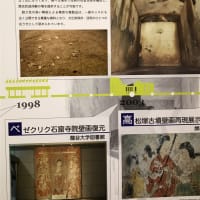週末のテレビも依然としてフジテレビvsライブドア問題で盛り上がっていた。
気になったのが、「放送の公益性と外資規制」という論点。
放送法2条1項3項の2では
「放送事業者」とは、電波法 の規定により放送局(中略)
の免許を受けた者、(中略)をいう。
とされていて、
電波法第5条では
左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代
表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の
一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
とされている。
つまり、外国人株主が1/3以上の会社はそもそも放送局の免許が下りないということが、外資規制の中身。
今回はライブドアがリーマン・ブラザーズから資金調達したことを理由に、外資規制の枠にかけられないか(広げられないか)という議論なのだろう。
しかし、これはかなり議論の必要な問題だと思う。
そもそも電波法は間接保有(外国人が100%支配している日本法人)を規制していないのであるから、まずは間接保有の規制をしたいらしい。
そうなると、間接支配は100%じゃなきゃいいのか、電波法基準だと代表者が外国人(=日産はダメ)、役員またはの1/3が外国人というのもダメとなりそうだが、間接支配1/3基準を延々と遡ると、相当の数の「外国人株主」が発生する可能性がある。
また、投資信託経由の外国人投資はどうなるとかの議論も必要。
さらに、転換社債を持っているだけでダメといするなら、理論的には外国人役員や従業員のストックオプションもカウント対象になることになる。
それと上の間接支配ルールをいっぺんに適用した瞬間に、放送局は外国人比率を数えることだけで忙殺されてしまう。
それに免許を与えた場合でも、表現の自由(放送法1条2項)が全面的にまかりとおるわけではなく、当然公共性の制約はある。
放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関に番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定めて諮問しなければならなかったり、 審議機関が意見を述べることもできる。(3条の4)
また、放送法に違反した場合、放送局免許の取り消しまでできる(電波法76条)
つまり、審議会や総務大臣がちゃんと仕事をすれば、放送事業の公益性は現在の枠組みでも守れるはずなのだ。
結局、外資規制基準見直し論は、「思いつき」か「牽制球」の域を出ていないと思われるので、以後の議論(もし続けば)では無視することにしよう。
* これ以前の記事は以下を参照
その1
その2
その3
気になったのが、「放送の公益性と外資規制」という論点。
放送法2条1項3項の2では
「放送事業者」とは、電波法 の規定により放送局(中略)
の免許を受けた者、(中略)をいう。
とされていて、
電波法第5条では
左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代
表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の
一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
とされている。
つまり、外国人株主が1/3以上の会社はそもそも放送局の免許が下りないということが、外資規制の中身。
今回はライブドアがリーマン・ブラザーズから資金調達したことを理由に、外資規制の枠にかけられないか(広げられないか)という議論なのだろう。
しかし、これはかなり議論の必要な問題だと思う。
そもそも電波法は間接保有(外国人が100%支配している日本法人)を規制していないのであるから、まずは間接保有の規制をしたいらしい。
そうなると、間接支配は100%じゃなきゃいいのか、電波法基準だと代表者が外国人(=日産はダメ)、役員またはの1/3が外国人というのもダメとなりそうだが、間接支配1/3基準を延々と遡ると、相当の数の「外国人株主」が発生する可能性がある。
また、投資信託経由の外国人投資はどうなるとかの議論も必要。
さらに、転換社債を持っているだけでダメといするなら、理論的には外国人役員や従業員のストックオプションもカウント対象になることになる。
それと上の間接支配ルールをいっぺんに適用した瞬間に、放送局は外国人比率を数えることだけで忙殺されてしまう。
それに免許を与えた場合でも、表現の自由(放送法1条2項)が全面的にまかりとおるわけではなく、当然公共性の制約はある。
放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関に番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定めて諮問しなければならなかったり、 審議機関が意見を述べることもできる。(3条の4)
また、放送法に違反した場合、放送局免許の取り消しまでできる(電波法76条)
つまり、審議会や総務大臣がちゃんと仕事をすれば、放送事業の公益性は現在の枠組みでも守れるはずなのだ。
結局、外資規制基準見直し論は、「思いつき」か「牽制球」の域を出ていないと思われるので、以後の議論(もし続けば)では無視することにしよう。
* これ以前の記事は以下を参照
その1
その2
その3