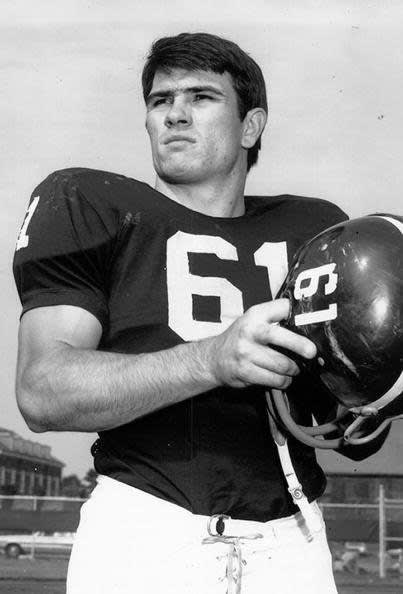昨日、映画館で『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』(中国原題:妖猫傳、英語タイトル:Legend of the Demon Cat、2017)を観た。あの『北京ヴァイオリン(和你在一起)』(2002)のチェン・カイコー監督(陳凱歌、1952‐)にして、老いてこの駄作的な娯楽映画か、ああ詰まらないと思って帰宅し、そのまま思い出すこともなく寝てしまった。ところが翌朝、起きたら、今さっき見てきた夢の後味を舐(な)めるように「ははーん、あの映画は、中国の今を反転して唐になぞらえ、夢仕立てにしたもので、現政権の『中国の夢』を悪夢にして描いた作品なのだ」と急に悟った。そう考えると、かなりの暗喩(あんゆ)に満ち、工夫に富んだ傑作である。日本語版では、興行的意味合いからか、映画の主人公はあくまで日本僧・空海(774‐835)とその友人の詩人・白居易(772‐846)になっているが(彼らは単なる歴史探訪のナビゲーターでしかない)、本当の主人公は中国原題や英語タイトルに示されているように、悪魔の猫=妖猫に化ける中国人民(特に民主化運動家?)なのである。映画では、この黒猫(中国ではもともと黒猫に悪いイメージはない)が玄宗皇帝(712‐756)の身代わりに自殺を強いられた楊貴妃(719‐756)の恨みを残酷なまでに晴らす復讐の物語展開になっている。それはまたシルクロードで西欧につながった唐の繁栄に比すべき一帯一路を推進する現代中国における人民の恨みを晴らす話になっているのだ。任期を撤廃した終身国家主席はいわば皇帝のようなものである。多分、われわれ一般の日本人や原作者の夢枕獏氏(1951-)ですら、夢枕にも思わなかった現代中国に対する批判的含意がこの文革世代の映画人によって撮られた映画には込められている。それが正夢になるかどうかは、未来しか分からない。日本で『空海』として上映された絢爛豪華(けんらんごうか)たる歴史ファンタジーの娯楽超大作を観て、こんなことを考えるのは邪推、曲解であろうか。