【2011年2月13日追記】
意外にも「光秀の天下」というタイトルで一気に光秀の死まで行ってしまいました。そして、予想通り光秀の辞世の句は出ませんでした。光秀の最期の言葉は脚本家の全くの創作で軍記物にも司馬遼太郎『国盗り物語』にも縛られていませんでした。これは喜ぶべきなのか、単に脚本家が自由に発想しただけなのか、評価を留保して「江」のこの先を見て行きたいと思います。
この先は司馬遼太郎『明智軍記』には書かれていない時代に入っていきます。そこを書いているのは吉川英治『新書太閤記』であり山岡荘八『徳川家康』だったりします。その元ネタは江戸時代に書かれた軍記物の各種『太閤記』などです。もう少し「江」をフォローしてみたいと思います。
【2011年2月12日追記】
どうやら一週間先走ってしまったようです。明日の放送は「光秀の天下」でした。本ブログ12日朝の記事は一週間あとまでとっておいてください。代わりに第5回放送への追加記事を書きましたのでご覧ください。
★ 光秀謀反決意の理由
【2011年2月12日朝記事】
明日の大河ドラマ「江」は光秀の滅亡です。昨日の本ブログ記事では明日間違いなく放送される「小栗栖の竹薮」は創作であることを事前に書いておきました。正しい歴史知識を持って見ていただきたいと思いましたので。
★ 大河ドラマ「江」の歴史捜査6:小栗栖の竹薮
光秀の死に関しては、もうひとつ有名な創作があります。それは辞世の句です。
「順逆二門無し 大道心源に徹す 五十五年の夢 覚め来たりて一元に帰す」
この句は悪名高き『明智軍記』が創作したものです。本能寺の変から百十年もたって初めて辞世の句が公開されたわけですので、それが史実か創作かは一目瞭然でしょう。
でも残念なことに光秀一族の菩提寺である坂本・西教寺には、この句碑が建ってしまっています。西教寺はとても由緒ある立派なお寺だけに残念を通り越して悲しくなります。
★ 先祖明智光秀の命日と光秀辞世の句
さて、明日の「江」で果たして、この辞世の句が出てくるでしょうか。
私は出てこないと思います。
なぜかというと司馬遼太郎『国盗り物語』にはこの句が書かれていないからです。これまでの放送内容から判断して、「江」の脚本家は司馬遼太郎『国盗り物語』を参照しており、その元ネタとなった『明智軍記』は読んでいないと推理しましたので。
ところで、『明智軍記』を元ネタとして『国盗り物語』を書いた司馬氏はなぜこの句を書かなかったのでしょう。単なる書き落とし?紙面や字数の関係で削除?余りに嘘っぽくて使えないと判断したから?・・・ちょっとした謎です。
一方、司馬氏は『明智軍記』に書かれている、もうひとつの有名な言葉は書いています。
「心知らぬ人は何とも言わば言へ 身をも惜しまじ名をも惜しまじ」
これは謀反を決意する際に書き残したと『国盗り物語』に書かれていますが、既に「江」で放映されたでしょうか。いつも晩酌をしながら見ているので、だんだん酔いが回って見逃してしまったのか記憶に残っていません。もし、まだ放送されていないようであれば、光秀の最期の言葉として脚本家が使うかもしれません。
さて、光秀はどんな言葉を残して死ぬでしょうか。明日の放送を「楽しみ」にしています。ただ、決して先祖の死を楽しみにしているわけではありませんので、誤解なきようにお願いいたします。
【大河ドラマ「江」シリーズ】
本能寺の変の通説:今年も「江」で登場
兄・万福丸の処刑の真相
万福丸ショック
父・浅井長政の頭蓋骨
正月の酒宴の出席者
森蘭丸さん?
光秀のきんかん頭
怨恨説踏襲ですね!
『明智軍記』踏襲ですね!
信長の遺体
小栗栖の竹薮
>>>トップページ
>>>ブログのご案内
>>>本能寺の変 四二七年目の真実
意外にも「光秀の天下」というタイトルで一気に光秀の死まで行ってしまいました。そして、予想通り光秀の辞世の句は出ませんでした。光秀の最期の言葉は脚本家の全くの創作で軍記物にも司馬遼太郎『国盗り物語』にも縛られていませんでした。これは喜ぶべきなのか、単に脚本家が自由に発想しただけなのか、評価を留保して「江」のこの先を見て行きたいと思います。
この先は司馬遼太郎『明智軍記』には書かれていない時代に入っていきます。そこを書いているのは吉川英治『新書太閤記』であり山岡荘八『徳川家康』だったりします。その元ネタは江戸時代に書かれた軍記物の各種『太閤記』などです。もう少し「江」をフォローしてみたいと思います。
【2011年2月12日追記】
どうやら一週間先走ってしまったようです。明日の放送は「光秀の天下」でした。本ブログ12日朝の記事は一週間あとまでとっておいてください。代わりに第5回放送への追加記事を書きましたのでご覧ください。
★ 光秀謀反決意の理由
【2011年2月12日朝記事】
明日の大河ドラマ「江」は光秀の滅亡です。昨日の本ブログ記事では明日間違いなく放送される「小栗栖の竹薮」は創作であることを事前に書いておきました。正しい歴史知識を持って見ていただきたいと思いましたので。
★ 大河ドラマ「江」の歴史捜査6:小栗栖の竹薮
光秀の死に関しては、もうひとつ有名な創作があります。それは辞世の句です。
「順逆二門無し 大道心源に徹す 五十五年の夢 覚め来たりて一元に帰す」
この句は悪名高き『明智軍記』が創作したものです。本能寺の変から百十年もたって初めて辞世の句が公開されたわけですので、それが史実か創作かは一目瞭然でしょう。
でも残念なことに光秀一族の菩提寺である坂本・西教寺には、この句碑が建ってしまっています。西教寺はとても由緒ある立派なお寺だけに残念を通り越して悲しくなります。
★ 先祖明智光秀の命日と光秀辞世の句
さて、明日の「江」で果たして、この辞世の句が出てくるでしょうか。
私は出てこないと思います。
なぜかというと司馬遼太郎『国盗り物語』にはこの句が書かれていないからです。これまでの放送内容から判断して、「江」の脚本家は司馬遼太郎『国盗り物語』を参照しており、その元ネタとなった『明智軍記』は読んでいないと推理しましたので。
ところで、『明智軍記』を元ネタとして『国盗り物語』を書いた司馬氏はなぜこの句を書かなかったのでしょう。単なる書き落とし?紙面や字数の関係で削除?余りに嘘っぽくて使えないと判断したから?・・・ちょっとした謎です。
一方、司馬氏は『明智軍記』に書かれている、もうひとつの有名な言葉は書いています。
「心知らぬ人は何とも言わば言へ 身をも惜しまじ名をも惜しまじ」
これは謀反を決意する際に書き残したと『国盗り物語』に書かれていますが、既に「江」で放映されたでしょうか。いつも晩酌をしながら見ているので、だんだん酔いが回って見逃してしまったのか記憶に残っていません。もし、まだ放送されていないようであれば、光秀の最期の言葉として脚本家が使うかもしれません。
さて、光秀はどんな言葉を残して死ぬでしょうか。明日の放送を「楽しみ」にしています。ただ、決して先祖の死を楽しみにしているわけではありませんので、誤解なきようにお願いいたします。
【大河ドラマ「江」シリーズ】
本能寺の変の通説:今年も「江」で登場
兄・万福丸の処刑の真相
万福丸ショック
父・浅井長政の頭蓋骨
正月の酒宴の出席者
森蘭丸さん?
光秀のきんかん頭
怨恨説踏襲ですね!
『明智軍記』踏襲ですね!
信長の遺体
小栗栖の竹薮
>>>トップページ
>>>ブログのご案内
>>>本能寺の変 四二七年目の真実
 | 本能寺の変 四二七年目の真実明智 憲三郎プレジデント社このアイテムの詳細を見る |










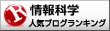














このブログでの「江シリーズ」を拝見して思ったのですが、NHKの大河ドラマこそ、現代の軍記物と言えるのではないでしょうか? 歴史の真実とは離れて(明智さんご指摘のように、史実との混同は危険です)、軍記物という創作活動が数百年継続している現象には興味深いものがあります。 それだけに、より深く史実に即した作品が、テレビであれ、映画であれ、あまりにも少ないことにも危惧を抱かざるを得ません。 427のテレビドラマ化は僕も大変楽しみにしていますし、仮によく出来たものが放映されたとすれば、その時にどんな反響があるか、想像しただけでも楽しくなります。
まもなく「光秀の滅亡」ですが、どんな竹薮が出てくるのか、待ちきれません。 これはドラマを観る上での楽しみですが、それとは別に「光秀の敗走と死」に関する検証の必要性も感じています。 ここでも相当議論が深まっていますが、山崎の合戦から死に至るまでの光秀の行動は、一言で言えば「不可解」です。 これを解明することで明智説の裏づけ、即ち「援軍を待っていた(それが誰からの援軍でどのくらいの規模かはひとまず措くとしても)」可能性が見えてくるような気がしてなりません。
付け足しですが、「嘘も100回言えば真実になる」と言ったのはゲッペルスです。 ただそう言っただけでなく、実際に「有言実行」してしまったのですが…。
やはりフロイス・2さんは赤ワインにゲッペルスときましたね。欧米の文化・歴史への造詣の深さにはいつも感服していますので納得しました。こちらの晩酌は芋焼酎。最近調べているのは千利休、島井宗室、古渓宗陳と純和風です。
これからは海外、といっても東アジアのことに関心を高めていきたいと思っています。私の歴史捜査とこれからの日本の生きる道の模索の両面からです。
大河ドラマが現代の軍記物というご指摘は私が「江」を追ってブログに連載していて、正に痛感していることです。「歴史がますます歪曲されていく」と焦っております。
歴史捜査レポートの「光秀の敗走とその死」が未決着で申し訳ありません。実はひとつの答が思い浮かんでいるのですが、証拠が不十分です。現段階で結論を出すと子孫の手前味噌となる可能性もあって筆が止まっています。「江」さんとのお付き合いが終わったら、復帰したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
僕は子供の頃から歴史は好きでしたが、「歴史研究」に興味を持ったのは、実は「OK牧場の決闘の真相を知りたい」と思ったことがきっかけでした。 明智さんの御著書や研究に触れることでわかったのですが、「軍記物」と称する「お話」がいつの間にか通説となり、それが大河ドラマで増幅されて定説となる、このパターンは西部開拓史におけるガンマンやアウトローに関しても見事に当てはまるのです。 多くの場合は彼らが存命中に、主として東部の読者を対象として書かれた「三文小説」(ほとんどホラ話です)がいつの間にかノンフィクションに見立てられ、それがハリウッド映画で世界中に配信されるわけです。 ジョン・フォードの「荒野の決闘」は確かに名作ですが、ドク・ホリデイが元外科医(本当は元歯医者)だったのには唖然とさせられました。 他にも事実誤認やむちゃくちゃな設定など、数え上げればきりがないほどです。
とは言え、実証的な研究も、特にこの25年ほど著しく進展しているようです。 これはワイアット・アープ研究に特に顕著なようですが、当時の新聞記事、裁判記録、土地の登記書類、同時代人や当事者の証言などの一次資料を掘り起こすことによって、蓋然性の確度を相当上げた研究となっています。 明智さんの本を読んだときに、これらの研究と全くと言っていいほど同質の説得力を感じました。 つまり、資料(特に一次資料)の掘り起こしと緻密な検証、端的に言えば優れた方法論です。 90年代に製作された「アープ物」は、かつてのそれと比較すれば相当事実に近づいてきた印象です。 427の影響も、近い将来にその成果に接することを期待しています。
私が生まれ育った故郷は名古屋駅から西に位置します。
帰省する途上は藤吉郎・虎之助・お松・市松・小六ゆかりの地を通り過ぎ・そして信長の支城のあった町にたどり着きます。
当然のことながら信長を敬い、秀吉に憧れる子供時代でした。
勉強がまったく出来ず、本をはじめて読んだのも小学5年生で太閤記が最初です。
それ以来武将ものに読みふけり、3年B組金八先生から坂本龍馬にのめりこみました。
龍馬の先祖が明智光春と知り、私と同じ光の字の光秀公に興味を抱きました。
なぜ徳川家が光秀や利三ゆかりの方々を用いたのか?
実は、私も天海上人が生き延びた光秀公というロマンにあこがれていました(笑)
そんな間違いを明快に記して真実を教えていただいた明智様に感謝いたします。
歴史は時の有力者が編纂していくうちに誤った解釈が史実のように伝わることを特に最近読んだ大好きな漫画「戦国武将列伝」で認識しました。
桶狭間の戦いは、奇襲ではなく正面から迎え撃ち多大な犠牲を払いながらも最後は見事今川を討ち取ったという成功法で打ち負かしたという史実は信長公記がやはり証明してそれを認識したのも最新刊を読んでのことです。
上京して有楽町が織田家ゆかりの地・上野は伊賀上野・不忍池は琵琶湖をモチーフに・・・
最近のパワースポットとして清正の井戸などなど。東京に出てきてはじめて知ったことが
多々ありました
社会人になり、羽柴秀長にあこがれ家老を勤めた藤堂高虎公が現在の私の中での一番大好きな武将でもあります。
娘がまだ2歳当時の家族旅行で京都に行った目的は坂本龍馬の墓参りと高台寺の秀吉とお寧の墓参りという支離滅裂な詣ででありました。それにしても「申し訳ありません。」
長宗我部家を討ったのも藤堂高虎公でしたね。
南禅寺の楼門をどうしても訪ねたくてそこから散策した道中に光秀公の首塚がありお参りをさせていただき饅頭を買って食べた思い出もあります。
明智様の著書にも登場する尾張津島で生を受け、両親が私の名前をつけるに当たり祝言を挙げた津島神社の神主さんに授けていただいた名前に光の字があるのもどこかで縁があるのかなと勝手に思っています。
父は秋田県の農家・母は三重県の農家出身でたまたま居を構えた実家が愛知県の武家文化のある町で育っただけで何の関係もないのですが(笑)
歴史の重要な局面で土岐氏末裔光秀公や龍馬公が登場するだけで凡民の私からすればとてつもない偉業であり、誰からも愛される龍馬のごとく光秀公にも光があたる世の中になればいいなぁと平和な世の中に生まれた自分の境遇に感謝しております。
大河ドラマの主人公になる過程で戦国武将列伝にて427年目の真実が取りあげられて少しずつでも世論が動いてゆけば必ず実現することになり、全国の竜馬ファンと連携を取れば悲願の光秀公復権が成就することが叶うのではないでしょうか?
願いごとが叶うことをお祈りし、私の戦国ロマンの楽しみとしたいと思います。
良くぞここまで、そして土岐氏繁栄のために尽力されるお姿に感動いたしました。
大河ドラマの実現を心よりお祈りいたします。
ありがとうございました。
敬具
2月13日 光彦
土岐氏 氏族長
明智憲三郎様