 |
もう一つの「幕末史」: “裏側”にこそ「本当の歴史」がある! (単行本) |
| クリエーター情報なし | |
| 三笠書房 |
ランキング参加しております![]()
![]()
●日本の情けなさMAX 「非独立国」を翁長知事に教えられ
以下は、吉川由紀恵氏の少々下手糞な日本語による、沖縄県辺野古基地問題を、沖縄県として、アメリカに伝える要の仕事をしていたことを通じても、同氏なりの、考えを、連続レポートしている。ひとつは、「沖縄の声」であり、もう一つが「ワシントンの誰に伝えるか」である。通読してみて、結論らしきものが見えてこないのが残念なレポートだが、日本の外務・防衛やアメリカの国務・国防の実態を知るには、それなりに参考になるレポートでもある。
鳩山由紀夫への言及では、ステレオタイプな評価にとどまり、実態が見えていないところ等を見ると、上っ面をなぞっている傾向もみられる。27日から、日本政府の聞く耳持たず非民主的な態度に“業を煮やした”沖縄県民の総意を背に、翁長知事が27日訪米する。知事の訪米は就任後初めてで、名護市の稲嶺進市長や県議会や経済団体が同行し、オール沖縄の姿を、アメリカ及びワシントンに直に伝えることになる。
今さら、沖縄県の米軍基地問題を蒸し返されることを、日本政府をはじめ、アメリカ政府、国務・国防共に嫌がるだろうが、安倍・菅レベルの聞く耳持たずな姿勢よりは、米軍にとって、日常的リスクが伴うことだけに、多少の危機意識はあると考える。軍事的に沖縄の米軍基地が、アジアの要衝と云う理屈は判るが、グアムでも事足りるのであれば、九州四国中国地方でも、軍事的要衝になり得る。その意味だけでも、絶対に沖縄県である必要はないし、まして、辺野古でなければいけない絶対的条件は一つも示されていない。
吉川氏のレポートを読めばわかるが、代替案など出す必要が沖縄県にあるわけがない。どうしても、安全保障上、喫緊の必要性があるのなら、山口県(長州)が最適だ。長州閥で明治維新以降の日本を駄目にしたのだから、頑張って貰おうではないか。世界遺産の登録するようだから、日本の非独立の象徴として、山口県の辺野古代替が最良の解決の道だ。その米軍基地を「日本の非独立歴史の象徴」として、何年かのちに、世界遺産登録も良いじゃないか。アメリカと云う国をシンボリックな見世物として、世界に示せる。
しかし、安倍と菅のコンビが、日本に、沖縄に「反権力」のヒーロー、英雄を生みだした事実は、非常に意義深い。琉球民族と云う表現は穏当ではないが、彼らから、日本の非独立性を教えて貰わなければ、どうにも平和ボケが直らないと云うのも、本土の大和民族としては、絶大に恥ずかしい。翁長知事は、あくまで穏当を旨としているが、安倍や菅の姿が姑息すぎるので、翁長知事の、顔つきが日ごと神がかってきている。筆者的には、琉球王国の紋章のハチマキと“かりゆし”でアメリカ中に旋風を巻き起こして欲しいものだ。おそらく最終的に、安倍政権は翁長に負けるだろう。
注:琉球王国・紋章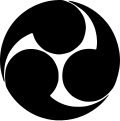
≪ 社説[翁長知事あす訪米]辺野古ノーの声を聞け
翁長雄志知事は、27日から6月5日までの日程で訪米する。ハワイやワシントンを訪れ、米軍普天間飛行場の早期返還と名護市辺野古の新基地建設反対などを米側に直接訴える。
24日、東京の国会議事堂周辺で行われた辺野古の新基地建設に反対する抗議行動には約1万5千人が集まり、「人間の鎖」で国会を包囲した。辺野古移設反対をテーマにした国会包囲行動で、これほど多くの人が集まるのは、過去に例がない。沖縄の民意への共感が広がっていることを象徴する出来事だ。
翁長知事は4月に安倍晋三首相、菅義偉官房長官と相次いで会談。5月には中谷元・防衛相との会談や東京での在京・海外メディアとの会見、さらに約3万5千人が参加した県民大会で、積もり積もった思いを発信してきた。
特に、安倍首相らとの会談ではかなり踏み込んだ発言で、県民の思いを代弁した。沖縄の戦後史を踏まえ、過重な基地の負担や新基地建設の不当性を強く訴えた。普天間については「自ら土地を奪っておきながら、嫌なら代替案を出せというこんな理不尽なことはない」と厳しく批判した。
翁長知事の毅然(きぜん)とした姿勢は、本土の人たちにインパクトを与え、沖縄への理解を促した。複数の全国メディアの世論調査では、辺野古移設に反対の意見が増えている。辺野古基金は短期間で2億5千万円を突破し、その約7割が本土からだ。沖縄の運動を支えようという機運が高まっている証しといえよう。
■ ■
辺野古移設反対の世論の広がりは、訪米の追い風になるに違いない。ワシントンでは国務省や国防総省の次官補、次官補代理クラスとの会談を希望しているほか、シンクタンクなどとの意見交換を予定している。
ただ、4月の日米首脳会談で、両政府が辺野古移設推進を確認した直後である。仲井真弘多前知事の埋め立て承認で、米政府や議会内で辺野古問題が「決着済み」との見方が広がっているともいわれ、厳しい対応も予想される。
翁長知事は25日、共同通信の取材に対し、前知事による埋め立て承認に関し、県の第三者委員会から7月上旬に承認取り消しが提言されれば「取り消すことになる」と明言した。政府が移設を強行すれば「日米同盟に傷を付ける」とも語った。
あらゆる手段を駆使し、新基地は造らせないという沖縄の覚悟を日米両政府は甘くみるべきではない。住民の敵意に囲まれた基地は機能しない、ということを米国は知っている。米政府は辺野古問題を真剣に考えるべきだ。
■ ■
上野千鶴子さん(ウィメンズアクションネットワーク理事長)は、17日の県民大会に向けて本紙に次のようなメッセージを寄せた。「沖縄の運命が沖縄抜きに決められようとしている。当事者主権の叫びは当然だ」
米軍基地の存在は、住民生活に大きな影響を及ぼす。「辺野古移設ノー」のまっとうな主張を、沖縄はさまざまな機会を通して、訴え続けていく。 ≫(沖縄タイムス・社説)
≪ 「沖縄の声」をワシントンに届ける
012年3月、筆者は縁あって沖縄県庁に勤務することになった。普天間飛行場移設問題について、沖縄の声を米国の首都、ワシントンに伝えるために。筆者はこの前、ワシントンにあるジョンス・ホプキンス大学高等国際関係大学院(通称SAIS)附属ライシャワーセンターの研究員であったため、ワシントンでのネットワークや知見を買われてのことだった。当時はまだ仲井真弘多知事が辺野古埋め立て承認をする約2年前であった。
まずは、「普天間飛行場移設問題」とは何か、「沖縄の声」とは何か、「ワシントン」とは誰を指すのかについて説明する。
普天間飛行場移設問題の経緯については新聞などで見かけることもあるだろう。1995年に起きた米兵による少女暴行事件を契機に、沖縄では参加者が約8万5000人に上る抗議の県民大会が開かれた。これを受け、日米両政府は沖縄の人々の怒りを鎮めるべく、沖縄が負う米軍基地の負担を軽減する措置を考えるためのタスクフォース(通称SACO)を新設。翌96年には、普天間飛行場を含めた在沖米軍施設を移設あるいは土地を返還すること通称SACO合意を発表した。
普天間飛行場は、宜野湾市の市街地のただ中に位置し、軍用機が墜落すれば大惨事に至ることが容易に想定された。実際に2004年、軍用ヘリが普天 間飛行場近くの沖縄国際大学キャンパス内に墜落している。奇跡的に死者は出なかったものの、普天間飛行場の危険性を改めて認識させるものだった。
ただし、普天間飛行場の移設先は1996年時点では検討継続とされた。そして2006年、日米両政府が移転先を辺野古に決定し、「再編実施のための日米のロードマップ」(通称ロードマップ)に明記した。
ところが2009年、この決定についての地元との調整が完全にはついていないうちに、「県外移設」を掲げる鳩山由紀夫氏が率いる民主党政権が誕生。その後、鳩山首相(当時)は発言を二転三転させ、結局、辺野古に戻った。
この間、地元沖縄では、辺野古を抱える名護市と沖縄県が2010年に、それぞれ市長選と知事選を実施。いずれも県外移設を求める候補を当選させる ことで民意を示した。しかし、県外移設を掲げて当選した仲井真弘多知事が2013年12月に辺野古埋め立てを承認。現在、埋め立てのための調査が辺野古で進められている。
■普天間飛行場を辺野古に移設させたい理由
普天間飛行場の移設スキームは意外に知られていない。普天間飛行場を管理しているのは、米国海兵隊である。海兵隊は、陸上部隊、空挺部隊、兵站部 隊の三位が一体となって行動する。沖縄では、陸上部隊は主にキャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブに、空挺部隊は普天間飛行場に、兵站部隊は主にキャンプ・キンザー、キャンプ・フォスターに点在する。
地図を見れば、くの字型をしている沖縄本島の北東(キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブ)から中部(普天間飛行場)、南西(キャンプ・キン ザー)へと斜めに突っ切るように各拠点が並んでいる。沖縄県の人口の8割は沖縄本島の中南部に集中しているため、この配置が交通渋滞を起こす。
例えば中部から南部の那覇へ通勤する人は、これらの基地の間を縫うように抜けるくねくねと曲がった幹線道路、もしくはそのバイパスを利用する。こ のどちらも、交通量はそのキャパを超えてしまっている。新しいバイパスを造る余地はない。また、本島中部を東西に移動するには基地を迂回しなければならない。このように、基地の存在は沖縄の生活に少なからぬ支障をきたしている。(実際にはこれに、騒音や事故の危険性が加わる)
この空挺、兵站機能を、陸上部隊がいる辺野古周辺に集約することで、沖縄と米軍はウィン・ウィンの関係になれる。沖縄は、普天間飛行場が有する危 険性を除去することができる。加えて、人口密度の高いエリアにあるキャンプ・キンザーなどの土地を返還してもらえる。海兵隊約5000人がグアムに移転すれば、駐留する米兵の数が減少する。米軍は、海兵隊の3機能を近いエリアに集約することができる。ただし、キャンプ・キンザーなど米軍が返還する予定になっている基地の代替地を日本政府が提供できれば、の話である。
■沖縄が感じる基地負担を巡る不公平感
ただし地元民としては、「基地の返還といいながら、単なる土地の移動にすぎない」――という思いをぬぐい去ることはできない。結局、沖縄に基地が 有り続けるからだ。基地負担を軽減してほしいとの願いは、戦後70年にわたって沖縄が抱いてきたもの。27年間にわたる米国統治が終結した1972年の日 本復帰以来、沖縄は日本政府に求めてきた。
現在、面積で言えば米軍専用施設の約75%が沖縄県にある。沖縄以外の場所では、米軍専用施設の59%が終戦直後、日本に返還された。沖縄が日本に復帰する際、県民は同様に負担が軽減されることを期待していたが、沖縄県にあった米軍専用施設の18%程度しか返還されなかった。ここに、基地負担を巡 る不公平感を沖縄が感じる根底がある。
こうした経緯に加え、鳩山首相の「海外移転が望ましいが、最低でも県外移設が期待される」といういわゆる「県外移設」発言が、それまで日本政府が してきた説明に対する不信感を膨らませた。同首相の発言は、沖縄は「地の利」(難しく言えば「地政学的要衝」、歴史的に言えば「太平洋の要石」)を持つために米軍基地を集中せざるを得ないという日本政府の従来の説明をくつがえすものだったからだ。さらに同首相が半年足らずで安易に発言を撤回したことへの怒りなどが絡み合う。
こうした感情が、基地に対する沖縄の人々の態度を硬化させ、2014年1月の名護市長選において、辺野古への移設に反対する稲嶺進氏を市長に再選させた。2014年11月の沖縄県知事選では、埋め立てを承認した仲井真知事を落選させた。
以上が普天間飛行場移設問題のこれまでの経緯と概要である。
■「沖縄への過度の負担は日米同盟の根幹を崩す」
次に、「沖縄の声」について考えよう。
筆者が「沖縄の声」としてワシントンに伝えるべきメッセージは次のようなものであった。「沖縄の民意はいまだ、普天間飛行場の辺野古への移設を容 認できる状況にはない。したがって日米両政府は辺野古以外の選択肢を速やかに模索すべきである。このまま辺野古案を進めれば、反対派との間に衝突が生じ、 死傷者が発生する可能性がある。そうなれば沖縄は、収拾がつかない騒然とした状況になるであろう(すべての基地を返還するよう要求するようになってもおかしくはない)。その場合、日米同盟にも大きな打撃を与えるだろうし、地域の安全保障にも深刻な悪影響を与えてしまう」。
全基地返還について少々解説しよう。沖縄には海兵隊以外にも、空軍、海軍、陸軍が駐留している。軍人だけで約2万6000人。これは日本全国にいる米兵の約7割に相当する。さらに、軍属や家族を含めれば約4万7000人に及ぶ(2012年6月現在)。これだけの規模の米軍を日本の他地域に移動させることがどれだけ大変なことか、想像するに余りある。
米軍にとって最重要な施設は、「東アジア最大の空軍基地」と言われる嘉手納飛行場である。面積は、成田空港の約2倍に当たる約20平方キロメート ル。米空軍最大の戦闘航空団である、第18航空団を抱えているほか、特殊作戦機能や偵察、哨戒機能も充実している。ベトナム戦争では、米軍出撃基地として機能。戦略爆撃機B52が連日、嘉手納飛行場を飛び立ちベトナムを爆撃していた。平時には東アジアをパトロールし、有事には主要攻撃・兵站拠点となる、米軍には不可欠な存在なのである。
米国の有識者の中には、普天間飛行場を返還すれば、沖縄は嘉手納飛行場の返還も要求するのではないか、と心配する声もある。それくらい虎の子の存在なのだ。米軍としては嘉手納飛行場の返還だけはなんとしても避けたいところだろう。 ≫〈吉川由紀恵レポート1〉
≪ 沖縄の声を「ワシントン」の誰に伝えるのか?
2012年3月、筆者は縁あって沖縄県庁に勤務することになった。普天間飛行場移設問題について、沖縄の声をワシントンに伝えるために。
前回は「沖縄の声」とは何かを説明した。今回は「ワシントン」とは誰を指すのか、を取り上げる。
■普天間移転問題を実質的につかさどる国務・国防次官補
米政府内でアジア政策をつかさどるキーパーソンは誰か? 基本的には、日本の外務省に当たる米国国務省の国務次官補(アジア担当)が主担当となる。ただし、普天間飛行場移設問題は軍事に関わることなので、日本の防衛省に当たる国防総省の国防次官補(アジア担当)も主担当だ。この他、NSC(国家安全保障委員会)にもアジア部長がいる。NSCは大統領に近い分、影響力を持ちうるだけに要注意である。
これらの官僚の上にもちろん、大統領や国務長官、国防長官がいる。さらにそれぞれの下に副長官、次官がいる。ただし、通常はこうしたクラスがアジア問題にそれほどの時間を割くことはない。ましてや米国は当時、アフガニスタンとイラクで軍事活動をしていた(イラクでは2012年末から、アフガニスタンでは 2014年末から、完全ではないものの撤退を進めている)。このため、政策を実質的に決定、実行するのは次官補となる。
■キーパーソンはリッパート国防長官首席補佐官
ただし、国務省と国防省の次官補だけを見ていればよいわけではない。大統領と国務長官、国防長官との力関係などが政策に影響する。実際には誰に力があるのか、担当が入れ替わるたびにキーパーソンを見極めることが大事である。
2012~13年は、マーク・リッパート国防長官首席補佐官(当時)がキーパーソンと言われた。前職はアジア担当の国防次官補。同氏が首席補佐官となっ た後、アジア担当の次官補はしばらく空席だった。リッパート氏は、バスケットボールの相手をするほどオバマ大統領との緊密な関係にあるとの評判であった。
■議会は予算に目をこらす
こうした状況をウォッチするだけでもそれなりに労力が要る。しかし、事は行政府内に限られない。米議会も無視できない存在である。大統領に物を申すことができる一大勢力なのだから。
米国の政治システムにおいて、大統領はあくまで行政府の長である。予算ひとつ通すにしても、行政府ができることは2つしかない。1つは要望書を作ること。行政府は予算案を議会に提出することさえできないのだ。もう1つは、立法府で成立した予算案に対してサインするか拒否するかを決めることだ。大統領が 拒否権の行使を示唆することはあるが、その言葉を受けて、議会がどこまで修正するかは別問題である。予算法案を含め、法案作成は議員の仕事であり、行政府 が口をはさむことはできない。
ただし、付言すれば、大統領と議会は協調しなければならない関係にある。議員の評価は、重要な法案をいくつ通したかで決まる。そのため、せっかく通した法案を、大統領に拒否されても困る。一方、大統領も予算がなければ実施したい政策を実行できない。要は、議会と大統領が政治的妥協を図るよう政治システム ができている。
というわけで、議会は大統領に政策の再考を促す立場にある。その議会には、外交委員会、軍事委員会といった委員会がある。
当時、軍事予算を検討する上院軍事委員会で、この普天間飛行場移設問題に興味を示していたのは、元海軍長官のジム・ウェッブ議員(民主党)とその盟友のカール・レビン軍事委員長(民主党)、ジョン・マケイン議員(共和党)であった。
これらの議員は、普天間飛行場移設スキームそのものに介入するのではなく、このスキームが予算面においてきちんと計算されたものなのかを検証すべきだという立場をとっていた。
辺野古など代替基地の建設・提供に関わる費用は日本政府が負担する。しかし、在沖海兵隊のグアム移転に伴う建設費用の一部は米政府が負担することになっている。この点を突いたのだった。
このスキームのコストがきちんと計算されているのかを検証すべきだというのは、米軍が提出する予算額があまりに変動するからだった。米会計監査院 (GAO)が2013年に発行したレポートによると、在沖海兵隊のうちグアムに移転する人数は2006年ロードマップでは8000人であった。これが、 2010年には8600人、2012年には9500人と増加した。米政府が見積もるコスト負担は2006年には42億ドルだったものが2010年には 127億ドルと約3倍に跳ね上がった。一方、2012年には90億ドルに減っている。 図省略 議会で活躍するのは議員だけではない。それぞれの委員会は専門スタッフを抱えており、政策について議員にアドバイスをする。もちろん、議員個人についているスタッフ(政策アドバイザー)もいる。
当時は、マイケル・シーファー氏が上院外交委員会の上級スタッフに移籍したばかりであった。彼は、国防次官補代理として直前までオバマ政権に席を占めていたため、普天間飛行場移設問題にも当然高い関心を持っていた。ちなみに上院外交委員会の上級スタッフは彼の古巣でもある。
■政権と大学を行き来するエキスパートたち
以上が、米政府のアジア政策決定者及び議会の有力者である。しかし、キーパーソンの輪はさらに大きい。彼らにアドバイスする、あるいはする可能性の高い 日本専門家たちがいる。こうした専門家は大学やシンクタンクに所属しているが、彼ら自身が政権に入り、政策実行者になってもおかしくない。米国ではこうした政治任命される政権スタッフが4000人から5000人もいると言われる。
筆者が地域安全政策課主任研究員に就任した2012年は、米国の大統領選の年。政策やその担当者が大きく変わる可能性があっただけに、日本専門家たちの動向も重要視した。
前述のマイケル・シーファー氏は、ジョン・ケリー上院外交委員長が国務長官になった暁には国務次官補の座を射止めるべく、外交委員会に戻ってきたと言われていた。
外交問題評議会(CFR)のシーラ・スミス女史の動向も無視できなかった。同氏はオバマ政権と濃いつながりがあり、第1次オバマ政権が発足した時に政権入りが取りざたされていたからだ。彼女は、沖縄の琉球大学で教えていた経歴も持っている。
加えて、ライシャワーセンター所長のケント・カルダー教授も、日米関係の第一人者であるだけに目が離せなかった。同教授は筆者の前職において上司だった。
このほか、米国の政治家に影響を与えるものにメディアがある。ジャーナリストの中には普段から詳細に日本をウォッチしている人もいれば、普段は特に見ているわけでもないが、何かあれば社説や論説を書く論説委員やコラムニストもいる。特に重要なのはワシントン・ポスト紙とニューヨークタイムス紙、ウォー ル・ストリート・ジャーナル紙だ。ワシントン・ポスト紙はオバマ大統領が自ら目を通すと言われている。
こうした様々な人々に対して沖縄の声を効果的に届ける――これが筆者に課せられた主要なミッションであった。 ≫〈吉川由紀恵レポート2〉
*吉川由紀恵 プロフィール
ライシャワーセンター アジャンクト・フェロー
慶応義塾大学商学部卒業。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)東京事務所にて通信・放送業界の顧客 管理、請求管理等に関するコンサルティングに従事。2005年米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院にて修士号取得後、ジョンス・ホプキンス大学高等国際研究大学院附属ライシャワーセンター上級研究員をへてアジャンクト・フェロー。また、2012年-2014年は沖縄県知事公室地域安全政策課にて主任研究員。 ≫(日経ビジネス:政治・経済 > 「沖縄外務省アメリカ局」での勤務を命ず!)
 |
幕末から維新へ〈シリーズ 日本近世史 5〉 (岩波新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |












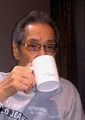





これ等の為に、税金の投入額を計算し判定て下さい。
資金・時間・人材投入、、、、、、驚く金額に。
いつも大変興味深く拝見しております。
このブログのほかにも、
内田樹氏や、小林よしのり氏のブログや著作を読み、
その主張の大部分に、賛同しておりました。
しかし最近、安倍政権の対米追従批判に対して、
「対米追従は、真の独立のために必要な軍事力を日本が獲得するための方便である。」
「現在の対米追従は、自主防衛のためのステップに過ぎない」
といった反論を耳にし、ある程度の説得力がある意見ではないか、とも思ったのです。
確かに現在日本の政治家や官僚が、アメリカの機嫌を取ることに汲々としているのも事実のように思います。
しかし、だからと言って、彼らの目的がアメリカに奉仕することにある、という結論は、いささか性急にすぎるのではないでしょうか。彼らも日本の政治家である以上、愛国心が(まともな形かどうかはともかくとして)あるはずです。少なくとも、アメリカに奉仕することが彼らの究極の目的である、とは自分には信じられないのです。
この反論について、あいば様はどのようにお考えでしょうか。
突然の長文と質問、失礼とは存じますが、よろしければ考えを伺いたいのです。