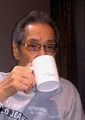人気ブログランキング
ブログセンター・ ニュースと時事
CIA 影の実力者ナイ教授の日中尖閣諸島問題インタビュー
ダイアモンド社オンライン:特別レポート
米国の歴代民主党政権を支えた重鎮が緊急提言!「日本は中国の謝罪・賠償要求に応じる必要なし日中対立の本当の解決策を語ろう」~ ジョセフ・ナイ元国防次官補(現ハーバード大学教授)インタビュー
尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件を契機とする日中対立の鮮明化に際して、米国のオバマ政権はいち早く日本支持の姿勢を表明した。しかし、「尖閣諸島は(米国の日本防衛義務を定めた)日米安全保障条約第5条が適用される」(クリントン国務長官)との発言の一方で、「尖閣は日本の施政下」(グレグソン米国防次官補)と、領有権ではなく施政権に言及するに止まり、どこか中国への配慮がにじむ。乱暴な想像だが、もし尖閣で日中が軍事衝突を起こすようなことがあったら、米国はどう出るのか。在日米軍は出動するのか。また、そもそもワシントンの権力中枢は今回の日中対立をどう見ているのか。カーター、クリントンら米国 の歴代民主党政権で国務次官補や国防次官補などの要職を歴任し、オバマ政権の対アジア外交にいまだ隠然たる影響力を持っているといわれるジョセフ・ナイ氏 (現ハーバード大学教授)に聞いた。(聞き手/ジャーナリスト、瀧口範子)
――日本は中国人船長を釈放したが、謝罪と賠償を求める中国側の要求には応じないスタンスだ。 これまでの日本の対応をどう評価するか。
中国の脅しに屈しなかったのは正しいことだ。中国は、この機会を過大に利用しようとしており、こういうやり方は長期的に見て中国の近隣諸国との関係を悪化させる。
――中国の本当の目的は何か。尖閣諸島は中国の領土であるという前提で謝罪と賠償を求めているが、何を達成しようとしているのか。
そもそも中国が謝罪を求めること自体が間違っている。船長が釈放された時点で、すべての要求を取り下げるべきだった。 尖閣諸島については、日中両政府が領有権を主張しているが、日本がずっと領有(in possession)してきた経緯がある。基本的に現在の状況は、日本が領有しているというものだ。そのことに挑戦しようという中国のスタンスは間違いだ。
――アメリカは、今回の対立をどう見ているのか。今後の対中関係を考え直すようなきっかけになるのか。
アメリカの立場は、日中両国と良好な関係を保ちたいというものだ。ただ、日本との間には日米安全保障条約がある。ヒラリー・クリントン国務長官が述べたように、アメリカは中国と友好関係を保持することを希望する一方で、同盟国としての日本をサポートする。漁船の衝突問題や領土問題の解決には乗り出さないが、安保条約を結ぶ同盟国としての日本が尖閣諸島を領有しているという事実を認識しているということだ。
――今回の中国の行動で、アメリカが日本に求めることは変化するか。
1年前、鳩山首相(当時)は中国との関係を重視し改善していくと発言した。アメリカは、それはかまわないが、日米安保条約を保持した上でのことだと述べた。それに対して、日本側にはいくらかの疑問があったのではないか。現在目前にある中国との問題は、安保条約がなぜ重要なのかを物語るものだ。中国 の威嚇行為を防ぐことができるからだ。
――日米関係はここ数年、特に日本で民主党政権が発足した後は、非常に不安定な状態にある。中国はその乱れにつけこんでいるのか。
中国の国内政治は最近、国粋主義に傾いている。加えて、(リーマンショック後)世界が経済危機に陥った中で、経済的に成功したことに高いプライドを感じている。それが、国際政治において積極的な行動に出させている。 つまり、(今回の威嚇行為は)日米関係が悪化していると見たからではなく、最近の中国の典型的な行動と言える。同様の領土問題は、尖閣諸島だけではなく、南シナ海や北ベトナムでも起きている。
――この問題はどう解決するのがよいと考えるか。
最良の方法は、中国が賠償要求を取り下げ、日中が直接協議のテーブルに戻ることだ。そして、日中両政府が合意している東シナ海のガス田共同開発プロジェクトを開始することだ。 このプロジェクトは、日中が友好的関係を強めていくために重要な役割を果たす。この当初の路線に戻るのが良策だろう。
――日本は、中国に漁船との衝突で破損した巡視船の修理費を要求している。
ディテールは問題ではない。繰り返す。最良の解決策は、両国が要求を取り下げて、ガス田の交渉というもっと広い議論に入ることだ。
――中国の権力中枢では、一体何が起きているのか。
ここ数日だけ見ても中国は対立姿勢を軟化させたり硬化させたり、対応がチグハグだ。 理由はふたつある。ひとつは先に述べたように、国内での国粋主義の高まりだ。中国国内のブログやインターネットでの投稿を見ると、それは明らかだ。アメリカの外交政策を批判する人民解放軍の高官の態度にもそれが出ている。 もうひとつは、2012年に予想される中国指導部の交代だ。温家宝首相や胡錦濤国家主席は、次期指導部が小平(故人)の敷いた注意深い外交政策を引き継いでいくことを望んでいるが、中国共産党の若い世代には、もっと強い中国を目指す傾向がある。それが表面化している。
――かなり乱暴な想像だが、もし中国が尖閣諸島に軍を配備するようなことがあれば、米国はどう出るか。
(現実と)非常にかけ離れた仮説に基づいて議論するのは有効ではないだろう。だが、繰り返すが、クリントン国務長官が強調したことは、アメリカは日米安保条約に基づいて行動するということだ。そうしたことが起これば、アメリカは日本をサポートしていることを示す行為に出るだろう。
――指導部交代と言えば、北朝鮮で金正日総書記の三男ジョンウン氏が事実上の後継に指名され た。中国は、この北朝鮮を外交カードとしてどのように利用しようとしているのか。
中国は、北朝鮮との関係でふたつの目標を持っている。ひとつは核保有を制限すること。もうひとつは国家崩壊を防ぐことだ。 北朝鮮が崩壊すると、難民が中国になだれ込む。中国はこのふたつの目標を並行して達成しようとしてきたが、北朝鮮の指導部と何らかの対立問題が生じると、後者を重視せざるを得なかった。つまり、北朝鮮に対して、中国は完全に厳格な態度に出てこられなかったということだ。逆説的だが、北朝鮮はその弱者的な立場を国家パワーとして利用しており、それを中国に対して行使しているのだ。 中国は、北朝鮮が国家崩壊を免れるためには中国的な経済改革を推進することが必要だと見ているが、北朝鮮にはその意思がないという状態だ。
――話を領土問題に戻せば、中国が近隣諸国に対して融和的姿勢に転じる可能性はあると思うか。
2002年~2003年にさかのぼれば、じつは中国はASEAN諸国に対して、南シナ海の領土問題でより穏やかな立場で臨むというソフトパワーを使っていた。ところが、ここ数年で態度が硬化してしまった。経済的な成功を背景に、若い共産党員の態度も強気になり、近隣諸国が中国の言い分を聞き入れるべきだと考えるようになったのだろう。 だが、中国は元の路線に戻るべきだ。アメリカは、アジア地域で中国が融和的姿勢を保つことは、中国、アメリカ、日本を含めたすべての国の経済発展にとっていいことだと見ている。
――現状を見ていると、その声が届くのかは分からない。 こう答えよう。ゲームには、双方が負けるものと、どちらも勝つものがあるが、われわれは後者を探求すべきだ。対立状態は何も生産しない。外交交渉こそ何物にも勝る。中国にもそう考えてもらうしかない。
●ダイアモンド社掲載のナイ教授紹介文
≪ジョセフ・ナイ(Joseph Nye) カーター政権で国務次官補、クリントン政権で国防次官補など米民主党政権下で要職を歴任。米国を代表するリベラル派の学者であり、知日派としても知られ る。クリントン政権下の1995年、ナイ・イニシアティブと呼ばれる「東アジア戦略報告」をまとめ、米国が東アジア関与を深めていくなかで対日関係を再評 価するきっかけを与えた。2000年代には、同じく知日派として知られるリチャード・アーミテージ元国務副長官らと超党派で政策提言報告書をまとめ、台頭 する中国を取り込むために日米同盟を英米同盟と同じように深化させるべきと説いた。オバマ政権誕生時には一時期、駐日大使の有力候補に浮上。国の競争力に ついて、ハードパワー(軍事力や資源)とソフトパワー(文化的・政治的影響力)を組み合わせた「スマートパワー」の重要性を提唱していることでも有名。 1937年生まれの73歳。≫
ダイアモンド社の紹介が表なら、裏の人物紹介は以下の通り。
通称「ナイ・イニシアティヴ」と呼ばれる「東アジア戦略報告(EASR)」を作成。東アジアに約10万の 在外米軍を維持するなど、冷戦後のアメリカの極東安保構想を示した。この構想は1997年の日米防衛協力のための指針(いわゆる新ガイドライン)における 日米同盟再定義とつながっていき、第一期においてはまとまった東アジア政策を持たず、日米経済関係を巡って緊張しがちだったクリントン政権が再び東アジア への関与を強め、対日関係を重視していく重要な契機となった。
2000年には対日外交の指針としてリチャード・アーミテージらと超党派で作成した政策提言報告「アーミテージ・リポート」を作成、2007年2月には、政策シンクタンク戦略国際問題研究所(CSIS)においてアーミテージと連名で再度超党派による政策提言報告「第二次アー ミテージ・レポート」を作成・発表し、日米同盟を英米同盟のような緊密な関係へと変化させ、東アジア地域の中で台頭する中国を穏健な形で秩序の中に取り込むインセンティブとすることなどを提言している。
≪*筆者:つまり、アーミテージの知的バックボーンでCIAの知恵袋と言われる男。かつてCIAを統括する米国大統領直属の国家安全保障会議NSCの議長で、同時に東アジア担当者。ナイは現在、米国の政治家養成スクール、高級官僚養成スクールであるハーバード大学ケネディ行政大学院の院長(*現在はハーバード大学特別教授)であり、そこから輩出された無数の政治家・行政マンの司令塔となっている人物である。この人物が「事実上」、米国の政策を起草している。まぁ米国の外交軍事戦略の元締めとも言われているが、そこまでの大物でもないだろう。
ジョセフ・ナイ著「対日超党派報告書」には以下の如く、ありゃりゃな戦略が述べられている。これは2000年に書かれたのだから、ゾクゾクものである。ただ、このような考えが米国中枢の対日観、常識と考えて、米国を観る必要はあるだろう。しかし、戦略好きとはいえ、些か荒唐無稽な感じも否めない。≫
*但し、このジョセフ・ナイ著「対日超党派報告書」の内容が実存するかどうかは定かではない。ただ、米国の東アジアを見る目には、このような戦略を考える要素は含めれているという参考資料としては面白い。
●アリャリャな戦略
1、 東シナ海、日本海近辺には未開発の石油・天然ガスが眠っており、その総量は世界最大の産油国サウジアラビアを凌駕する分量である。米国は何としてもその東シナ海のエネルギー資源を入手しなければならない。
2、そのチャンスは台湾と中国が軍事衝突を起こした時である。当初、米軍は台湾側に立ち中国と戦闘を開始する。日米安保条約に基づき、日本の自衛隊もその戦闘に参加させる。中国軍は、米・日軍の補給基地である日本の米軍基地、自衛隊基地を「本土攻撃」するであろう。本土を攻撃された日本人は逆上し、本格的な日中戦争が開始される。
3、米軍は戦争が進行するに従い、徐々に戦争から手を引き、日本の自衛隊と中国軍との戦争が中心となるように誘導する。
4、日中戦争が激化したところで米国が和平交渉に介入し、東シナ海、日本海でのPKO(平和維持活動)を米軍が中心となって行う。
5、東シナ海と日本海での軍事的・政治的主導権を米国が入手する事で、この地域での資源開発に圧倒的に米国エネルギー産業が開発の優位権を入手する事が出来る。
6、この戦略の前提として、日本の自衛隊が自由に海外で「軍事活動」が出来るような状況を形成しておく事が必要である。
今夜はこの辺で失礼します。長い引用で読むだけでも大変ですが、一種の修業だとお思いくだされば幸いです。
ランキング応援感謝いたします!
人気ブログランキング
ブログセンター・ ニュースと時事












 https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif
https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif