

【梶原得三郎・新木安利編、『松下竜一 未刊行著作集4/環境権の過程』】
下河辺淳氏とはそういう人だったのか、と納得(p.62、103、129)。
巨大開発の夢のような話の裏。「なんのことはない。その新コンビナートがまた新しい公害を生む。その対策費をひねり出すためには第四コンビナートを造る。このとめどない悪増殖をどのように考えればいいのか。市民を待ち受けるのは地獄ではないのか」(p.90)。
「そうなのだ。それでいいじゃないか。おれ貧乏なのかなあ、などと無理に悩む必要などありはしない。/〈ゆたかさ〉とは意識問題なのだ。・・・松林の海岸を持つし、遠浅の海では貝掘りも楽しめる。心身を破壊する公害とは無縁だ。―――これほどゆたかな生き方があろうか。/・・・演劇を見ることによる一時的感興と、中津市の子供たちが幼い頃からゆたかな自然の中で生育していくことのすばらしさを比較すれば、私はためらいもなく後者を選ぶ。/・・・都市化により喪われた自然が市民の心の生育に与える底深い破壊は、その何をもってしてもつぐないうるものではない」(pp.92-93)。
内在的価値の萌芽。あのトンデモナイ冤罪事件で有名な志布志。「若者の流出に対する志布志の人たちの考えは面白い。若者が都会に働きに出て送金して来るのはやむをえないじゃないか。その若者たちが時折帰郷するときのために、あくまでも美しく静かな町を残しておくのだという」(p.94)。「「あなたの息子さんが疲れて帰郷して来るとき、せめて憩いを与えるような美しい故郷を守り通すのが、われわれの務めではないでしょうか」・・・今までの開発論議で常に欠落していたのは、自然愛好的心情論であった」(p.108)。「・・・漁業者が放棄したのは漁業権にすぎない。埋め立て海域で漁業を営む権利を放棄したに過ぎない。しかして、海は厳然として残るはずである。海そのものを売買する権利などは誰にもありえない。魚業権の放棄されたあとの海は、誰のものなのか。それは誰のものでもあるまいし、同時に誰もの共有物だろう。私企業が、漁業権を買い上げたからといって、それがあたかも海そのものまで買い上げたかの如く専横に海を埋め立てることが許されるとは呆れ果てるばかりである。」(p.184)。「漁業権さえ買い上げれば海を占有できるなどということが許され続けて来たこと自体、不思議なほどである。・・・今の社会機構が、「物の生産高計算」でしか評価基準を持たぬゆえ・・・。/海というものの評価の中で、実は生産高での計算はもっとも矮小な評価でしかなく、万人が来て海を楽しむ価値は、計算を超えて巨大なはず、その楽しみは万人がもつ権利であり、それこそが環境権なのである(私は安易に、海を楽しむ価値と書いてしまったが、それではまだ卑小ないいかただという気がする。海がそこに存在する、その存在自体の価値というべきか)」(p.137)。
埋め立て「協定調印の翌夜・・・一人のおじいさんが、さも納得いかぬげに質問に立った。「わしゃあ百姓をしちょるもんじゃが・・・・・・協定がもう結ばれたちゅうけんど、そらあおかしいなあ。わしんとこには、なんの相談もこんじゃったが・・・・・・」/・・・まさに自分は市民の一員なのだから。/首をかしげいうおじいさんの疑問に、私は胸が熱くなり「そうなんです。市民一人一人の声に耳を傾けてまわらない政治が間違っているのです」と答えた。・・・むしろ、おじいさんの発言を常識外れとして失笑した人々の、その〈ならされた常識〉にこそ、現今の民主主義の衰退があるのだ。/・・・その可否には、それこそ市民一人一人の意見を徴して回るのが当然である。今の行政機構の中でそれが不可能だとしても、そのような姿勢だけはもたねばならぬ。」(p.106)。「それこそが真の民主主義である」(p.141)。

















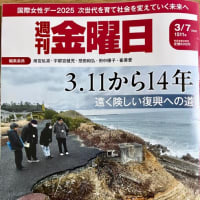







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます