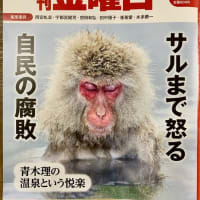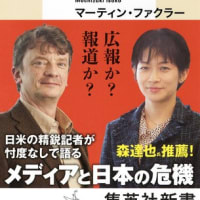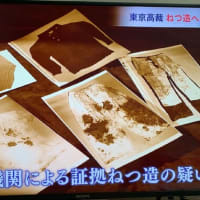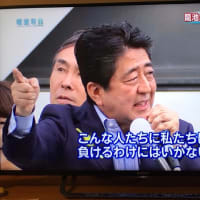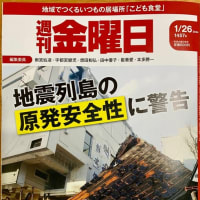東京新聞の社説【集団的自衛権 「限定容認」という詭弁】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014040502000148.html)と、
コラム【筆洗』(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2014040502000114.html)。
「限定的なら認められる、というのは詭弁(きべん)ではないのか。集団的自衛権の行使の「限定容認論」である。政府の憲法解釈は長年の議論の積み重ねだ。一内閣の意向で勝手に変更することは許されない」・・・・・・暴走する自公政権は聞く耳持たず。それにしても、「平和を愛する公明党」が聞いて呆れる。それに同調する翼賛野党。『集団的自衛権 「限定容認」という詭弁』。
『●「与党公明党」: 平和を願っているらしい
「学会さん」も「テロリスト」と呼ばれる日がいつか』
『●ブレーキは無く、二つの「アクセル」な自公政権』
「日本も世界の兵器市場に打って出るという。長年の信条だった「武器輸出の原則禁止」をやめると政府が決めた。政府開発援助(ODA)をからめた武器輸出の促進も考えているともいう▼NATOに加盟し米国製兵器のお得意さまとなった東欧諸国は、イラク戦争に出兵し、血を流すことになった。そのイラク戦争で兵器産業の巨人たちは、また大いに潤った。武器輸出というのは、そういうビジネスである」・・・・・・「積極的平和主義」の本性とは、つまり「死の商人」になって火に油を注ぎ、「人殺し」で「おカネ儲け」しましょう、ということ。「そういうビジネス」。自公に騙されること、無関心・無視でいいのか?
『●「平和憲法」が泣いている』
『●「(積極)平和主義」「不戦の誓い」が聞いて呆れる、
「死の商人主義」「外交破壊主義」』
『●「人道なんてなかった」頃の「戦争できる国」の現実』
『●城山三郎さんと反戦』
「▼城山さんは「日本は先の戦争で、ほとんどすべてを失ってしまった。
唯一、得られたのは、憲法九条だけだ」と語っていた。戦争体験と憲法が
強く結びついた世代は減っている。憲法への思い入れの少ない若い世代に
城山さんの言葉はどう伝わるのだろうか▼あの戦争で新聞は「旗」を振り、
国民を熱狂させ国を破滅に導いた」
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014040502000148.html】
【社説】
集団的自衛権 「限定容認」という詭弁
2014年4月5日
限定的なら認められる、というのは詭弁(きべん)ではないのか。集団的自衛権の行使の「限定容認論」である。政府の憲法解釈は長年の議論の積み重ねだ。一内閣の意向で勝手に変更することは許されない。
限定容認論とは、集団的自衛権の行使を「日本近海を警戒中の米艦船が攻撃を受け、自衛隊が防護する場合」など事例を限定して認めようというものだ。自民党の高村正彦副総裁が主張した。
高村氏のよりどころは、米軍駐留の合憲性などが争われた最高裁による一九五九年の「砂川判決」である。
日本の自衛権について「わが国が、存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは国家固有の権能の行使として当然」との判断を示した。
高村氏はこれを論拠に「国の存立を全うする必要最小限度(の実力行使)には、集団的自衛権の範疇(はんちゅう)に入るものはある」として、米艦船の防護などは「必要最小限度に当たる」と主張している。
政府の憲法解釈で違憲としてきた集団的自衛権の行使を、一内閣の判断で合憲とすることには公明党や自民党の一部に根強い慎重論がある。限定容認論は説き伏せる便法として出てきたのだろう。
しかし、いかにも無理がある。
個別的自衛権を有するかどうかが議論されていた時代の判決を、集団的自衛権の行使の一部を認める根拠にするのは「論理の飛躍」(公明党幹部)にほかならない。
公明党の山口那津男代表は高村氏との会談で、個別的自衛権で対応できないか、まず検討すべきだと、限定容認論に慎重姿勢を示したという。当然だろう。
集団的自衛権をめぐる議論の本質は、日本が直接攻撃されていないにもかかわらず、他国のために武力行使することが妥当か、長年の議論に耐えてきた政府の憲法解釈を、一内閣の意向で変えていいのか、という点にある。
たとえ限定的だったとしても、政府の憲法解釈を根本的に変えることにほかならない。
このやり方がいったん認められれば、憲法の条文や立法趣旨に関係なく、政府の勝手な解釈で何でもできる。憲法が空文化し、権力が憲法を順守する「立憲主義」は形骸化する。イラク戦争のような誤った戦争に巻き込まれることも現実味を帯びてくる。
限定容認なら大丈夫と高をくくってはいけない。立憲主義の危機にあることを、すべての国会議員が自覚すべきである。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2014040502000114.html】
筆洗
2014年4月5日
米国のロッキード・マーティン社は、軍需での売上高が世界一とされる兵器産業の雄だ。日本の本年度の防衛予算四兆八千億円余にほぼ匹敵する売り上げを誇ると言えば、巨人ぶりが分かるだろう▼その実態を描いた『ロッキード・マーティン 巨大軍需企業の内幕』(草思社)を読めば、この巨人がいかに米政府に影響力を行使し、外交の舞台裏で動いてきたかが分かる▼冷戦が終わってから、米国は北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大を進めた。東欧の民主化支援が旗印に掲げられたが、ロシアとの関係悪化を危ぶむ声もあった。だがロ社は異論を抑えるため巨額の政治献金も使って、猛烈な働き掛けをした▼東欧諸国がNATOに入れば、ソ連製兵器を買い替えることになる。東方拡大は米軍需産業にとっては、市場拡大。米政府に兵器の購入費を援助させることまでして、市場を獲得していったというのだ▼日本も世界の兵器市場に打って出るという。長年の信条だった「武器輸出の原則禁止」をやめると政府が決めた。政府開発援助(ODA)をからめた武器輸出の促進も考えているともいう▼NATOに加盟し米国製兵器のお得意さまとなった東欧諸国は、イラク戦争に出兵し、血を流すことになった。そのイラク戦争で兵器産業の巨人たちは、また大いに潤った。武器輸出というのは、そういうビジネスである。
==============================================================================