
いやー、
昨日の更新はひどかったー。
ほぼ寝ながら書いたので、
最後どうなってたかわからなかったのですが、
いま読み返してみたらひどいっすね最後。
完全に意識失ったまま書いてますよあれ。
やばいやばい、
ネペンテス普及という大きな目標があるのに、
あんな低いクオリティの記事連発してたら、
委員会解散になってしまいますよ。
で、
昨日ぶつ切れになった今後の課題ですが、
二つありまして、
まずは袋の残存率。

これは前から気になってたんですよね。
プロが育てたネペンテスは、
みんな数個の袋をつけているのに、
委員会で育てると、
新しい袋ができると前の袋が枯れるという、
まったくおもしろくない、
一進一退の攻防が繰り広げられるわけですよ。
委員のいぼがえる氏の見解では、
栽培環境により、
袋の寿命が伸びているのではないか、
という見解ですが、
これが一番有力かなと私も思います。
プロが育てると成長が早いから、
袋が枯れる前に次々と袋ができる、
という見方もできます。
が、
小さいサイズのネペンテスが、
そんな急成長をするとは思えません。
するとやはり、
いかに袋を長持ちさせるかがポイントとなるわけですね。

えー、
皆様が飽きないように、
無駄に過去の写真を挿入してみる、
姑息な手法の当ブログ、
しばらくこのスタイルでやってみようと思います。
で、
袋の長持ち方法なのですが、
プロが気をつけて、
委員会ではまったく気にしてない要素が、
一つだけ心当たりがあります。
それはですね、
ズバリ、
湿度。
そう、
湿度と袋の寿命には、
密接な関係があるのではないかということです。

えー、
思ったより袋の写真がなくて、
いきなり終わりそうですはい。
そこで新たに、
湿度と袋の関係性を解き明かす、
新プロジェクトを企画することにしました。
で、
それに並行するように、
もう一つの問題点、
それは、
栽培数が増えるほど、
鑑賞しにくいということ。

ネペンテス達があっちゃこっちゃに葉を伸ばし、
その先からあっちゃこっちゃに袋ができるので、
鉢や茎に隠れて撮影もできねーよってな状態になっちゃうわけです。
これはいつか解決せねばと思ってたのですが、
かなり重要な問題です。
場所の整理や、
葉が増えたことによる光量の変化などにより、
ネペンテスの鉢を動かすときがあるのですが、
ここで本当に事故が多い。
ネペンテス同士が引っかかって、
どちらかが千切れそうになるなんて日常茶飯事。
鉢やネペンテス本体、
手やそでに袋が引っかかって、
何週間もかけて膨らんできた袋がブチっとなった日なんか、
本当に、
OH MY GOD!
と叫びたくなりますよマジで。
で、
この栽培における問題点の切り札として、
当委員会では生ミズゴケに注目したわけです。
問題点と生ミズゴケがどう関係しているのか、
それは検証を進めていくうちに追々話すとして、
まずはAmazonをポチっとな。
生ミズゴケがこれしか残ってないので、
追加発注しました。

きました。

知ってる方もいらっしゃると思いますが、
新鮮な生ミズゴケって、
用土としては超高いんですよ。
ほんでもって私が発注しているところは、
こんな焦げたヤキソバみたいな状態で送られてくるわけですね。

このままでも使えるのかもしれませんが、
私は青々とした状態の生ミズゴケを使いたいので、
しばらく育ててから使います。
なのですぐには使えません。
そうなってくると、
常に新鮮な生ミズゴケのストックが欲しくなってくるわけです。
で、
この夏にネペンテスと一緒に植えた生ミズゴケが、
だいぶ青々としてきましたので、
切り取って使ってみることにしました。

ここでようやく、
本日表題のミズゴケ増殖計画に戻る訳ですが、
順調にミズゴケ増えてんじゃんって感じはあります。
しかし、
ミズゴケの成長の形態をよく見てみると、
どうもですよ、
一本の茎のような本体を伸ばしながら成長しているようなんですね。
つまり、
増えているというよりも、
伸びていると表現した方がいいような状態なんですね。
これは問題でして、
どんなに伸びても絶対本数は決まっているわけですから、
使えるミズゴケの回数は、
最初の本数で決まってしまうということになるわけですよねこれ。
うーん、
そうなると、
今後、
大量に生ミズゴケを使う検証が何本か控えているのですが、
一つの検証が終わるまで、
他はなんも進めることが出来ないということになってしまいます。
そこで、
このミズゴケの増殖計画の検証項目はただ一つ。
切ったミズゴケは再生するのか
ということです。
つまり、
長く伸びたミズゴケを切り、
本数を増やすことは可能かという趣旨の計画であります。
そんなわけで、
もったいないですが、
この鉢から伸びた生ミズゴケを失敬していきます。

ほんとフサフサです。
変な水草みたいなのまで生えてるし。

それで今後、
この鉢からまたミズゴケが再生し、
切り取ったミズゴケも伸び始めれば、
実験は大成功というわけですね。
で、
切ると表現しましたが、
実際は、
ミズゴケの頭みたいなところをつまんで引っ張ると、
思ったよりあっさりと引き抜けます。
柔らかい土の草むしりみたいなイメージです。
これがですね、
もう病みつき。
超高級スポンジから抜いてるような感触です。
超高級スポンジってよくわからないけど、
とにかくそんな感じなのです。
それとともに、
微かに香る、
生ミズゴケ独特の青くさい匂い。
新鮮で爽やか。
これで水の流れる音がすれば、
もう清流ですよ。
もうね、
体全身と、
心の奥から、
疲労が抜けて完全にリラックス。
生ミズゴケの超優しい極上の触り心地にうっとり。
ヤバイこれ。
本気でヤバイ。

病みつき。
もう病みつき。

あー、
癒されるー。
生ミズゴケに癒されるー。

これ凄い。
本当に凄いこれ。
セラピーとしてなんか作ろうかなマジで。
なんか知らないけど、
極上の癒し空間だよこれ。
よくわからない匂いのロウソク炊きまくるより全然いいよこれ。
炊いたことないけど全然いいよこれ。
あれ、
世の中のみんな、
この癒し知ってるのかなこれ。
マジでネペンテス栽培記終了して、
ミズゴケ栽培記にしようかなこれ。

これは想像以上の副産物です。
きっとポイントは、
自分で育てたってところなのかもしれませんが、
なんだかわからないけどとにかく癒されます。
そうそう、
元の鉢はミズゴケ抜いたらこんな感じになりました。

ネペンテスを傷つけられないのと、
全部抜いてしまうと再生が困難になると判断し、
緑の部分は少し残してあります。

どれぐらいで復活するか、
非常に楽しみです。

成功すれば、
ほぼ無限に生ミズゴケが採れるわけですから、
これは期待せずにはいられません。
この検証も定期的にご報告していこうと思います。
ではでは、
次回もお楽しみに。
昨日の更新はひどかったー。
ほぼ寝ながら書いたので、
最後どうなってたかわからなかったのですが、
いま読み返してみたらひどいっすね最後。
完全に意識失ったまま書いてますよあれ。
やばいやばい、
ネペンテス普及という大きな目標があるのに、
あんな低いクオリティの記事連発してたら、
委員会解散になってしまいますよ。
で、
昨日ぶつ切れになった今後の課題ですが、
二つありまして、
まずは袋の残存率。

これは前から気になってたんですよね。
プロが育てたネペンテスは、
みんな数個の袋をつけているのに、
委員会で育てると、
新しい袋ができると前の袋が枯れるという、
まったくおもしろくない、
一進一退の攻防が繰り広げられるわけですよ。
委員のいぼがえる氏の見解では、
栽培環境により、
袋の寿命が伸びているのではないか、
という見解ですが、
これが一番有力かなと私も思います。
プロが育てると成長が早いから、
袋が枯れる前に次々と袋ができる、
という見方もできます。
が、
小さいサイズのネペンテスが、
そんな急成長をするとは思えません。
するとやはり、
いかに袋を長持ちさせるかがポイントとなるわけですね。

えー、
皆様が飽きないように、
無駄に過去の写真を挿入してみる、
姑息な手法の当ブログ、
しばらくこのスタイルでやってみようと思います。
で、
袋の長持ち方法なのですが、
プロが気をつけて、
委員会ではまったく気にしてない要素が、
一つだけ心当たりがあります。
それはですね、
ズバリ、
湿度。
そう、
湿度と袋の寿命には、
密接な関係があるのではないかということです。

えー、
思ったより袋の写真がなくて、
いきなり終わりそうですはい。
そこで新たに、
湿度と袋の関係性を解き明かす、
新プロジェクトを企画することにしました。
で、
それに並行するように、
もう一つの問題点、
それは、
栽培数が増えるほど、
鑑賞しにくいということ。

ネペンテス達があっちゃこっちゃに葉を伸ばし、
その先からあっちゃこっちゃに袋ができるので、
鉢や茎に隠れて撮影もできねーよってな状態になっちゃうわけです。
これはいつか解決せねばと思ってたのですが、
かなり重要な問題です。
場所の整理や、
葉が増えたことによる光量の変化などにより、
ネペンテスの鉢を動かすときがあるのですが、
ここで本当に事故が多い。
ネペンテス同士が引っかかって、
どちらかが千切れそうになるなんて日常茶飯事。
鉢やネペンテス本体、
手やそでに袋が引っかかって、
何週間もかけて膨らんできた袋がブチっとなった日なんか、
本当に、
OH MY GOD!
と叫びたくなりますよマジで。
で、
この栽培における問題点の切り札として、
当委員会では生ミズゴケに注目したわけです。
問題点と生ミズゴケがどう関係しているのか、
それは検証を進めていくうちに追々話すとして、
まずはAmazonをポチっとな。
生ミズゴケがこれしか残ってないので、
追加発注しました。

きました。

知ってる方もいらっしゃると思いますが、
新鮮な生ミズゴケって、
用土としては超高いんですよ。
ほんでもって私が発注しているところは、
こんな焦げたヤキソバみたいな状態で送られてくるわけですね。

このままでも使えるのかもしれませんが、
私は青々とした状態の生ミズゴケを使いたいので、
しばらく育ててから使います。
なのですぐには使えません。
そうなってくると、
常に新鮮な生ミズゴケのストックが欲しくなってくるわけです。
で、
この夏にネペンテスと一緒に植えた生ミズゴケが、
だいぶ青々としてきましたので、
切り取って使ってみることにしました。

ここでようやく、
本日表題のミズゴケ増殖計画に戻る訳ですが、
順調にミズゴケ増えてんじゃんって感じはあります。
しかし、
ミズゴケの成長の形態をよく見てみると、
どうもですよ、
一本の茎のような本体を伸ばしながら成長しているようなんですね。
つまり、
増えているというよりも、
伸びていると表現した方がいいような状態なんですね。
これは問題でして、
どんなに伸びても絶対本数は決まっているわけですから、
使えるミズゴケの回数は、
最初の本数で決まってしまうということになるわけですよねこれ。
うーん、
そうなると、
今後、
大量に生ミズゴケを使う検証が何本か控えているのですが、
一つの検証が終わるまで、
他はなんも進めることが出来ないということになってしまいます。
そこで、
このミズゴケの増殖計画の検証項目はただ一つ。
切ったミズゴケは再生するのか
ということです。
つまり、
長く伸びたミズゴケを切り、
本数を増やすことは可能かという趣旨の計画であります。
そんなわけで、
もったいないですが、
この鉢から伸びた生ミズゴケを失敬していきます。

ほんとフサフサです。
変な水草みたいなのまで生えてるし。

それで今後、
この鉢からまたミズゴケが再生し、
切り取ったミズゴケも伸び始めれば、
実験は大成功というわけですね。
で、
切ると表現しましたが、
実際は、
ミズゴケの頭みたいなところをつまんで引っ張ると、
思ったよりあっさりと引き抜けます。
柔らかい土の草むしりみたいなイメージです。
これがですね、
もう病みつき。
超高級スポンジから抜いてるような感触です。
超高級スポンジってよくわからないけど、
とにかくそんな感じなのです。
それとともに、
微かに香る、
生ミズゴケ独特の青くさい匂い。
新鮮で爽やか。
これで水の流れる音がすれば、
もう清流ですよ。
もうね、
体全身と、
心の奥から、
疲労が抜けて完全にリラックス。
生ミズゴケの超優しい極上の触り心地にうっとり。
ヤバイこれ。
本気でヤバイ。

病みつき。
もう病みつき。

あー、
癒されるー。
生ミズゴケに癒されるー。

これ凄い。
本当に凄いこれ。
セラピーとしてなんか作ろうかなマジで。
なんか知らないけど、
極上の癒し空間だよこれ。
よくわからない匂いのロウソク炊きまくるより全然いいよこれ。
炊いたことないけど全然いいよこれ。
あれ、
世の中のみんな、
この癒し知ってるのかなこれ。
マジでネペンテス栽培記終了して、
ミズゴケ栽培記にしようかなこれ。

これは想像以上の副産物です。
きっとポイントは、
自分で育てたってところなのかもしれませんが、
なんだかわからないけどとにかく癒されます。
そうそう、
元の鉢はミズゴケ抜いたらこんな感じになりました。

ネペンテスを傷つけられないのと、
全部抜いてしまうと再生が困難になると判断し、
緑の部分は少し残してあります。

どれぐらいで復活するか、
非常に楽しみです。

成功すれば、
ほぼ無限に生ミズゴケが採れるわけですから、
これは期待せずにはいられません。
この検証も定期的にご報告していこうと思います。
ではでは、
次回もお楽しみに。
















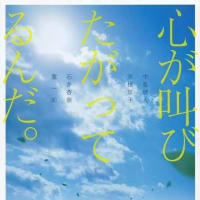





ネペンテスの一般普及を目指す者にとって、湿度とは最大の壁ですよね。
温室があればすべて解決って話なんでしょうけど、それじゃ元も子もないですし…
しかも家庭の環境では季節による影響もダイレクトに受けてしまうので、そういった環境の変化によるストレスも袋の寿命を削っている要因だと思うんですよね~
うーん…
国内で実生を繰り返せば日本の環境でも育て易い個体が生み出せるかもしれませんが、素人がネペンテスの実生ってそれこそ現実的じゃないですもんね。。
うーん、一体どうすればいいのやら(~_~;)
やっぱりですか。
やっぱりネペン業界にとって湿度は避けられない問題なんですね(^ω^;)
維持もままならないのに、実生なんて私もハードルが高すぎて手を出そうという気も起きないですね(笑)
何年かかることやら(^^;)
私なりに問題解決に向けて検証していくつもりです。
いぼがえるさん、これからもよろしくお願いします(^^)