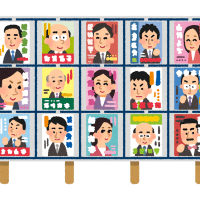論語を現代語訳してみました。
(なお、郷党第十については、当時のシナ王朝の礼式や作法(しきたり)などの記述が多く、修身という分野からは少し外れている内容となっています。よって、当時のシナ王朝のそうした礼式や作法などに関心のある方のみ、ご覧になっていただければ幸いです。)
郷党 第十
《原文》
君召使擯、色勃如也、足躩如也。揖所與立、左右手、衣前後襜如也。趨進翼如也。賓退必復命曰、賓不顧矣。
《翻訳》
君〔きみ〕 召〔め〕して擯〔ひん〕せ使〔し〕むれば、色〔いろ〕 勃〔ぼつ〕 如〔じょ〕たり、足〔あし〕 躩〔かく〕 如たり。与〔とも〕に立つ所に揖〔ゆう〕し、手を左右にするとき、衣〔ころも〕の前後〔ぜんご〕 襜〔せん〕 如たり。趨〔はし〕り進むとき翼〔よく〕 如たり。賓〔ひん〕 退〔しりぞ〕けば必〔かなら〕ず復命〔ふくめい〕して曰〔のたま〕わく、賓 顧〔かえり〕みず、と。
《現代語訳》
(あるお弟子さんが、次のように仰られました。)
国君が孔先生を召して、賓客〔ひんきゃく〕を迎える介添役〔かいぞえやく〕を命ぜられたとき、その顔色を正し、足は進めないようなありさまで、敬〔つつし〕んで君命を受けられた。
(そして賓客を迎えての儀式のとき、)ほかの介添役に揖〔ゆう〕する際、手を左右にされるが、(その揖のとき)衣の前も後ろも整然としており、乱れ動くことがなかった。
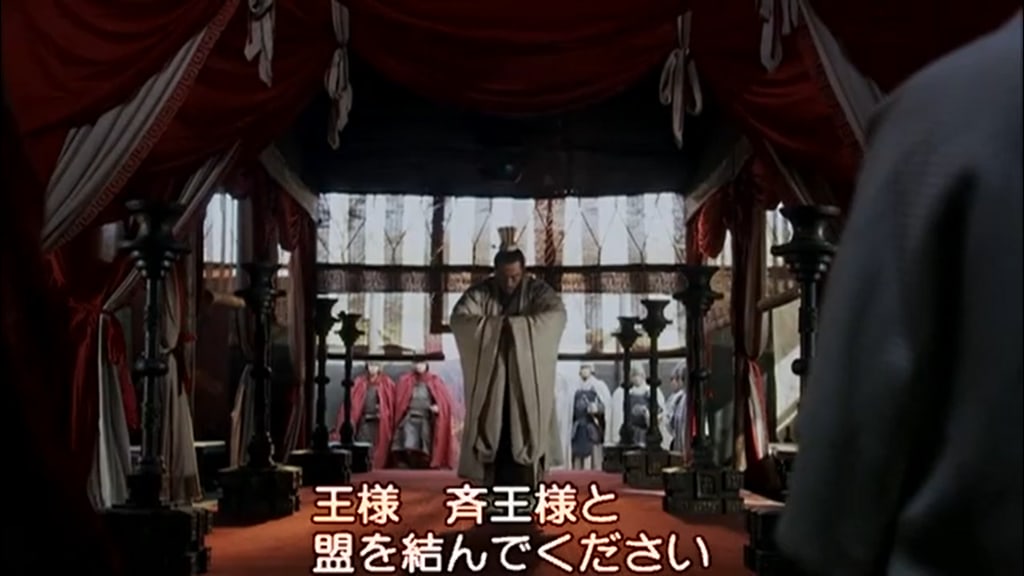
趨〔こばし〕り進まれるときは、(両手を高く拱〔こまね〕き張るが、均衡がとれていて)鳥が翼を広げるように端正〔たんせい〕であった。
(行事が終わり)賓客の退出を見送りなされたあと、必ず国君にこう報告された。
「賓客は(心残りなく満足されて)振り向かれることなく帰られました」と。
《雑感コーナー》 以上、ご覧いただき有難う御座います。尚、現代語訳ならびに以下の(注)については、加地伸行先生の「論語」全訳注より引用させていただいております。
(注1)「擯」は、介添役。
(注2)「勃如」は、顔色を変える。
(注3)「躩如」は、進もうとして進めないさま。
(注4)「所与立」は、同僚の介添役。
(注5)「襜如」は、整ったさま。
(注6)「翼如」は、端正なさま。
※ 孔先生とは、孔子のことで、名は孔丘〔こうきゅう〕といい、子は、先生という意味
※ 原文・翻訳の出典は、加地伸行大阪大学名誉教授の『論語 増補版 全訳註』より
※ 現代語訳は、同出典本と伊與田學先生の『論語 一日一言』を主として参考