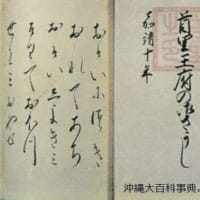1300年代中期頃に、北山王の二男であった真松千代が沖永良部島の世之主(島主)として島へ派遣され、島の中心にある越山の南側に、家臣であった築城の名手:後蘭孫八に命じて築いたといわれている城が「世之主城」です。
現在は城の建物や城壁などがはっきりとわかる状況ではないのですが、親元である今帰仁城によく似た作りだったようであるといった話もあります。
ここはずっと昔から古城地であったという伝承ですが、近年では世之主神社が建立され、神社がある場所というイメージの方が強かったようです。
そしてこの城跡一帯は木々で覆われていて、その全貌が分からない状態であったのが、2016年に世之主600年祭が行われたときに、周りの木々を伐採したことによって、隠れていた石積みの城壁跡や城としての景観がリアルに見えてきたのだそうです。
このショットは2016年に伐採した当時の様子をドローンで動画撮影されたもので、ELOVE DOGAさんの「琉球浪漫飛行 世の主神社💫沖永良部島 ドローン映像」からスクショで拝借致しました。
世之主神社も立て替える前の古い神社の時です。敷地の後方北側の土手にも石が張り付いているのが分かります。

600年もの間、頑張って張り付いている石達です。

この部分だけ見ても、かなりの数の石が使われているのが分かります。この付近にはこれだけの石は無いといいますので、どこから運んできたのかも興味深い。

もしかして右手下部の平場で、草が生えていない部分が幻の二の郭だったのかも?と想像が膨らみます。(二の郭については後半に記載あり)

下は現在の城址の空中からのショットです。軍艦のような形をしているこんもりとしたコンパクトな城址です。あっという間に木々が繁殖しますので、今は石垣の石などは分かりません。しかしこの木々が600年もの長い間、崩落を防いでくれていたのかもしれません。

道路の工事などで敷地を分断されたりしているので、本当の城の敷地の範囲はもっと広かったようです。
そして昨年7月の城址の様子です。
参道階段の右(東側)が大雨などで崩落してしまったのです。
かなり危険な状態なのではと思います。

上の状況は昨年に記事に書きましたが、実は現在も崩落個所はそのままになっています。応急処置とシートはかけてありますが、修復はまだされておりません。

崩落個所は下のブルーの個所です。この場所、実は昭和52年頃までは、赤矢印の高さ位までの二の郭があったのだそうです。その範囲は、だいたいですが赤枠の範囲のようです。(かなりざっくりですので、実際にはもっと低く小さい範囲だったかもしれません。イメージでお願いします。)

現在二の郭だと思われている場所は、二の郭と三の郭になるようです。
この二の郭に城壁があったのではないかといわれています。
二の郭が無くなってしまった理由は、当時の土地の所有者の方が畑にするために削り取ったのだそうです。
実際の二の郭の範囲や高さなどは、きちんと調査がなされれば何か分かってくるかもしれません。本来の城の姿を見てみたいですね。
こちらは参道階段です。
珊瑚石を使った石の階段があり、両サイドにはそんなに高くはなかったが石垣があったといいます。
現在の新しい階段が付く前の状態です。階段左の少し高くなっている場所は二の郭に該当する部分だったのかもしれません。

階段工事中の様子。

出来上がった階段。
空中に浮いたような気分になる階段でした。天気が良いときには、とても気持ちが良いです。

石の階段は崩れ落ちて危険な状態であったので、ずっと進入禁止になっていましたが、階段を作り直す段階で発掘調査をしたところ、いろいろな物が出土したため、今後の本格的な発掘を見据えて、いったんはこの木の階段にしたのだそうです。
いつかは往時を偲ばせる石の階段につくりかえて欲しいとは思いますが、今はそういった理由でこの階段で我慢我慢。
この城址、実はもう1ケ所ご案内したい場所があります。
ここは上の神社社殿の裏である北側の下になるのですが、ちょうど宗川の泉と呼ばれていた、水の枯れることのない泉があった場所です。
世之主の時代から使われていた泉であったそうですが、近年はその泉も上に側溝ができたりしてだんだん水が枯れていっているということですが、その泉の上の斜面が崩落しているのです。

以前の記事で、この城址は第二次世界大戦中は日本軍の陣地となっていたことを書きましたが、その時に削り取られたりした個所もあったのかもしれません。
神社のある敷地の下には高さ1メートルほどの地下道があって、ちょうど参道階段横の崩落した個所の側面の東側向きにぐるっと銃口があったといいますから、もしかしたら崩落の原因に繋がっているのかもしれません。
その地下道は今はどうなっているのか、大変興味があります。
こんな風に現在トラブルにみまわれている世之主城址ですが、兼ねてから関係者や島の方々は、この島の宝である貴重な場所を、後世に残していくために文化遺産にして欲しいと願っていました。しかし国の文化遺産は、そう簡単になることはできません。
住民や関係者からの声によって、まずは地域の行政機関が文化遺産の認定に向けて取り組むことを掲げなければなりません。
残念ながらこの場所はこれまでは正式な候補にはあがっておりませんでした。
しかし、関係者の方々の熱い思いと努力によって、先日の町の議会で国の文化遺産登録に向けて今後取り組んでいくようなことで話が進んでいるということです。
最終ゴールは城の復元となってくれれば嬉しいですが、まずは崩落が続くこの場所自体を守らなければなりません。そういった意味でも、今回町が取り組んでくださるということに、ホッと致しました。
まだまだこれから測量や発掘調査といった事前準備にたくさんの時間がかかると思います。そして町のプロジェクトとして大きく動き出すのには少し時間が必要かもしれませんが、取り組みが決まったことは大きな前進だといえると思います。
これから文化遺産登録に向けての進捗も書いていきたいと思いますので、いつか実現されますよう皆様からの応援もよろしくお願い致します。