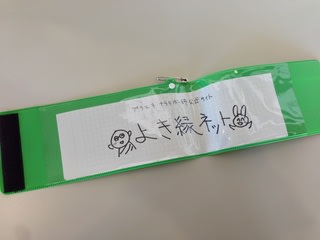プラユキ師講話
プラユキ師講話
・「私たちは仏教の文脈で、自我をいじめすぎていませんか?」
瞑想会でのプラユキ師の法話から
・スカトー寺での法話の音声データ集(タイ語)
・2015年10月、魚川祐司さんによりスカトー寺で収録されたツイキャス。
「プラユキ・ナラテボー師との対話@スカトー寺」
「姫が「女性」になるまで(スカトー寺での対話2)」
一本目は主に魚川さんの私へのインタビュー・視聴者コメントへの応答。
二本目は主に魚川さんのスカトー寺体験者へのインタビュー(+プラユキ師の解説付き)。
親からの虐待を受けた子供時代の苦悩。そしてスカトー寺での修行や夢分析を通して、
苦しみの淵から蘇っていくプロセスが仔細に語られています
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 公式イベントの報告
公式イベントの報告
・2016年2月5日
新刊『自由に生きる』出版記念講演会 主催:出版社サンガ
当ブログ管理人による報告です。
【シェア】「自由に生きる」の刊行記念講演会が開催されました
参加された方の報告です。
プラユキさんのサンガくらぶに行ってきました(その1)
プラユキさんのサンガくらぶに行ってきました(その2)
・2013年11月30日
凱旋(!?)講演・瞑想会
「こころワクワク人生を楽しむ「気づきの瞑想」 埼玉県本庄市
主催者の報告
「よき縁ネット」管理人の報告
 各種イベントの報告や感想などのリンク
各種イベントの報告や感想などのリンク
執筆された方々、ありがとうございます。
・2017年3月18〜20日 瞑想リトリートin御岳山
プラユキ師瞑想リトリートin御岳山 主催者の報告
ブログ「ハッピーコラージュ」 参加者の報告
・2017年1月14日 子育て講座 「受容的かかわりを学ぶ」
プラユキ師とのコラボ講演会を終えて 共演者・須賀義一氏の報告
イベントレポートまとめ 主催者の報告
・2016年12月4日 浜松瞑想会
智慧・慈悲・自由をテーマにした「気づきの瞑想会」 主催者の報告
大盛況?プラユキ・ナラテボー師の浜松瞑想会! 参加者の報告
・2016年11月27日 マインドフルネス気づきの瞑想会」関西瞑想会
マインドフルネスと瞑想|プラユキ・ナラテボーさんの講座に行って来ました
歩行瞑想での気づき|瞑想難民にならぬプラユキ・ナラテボーさんの教え
プラユキ・ナラテボーさんと魚川祐司さん対談会&プラユキ先生瞑想会(同志社大での魚川祐司氏との対談レポートもあり)

・2016年11月12日(土)「やすらぎの対話と瞑想レッスン」
ご参加ありがとうございました。フォトレポート
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ1
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ2
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ3
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ4
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ5
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ6
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ7
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ8
プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」 イン 中野サンプラザ9
・2016年7月1〜3日 気づきのリトリート
【ご報告】プラユキさんをお招きして、マインドフルネスを育む「気づきのリトリート(瞑想合宿)」を開催しました。
・2016年06月30日 『十二因縁』ワークショップ
『十二因縁』ワークショップを開催しました
『十二因縁』WS・ご参加の感想
・2016年06月20日 「ぽっちり舎スタートアップ講座 第二回」
ぐらぐらしない場所に自分の土俵をたてる「タイの僧プラユキさん講座報告・ご感想」
・2016年06月04日 プラユキさんの「やすらぎの対話と瞑想レッスン」イン 志木ふれあいプラザ
フォトレポート
・2016年05月18日 浜松瞑想会
人間関係とコミュニケーションがよくなる「気づきの瞑想(マインドフルネス)」
・2016年4月16日 One Day リトリート第2弾 東京
「One Day リトリート 第2弾 開催しました」
・2016年1月23日 One Day リトリート 東京
One Day リトリート開催されました①
One Day リトリート 開催報告②
One Day リトリート 開催報告③
One Day リトリート 開催報告④
・2016年1月17日 講演会&瞑想ワークショップ 札幌
プラユキ・ナラテボー師にお会いして
・2015年12月16日 夜のお話と瞑想の会 東京
「自由に生きる」
・2015年12月15日 浜松瞑想会 静岡県浜松
実学としての仏教と「いまここ」カウンセリング
・2015年11月28,29日プラユキ・ナラテボー滋賀気づきの瞑想会 滋賀
プラユキ先生の滋賀での瞑想会で良き縁にふれました!
・2015年11月21日 プラユキ・ナラテボー師によるお話と瞑想会 東京
プラユキ師 瞑想会が開催されました
瞑想会の感想届いてます
・2015年11月21日 プラユキ・ナラテボー師によるお話と瞑想会 東京
プラユキ・ナラテボー先生の瞑想会で瞑想方法を学んできた
・2015年6月19日 夜の瞑想とお話の会 東京
【報告】プラユキ師「夜のお話と瞑想の会」
・2015年5月18日 浜松瞑想会 静岡県浜松市
自我を超えて苦しみから自由になる
・2015年1月17日 新春の瞑想とお話の会 東京
【報告】今年も灯明とともに!「新春のお話と瞑想の会」
・2015年1月6日 プラユキ師がネットラジオ「オシキリシンイチの脱力主義!」に出演され、
レポートが公式サイトにアップされました。
【ブログ-銀座】番組史上初☆お坊さんがスタジオに!
・2014年11月30日 カイロジャーナル創刊25周年記念イベント
特別講演会「カイロプロクテッィクと仏道の融合 ”今ここ” 」
・2014年11月28日 第12回サンガくらぶ
プラユキ師法話会「よく生きること、よく死ぬこと」
「慈悲パワーに満ちたプラユキ・ナラテボーさんのサンガくらぶ」
・2014年11月22日 東京
日本トランスパーソナル学会主催「プラユキ・ナラテボー師来日講演&ワークショップ」
当サイト管理人の報告
・2014年11月22日 東京
日本トランスパーソナル学会主催「プラユキ・ナラテボー師来日講演&ワークショップ」
「プラユキ・ナラテホーさんのお話をきいて」(学会関係者の感想)
・2014年11月16日 プラユキ師瞑想会 浜松
プラユキ師瞑想会報告
在家にふさわしいダンマの実践方法~真理と善性による「布施、持戒、瞑想」
・2014年10月25日 お話と瞑想の会 東京
「プラユキさんの仏教超入門」
・2014年6月13日 夜のお話と瞑想の会 東京
怒りの背後には切なさがあり、願いがある
・2014年5月3~5日 気づきの瞑想合宿 静岡県浜松市
手動瞑想(四念処)を学ぶ瞑想合宿~浜松「森の家」
プラユキ・ナラテボー師 気づきの瞑想合宿
・2014年1月5日 東京
「気づきとともにすごす1日~新春の『お話と瞑想の会』」
・2013年12月20日~23日 沖縄
「プラユキ・ナラテボー先生の瞑想会 in 沖縄」~“今ここ”にパッと気づく 心が軽くなる瞑想会~
・2013年12月3,17日 プラユキ・ナラテボーの気づきの瞑想 朝日カルチャー新宿校
プラユキ・ナラテボーさん「気づきの瞑想」~衣食住編~
プラユキ・ナラテボーさん「気づきの瞑想」~お勉強編~
プラユキ・ナラテボーさんの瞑想会に出て、サンガジャパンvol.11に帰る
・2013年11月23日 気づきの瞑想ワークショップ 大坂
おもてなしマインドあふれる、「気づきの瞑想ワークショップ@大阪」
「私たちは仏教の文脈で、自我をいじめすぎていませんか?」師の法話から
・2013年11月17日 「深まる秋の瞑想会」 静岡県浜松市
ブッダの四念処瞑想講義~プラユキ・ナラテボー師浜松瞑想会の要点
・2013年11月8日 夜の「お話と瞑想の会」 東京都世田谷区
恐れ、不安との付き合い方 ~自己投影からの自由と活用
・2013年7月15日 海の日の「お話と瞑想の会」 東京都渋谷区
・2013年7月5~7日 瞑想リトリート in 穂高養生園 長野県安曇野市
・2013年5月17日 夜の「お話と瞑想の会」 東京都目黒区
・2013年4月27~29日 安曇野リトリート 長野県安曇野市
・2013年1月20日 浜松瞑想会 静岡県浜松市
・2008年11月20日 「混迷の時代を生き抜く手習い ~身・心・人間関係を活かす優れたインターフェイス作りとしてのブッタの瞑想技法~」 江戸川大学
江戸川大学で講演したときの主催者の平山満紀先生(現在は明治大学で教鞭をとられています)のレポートです。
・参加イベント不明
マインドフルネス ~呼吸瞑想の方法~
【業務連絡】
プラユキ師の瞑想会やリトリートを主催されている方にご連絡です。
開催後、自身や参加者のサイトで報告や感想などがアップされましたら、
ご連絡いただければ「シェアリング」のページで紹介いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 学びのシェアリング
学びのシェアリング

・個人面談体験者の手記
「手動瞑想を始めて1ヶ月で、40年来悩んだ母との関係が改善〜気づいた人から今すぐ働きかけよう〜」
・恋愛ユニバーシティ
「嫉妬・プライド・恋愛感情」の罠にはまらないで!~仏教に学ぶ“感情に振り回されない3つの方法“
雑誌『クロワッサン』のプラユキさんのコメントを引用しています。
・あたま出版HP
タイのテーラワーダ比丘 プラユキ・ナラテボー師インタビュー
「子育てにとって大切なこと」
・プラユキ師と人気ブロガーのイケダハヤトさん、ヒビノケイコさんの3人による鼎談が、
電子書籍化されて発刊されました。収録についてお2人が記事を書かれています。
イケダハヤトさん
「プラユキ大長老にお会いして、ついに「お寺」の存在意義がわかっちゃった話。」
ヒビノケイコさん
「『人を萎縮させない話し方のひみつ』イケハヤさんと僧プラユキさんと3人で対談本収録したよ」
・ブログ『ヒビノケイコの日々。人生は自分でデザインする』より。16年春に収録したプラユキ師との対話を抜粋して、文字起こしした内容を中心に構成されています
「自分らしさって何ですか?」対談・タイの僧プラユキナラテボーさん×ヒビノケイコ
新しいことに挑戦する時、怖さを乗り越えるためには?僧プラユキ・ナラテボーさん対談2
・純粋仏教界、第三の波「手動瞑想とプラユキ師」の巻 ブログ「純粋仏教徒の妄想世界散策記」
・プラユキさんの法友である故カンポンさんの肉声が聞ける、魚川祐司さんによる貴重なインタビュー。通訳は浦崎雅代さんです。
(第一回 2015/10/18)http://twitcasting.tv/neetbuddhist/movie/209501493
(第二回 2015/10/19)http://twitcasting.tv/neetbuddhist/movie/209785000
・10月、魚川祐司さんによりスカトー寺で収録されたツイキャスが試聴できます。
1).「プラユキ・ナラテボー師との対話@スカトー寺」
2).「姫が「女性」になるまで(スカトー寺での対話2)」
1)の内容は、魚川氏のプラユキ師へのインタビュー、ならびに視聴者コメントへの応答。
2)の内容は、魚川氏のスカトー寺体験者へのインタビュー(+プラユキ師の解説付き)。
親からの虐待を受けた子供時代の苦悩。そしてスカトー寺での修行や夢分析を通して、
苦しみの淵から蘇っていくプロセスが仔細に語られています。
・人気ブロガー・イケダハヤトさんのプラユキ師関連記事
「トラウマと戦っているのなら、いい師匠のもとで「瞑想」をするといいかも。」
「プラユキ大長老にお会いして、ついに「お寺」の存在意義がわかっちゃった話。」
・人気ブロガー・ヒビノケイコさんのプラユキ師関連記事
「『人を萎縮させない話し方のひみつ』イケハヤさんと僧プラユキさんと3人で対談本収録したよ」
「『お寺はトレーニングジム、瞑想は自分を癒せる心の筋トレ」瞑想と仏教に触れて良かった20のこと」
「『仏教と夢分析』悪いパターンから脱出して新しいパターンを作る方法「ネズミとネコの話」
・プラユキ師のインタビューが、超宗派仏教徒によるインターネット寺院「彼岸寺」に掲載されました。
【インタビュー】彼岸寺に期待を寄せるタイの日本人僧侶、プラユキ・ナラテボーさん
・ 2015年1月6日(火)、プラユキ師がネットラジオ「オシキリシンイチの脱力主義!」に出演されたレポートが、公式サイトに掲載されています。
 【ブログ-銀座】番組史上初☆お坊さんがスタジオに!
【ブログ-銀座】番組史上初☆お坊さんがスタジオに!
・生き方つながるコミュニティーサイト「こころーたす」に、算命学カウンセラーの中森じゅあんさんによるプラユキ師のインタビューが掲載されました。
仏教は生活に生かせる智慧(前編) 「今ここ」に焦点をあてる
仏教は生活に生かせる智慧(後編) 思いやりのある言葉を
・カイロプラクティックの業界紙「カイロジャーナル」に掲載されたインタビュー記事です。
「プラユキ・ナラテボー師 仏教を基盤に精神的にも物質的にも豊かに 上」
「プラユキ・ナラテボー師 仏教を基盤に精神的にも物質的にも豊かに 下」
カイロプラクティックの業界紙「カイロジャーナル」に掲載されたインタビュー記事です。
・「松下幸之助塾」記事からの引用されたプラユキ師の名言が紹介されています。
「名言DB:リーダーたちの名言」
・主催者ざぼんさんによる報告です。写真やイラストも満載で、とてもわかりやすく構成されています。
2012年11月17日 「気づきの瞑想」会
・2005年12月19日 第8回フォーラム
「苦しみを手放す「今ここ」の智恵 ~タイ森林寺の18年で見えてきたこと~」
2005年に「地の人・仏教対話センター」で行われた講演の、
主催者による文字起こしのページです。だいぶ前の講演のため、今日のプラユキ師の法話とは
多少ニュアンスが異なる部分もありますが、写真付きでまとまった内容になっています。
・ヤマカフェオーナーのケイコさんのブログ「ヒビノケイコの日々。人生は自分でデザインする」に、プラユキ師との4コマ対談漫画が公開されています。→「タイ僧プラユキさん漫画」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 本や雑誌記事の感想
本や雑誌記事の感想

「悟らなくたって、いいじゃないか」
・『悟らなくたって、いいじゃないか 普通の人のための仏教・瞑想入門』(ブログ「徒然日記 ー横浜生活ー」)
【書評】「悟らなくたって、いいじゃないか(著:プラユキ・ナラテボー、魚川祐司)」幻冬舎新書(ブログ「ゆ〜ろぐ」)
「自由になるトレーニング」
・イライラしやすい人におすすめな本!「自由になるトレーニング」 (ブログ「私は『土』になりたい」)
・「自由になるトレーニング」を読んで思ったこと。(ブログ「隠居系男子」)
「自由に生きる」
・「自由に生きる よき縁となし、よき縁となる。抜苦与楽の実践哲学」プラユキ・ナラテボー (ブログ「まるちゃんの めざせ!快適スローLife」)
・是誰庵のひとやすみ~プラユキ師著「自由に生きる」雑感-1
・是誰庵のひとやすみ~プラユキ師著「自由に生きる」雑感ー2
・是誰庵のひとやすみ~プラユキ師著「自由に生きる」雑感ー3
(ブログ「wong0110's diary」)
・『身施』としてのプロボノと、タイの開発僧と、健康経営。『自由に生きる』プラユキ・ナラテボー(ブログ「猿ばかりが人ではない」)
「脳と瞑想」
・脳と心の使い方「脳と瞑想」(ブログ「パレオな男」)
・「脳と瞑想」から考える、瞑想のポジティブな副作用(ブログ「原始仏教ガール's日記」)
・「脳と瞑想」書評(ブログ「智恵の海」)
・「脳と瞑想」のレビュー(ブログ「仏教の気付きの瞑想・マインドフルネスの世界)
「苦しまなくて、いいんだよ」
・「苦しまなくて、いいんだよ。」プラユキ・ナラテボー
・「苦しまなくて、いいんだよ。」=「四聖諦」
(ブログ「まるちゃんの めざせ!快適スローLife」)
・「気づきの瞑想」で「今ここ」を意識すれば予期不安も広場恐怖も消えるかもね[パニック障害](ブログ「エム氏のごグ」)
・不安と苦しさの正体とは?精神分析と仏教、瞑想を学ぶ2(ブログ「さすてなLABO」)
・読書感想「苦しまなくて、いいんだよ。」(ブログ「純粋仏教徒の妄想世界散策記」)
・プラユキ・ナラテボーさんの「苦しまなくて、いいんだよ」読んだ。良書です。(ブログ「kazk1979's diary」)
・瞑想および人生について──本当に『受容』するということは?(ブログ「U型改」)
・最強の権威による、権威主義の否定(ブログ「U型改」)
・「今ここ」に意識をおいて生きていこう~『苦しまなくていいんだよ』(ブログ「ユキヒラのブログ~人間らしい生き方をしたい~」)
・【読書感想】プラユキ・ナラテボーさん(タイの日本人僧侶)著「苦しまなくて、いいんだよ。」少し楽になれたし仏教が身近になった(ブログ「あうろーブログ」)
・オススメの本の紹介:色々辛くて自分の気持ちに落ち着く場所を見つけられない方に『苦しまなくて、いいんだよ 心安らかに生きるためのブッダの智恵』(ブログ「こころはからだのいれものだから」)
・鬱に効く本 「苦しまなくて、いいんだよ」(ブログ「まだ鬱病で消耗してるよ!~心の病と戦いながら働く、お父さんのblog~」)
・【オススメ本】苦しまなくて、いいんだよ(ブログ「未来少女日記」)
・本の紹介:「苦しまなくて、いいんだよ。」(ヒューマン・ギルド岩井俊憲の公式ブログ)
「気づきの瞑想を生きる」
・『「気づきの瞑想」を生きる』 プラユキ・ナラテボー著(ブログ「まるちゃんの めざせ!快適スローLife」)
・「気づきの瞑想」を生きる-タイで出家した日本人僧の物語(ブログ「Samtenの備忘録」)
・プラユキ・ナラテボー「気づきの瞑想を生きる」(ブログ「ブラフマチャリヤの力~静寂編~」)
雑誌などの掲載記事
・「大法輪」2012年11月号「プラユキ・ナラテボー師の夢分析」(ブログ「仏教の気付きの瞑想・マインドフルネスの世界)
・サンガジャパンVol.8「苦があること」と「苦しむこと」を混同するな(ブログ「釈迦牟尼スーパースター ~仏教のつれづれ~」)